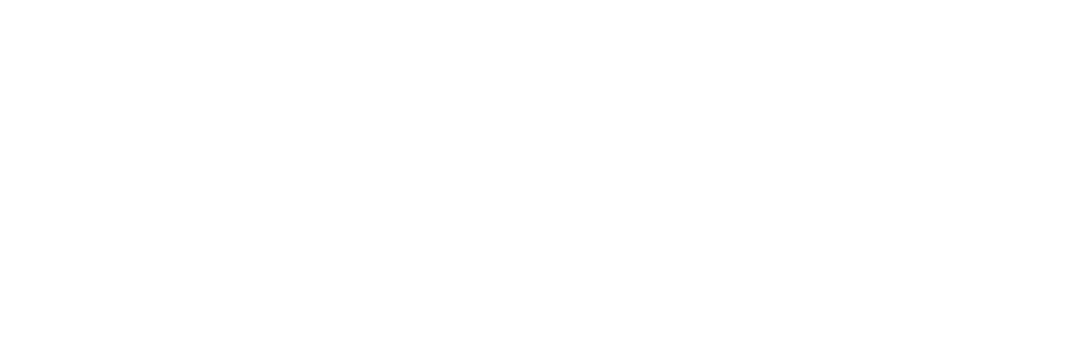未来のために何ができる?が見つかるメディア
性同一性障害ってどういうもの?行政や司法の判断事例を参考に新しい視点で考えてみる

執筆:清水沙矢香
体の性と自己認識している性が異なる「性同一性障害」のある人は、日常のさまざまなところで不便を感じたり、一部で差別的な扱いを受けたりする場面がある。
同性カップルについては、婚姻に準ずる関係として公に証明する「パートナーシップ制度」を導入する自治体も出てきた。中には戸籍上の性を問わずパートナーシップを結ぶことができる自治体もあるが、制度から漏れる人は少なくない。
性同一性障害のある人が社会の中でどのようなことで苦労しているのか、また、司法の場ではどのような待遇を受けているのかを紹介し、性同一性障害のある人が抱える問題について改めて考えてみたい。
同性カップル「パートナーシップ制度」の裏側で
2015年に東京都渋谷区、世田谷区が同性パートナーシップ制度を導入して以降、パートナーシップ制度は全国147の自治体に広がった(2022年1月4日現在※資料1)。また、2021年12月31日時点では、2,537組にパートナーシップ証明書等が交付されている(※資料1)。
同性パートナーシップは同性婚に適用される制度として始まったが、今では、一歩進んで戸籍上の性別にかかわらず「パートナーシップ」を結ぶことができる自治体も出てきた。
世田谷区などはその一例である。

ただ、こうした流れはまだ限定的だ。パートナーシップ制度のない地域に住む人の場合は恩恵を受けられないままである。この場合、戸籍上の性別を変更し婚姻関係を結ぶしか手段はないが、実はそのハードルは高い。
「戸籍変更」の高いハードル
性同一性障害に対する認識は、ある意味では広がっている。2003年には「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(以下、特例法)」が制定され、一定の条件を満たせば戸籍上の性別を変更できることになった。
この特例法にもとづけば、戸籍上の性別を変更することで同性パートナーと婚姻関係を結ぶことができる。しかし、これはそう簡単なことではない。
あまり知られていないことかもしれないが、特例法では、性別の取扱いを認めるには、次の条件(※)を全て満たさなければならないことが定められているのだ。
- 十八歳以上であること
- 現に婚姻をしていないこと
- 現に未成年の子がいないこと
- 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
- その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること
「生殖腺がないこと」
「その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること」
つまり、性適合手術を前提としているのである。身体の性と性自認が違う状況を、体にメスを入れるという、ある意味乱暴な形で解決しようというわけだ。
トイレ利用をめぐる裁判
このハードルの高さを示した裁判例がある。2021年5月に、東京高裁で行われたある裁判の控訴審だ。
東京地裁に一審の訴えを起こしたのは、経済産業省に勤務する、戸籍上は男性、性自認は女性というトランスジェンダー(Male to Female※)の職員である。
- ※ 「身体の性」は男性でも「心の性」は女性というように、「身体の性」と「心の性」が一致しないため「身体の性」に違和感を持つ人
職員は戸籍上の性別変更はしていないが、職場に自らの性自認を説明し、外見上も女性同様で勤務している。
一方で女性は庁舎内の女性用トイレを使用することに制約を設けられていた。職員が性同一性障害であることを女性職員に告知し、理解を得なければ女性トイレの自由な利用はできないというものである。
一審の東京地裁は、自らの性自認にもとづいた性別で社会生活を送ることは法律上保護された利益であるとして職員の訴えを支持した。経済産業省のトイレ利用に関する条件を取り消すと共に、慰謝料132万円などの支払いを命じた。
しかし、その後両者が控訴し、裁判は東京高裁に持ち込まれた(※資料2)。さて、二審の東京高裁の判断はどのようなものだったか。
結論からいえば、一審判決は覆された形だ。他の行政機関などでの実例や裁判例がない、ということも理由の1つになっている。
自らの性自認にもとづいた社会生活を送ることは法律上保護されているとは認めたものの、その他については棄却された形だった。
「前例がないから」。よく聞く言葉である。なお、東京弁護士会はこの高裁判決を「時代に逆行するような判断」と非難している(※資料3)。
「もう男に戻ってはどうか」
判決要旨の説明が長くなってしまったが、職員が訴えを起こすまでにはさまざまな経緯がある。職員は、ホルモン治療を受けていること、そして数年後には性適合手術を受ける予定である旨を上司に伝えていた。
しかし、体調面でなかなか手術を受けられず、時間が経過していた。その際、上司が発した言葉はこのようなものである。
「なかなか手術を受けないんだったら、もう男に戻ってはどうか」(※資料4)。
あまりにも心無いものではなかろうか。
また、筆者個人としては、自分の障害について周囲の女性職員に説明し理解を得なければならないとする経済産業省の措置について、何か工夫のしようがあったのではないかと考える。セクシャルマイノリティのカミングアウトは、心理的にそう簡単でない人も多いからだ。
その他の性同一性障害をめぐる裁判
性同一性障害に関する裁判は他にもある。
特例法にもとづき男性からの性別変更が認められた女性が代表取締役を務める会社が、この性別変更を理由にゴルフクラブから株主入会を拒否されたという事案である。
これに対しては、東京高裁は一審の東京地裁の判決を支持し、ゴルフクラブ側の違法性を認めた(事件番号:平成26年(ネ)第5258号)。
また、性同一性障害のある会社員が、性同一性障害を同僚にカミングアウトしたことをきっかけに同僚から嫌悪感を抱かれたり上司から嫌がらせなどを受けたりして退職を強要されたことで、抑うつ状態になり自死したことに関する裁判もある。
訴えを起こしたのは会社員の親で、処分行政庁に対し、労災保険法による遺族補償年金の支給を求めたが、一審の東京地裁はこれを認めなかった。原告は控訴したが、東京高裁は一審の東京地裁の判決を支持し、遺族の訴えを退けた(事件番号:平成29年(行コ)第2号)。
この事件では、自死した会社員は、カミングアウトできないことに精神的負荷を感じていた。この点に関しては、東京高裁も認定はしている。
性別はグラデーション
ここまで見てきた3つの判例に共通するのは、「明らかな差別」はあってはならないとするものの、目に見えない部分、つまり「性的マイノリティが抱える内面について争うことは難しい」という現在の状況だと筆者は考える。
性同一性障害に対する社会の認知は広がりつつあるが、一方で法的な基盤はまだ構築されていないとも言える。
ところで最近では、性的マイノリティのカミングアウトはそう珍しいものではなくなってきている。しかし、カミングアウト前後の心理的負荷が大きいと感じる人が少なくないのもまた事実である。
そうした中で、「性別は男女の2つではなく、双方の特性を持つグラデーション」とみる「性スペクトラム」の考え方(※)も紹介されている。
「2015年ごろから性を再定義する研究が広がり、完全な男、完全な女はむしろ少数派だとわかってきた。男と女の特性はグラデーションでつながっているというのが新しい性の概念。ホルモンのバランスによって女性でも声が低かったり、男性でも胸が膨らんだりすることが頻繁にある。いろいろな性のバリエーションを持っている人が多くいる」
「さらに、1人の人間でも一生のうちで性的指向や性自認が変わることもある。ここからが正常で、ここからが異常という線引きも簡単にはできない。ただ、出産は女性にしかできないし、男女の差は明確にある。男女の違いは個性として認め、スペクトラムとしてみんなが持っていることを理解することが大事だ」
これらは国立成育医療研究センター研究所副所長・小児科医の深見真紀(ふかみ・まき)さんの言葉だ。筆者は生物学を学んだ身としても、この考え方に賛同する。
人間社会は「1か0か」という世界で片付けられるものではないことを肌身で感じている人は多いことだろう。性についても同じである。難しい話ではなく、そう考えてみてはどうだろうか。

憲法に掲げられる「婚姻は、両性の合意のみにもとづいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」という言葉があるが、そこには生物学的な性についても、心理的な性についてもなんら規定はない。
性とは非常にパーソナルなものであり、かつ人の尊厳に関わるものである。一部の当事者だけが、それを開示しなければならないという決まりは、「マイノリティは心理的負担を背負わなければならない」という前提をともなっている。
性に限らず誰だって、何かに関してはマジョリティであり、何かに関してはマイノリティであることは珍しくはない。それを隠して生きている人も少なくないだろう。
なお全国の中高生のうち25万人が自身の性認識に悩んでいる、という報道もある(※資料5)。
世の中はコンピューターのように「0か1か」という2進数で構成されているわけではない。繰り返しになるが、大人こそ、その現実を知っているはずだ。若い彼ら・彼女らのためにも、アイデンティティを損なわない世の中になってほしいと願うばかりである。
[資料一覧]
※1.参考:「地方公共団体におけるパートナーシップに関する制度の状況」内閣府(外部リンク/PDF)
※2・4.参考:「労働判例ジャーナル」No.113 p1-3、p22
※3.参考:「経産省行政措置要求判定取消等請求控訴審判決について」(2022年1月20日号)東京弁護士会(外部リンク)
※5.参考:「全国の中高生のうち25万人が自身の性認識に悩んでいる」(2022年5月25日)ニューズウィーク日本版(外部リンク)
〈プロフィール〉
清水沙矢香(しみず・さやか)
2002年京都大学理学部卒業後、TBSに主に報道記者として勤務。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種市場・産業など幅広く取材、その後フリー。取材経験や各種統計の分析を元に多数メディアに寄稿中。
- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。