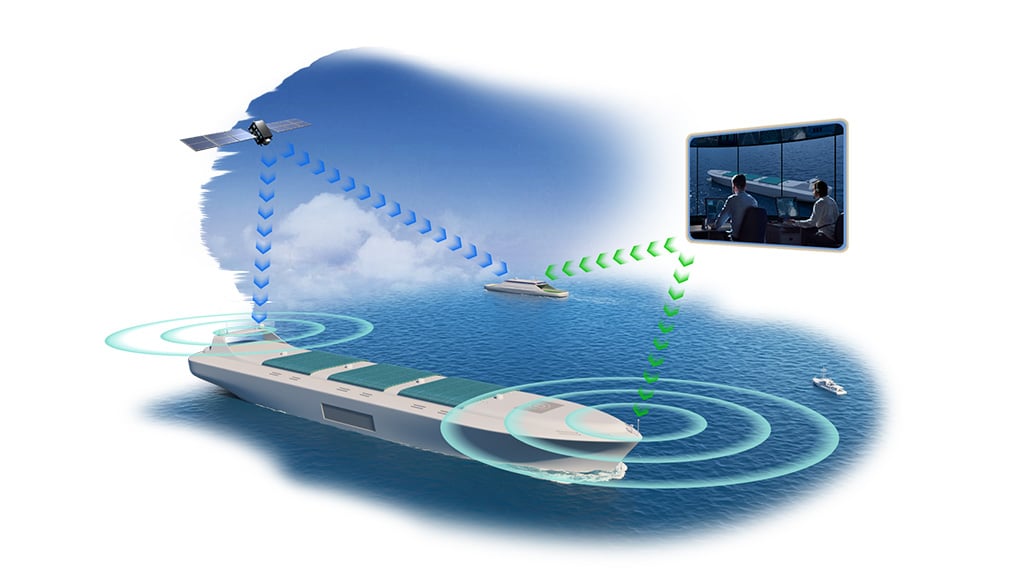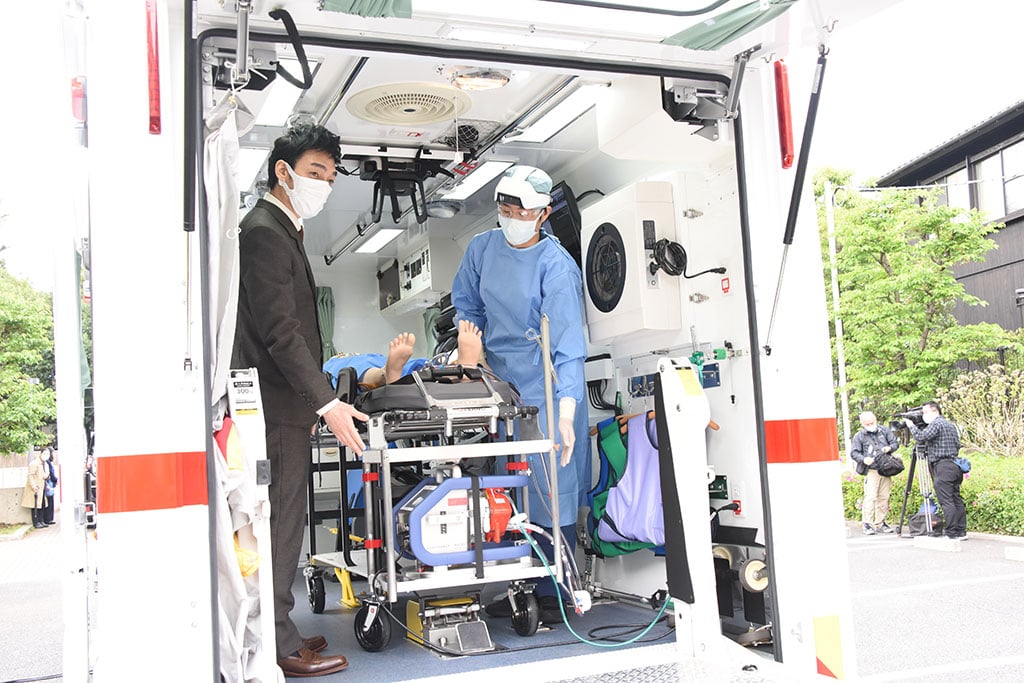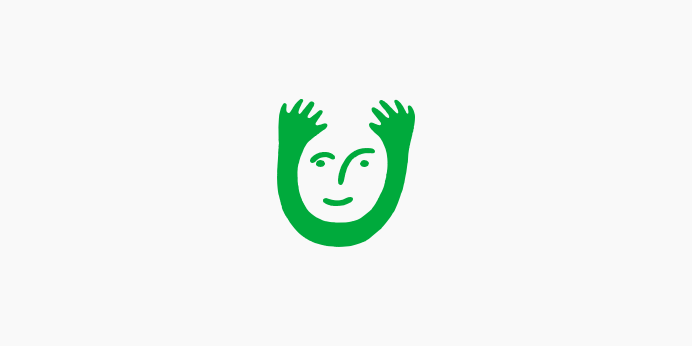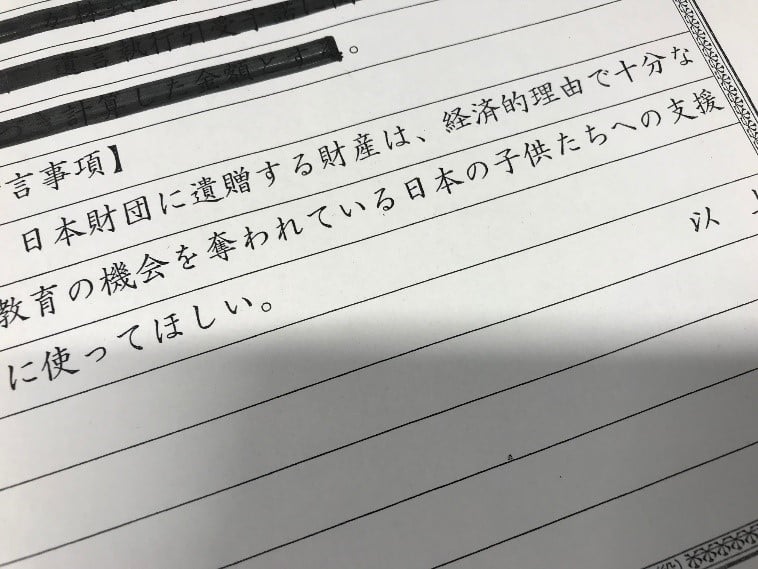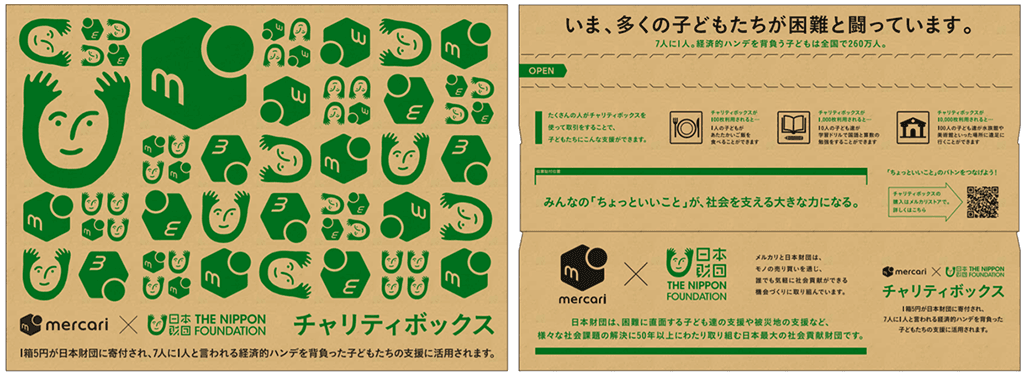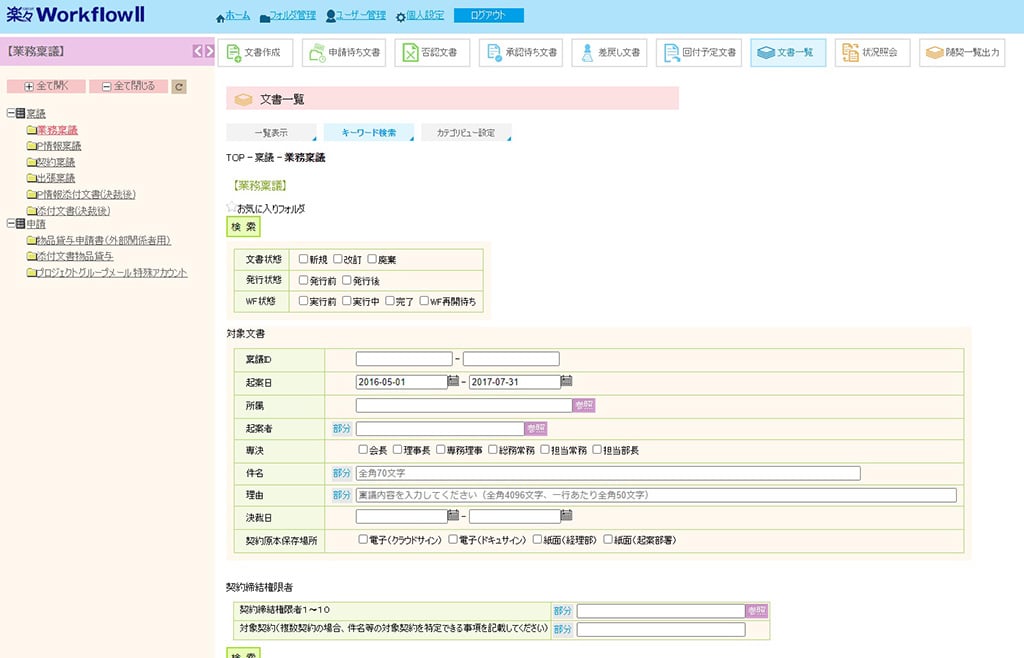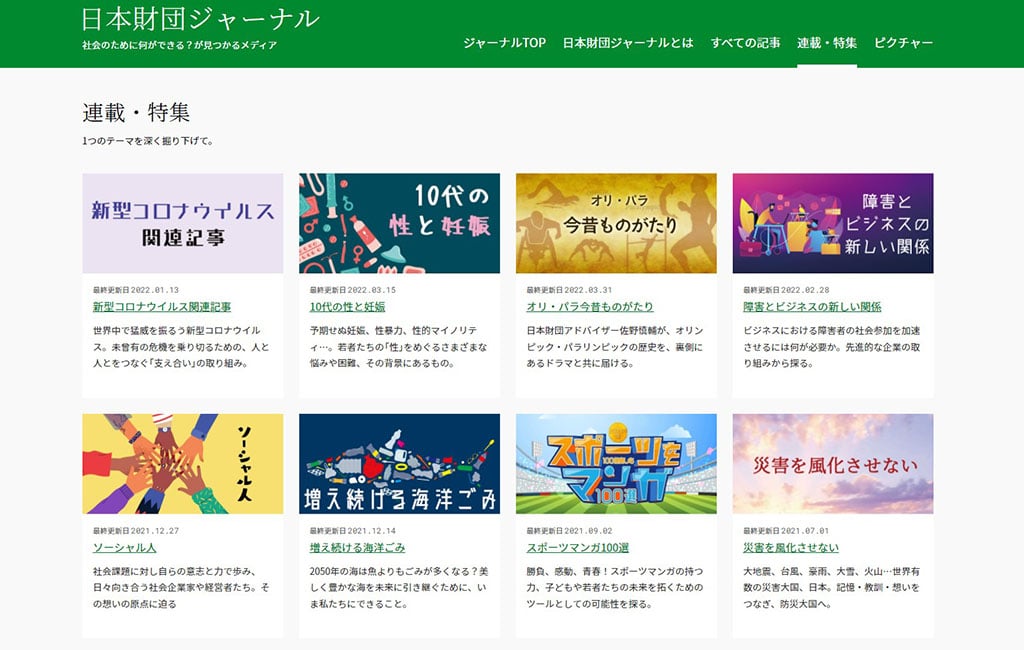60年史
2022年10月1日で創立60周年を迎え、
近年10年間を中心にまとめました
第1章 事業の軌跡
第1節トピックス
第2節 海の未来
第3節 あなたのまちづくり
第4節 みんなのいのち
第5節 子ども・若者の未来
第6節 豊かな文化
第7節 人間の安全保障
第8節 世界の絆
第9節 新しい社会に向けて
第10節 新型コロナウイルス感染症への取り組み
第2章 日本の寄付文化醸成を目指して
第3章 管理業務
資料編
-
 補記 九州南西海域における 北朝鮮工作船事件から21年
補記 九州南西海域における 北朝鮮工作船事件から21年
-
 年表(PDF / 917KB)
年表(PDF / 917KB)
-
 ボートレース売上の推移(PDF / 704KB)
ボートレース売上の推移(PDF / 704KB)
-
 ボートレース場・ボートレースチケットショップ一覧(PDF / 724KB)
ボートレース場・ボートレースチケットショップ一覧(PDF / 724KB)
-
 各年度受入交付金一覧(PDF / 677KB)
各年度受入交付金一覧(PDF / 677KB)
-
 施行者別各年度受入交付金一覧(PDF / 748KB)
施行者別各年度受入交付金一覧(PDF / 748KB)
-
 年度別受入寄付金一覧(PDF / 801KB)
年度別受入寄付金一覧(PDF / 801KB)
-
 振興業務一覧(全体総括)(PDF / 698KB)
振興業務一覧(全体総括)(PDF / 698KB)
-
 特別協賛事業の実績一覧(PDF / 657KB)
特別協賛事業の実績一覧(PDF / 657KB)
-
 造船貸付事業の推移(PDF / 752KB)
造船貸付事業の推移(PDF / 752KB)
-
 1号交付金補助事業の推移(PDF / 734KB)
1号交付金補助事業の推移(PDF / 734KB)
-
 2号交付金補助事業の推移(PDF / 724KB)
2号交付金補助事業の推移(PDF / 724KB)
-
 協力援助事業の推移(PDF / 525KB)
協力援助事業の推移(PDF / 525KB)
-
 調査研究事業の推移(PDF / 693KB)
調査研究事業の推移(PDF / 693KB)
-
 情報公開事業の推移(PDF / 695KB)
情報公開事業の推移(PDF / 695KB)
-
 社会変革推進事業の推移(PDF / 739KB)
社会変革推進事業の推移(PDF / 739KB)
-
 海洋連携推進事業の推移(PDF / 739KB)
海洋連携推進事業の推移(PDF / 739KB)
-
 寄付文化醸成事業の推移(交付金)(PDF / 739KB)
寄付文化醸成事業の推移(交付金)(PDF / 739KB)
-
 寄付文化醸成事業の推移(寄付金)(PDF / 712KB)
寄付文化醸成事業の推移(寄付金)(PDF / 712KB)
-
 船舶等振興業務以外の業務の一覧(PDF / 656KB)
船舶等振興業務以外の業務の一覧(PDF / 656KB)
-
 収益事業(施設貸与)の推移(PDF / 739KB)
収益事業(施設貸与)の推移(PDF / 739KB)
-
 事業評価実施状況一覧(PDF / 700KB)
事業評価実施状況一覧(PDF / 700KB)
-
 機構の変遷(PDF / 745KB)
機構の変遷(PDF / 745KB)
-
 歴代役員任期一覧(PDF / 730KB)
歴代役員任期一覧(PDF / 730KB)
-
 歴代評議員任期一覧(PDF / 650KB)
歴代評議員任期一覧(PDF / 650KB)
-
 歴代専門委員任期一覧(PDF / 748KB)
歴代専門委員任期一覧(PDF / 748KB)
-
 歴代アドバイザリー会議委員任期一覧(PDF / 661KB)
歴代アドバイザリー会議委員任期一覧(PDF / 661KB)
-
 日本財団の概要(PDF / 265KB)
日本財団の概要(PDF / 265KB)
-
 主な資料・写真の提供先(PDF / 188KB)
主な資料・写真の提供先(PDF / 188KB)
-
 あとがき(PDF / 254KB)
あとがき(PDF / 254KB)