誰もが取り残されない支援を~被災地の聴覚障害者に必要なものとは?
緊急避難速報、テレビやラジオによる避難の呼びかけ、避難所での連絡・呼び出し・・・。災害発生時の情報は、ほとんどが「音声」で提供されます。そのため、聴覚に障害のある方は避難が遅れてしまったり、無事に避難できたとしても避難所などで周囲から孤立してしまったりして、被災前の生活を取り戻すのが遅れてしまうケースが珍しくありません。そんな方たちのために立ち上がったのが、日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会の皆さん。具体的な活動内容や現場での手応え、課題などについて同協会会長の舘脇千春さん、監事の竹林伸子さんに聞きました。
聴覚障害ソーシャルワーカーとは?

日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会は、2006年に聴覚障害者とコミュニケーションができる社会福祉士、精神保健福祉士の有志のグループとして設立されました。目的は聴覚障害者一人ひとりの悩みや不安に寄り添い、それぞれの特性にあわせた支援を行うことです。当初は、聴覚に障害がある会員を中心に数名のメンバーが、主に全国の聴覚障害者から寄せられる相談に応える活動を行っていました。
同協会によると、聴覚障害のある方からは主に次のような悩みが寄せられることが多いそうです。
- 企業で働いているがコミュニケーションがうまくできず、孤立している
- ろう学校に通学したいが、手話がわからないためいじめが不安
- 子どもに聴覚障害があるが、どこに相談すればいいかわからない
- 病院で適切な治療をうけたいが医師と正しく意思疎通ができるかどうか不安
- 老後の財産管理や生活支援が心配
ソーシャルワーカーとしても活動する舘脇さんは次のように話します。「一口に聴覚障害者と言っても、その特性は人それぞれ。年齢や立場も違えば、受けてきた教育も聞こえなくなった時期も異なります。抱えている悩みも健康の悩みから教育、就業、家族関係まで千差万別。そんな特性を踏まえた上で、各分野の専門家と協力しながら最適な支援をするのが私たち社会福祉士や精神保健福祉士といったソーシャルワーカーの役割です」。
被災地における聴覚障害者の「孤立」を防ぐには?
活動開始当初は、ごく小規模に活動を続けていましたが、2011年3月の東日本大震災をきっかけに大きな転機を迎えました。被災聴覚障害者の生活状況把握のために現地調査に赴いた舘脇さんらは、想像を超える困難な状況を目の当たりにしたそうです。「被災地では情報発信のほとんどが音声によるものです。聴覚障害者はサイレンや災害放送が聞こえずに逃げ遅れてしまったり、呼びかけが聞こえなくて救援が遅れてしまうケースが珍しくありません。避難所ではコミュニケーションに壁があるために必要な情報やサービスが受けられず、孤立してしまったり、十分な支援を受けられないリスクもあります。例えば避難所で『お弁当を配布します』とか、『毛布が欲しい人は取りに来てください』という場内放送があっても聞こえないので気が付かず、空腹や寒さに耐え続けた方もいらっしゃいます」。
加えて舘脇さんらが痛感したのは、圧倒的なマンパワー不足でした。
「被災地では、普段なら比較的スムーズに受けられる手話通話や要約筆記などが受けられないケースが多く、一般的な支援ネットワークによる個別援助方法(障害者総合支援法事業における計画相談、福祉サービス利用事業所、民間のこころの健康相談統一ダイヤル等)も通用しない状況が多くみられました。さらに手話通訳者自身も被災者となっており、人手不足によるジレンマを抱えている状況でした」。

このときの経験を教訓に、舘脇さんらは支援体制の拡充と人材の育成に着手。2011年7月には日本財団から助成を受けて東日本大震災被災聴覚障害者相談支援事業聴覚サポート「なかま」事業をスタート。東日本大震災の被災地に会員である社会福祉士、精神保健福祉士を派遣し、支援活動を行いました。12年には研修会を実施、翌年13年からは各地の仲間と連携して聴覚障害者相談支援事業を全国に展開しています。全国の社会福祉士や精神保健福祉士資格保有者に事業への参画を呼び掛け、希望者には手話など聴覚障害者とのコミュニケーションについての研修会も行う体制を整えました。その結果、少しずつ活動の輪が広がり、会員は109名(うち聴覚障害のある会員36名)に上っています(2024年3月現在)。
日本財団の支援で、能登半島地震被災地への訪問支援を実践

そして東日本大震災から13年後、2024年1月に能登半島地震が発生。舘脇さんらは東日本大震災以降に培った人脈やノウハウをフル活用して、発災直後から情報収集と準備を始めました。発災当時、能登半島在住の聴覚障害者(身体障害者手帳保持者)は約270人、そのうち約50人は1週間ほどで無事に生存が確認できたものの、残りの200人について当初は状況が確認できていない状況だったそうです。
また、もともと奥能登地域には自治体設置手話通訳者が4名いましたが、自宅倒壊や集落孤立で身動きができない、携帯電話の電波が通じないために連絡が取れないといった理由で、すぐには支援活動が行えない状況でした。そこで石川県聴覚障害者協会では、石川県が金沢市内に設置する1.5次避難所(被災地の避難所から被災地外の避難所に移動するまでの一時的な避難所)に聴覚障害者を集約するよう要望。ここに手話通訳者を常駐させて、聴覚障害のある皆さんの支援に当たることで、一人ひとりが「今、何が起きているのか」、「何をしなくてはいけないのか」を理解できるようにサポートしました。石川県では2007年にも大きな地震が起きており、その際の教訓を生かした災害時の対策が進んでいました。そのため、安否確認や1.5次避難所への集約など聴覚障害者の孤立を防ぐ取り組みが比較的にスムーズに行われたといいます。
しかし、人間は誰しも環境の変化によるストレスを感じてしまうもの。被災生活が長引くにつれてメンタルケアの必要性が指摘されるようになり、現地から舘脇さんら聴覚障害ソーシャルワーカー協会への支援要請がありました。協会は、日本財団を通じた能登半島地震支援のためのご寄付による支援を受けて、被災地訪問事業を実施。2024年5月15日~7月31日まで実施した第1期支援では実態調査を兼ねて、能登の就労支援事業所「やなぎだハウス」に通所する利用者との面談を行いました。「皆さんとお話をした結果、利用者と支援者計16名の方々に継続的なメンタルケアが必要なことがわかりました」と舘脇さん。「家族や知人を亡くした悲しみを抱えた方、倒壊した自宅の再建など、今後の生活への不安を抱えている方など、それぞれが様々な想いを抱えています。私たちソーシャルワーカーは皆さんとの対話を通じてニーズを把握し、不安やストレスを吐き出してもらいながら、次のステップに進めるよう支援していくのですが、被災者の皆さん(特に高齢の方々)はとても我慢強くて『今はみんなが大変なときだから、私だけわがままを言えない』と多くを語りません。私自身も『もっと対話のスキルを高めていかねばならない』と痛感しました」。
もう一つ、今回の支援事業で痛感したのは、障害を抱えた人への支援にあたる方々に対するケアの大切さでした。同協会の監事で舘脇さんらとともに能登半島地震被災地への訪問に従事した竹林伸子さんは「私たちのような『よそ者』の存在が役に立つ場面もあることを改めて学びました」といいます。忘れられないのは、ある支援員の方のこと。「能登は高齢化が進んでいるため、被災者も支援員も高齢の方が多いのですが、その中で頑張って活動をしていました。しかし、お話を伺ってみると、周囲からの期待の大きさや求められる業務の多さ、そして何より自分自身の『頑張らなくては』というプレッシャーでかなり追い詰められており、涙を流しながらため込んでいた気持ちを吐き出してくれました。誰もがギリギリの状態での暮らしを余儀なくされている中、身近な人にはなかなか吐き出せない思いを受け止め、共感することができるのも、私たち『よそ者』の役割。引き続き、聴覚障害者の方だけでなく支援者の方にもしっかり寄り添っていきたいと思っています」。

大切なのは立ち続けること。「立ちすくみながらも立ち尽くす」を実践したい
第1期の支援期間終了後の2024年9月に能登が豪雨災害に見舞われたまま、一時活動をストップせざるを得ませんでしたが、10月末からソーシャルワーカーの派遣を再開、現在は第2期の支援活動に取り組んでいます。第1期は被災地の方々の現状と課題の把握に重きをおいて活動していましたが、第2期はもう1歩進んで課題解決に向けたアクションの支援も行いたいと話す舘脇さん。地震発生から1年を経た今も、聴覚障害者を含め多くの被災者が生活再建の見通しがなかなか立たないまま不安な生活を余儀なくされています。「震災に続いて豪雨被害の影響も大きく、現地の支援者の皆さんが本当に疲弊しています。支援者の皆さんの力なくしては、私たち外部からの支援が入ることも難しいので、今後は支援者の皆さんが休めるような体制の構築の必要性も実感しています」と舘脇さん。さらに、次なる災害に備えて、災害ソーシャルワーカーへの養成や地域のDWAT(災害派遣福祉チーム)との連携・協働体制構築やDPAT(災害派遣精神医療チーム)に関する提言などにも取り組んでいきたいと考えているそうです。
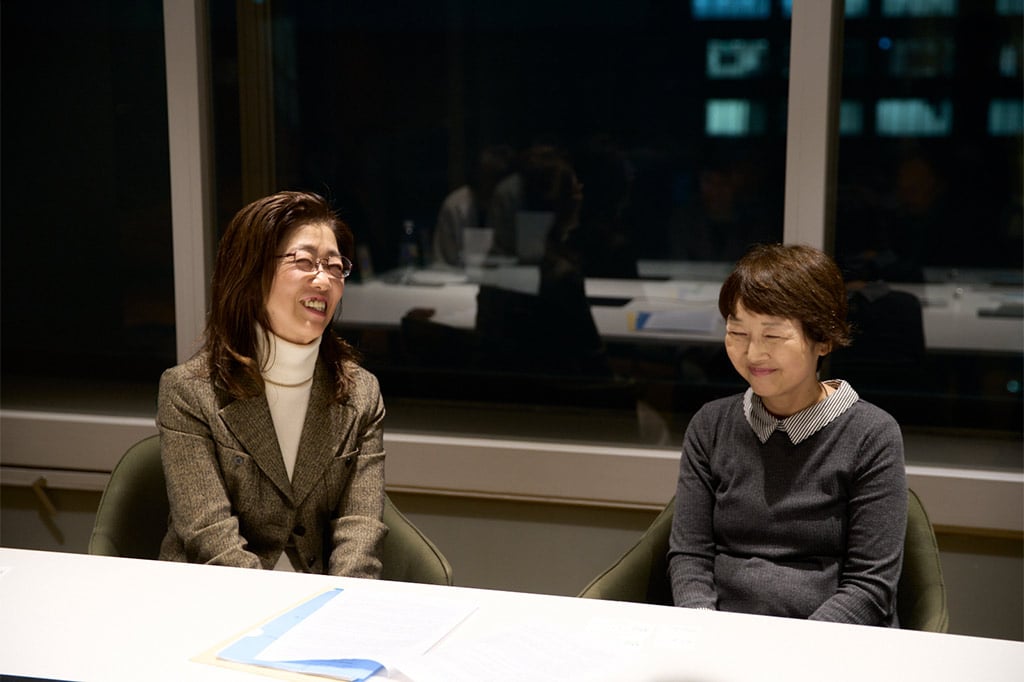
「復興への道のりの遠さ、取り組むべき課題の多さ・大きさに、正直、立ちすくんでしまいそうになることもあります」という舘脇さんを支えているのが、大学時代に出会い、今は座右の銘としている『立ち尽くす実践』という言葉です。「聴覚障害ソーシャルワークの実践にあたっては、私自身が聞こえない当事者として壁にぶつかることも多々あり、心折れて立ちすくんでしまうこともあります。でも、立ちすくむことはあっても逃げ出さないで、せめて立ち続ける自分でありたいと思っています。今、私たちソーシャルワーカーにできることは現場経験を積み、災害に特化した研修を受け、さらに研鑽を積むことです、これもまた、立ちすくみながらも立ち尽くす(立ち続ける)の実践。日本財団を通じて寄せられた皆さまの寄付・ご支援の気持ちを励みに、これからも協会のメンバー一同が力を合わせて頑張ってまいります」。





