医療・福祉の専門知識を活用した避難所運営

平成30年7月豪雨災害により自宅に住めなくなった被災者の多くは、避難所生活を余儀なくされます。ある日突然、多くの人が共同生活を送ることになる避難所の環境を整えることは、被災地の復旧・復興を考える上でも欠かせません。そして避難所の環境を改善していくにあたっては、専門知識を持つ支援者の存在が重要になります。
避難所で重視される被災者の健康管理
「県外からも医療・福祉の専門家の方が多くいらして、避難所で暮らす方々へ健康に関するヒアリングを行っています」
日本財団の先遣隊として被災地のニーズをヒアリングしている渡嘉敷唯之さんが、避難所で行われる健康管理について説明してくれました。
渡嘉敷さんは一般社団法人ピースボート災害ボランティアセンター(以下、ピースボート)の方々とともに、倉敷市真備町の二万小学校で避難所の運営を支援しています。

真備町では町の大部分が浸水被害に遭ったため、多くの被災者が避難所での生活を余儀なくされました。二万小学校でも200人弱の被災者が、避難所となった体育館と校舎で生活しています。
避難所では被災者が体調を崩さないような管理体制を維持する必要があります。そこで日本赤十字社や災害派遣福祉チームなど、医療・福祉の専門家が避難所生活を送る被災者の健康を維持するために、アドバイスをしてくれます。
「これから避難所にダンボールベッドを導入するところです。床の上に直接シーツを敷くと、床に積もった粉塵を吸い込んでしまう可能性があるので、ベッドのほうが健康的です。また、この避難所には高齢者の方も多いので、ダンボールベッドを導入すれば寝ていても起き上がりやすくなるという利点もあります」
渡嘉敷さんと一緒に避難所運営を行っているピースボートの方が、避難所にダンボールベッドを導入する理由を説明してくれました。

ダンボールベッドを導入するにあたり、被災者の方は一度、自分たちの荷物を別のところに移しました。そして体育館の床を掃除した後にダンボールベッドを敷き、その上に再度、自分たちの荷物を置くという作業を行いました。

ダンボールベッドの導入に合わせて避難所のレイアウト変更も行い、憩いのスペースを設けるなど、被災者の方々のコミュニケーションを促進するための取り組みも行われるとのことです。
また、被災者の中には日中、浸水した自宅で土砂の撤去作業を行い、昼食にいったん避難所で休憩してから自宅に戻り、夜間になると寝るために帰ってくる方が多くいらっしゃいます。撤去作業をするために被災者の方も作業着を着たりしますが、作業着のまま避難所の中で飲食をすると不衛生なので、炊き出し場所の横に飲食スペースを作り、飲食は外で行うようにするなどの対策も取られていました。

被災者の方々にとって避難所とは、災害から復旧・復興し、生活を再建していくためのベースとなる場所です。そのベースを運営面から支えていく上でも、二万小学校の避難所のように医療・福祉の専門知識が必要になります。
被災者と避難所を支える「まちづくり推進協議会」
二万小学校の避難所では運営体制が徐々に出来上がりつつありますが、支援団体以外にも、避難所運営を支える組織として「まちづくり推進協議会」があります。
「まちづくり推進協議会」とは地域住民で構成される自主的な組織であり、平時にはお祭りなどを通して住民の交流を図り、災害時には「何でも屋」のような存在として、地域の様々な課題の解決に取り組みます。
「とにかく避難所にいる人たちを元気づけること。そのためには相手の話を親身になって聞いてあげることが大切」
二万小学校の避難所運営を支える「二万地区まちづくり推進協議会」の神崎さんは、被災者の方々を元気づけることの重要性をそう表現します。

神崎さんによれば発災直後、浸水した家に取り残された方々を自衛隊などがボートで救出し、二万小学校の避難所に連れてきたものの、その後どうすればよいか四苦八苦されたそうです。
「避難してきた人たちの体がびしょ濡れだったので、とにかくタオルとスリッパを渡して、必要な物資を集めるために町内アナウンスで呼びかけを行いました」
二万小学校の避難所に外部からの支援が届いたのは、災害が発生して数日が経ってからのことでした。
被災地で必要不可欠な専門的支援
「当初は300人の被災者の方を受け入れる計画だったのですが、実際には2,000人近くの方が避難されてきて、完全にキャパシティオーバーでした」
真備町の避難所の一つである岡田小学校の狩野隆校長先生は、被災した方々が避難して来た当時の様子を説明してくれました。
体育館だけでは入りきらなかったため、岡田小学校ではすべての教室を開放し、とにかく被災者の方を受け入れて何とか朝を迎えることができたそうです。
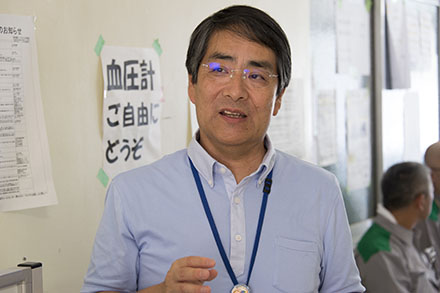
その後、様々な支援団体が入ることで、少しずつ避難所の運営体制が出来上がりました。また、岡田小学校でも二万小学校と同じように、被災者の健康を管理するために日本赤十字社や災害派遣福祉チームなど、医療・福祉の専門家が支援に入りました。
こうした専門家のアドバイスに従い、最初は土足だった校舎内を感染症のリスクを考えて上履きに変えたり、夜間の医療・福祉体制の整備を行ったそうです。

避難所運営に限らず、被災地では専門的な知識を持つ支援者が不可欠です。日本財団では医療、福祉、水害対応など専門支援を行うボランティア団体やNPOなどに対し、支援金を交付することで被災地の復旧・復興を後押ししていきます。
取材・文:井上 徹太郎(株式会社サイエンスクラフト)
写真:和田 剛





