未来のために何ができる?が見つかるメディア
価値観が合うかが最大のポイント。「NPOに就職する」という選択

- 社会課題への関心は世間的にも高まっているものの、人材不足という課題を抱えているNPOは多い
- NPOへの就職が成功するかどうかは、その団体と自分の価値観が合致しているかが重要なポイント
- 副業やプロボノ(※)などを通してソーシャルセクターに多様な人材が入ることは、NPO側の経験値を高める上でもとても重要
- ※ 職業上のスキルや経験を活かして、社会貢献活動を行うこと
取材:日本財団ジャーナル編集部
さまざまな社会課題の解決を目指し、活動するNPO。そんなNPOを運営する上で課題となりやすいのが人手不足だという。内閣府の「2023年度(令和5年度)特定非営利活動法人に関する実態調査」(外部リンク/PDF)によると、認定・特例認定法人では、法人が抱える課題について、「人材の確保や教育」と答えた団体が70.6パーセントとなった。
人手不足の状況が生まれるのは、NPOへの就職がまだ一般的ではなく、キャリアの選択肢としてハードルを感じる場合があることも要因の1つだろう。
この記事では、特定非営利活動法人ETIC.(外部リンク)が運営する、NPOなどのソーシャルセクター(※)向けの転職支援サービスDRIVEキャリア(外部リンク)で、求職者と団体のコーディネーターを務める腰塚志乃(こしづか・しの)さんに、一般企業への就職との違い、NPOへの就職を成功させる秘訣などを伺った。
- ※ NPOやNGOなど社会課題解決を目的とした組織や団体のこと
NPOへの就職でもっとも重要なのは、「価値観」の一致
――まず、DRIVEキャリアについて教えてください。
腰塚さん(以下、敬称略):NPOなどの社会課題を解決する仕事に特化した、転職支援サービスです。主なサービスの軸は2つあり、エージェント契約を結んだ団体と求職者のコーディネートを行うエージェントサービスと、サイト上の求人広告となっています。

――DRIVEキャリアの運営を始めた理由は。
腰塚:運営元のETIC.が起業支援や起業家教育から活動をスタートしていて、その中でもNPOや、社会起業家の方に対して支援を行う機会が多々ありました。
そのつながりで起業後にお話を伺うと、事業が成長していく中で皆さんが課題になると感じていたのが、人材不足や人材のアンマッチが起きてしまうという問題だったのです。そこで、何か支援ができないかと考えて、2013年に立ち上げたのが、社会課題解決の仕事に特化した転職サービス「DRIVEキャリア」でした。

――ソーシャルセクターに特化した求人ということですが、求人情報にはどんな特徴があるのでしょうか。
腰塚:ソーシャルセクターへの転職は、スキルと条件をベースに就職先を決める一般企業への転職とは違い、社会に対する価値観や、つくっていきたい未来に対しての思考がフィットしているかどうかがとても大事になります。そのため、「DRIVEキャリア」の一番の特徴として、各団体が取り組んでいる社会課題や、大切にしている価値観を分かりやすく示しています。
求人を掲載していただく団体の方にも、タイトルにはどんな社会課題に向き合っているのか、その中で採用された方にはどういった役割を担ってほしいのか、この2つの要素を必ず入れるようにお話ししています。


――役割というと、職種とは違うのでしょうか。
腰塚:そうですね、職種というより、「コーディネーター」「業務改善」「リサーチ、分析」など能力や得意分野でしょうか。
ソーシャルセクターへの転職の場合、ビジネスセクターと比べると市場が小さいこともあり、転職者はキャリアチェンジによってこれまでとは違う職種で働き出すことがとても多いんです。そのため、応募される方のベースにある能力や得意な分野を把握することで、求職者、団体・企業ともに納得できる採用になるよう工夫をしています。
NPOへの関心は増加傾向。価値観との相性が転職成功の鍵に
――腰塚さんはコーディネーターとして、求職者の方のお話もよく聞かれるとのことですが、NPOへの就職を考えている人が、不安に感じる要素にはどんなものがありますか。
腰塚:給与水準が低いのではないかというような、条件面を気にされる方はやはり一定数いらっしゃいます。しかし、それ以上に私がコーディネーターの現場で聞く声の中で多いと感じるのが、募集内容を読んでも自分に合う仕事・団体なのかが分かりにくいということです。
ビジネスセクターの仕事は、大半の仕事が市場化されているため、求人を見れば仕事内容まで想像できると思います。一方、ソーシャルセクターの場合、例えば「貧困状態にある子どもを支援するための資金調達担当」と仕事内容を書かれていても、それがどんな仕事を意味するのか一般の方には分かりづらいという点があります。
また、応募したい団体が財務上でも信用できる組織なのか、経営的に不安要素はないか、など目利きが難しいといった声も多いです。「会計データは公表されてはいるものの、健全なNPO運営なのかは見ても分からない」と。
――そういった不安は、団体の方と直接お会いして話すことで解決できるのでしょうか。
腰塚:そうですね。ただ、団体の職員に、直接聞きづらいこともあるので、そういうときにこそ私たちコーディネーターの出番かなと思っています。事前のキャリア相談をしっかり行い、今回の転職で大切にしたい価値観などを確認したうえで、相性が良いと思われる転職先を紹介しています。

――ちなみにNPOの給与水準は、やはり一般企業と比べると低いのでしょうか。
腰塚:それがそんなこともないんです。2017年と少し古いデータにはなりますが、新公益連盟のソーシャルセクター組織実態調査2017(外部リンク/PDF)によると、ソーシャルセクターの平均年収は339万円なのに対し、一般中小企業では292万円と、給与面ではソーシャルセクターが上回っていることが分かりました。
ここ10年ほどで、処遇の良くなったNPOが増えていて、私たちの扱っている求人での相場では、NPOで働く層の20代の年収は250~400万円程度、30代~50代の一職員は400~600万円程度、マネジメント層であれば600~800万円程度と、一般企業と比べても大きな違いを感じることがなくなっています。
――では、NPOで働きたいと思っている人は増えているのでしょうか。
腰塚:私たちの体感として、社会課題解決への関心を持っている人、社会課題解決を仕事にしたい人の割合は確実に増えていると考えています。10年前なら、「NPO 転職」と検索する人はほとんどいませんでしたが、現在は検索数が大きく増えていることを表すデータも公開されています。
――DRIVEキャリアへの相談者は、どんな年代の方が多いですか。
腰塚:20代から30代を中心に、最近3年くらいは、40代後半から50代の方のNPOに対する転職への関心がとても高まっていると感じています。
要因としては早期退職が増えていること、また、、60歳を迎えても雇用を継続したり、別の仕事に就いたりする方も多いなど、現役世代の幅がとても広くなっているからではないかと考えています。
60歳の少し先に自分のゴールを設定したときに、「自分は何をしたいのか」を改めて考えた結果、社会貢献につながり、やりがいを持てる仕事を選ぶ人が増えてきているように感じます。
垣根を超えてNPOに入ってくる人が増えれば、社会課題解決にも良い影響が期待できる
――NPOへの就職がうまくいくのは、どんなケースが多いのでしょうか。
腰塚:気になる団体が取り組む課題への思いが強いかどうかよりも、団体との価値観が合っているかを重視した方が、活躍できる確率が高まると思っています。
また、自分が仕事において幸せを感じるポイントが、団体の仕事でどれだけ重なり合うかも、とても重要な視点だと思うんです。私は個人的に、仕事というのはやはり、自分が幸せになるためにあるものだと思っています。自分の仕事がどのくらい社会的に価値があるかということに偏り過ぎず、自分が幸せを感じられる仕事を選ぶとうまくいくのではないでしょうか。
――NPOで働く人材がを増えるためには、どういったことが必要でしょうか。
腰塚:NPOへの転職をすることも、もちろん素晴らしい選択です。ただ、NPOに携わる方法は他にもたくさんあります。例えば、ボランティア、プロボノなどを通して、一歩を踏み出す方が増えるとよりいいと思っています。そんなふうに少しずつ点を打つように経験を積んでいくことで、自分に合った方向へと進んでいけるはずです。
ETIC.では、副業で地方企業の課題解決を行う「YOSOMON!」(外部リンク)や、ソーシャルセクターに3カ月間参加できる「Beyonders」(外部リンク)などのプロジェクトも運営しています。まずは、こういった機会を活用しながら、小さく前進していただけたらと思っています。
社会課題の解決には、ソーシャルセクターにさまざまな人が流動的に入ってきて、団体のノウハウや経験値が上がっていくことがとても重要だと思います。気軽にNPOを体験してみることが、その一歩となるはずです。
編集後記
なんとなく「怪しいかも……」という思いから、NPOへの転職をちゅうちょしてしまう人もいるのではないでしょうか。
腰塚さんに「なぜNPOが怪しく思われるのか」と聞いてみると、「いいことをやっているはずのNPOがメディアに出る際には、不正にお金を使っていたなど、ネガティブな取り上げ方をされることが多いからでは?」との回答でした。
ニュースに耳を傾けることももちろん大切ですが、そういった団体はごく一部のはず。自分の足でさまざまなNPOに出会い、体験してみることは、NPOの実像を知り、その仕事のやりがいに気づけるいい機会となるのではないかと感じました。
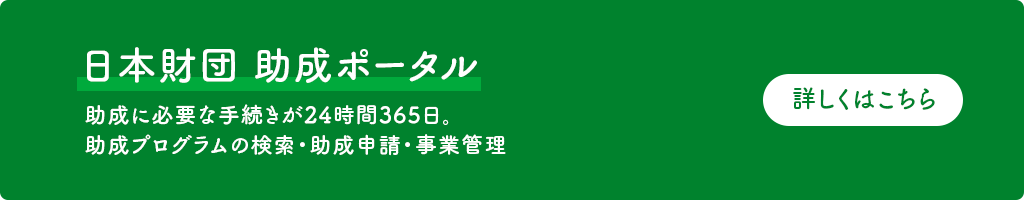
- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。













