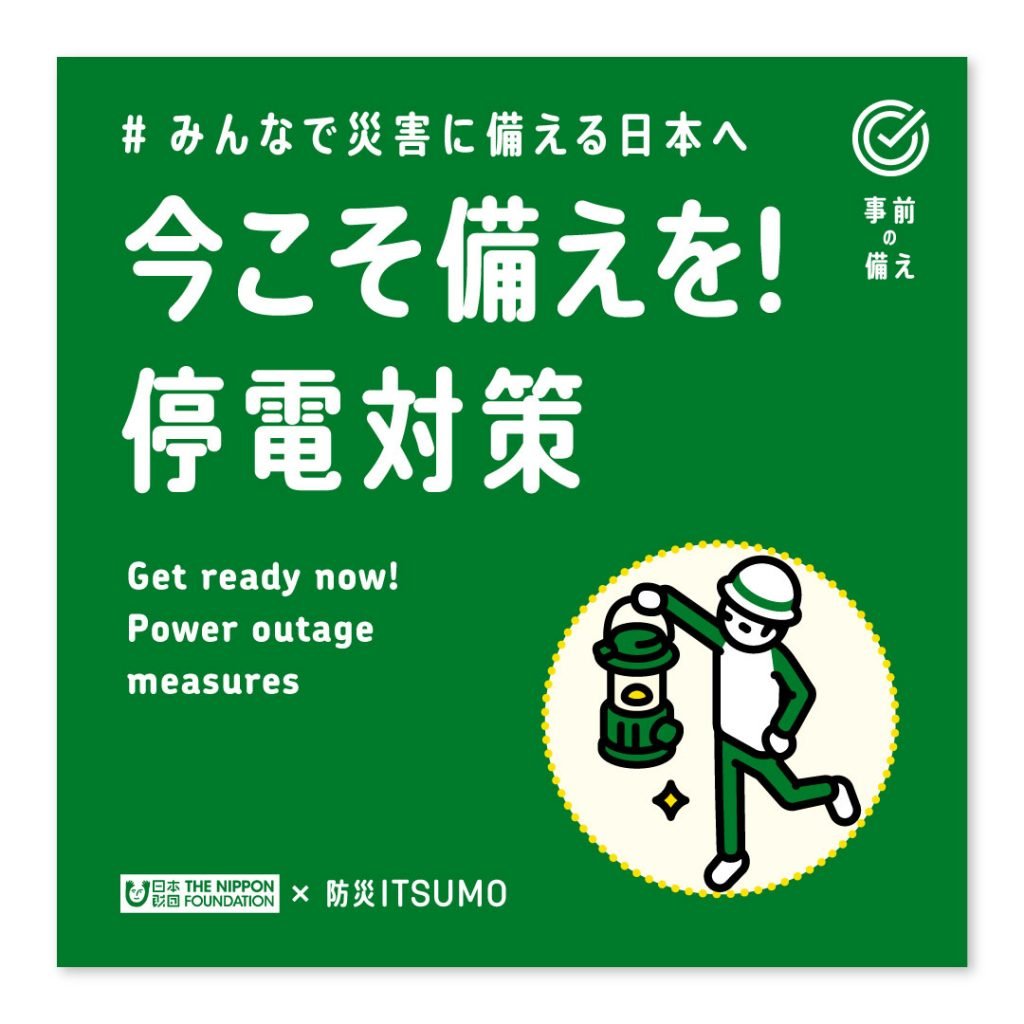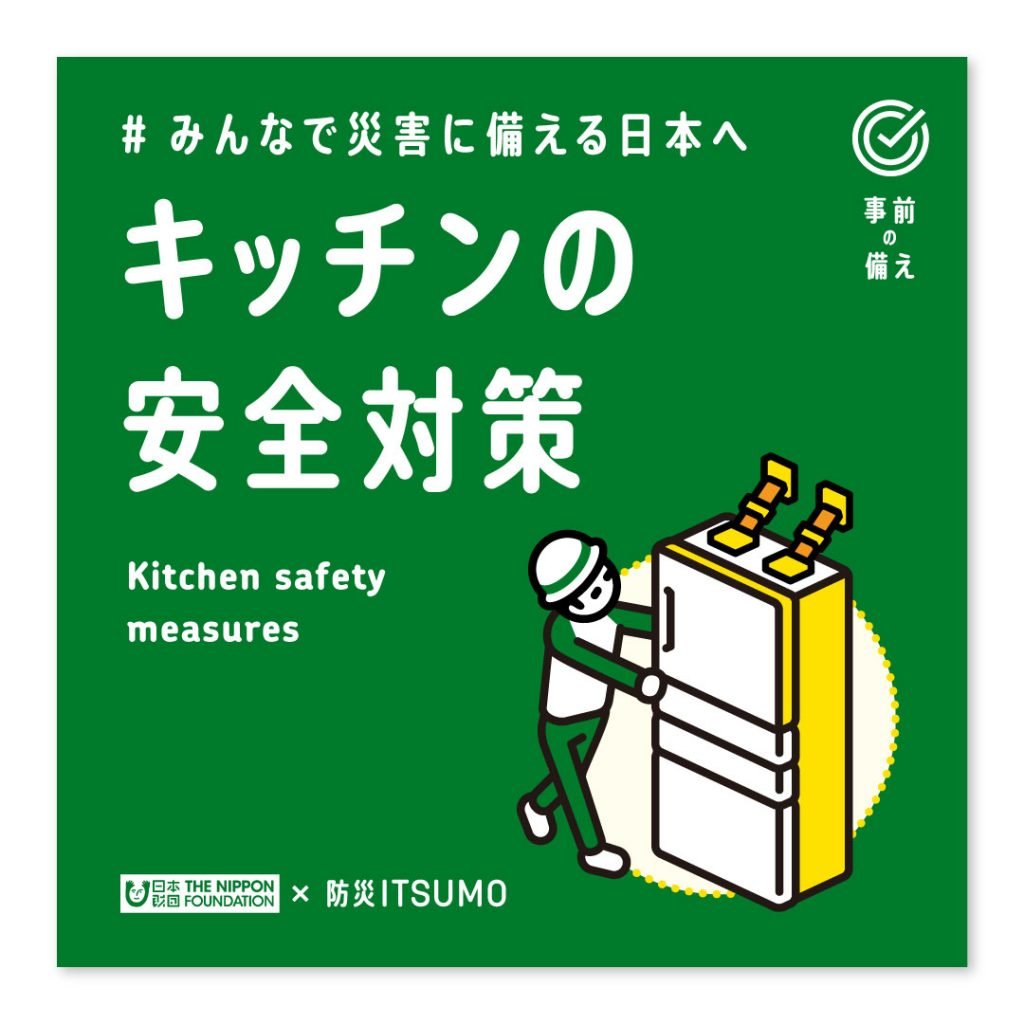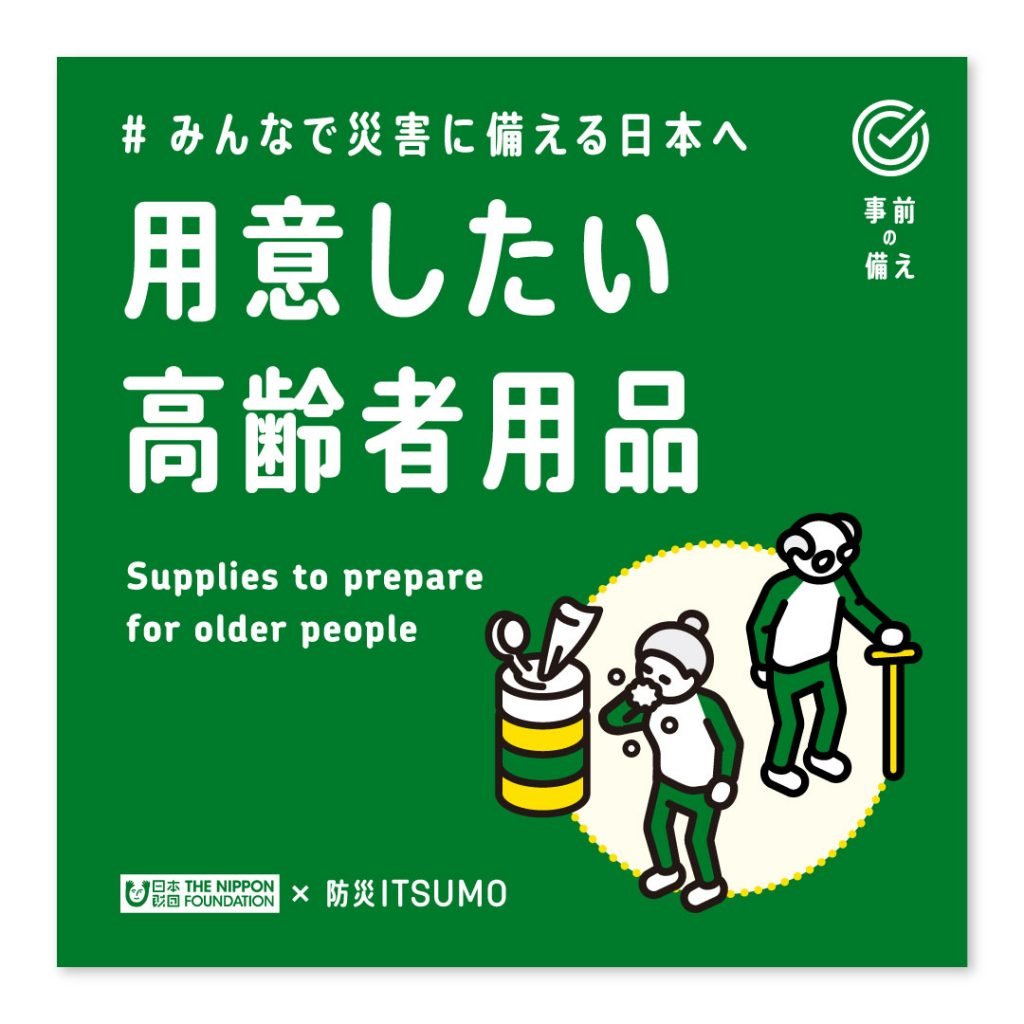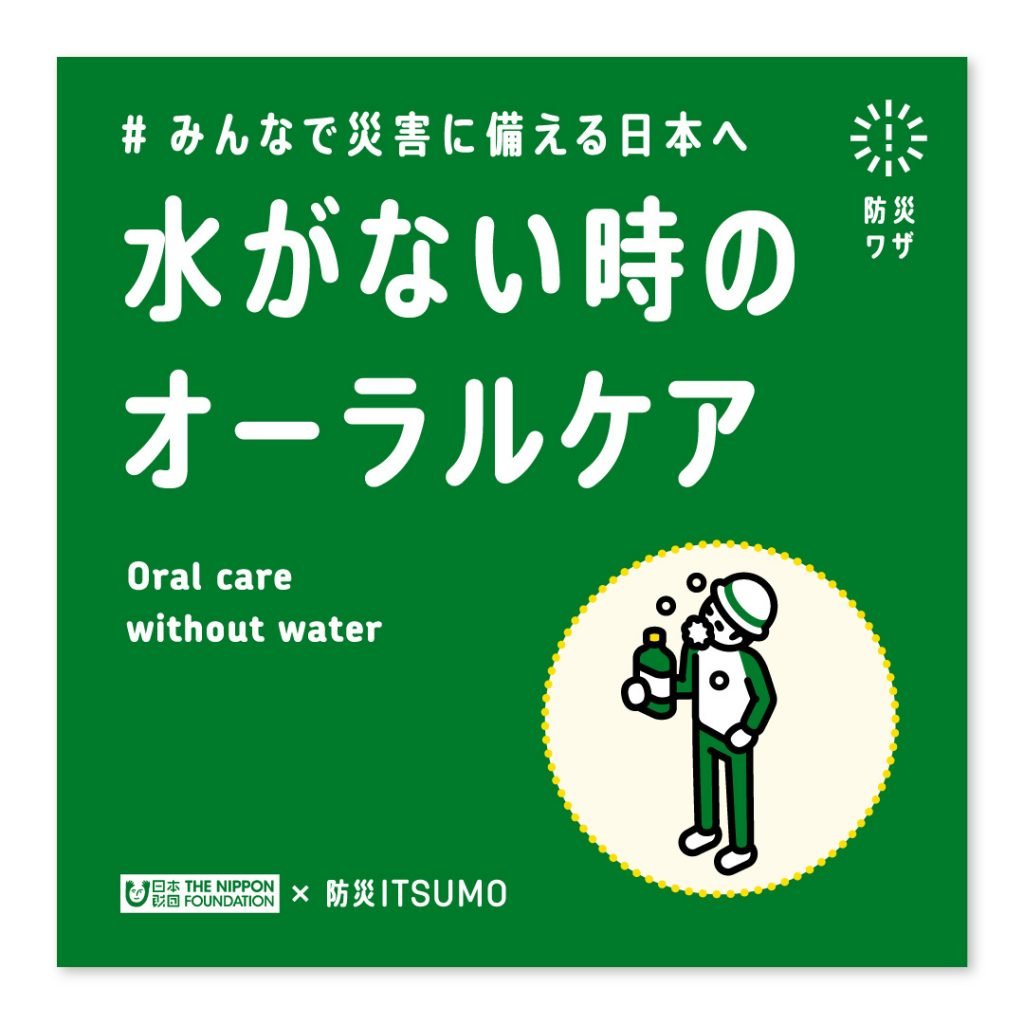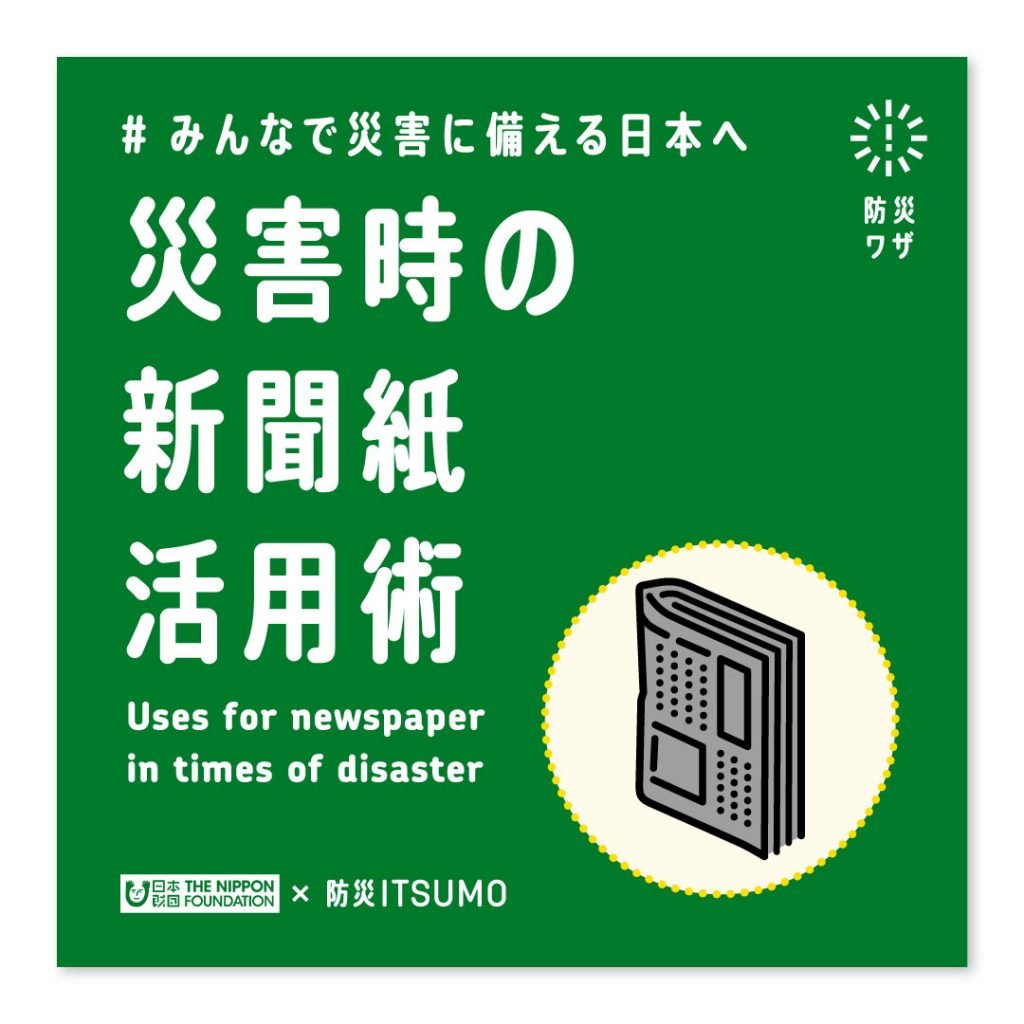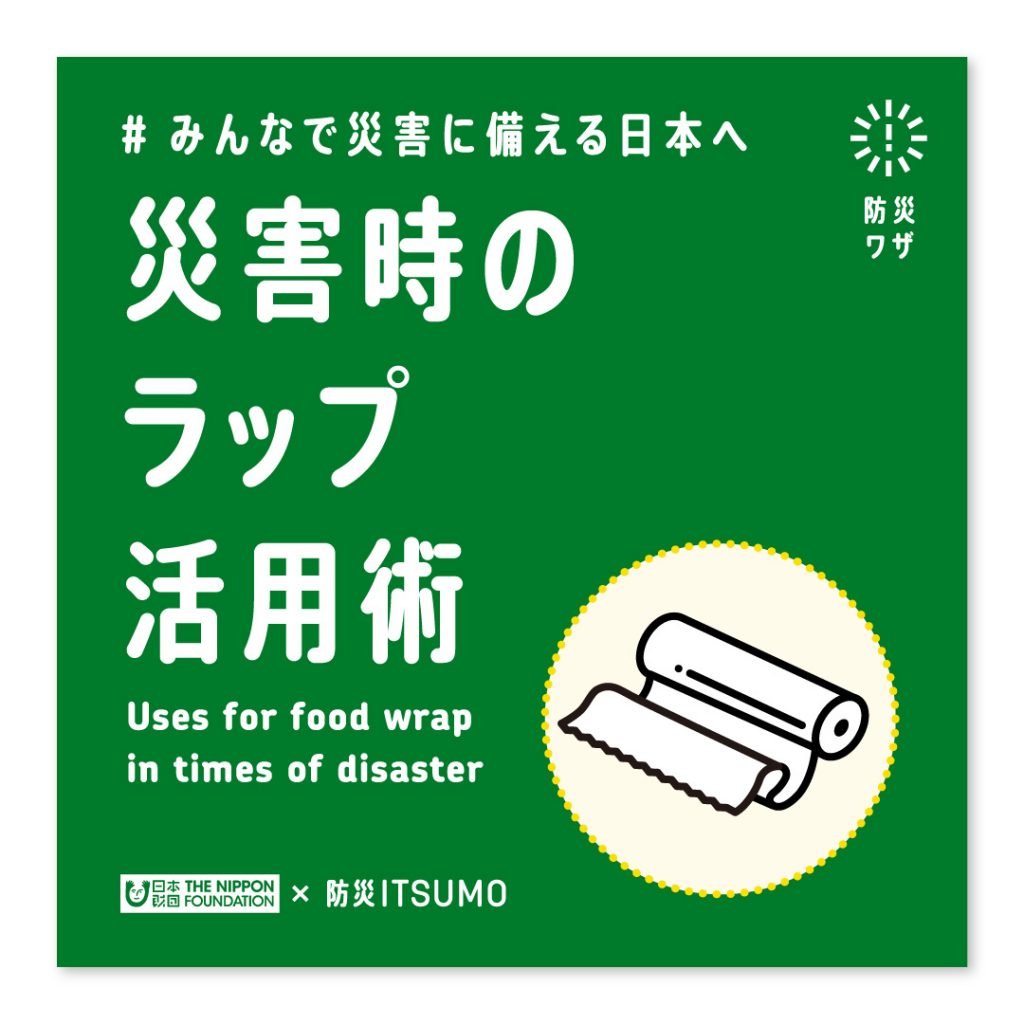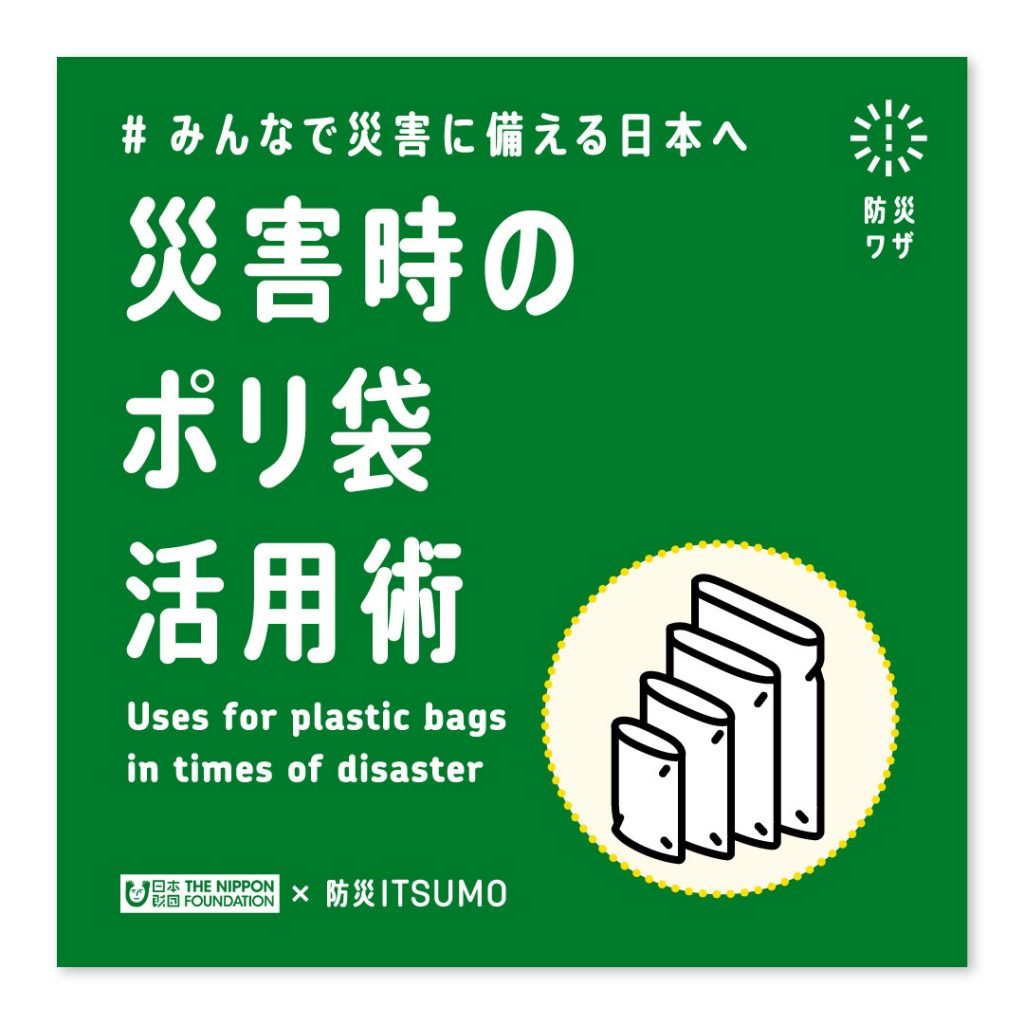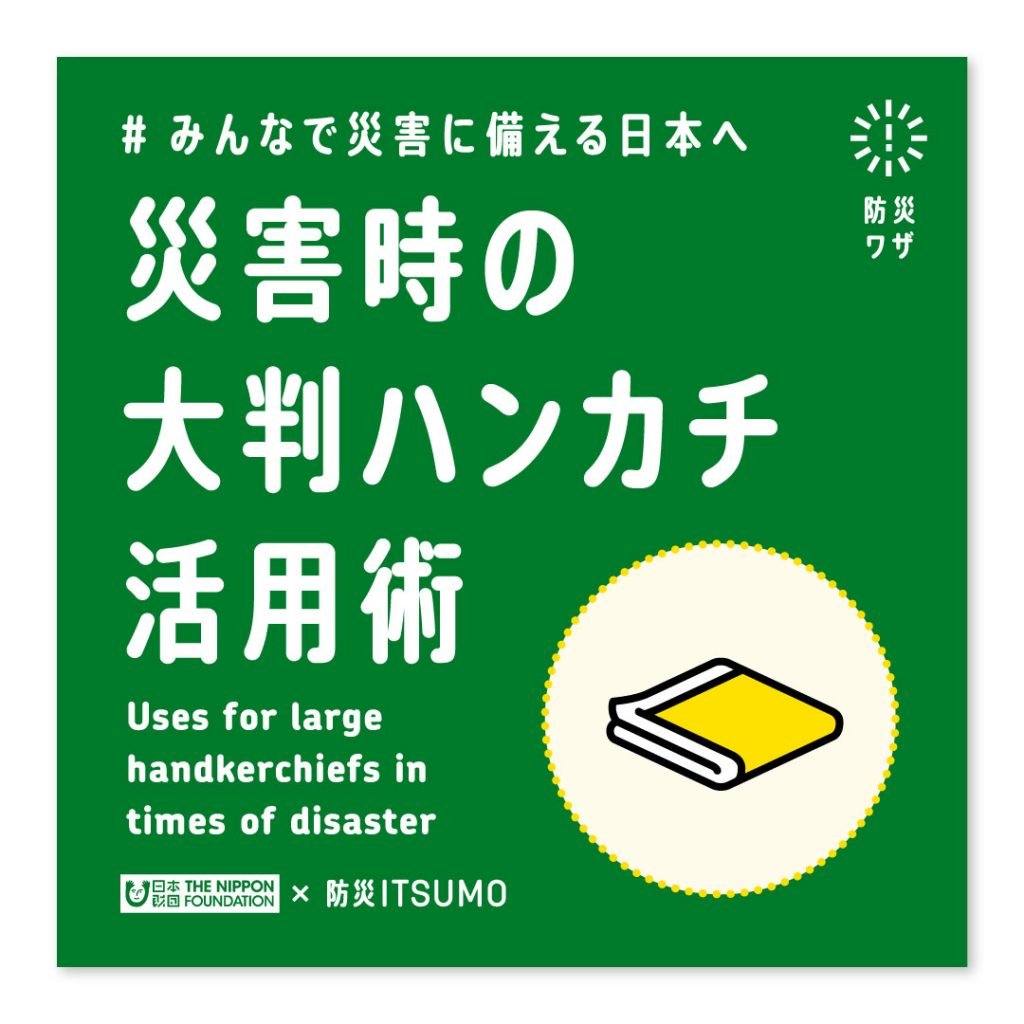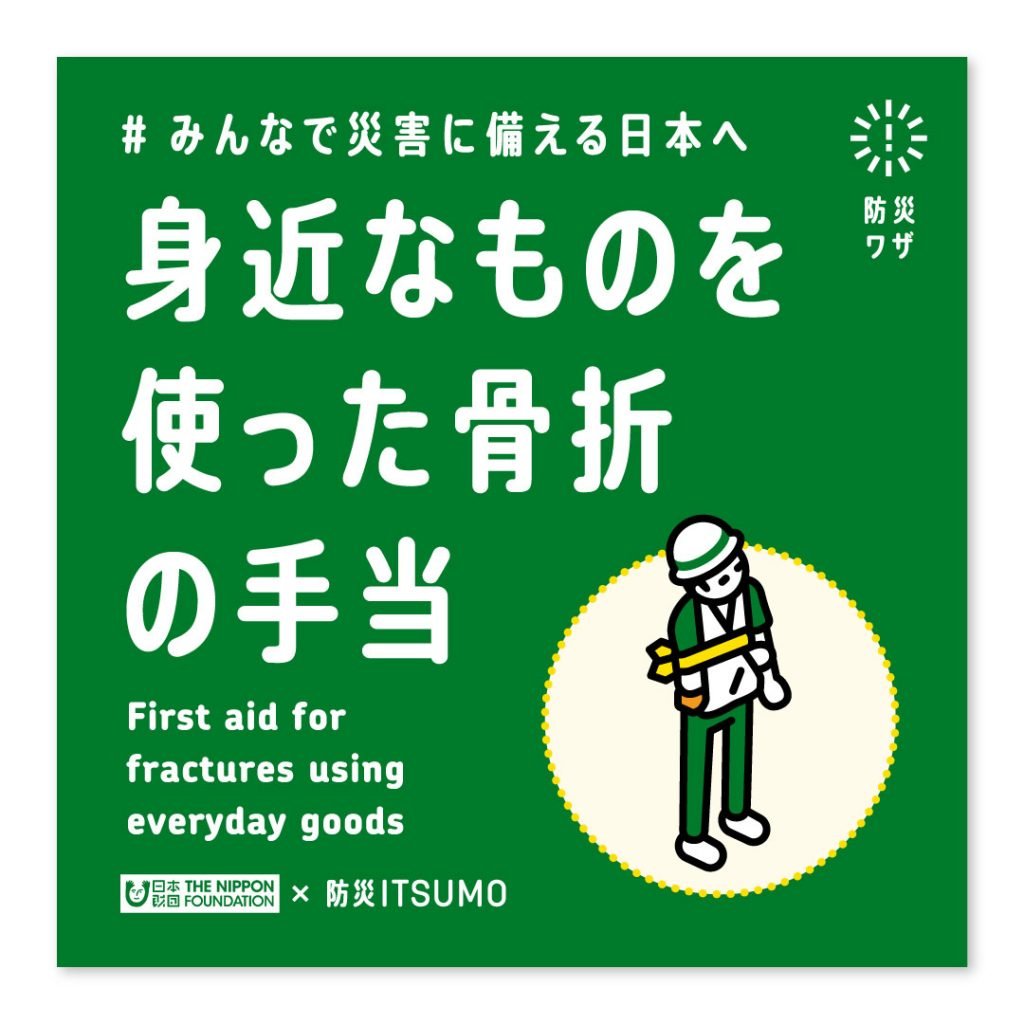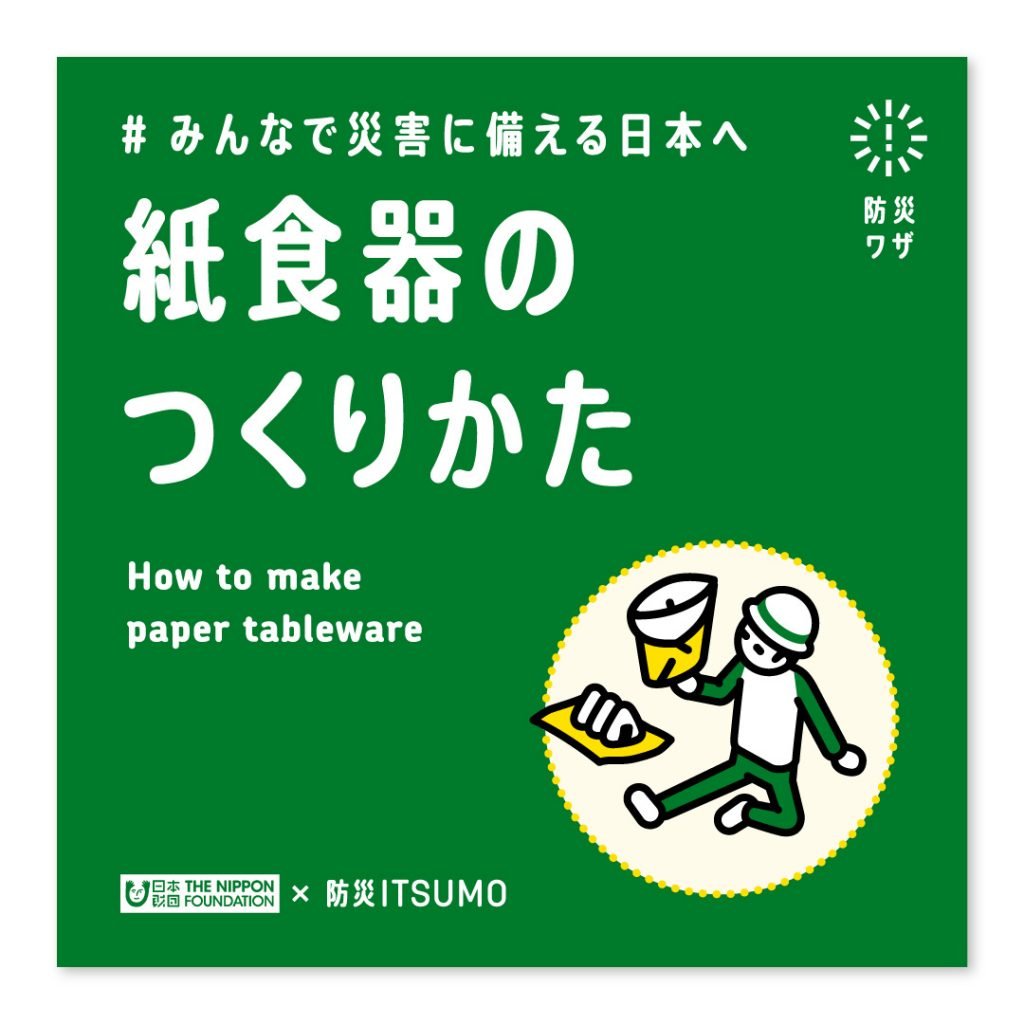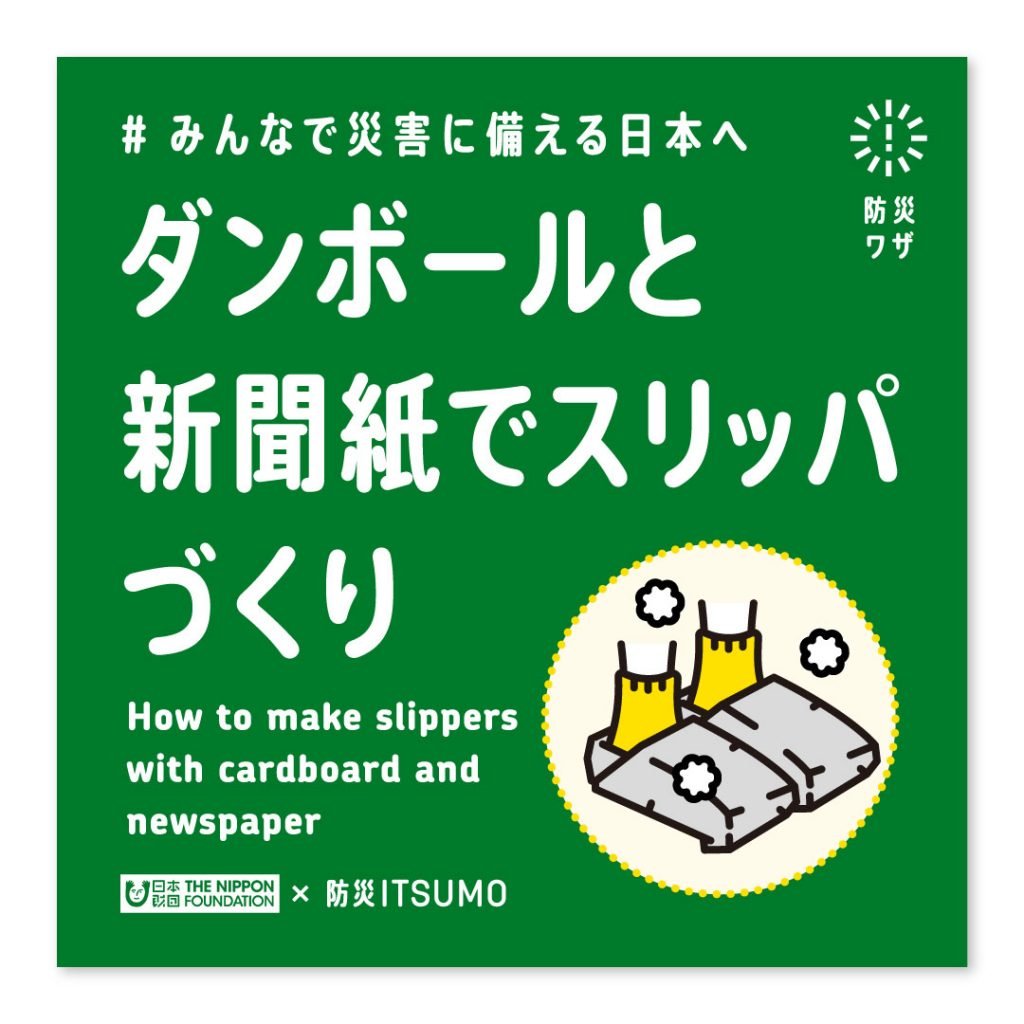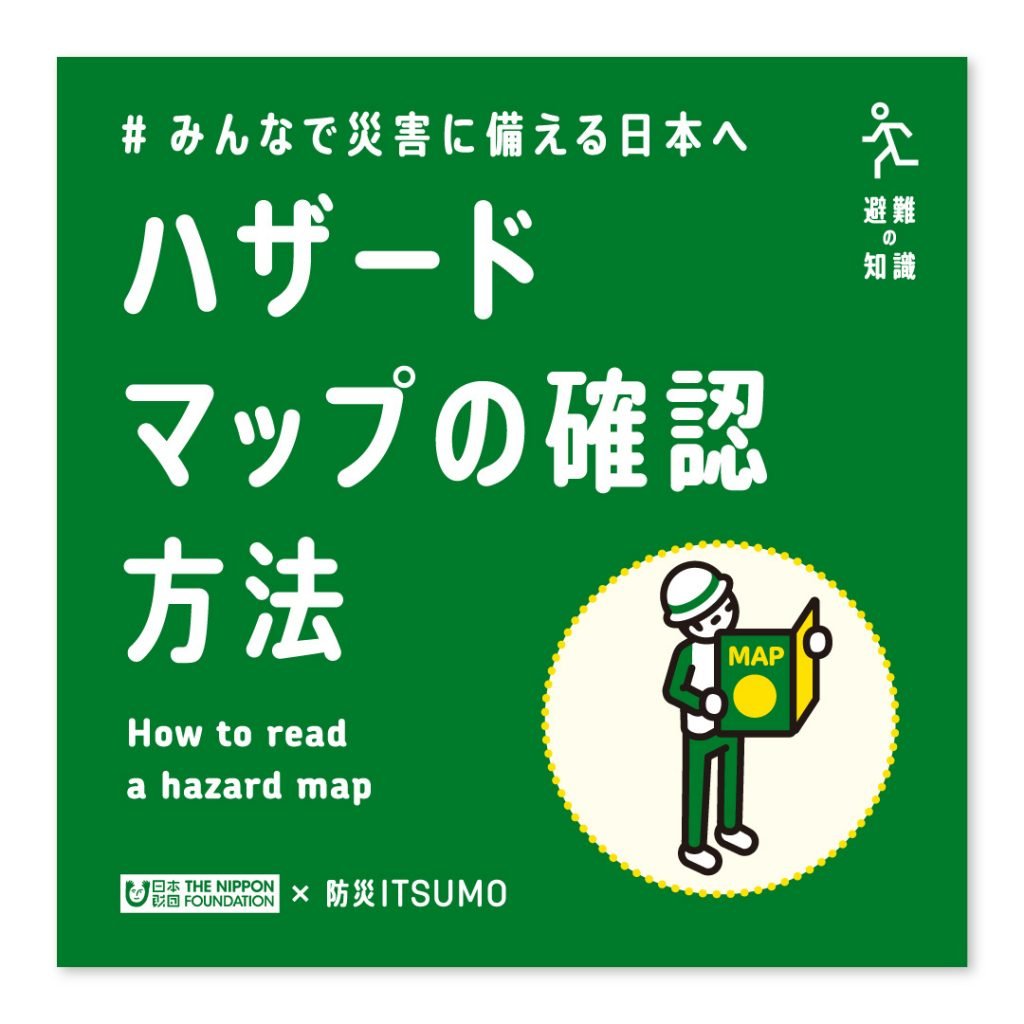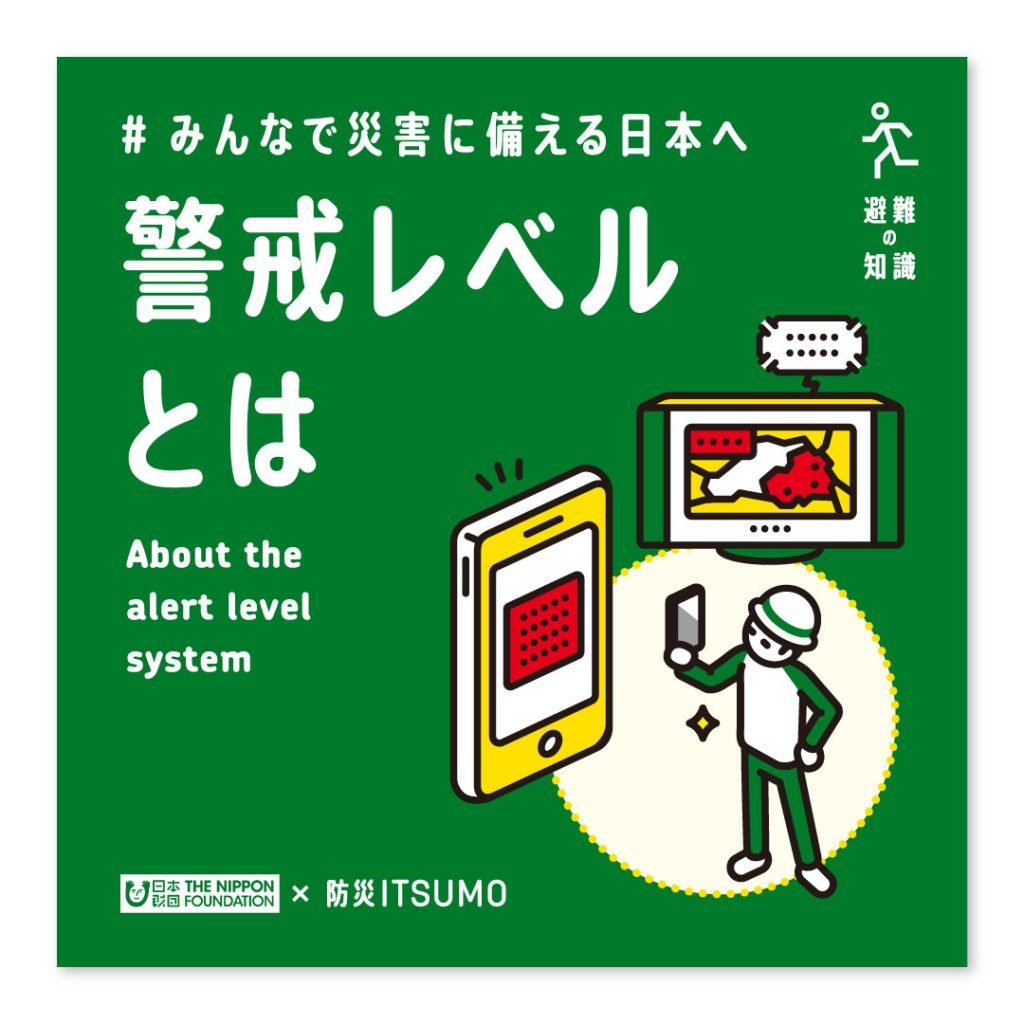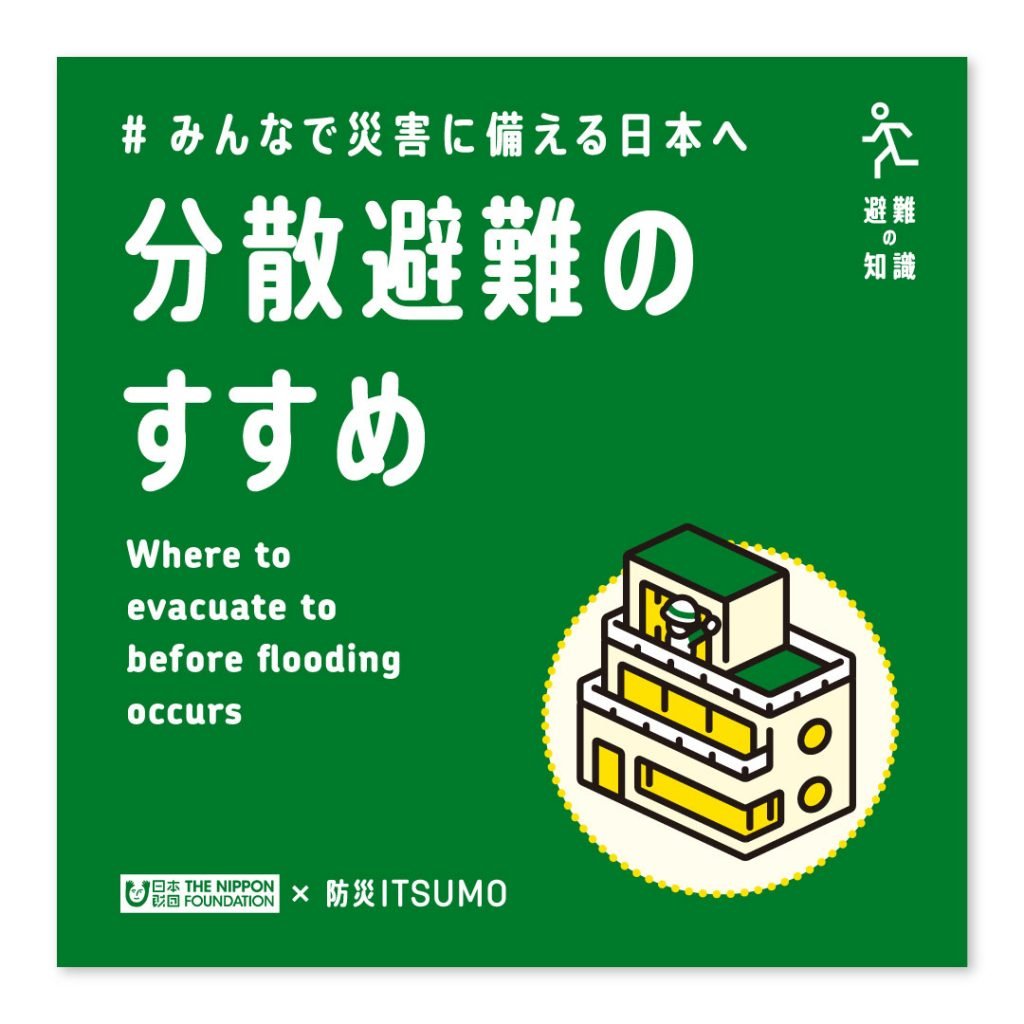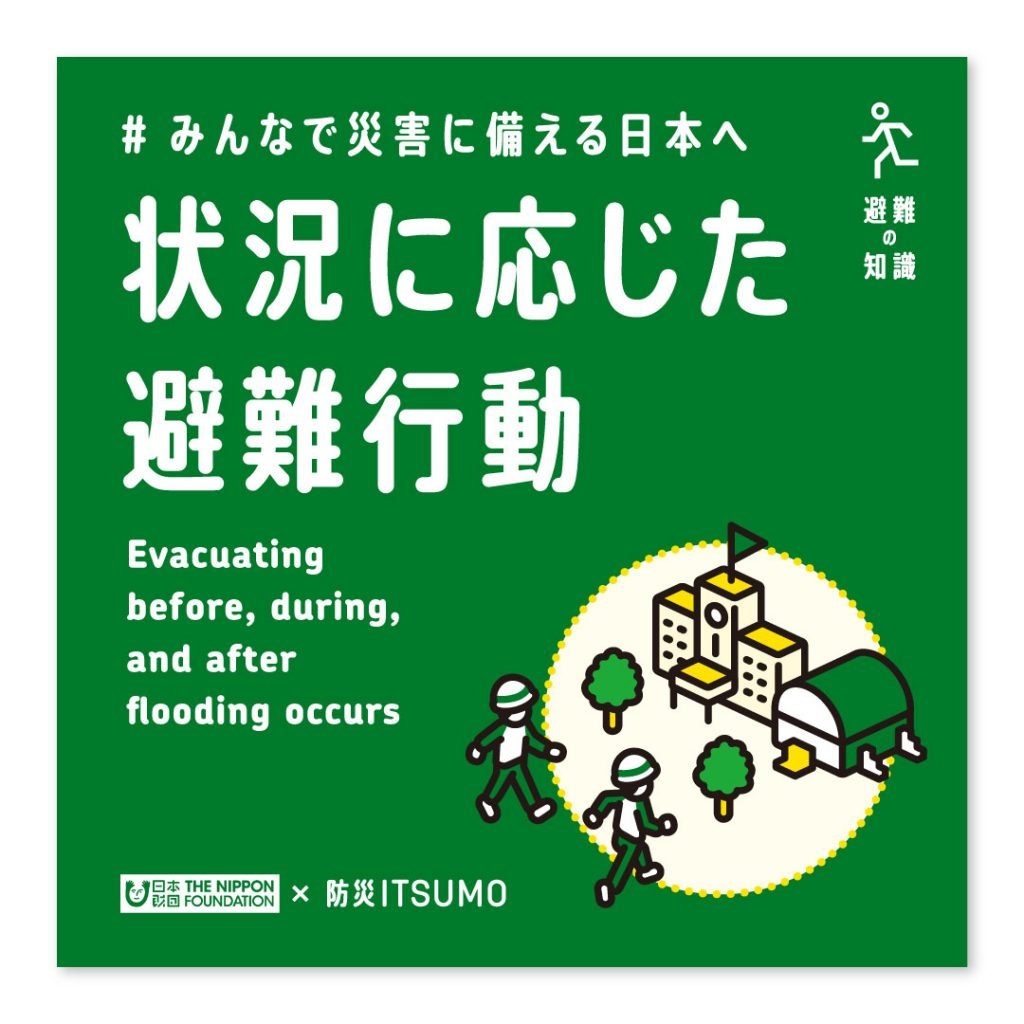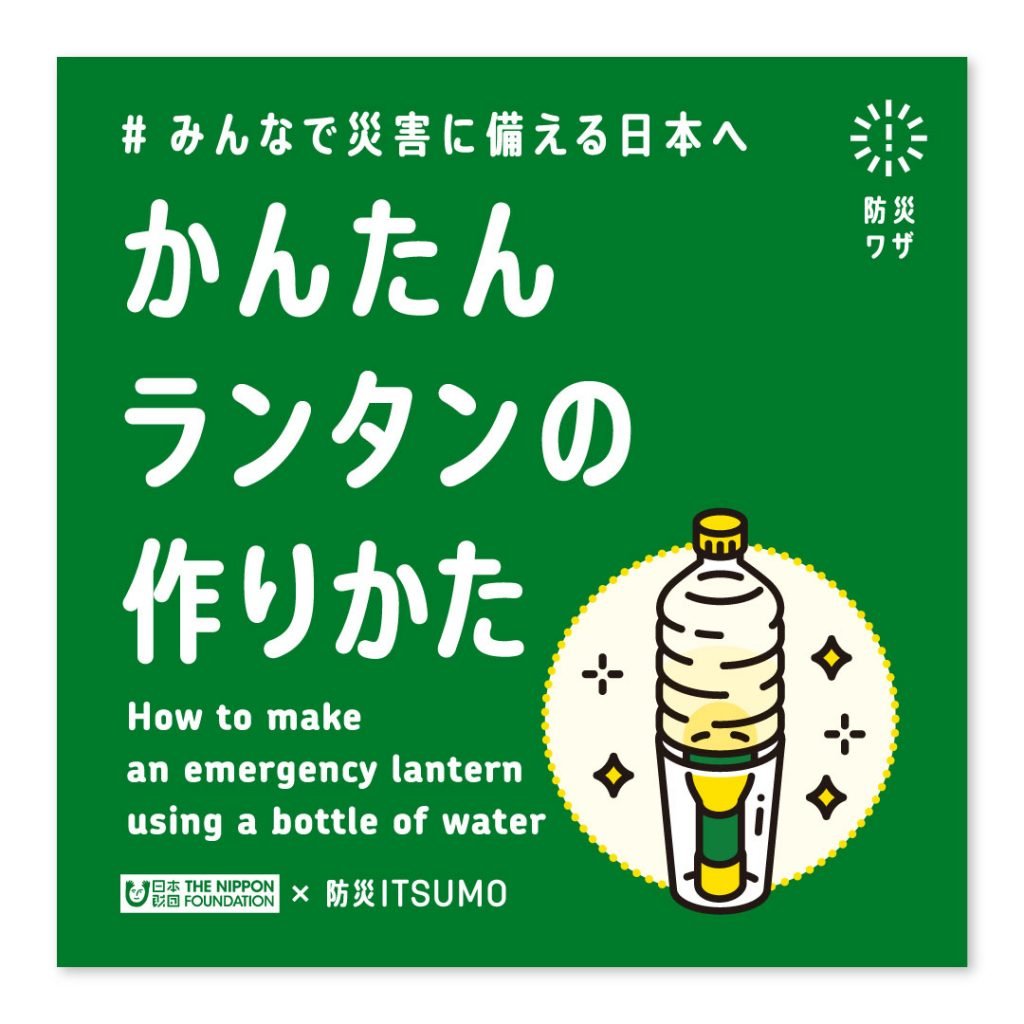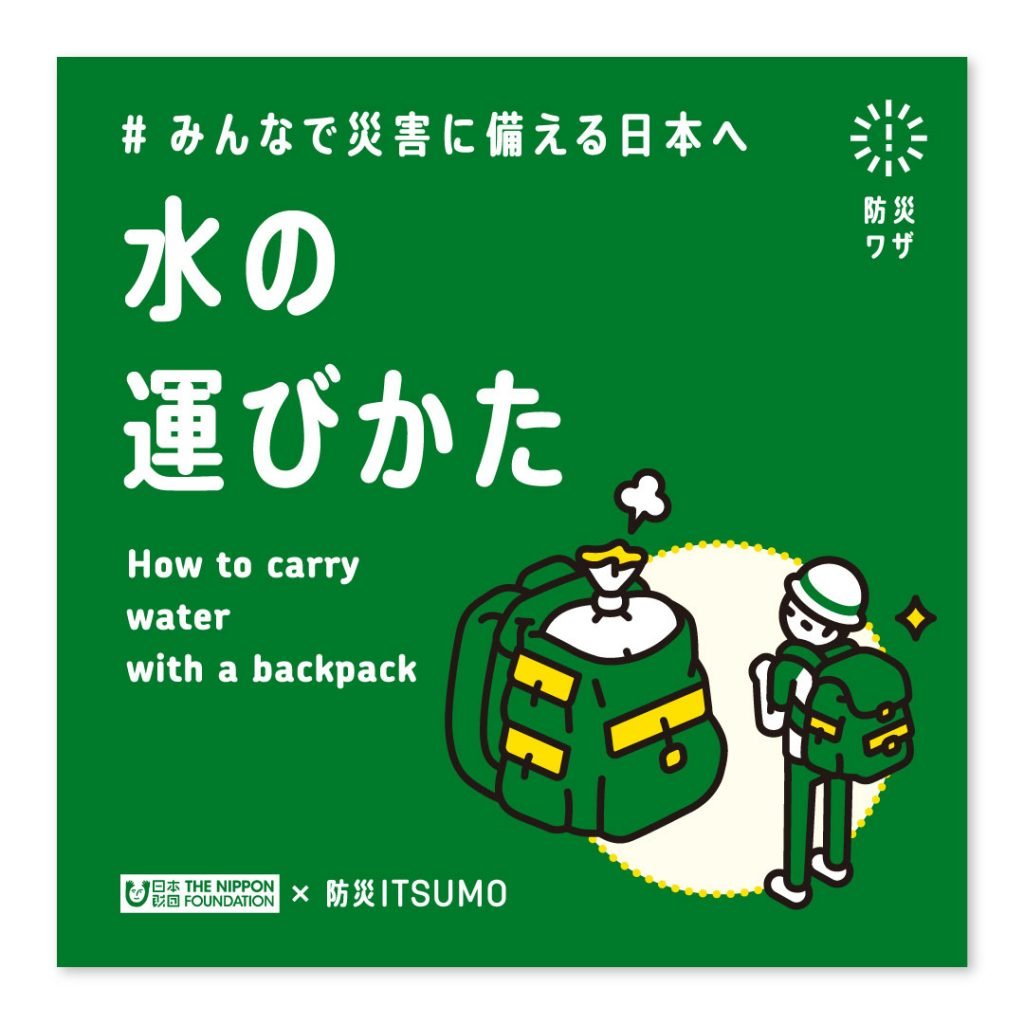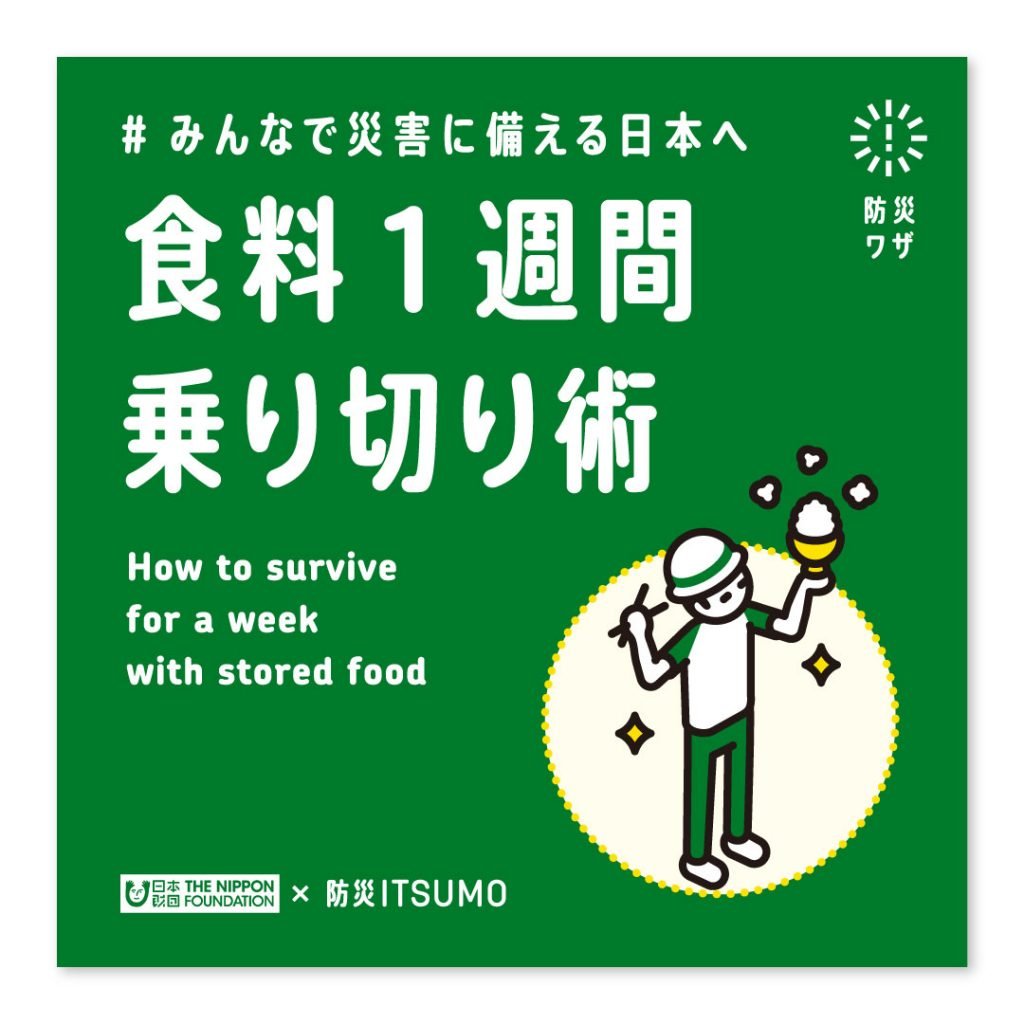みんなで災害に備える日本へ。日本財団の災害復興支援活動

日本財団の能登半島地震での活動
能登半島地震が発生した2024年1月1日、私たち日本財団の職員と、連携する災害支援団体や有志が、現地へと向かいました。甚大な被害を受けた石川県珠洲市に重機を扱う技術系団体の活動拠点を設け、道路啓開や倒壊家屋からの車両・貴重品の救出作業にあたりました。

被災地では大規模な断水や停電が続いた地域もあり、衛生環境の悪化が懸念されていました。被災者の方々に少しでも安心して過ごしてもらえるよう、日本財団では海上輸送による支援物資の搬送を実施しました。循環式シャワー・手洗機、大型発電機、暖房用の灯油などを奥能登地域の避難所・医療機関に届けました。

同年9月には豪雨による被害も発生し、輪島市に活動拠点を移して再び啓開作業などを進めています。被災地の復旧・復興は息の長い取り組みとなることも予想されます。少しでも早く日常を取り戻すべく、民間の立場としてハード・ソフト両面における継続的な支援を実施していきます。
イラストで学ぶ防災の知恵
災害時に役立つ防災の知恵を、イラストと合わせて4ステップで分かりやすくまとめています。日本財団のInstagramやXで、毎年公開している人気シリーズです。
それぞれの詳細は下記サムネイル画像からもご覧いただけます。
被災地支援ボランティアに登録・研修を受ける

日本財団ボランティアセンターは、被災地への災害ボランティア派遣を実施しています。2024年は、能登半島地震の発生直後から支援を開始し、7月の山形県での豪雨災害、9月の奥能登豪雨にも対応。1年間に延べ約700人のボランティアを派遣しました。
また、マッチングプラットフォームサイト「ぼ活!」を通して、いつ発生するか分からない災害に備え、災害現場で活動するボランティアのノウハウを学ぶことのできるセミナーの実施や、WEB記事での情報発信をしています。また、ぼ活!会員の方(登録無料)には、ボランティア活動やセミナーの情報を随時メールでお送りしています。
災害ボランティア研修を受ける
災害現場でのボランティア活動をしたことがない初心者向けの研修から、工具の使い方や被災者の方との接し方など、災害現場で必要な知識やスキルを学ぶ研修まで、様々なレベルの研修を実施しています。
- ※ 日本財団は、日本財団ボランティアセンターを助成金により支援しています。本ページで紹介するボランティアの募集・派遣等は、日本財団ボランティアセンターによって行われます。
未来の災害に備える基金に寄付する
日本財団は、東日本大震災などでの経験から、「災害復興支援特別基金」を立ち上げました。
東日本大震災の最大の教訓は、災害対策は起きてからでは遅いということです。
大災害が起きたとき、真っ先に動くための支援金を蓄えておく仕組みが必要です。
頂いたご寄付から、日本財団が経費を受け取ることはありません。
寄付の100%が、実際の災害支援活動に使用されます。
あなたも、災害大国日本の未来のため、この基金に参加してください。
日本財団のこれまでの災害支援活動
日本財団は、日本中の誰もが安全に安心してくらせるように、災害が発生した直後の緊急支援から、元の生活に戻り、復興していくための中長期の支援、そして、普段からの備えの仕組みづくりを行っています。
これらの活動には、政府や地域社会、NPO、企業など、多くの方々との連携が欠かせません。日本財団は、皆さまをつなぐ役割を担い、ネットワークの力で災害に立ち向かっています。
阪神・淡路大震災以降、50回以上の被災地支援に出動してきました。これまでの活動の一部をご紹介します。
1995年 阪神・淡路大震災

1月17日未明に発生した直下型地震により、老朽化した木造住宅密集地では建物の倒壊と延焼火災が多発しました。高速道路の高架橋崩落や鉄道寸断、市街地での大火災、電気・水道・ガス・交通機関などライフラインの壊滅的被害が発生し、多数の住民が長期避難を強いられました。
この震災をきっかけに、市民による支援活動が活発化し、日本におけるボランティア活動の歴史を大きく変えた「ボランティア元年」とも言われています。
日本財団は、地震の発生直後から、ただちに現地調査を行い、被災地の民間団体を回って資金等を届けました。
翌年には、復興とコミュニティ再建のため「阪神・淡路コミュニティ基金」を設立し、この基金は多くの団体やボランティア組織の発展につながりました。
最後の仮設住宅が撤去されるまでの数年間、総額約10億円規模の支援を行い、被災地の復興に取り組みました。
2011年 東日本大震災

3月11日に我が国観測史上最大規模の地震が発生、また地震に続く巨大津波が沿岸部に大きな被害をもたらしました。東京電力福島第一原子力発電所の事故も発生し、地震・津波・原発事故という未曾有の複合災害となり、今なお避難生活を強いられている方もいます。
日本中・世界中から支援が集まり、個人による寄付が史上初めて1兆円を超えた「寄付元年」とも呼ばれています。
日本財団は、発災直後から、阪神・淡路大震災の経験を持つ職員を現地に派遣し、避難所や被災者のニーズを調査、妊産婦や障害のある方に対する支援を届けました。
一日でも早く被災者に支援を届けようと、弔慰金・見舞金を職員自ら現地に運び、84の自治体で1万7,329人の方に手渡しで配布を行いました。
緊急期を乗り越えた後も、産業や文化の復旧・復興のため、地域の基幹産業である水産業や、伝統芸能の再生のための助成金・支援金等を継続しました。
2016年 熊本地震

4月14日の強い地震発生直後から多数の余震が続き、人々が避難生活を送る中で、16日未明に本震が発生するという異例の経過をたどりました。2度の震度7により家屋倒壊が相次ぎ、阿蘇大橋の崩落や熊本城の石垣崩壊など象徴的な被害も発生しました。広域で断水・停電・ガス供給停止が起こり、一時避難者は県内外で18万人を超えました。
避難所での長期生活や医療ケア不足により、「災害関連死」が全死者数の8割にも及んだことが社会問題となりました。
東日本大震災後に設置した「災害復興支援特別基金」に資金を積み立てていたことで、発災直後から迅速に大規模な支援を展開することができました。
本震発生から3日後には、総額93億円の緊急支援策を発表。被災地の象徴である熊本城の復旧や、自宅が全壊・大規模半壊となった23,818世帯に住宅損壊見舞金を届けました。
熊本本部を開設し、日本財団の職員が常駐して避難所や仮設住宅をめぐり、現地の支援ニーズを的確に捉えた支援を行いました。
2018年 北海道胆振東部地震

9月6日、北海道厚真町で最大震度7を観測しました。本震後も震度5強クラスの強い余震が相次ぎました。また、大規模な土砂崩れが発生し、家屋が多数埋没する被害が出ました。一部損壊も含めると、地震による住家被害は数万件に及びました。
苫東厚真火力発電所が被災停止したことをきっかけに、北海道全域がブラックアウト(全域停電)となり、道内約295万戸が停電し復旧に数日を要しました。
日本財団は、全道的な停電や断水に対応し、断水地域の避難所に水不要の簡易トイレを設置しました。
行政の義援金とは別に民間基金から弔慰金を直接届けることで、突然家族を失った遺族の生活支援を行いました。
また、北海道内の団体や、災害支援経験が豊富な団体に、迅速に活動資金を提供し、避難所での炊き出しや被災家屋の片付け支援など、民間による支援活動を後押ししました。
2024年 能登地震

1月1日未明、石川県能登半島を震源とする地震が発生、石川県輪島市・志賀町では最大震度7を記録しました。土砂崩れや地盤陥没によって、多くの道路が通行不能となり、一部集落が孤立しました。
広範囲での建物被害や断水が発生するなど、インフラ・産業被害は甚大です。さらに、同年9月の記録的豪雨により、追い打ちをかけるように、土砂災害・浸水被害が発生しました。
日本財団は、陸路寸断に備えて、いち早く海上ルートを活用しました。トラック積載型のRORO船で支援物資を輸送し、港から避難所や福祉施設へ物資を届ける体制を整えました。
断水への対応として避難所にポータブルシャワー等を設置し、被災者が清潔を保てる環境を整えました。また、孤立集落の解消のため、重機による道路啓開を行う等、迅速な支援を展開しました。
今後の復旧・復興フェーズにおいても、民間ボランティアセンター運営や地域コミュニティの維持・形成支援等を中長期的に行っていく予定です。
日本財団とは?
日本財団は、日本最大の社会貢献団体です。営利を⽬的とせず、ボートレースの売上金からの交付金を財源に活動しています。
2022年に60周年を迎えた私たちは、子ども・災害・障害者・海洋環境など、国内外で幅広い社会貢献活動を支援してきました。その経験とネットワークを活かし、災害発生時の緊急支援に留まらず、災害に備える寄付の募集、被災地を支えるボランティアの派遣も推進しています。