「子どもWEEKEND 2025」登壇者プロフィール
全体会 登壇者プロフィール
ご挨拶
源河 真規子(げんか まきこ)
こども家庭庁長官官房審議官
1993年労働省(現厚生労働省)入省。イギリス留学、厚生労働省職業生活両立課、障害福祉課、人事課勤務等を経て、2024年7月より現職。

1. 小澤いぶき
児童精神科医・精神科専門医・精神保健指定医/一般社団法人Everybeing共同代表
臨床研修医・精神科臨床医としての経験後、東京医師アカデミーにて児童精神科の研修を積み、東京都立小児総合医療センター、児童相談所、精神保健福祉センター等にて子どもの心のケアに携わる。その後、東京大学先端科学技術研究センター特任研究員を経て、認定NPO法人PIECESを創業。Fish Family Foundation JWLIフェロー。2017年、ザルツブルグカンファレンスにて、子どものウェルビーイングのためのザルツブルグステイトメント作成に参画。日本及び中東での子ども及び子どもに関わる人のmentalhealth and wellbeingのプロジェクト、心のケア、およびコレクティブトラウマやトラウマケアに関わる。2022年7月よりこども家庭庁設立準備室(現・こども家庭庁)アドバイザーを兼務。
京都大学国際保健分野協力研究員。

2. 尾形 武寿(おがた たけじゅ)
日本財団会長
1944(昭和19)年生まれ。東京農業大学農学部卒業。68年社団法人日本舶用機械輸出振興会に入会。74年、同ロッテルダム事務所所長に就任。80年、財団法人日本船舶振興会に入会。90年、笹川平和財団総務部長に就任。93年、財団法人日本船舶振興会総務部長に就任。97年、同会 常務理事に就任。2005年、同会 理事長に就任。11年、財団法人から公益財団法人へ移行と共に法人名を日本財団へ改称し、25年、同財団 会長に就任、現在に至る。
日本財団では子ども基本法の成立、子ども第三の居場所、家庭養育自治体モデル事業などの子ども関連事業に精力的に取り組むとともに、23年には子ども支援チームの体制づくりを主導した。
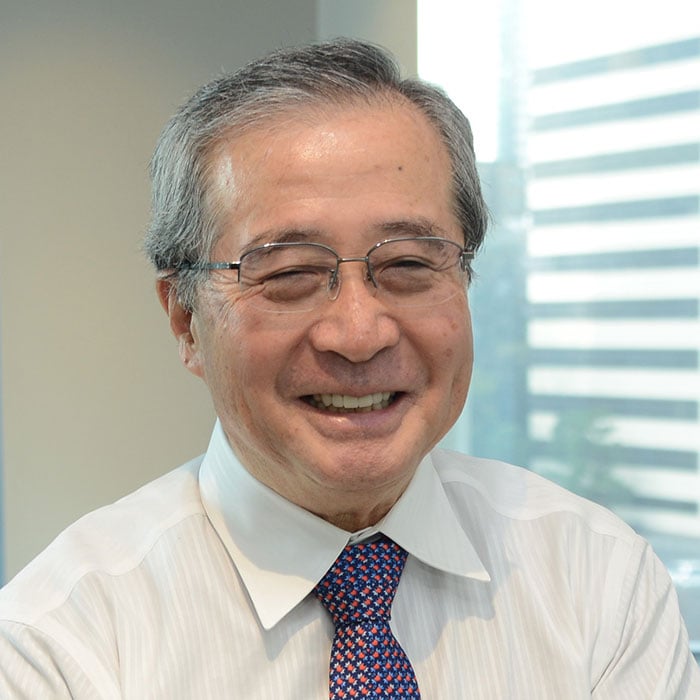
3. 高橋 恵里子(たかはし えりこ)
日本財団公益事業部子ども事業本部長
1971年東京都生まれ。上智大学卒、ニューヨーク州立大学修士課程修了。1997年より日本財団で海外の障害者支援等を担当した後、2013年に日本財団「ハッピーゆりかごプロジェクト」(現:子どもたちに家庭をプロジェクト)を立ち上げ、特別養子縁組、里親制度、妊産婦支援等の子ども家庭福祉の拡充に取り組む。児童福祉法改正やこども基本法の制定などの政策提言等にもかかわる。ハフポストでたまにコラムを執筆中。

分科会 登壇者プロフィール
【分科会1】児童育成支援拠点(第三の居場所)
1. 安里 賀奈子(あさと かなこ)
こども家庭庁 成育局 成育環境課長
2000年厚生省(現厚生労働省)入省。児童家庭局、健康局、労働基準局、多摩市、広報室長、文部科学省男女共同参画共生社会学習・安全課長等を経て昨年7月より現職。

2. 酒井 美里(さかい みさと)
特定非営利活動法人ふれあい福祉の会山びこへるぷ 子育て支援事業部 統括マネージャー
声楽家。マレーシア国立サラワク大学元講師。現在、徳島県鳴門市内にて2ケ所の子ども第三の居場所を運営している(2019年から開所した拠点は2024年度より児童育成支援拠点事業として運営委託を受けている)。4児の母。

3. 平谷 祐宏(ひらたに ゆうこう)
尾道市長
尾道市出身。1977年山口大学教育学部を卒業後、中学校教諭として従事。教育事務所長などを歴任後、尾道市教育委員会教育次長を経て、2003年尾道市教育委員会教育長に就任。2007年尾道市長に就任し、現在5期目。

4. 李 炯植(り ひょんしぎ)
認定特定非営利活動法人Learning for All代表理事
一般社団法人社会的養育地域支援ネットワーク共同代表
2014年にNPO法人Learning for All を設立、同法人代表理事に就任。困難を抱えた子どもへの無償の学習支援や居場所づくりを行う。一般社団法人社会的養育地域支援ネットワーク共同代表。

5. 山下 大輔(やました だいすけ)
日本財団公益事業部子ども支援チーム チームリーダー
2006年(財)日本船舶振興会(現日本財団)入会。入会以来、事業部として犯罪被害者支援、プロボノ支援、地域づくり等を、総務部として事業の統括管理、事業計画・事業報告の作成等を担当し、本年6月より現職。二児の父。

【分科会2】セーフガーディング
1. 岩田 達仁(いわた たつひと)
社会福祉法人 大阪児童福祉事業協会 アフターケア事業部
児童相談所・一時保護所にて約10年勤務。現在はアフターケア事業部で施設出身者へ相談支援等を行うと共に法人内の自立援助ホーム「ホームそらまめ」にて宿直業務も担う。
2. 嶋本 祐子(しまもと ゆうこ)
一般社団法人まどかこどもレグル代表理事
千葉県白井市で学童保育・自然教育・音楽療法の事業を運営。2015年から関連施設まどか幼稚園で自然教育を担当。2024年に子ども第三の居場所CoMADOを開設。
3. 徳田 絵美(とくだ えみ)
特定非営利活動法人とこっ子代表理事
CFSW・子どもアドボケイト・成年後見支援専門員・専門里親。児童福祉及び障害福祉の活動を行う法人の代表として、ファミリーホームのママさんとして、幸せな日々を送っている。

4. 西崎 萌(にしざき めぐみ)
一般社団法人Everybeing共同代表
こども家庭庁長官官房参事官付アドバイザー
教育学修士。民間企業・高校教員を経て、セーブ・ザ・チルドレンで約8年間アドボカシー活動等に従事。現在こども家庭庁アドバイザー、Everybeing共同代表。
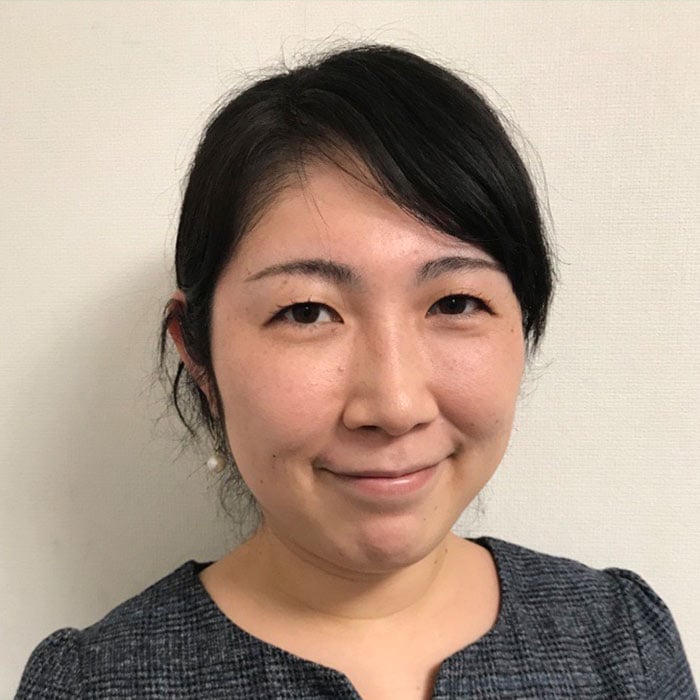
5. 村田 安奈(むらた あんな)
日本財団公益事業部子ども支援チーム
放課後児童クラブに勤務後、2021年に日本財団入会。「子ども第三の居場所」事業、「難病児と家族を支えるプログラム」、子ども若者のセーフガーディング業務を担当。

【分科会3】新しい里親 × パートナー・ファミリー × QPI
1. 北川 聡子(きたがわ さとこ)
特定非営利活動法人家庭養育支援機構副理事長
社会福祉法人麦の子会理事長
大学卒業と同時にむぎのこ設立。障害のある子や家族の困り感に寄り添い1km圏内に妊娠期から成人期まで支援する50以上の事業所をお母さん達と一緒に設立。
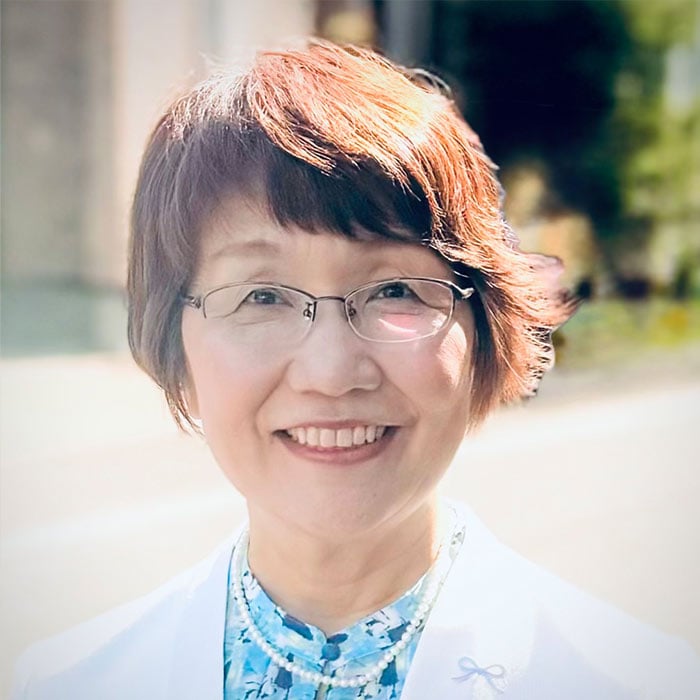
2. 河内 美舟(こうち みふね)
公益財団法人全国里親会会長
養育里親として家族再構築を踏まえ、心身障害児童やベトナム難民児童を含む里子8名、実子3名を養育、ファミリーホーム開設後は、42名の児童の養育を経験

3. 小松 秀夫(こまつ ひでお)
こども家庭庁支援局家庭福祉課長
H3厚生省入省後、虐待防止対策室長補佐(H25)、家庭福祉課長補佐(H29)、きぬ川学院長(R2)、秩父学園長(R4)、R5年4月より現職。

4. 土井 一平(どい いっぺい)
保育士
夫婦で保育士をしている。子どもを授かることが出来ず「特別養子縁組をしよう」と夫婦で里親の研修へ。「保育士の知識を活かせるのなら」と思い、養育里親になる。
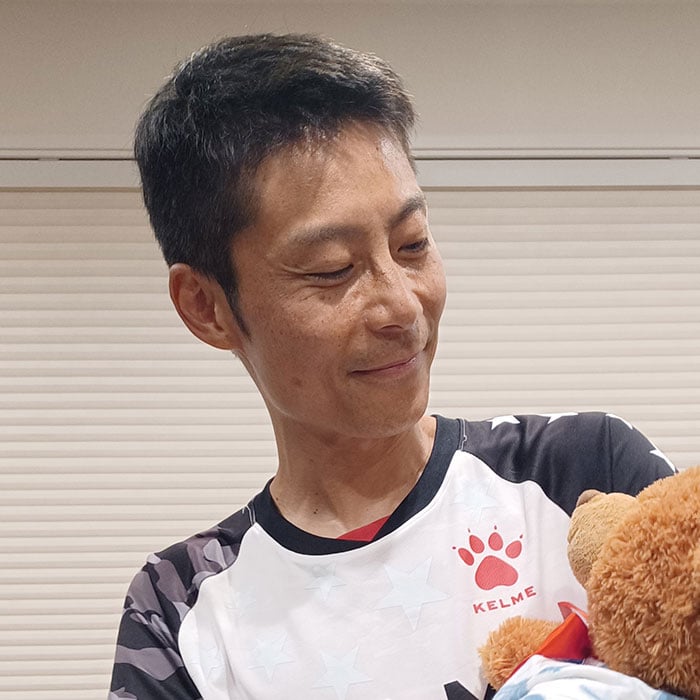
5. 中村 みどり(なかむら みどり)
Children’s Views & Voices副代表
乳児院・児童養護施設を経験、2001年に社会的養護経験者のための居場所CVV(Children‘s Views &Voices)の立ち上げに携わり、現副代表。
こども家庭庁 児童虐待防止対策部会委員

6. 中山 健太郎(なかやま けんたろう)
社会福祉法人共立福祉会 つくし保育園主任
子ども食堂 あそびの木のびのび共同代表
山梨県社会福祉労働組合 執行委員長
保育士として働き続けてきた経験を活かし、里親として「子どもの命を守り、社会へつなげていきたい」と強く思い、現在は二人目の里子を夫婦で愛情をかけて養育している。
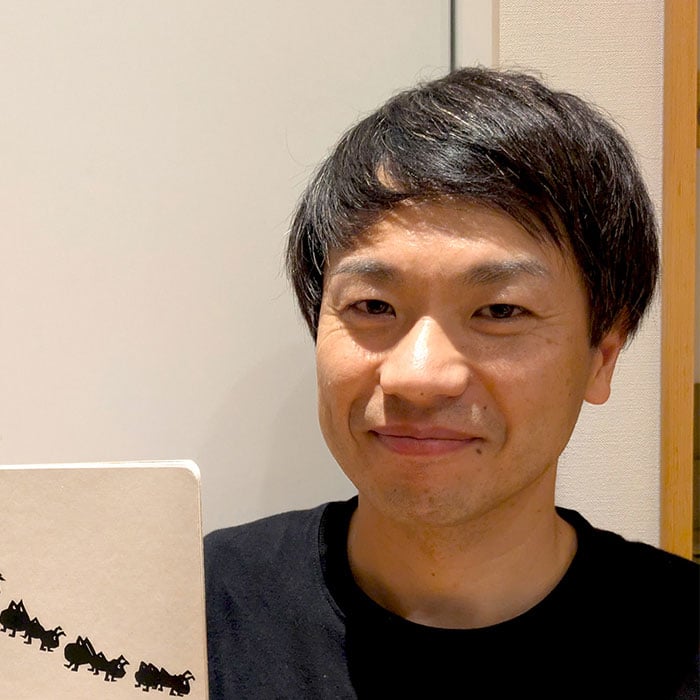
7. 安留 昭人(やすとめ あきひと)
山梨県中央児童相談所 処遇指導・移行支援課長
早稲田大学社会的養育研究所 招聘研究員
早稲田大学大学院修了後、民間企業勤務を経て山梨県に入庁。現在は児童相談所にて社会的養護を必要とするこどものパーマネンシー保障に取り組む。2017年養育里親登録。

8. 高橋 恵里子(たかはし えりこ)
日本財団公益事業部子ども事業本部長
1971年東京都生まれ。上智大学卒、ニューヨーク州立大学修士課程修了。1997年より日本財団で海外の障害者支援等を担当した後、2013年に日本財団「ハッピーゆりかごプロジェクト」(現:子どもたちに家庭をプロジェクト)を立ち上げ、特別養子縁組、里親制度、妊産婦支援等の子ども家庭福祉の拡充に取り組む。児童福祉法改正やこども基本法の制定などの政策提言等にもかかわる。ハフポストでたまにコラムを執筆中。

【分科会4】ヤングケアラーとつながる多様な実践
1. 大橋 雄介(おおはし ゆうすけ)
特定非営利活動法人アスイク代表理事
社会的養育地域支援ネットワーク理事
リクルートのグループ企業で組織開発・人材開発のコンサルティングに携わった後、独立。2011年の震災直後にアスイクを設立。著書に「3・11被災地子ども白書」等。
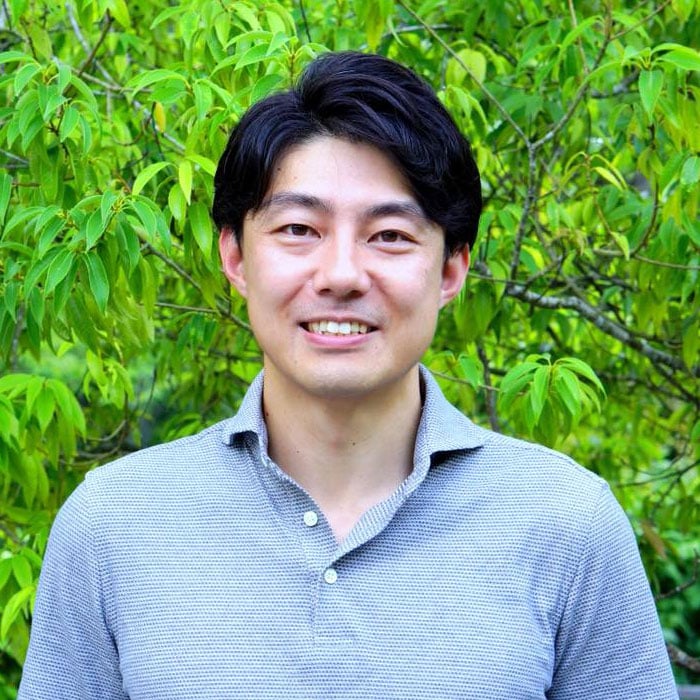
2. 木村 朱(きむら あかね)
宮城県涌谷町こども家庭センター統括支援員
2024年4月にこども家庭センター「わくやっ子センター」を開設し、地域連携と支援体制の強化を図りながら、多職種連携による子育てしやすいまちづくりに取り組んでいる。
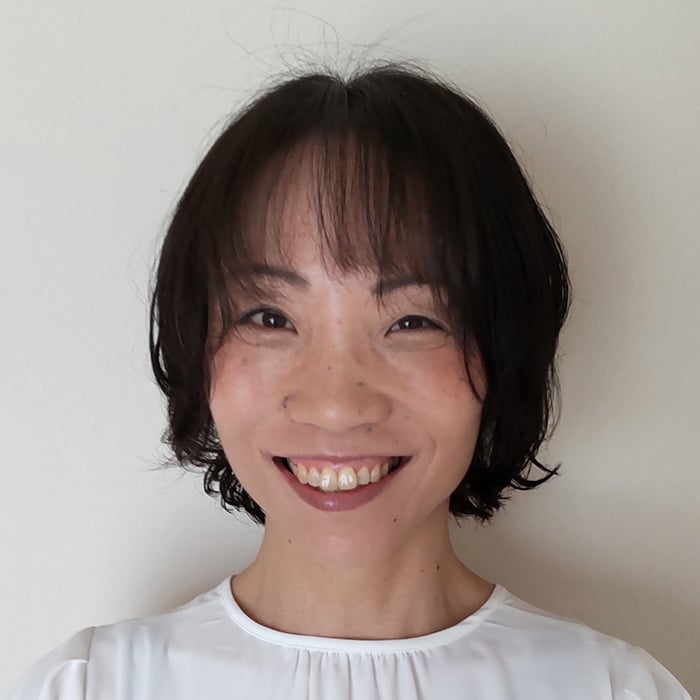
3. 平井 登威(ひらい とおい)
特定非営利活動法人CoCoTELI理事長
関西大学4年生
2001年生まれ、関西大学4年生。幼稚園年長時に父親がうつ病になり、名前のつかない困難や虐待、ケアを経験。2023年5月に特定非営利活動法人CoCoTELIを設立。

4. 森川 ゆとり(もりかわ ゆとり)
特定非営利活動法人アスイク ヤングケアラーユニットリーダー
2022年アスイク入職。ヤングケアラー支援事業に従事し、仙台市や宮城県等と協働しながら、オンラインサロンの立ち上げや相談対応、学校内の居場所づくり等に取り組む。

5. 山本 さやか(やまもと さやか)
社会福祉法人清浄園 児童家庭支援センタ―「和(やわらぎ)」副センター長
平成22年、社会福祉法人清浄園入職。児童家庭支援センターでショートステイ事業や居場所事業、アウトリーチなど在宅支援を行いながら、地域の子育て家庭をサポートしている。

6. 長谷川 愛(はせがわ あい)
日本財団公益事業部子ども支援チーム
2020年に日本財団に入会。社会福祉施設の修繕事業等を担当後、現在は里親制度の普及や、ヤングケアラーとその家族への支援に関する助成プログラムに携わる。

【分科会5】居場所&訪問のハイブリッド
1. 岡田 妙子(おかだ たえこ)
認定特定非営利活動法人 バディチーム 理事長
精神科看護や企業での健康管理業務などに従事したのち、2007年にバディチーム設立。都内14自治体からの受託事業や、民間機関と連携した家庭訪問型の支援に取り組む。

2. 奥山 千鶴子(おくやま ちづこ)
認定特定非営利活動法人 びーのびーの 理事長
特定非営利活動法人 子育てひろば全国連絡協議会 理事長
2000年、横浜市港北区にて親子の交流の場を開設。現在4か所運営。ファミサポ、産前産後ヘルパー事業等、妊娠期からの切れ目ない支援を包括的に提供できるよう推進中。

3. 濱田 壮摩(はまだ そうま)
認定特定非営利活動法人 バディチーム 理事
大学在学中の2008年にバディチーム入職。2013年に一度離職したが、複数の業界・業種を経たのち、2019年に復帰して現職。

4. 山浦 健二(やまうら けんじ)
一般社団法人 彩の国子ども・若者支援ネットワーク(アスポート) 副統括責任者・理事
元児童相談所児童福祉司。現在はアスポート事業副統括責任者。埼玉県26市と埼玉県から生活困窮者自立支援事業の学習支援と4市1町から子どもの見守り事業を受託している。

5. 山本 博子(やまもと ひろこ)
特定非営利活動法人 Mama’s Café 理事長
経営コンサルタント会社勤務ののち、結婚を機に岐阜県多治見市に移住。2001年にMama’s Cafe設立。県内7市からの受託事業の他、自主事業も幅広く取り組む。

【分科会6】里親支援センターのあり方
1. 荒木 康生(あらき やすお)
児童家庭支援センター絆 センター長
九州ファミリーホーム協議会 研修委員長
佐賀県ファミリーホーム協議会 事務局長
平成11年より児童養護施設聖華園の指導員、里親支援専門相談員を務める。現在は児童家庭支援センター絆のセンター長。社会福祉士。

2. 黒田 信子(くろだ のぶこ)
認定特定非営利活動法人優里の会 理事長
熊本里親支援センター協議会 事務局長
熊本県福祉総合相談所で地区CWとして児童相談に従事した。「コウノトリのゆりかご」開設時は児童相談課長として活動、2013年優里の会を立ち上げ現職。社会福祉士。

3. 阪口 千晴(さかぐち ちはる)
里親センターならセンター長
奈良学園大学人間教育学部非常勤講師
児童養護施設の児童指導員、里親支援専門相談員、事務を務めたのち、児童家庭支援センターの相談員兼里親支援機関担当として勤める。現在は里親支援センターの施設長。

4. 橋本 達昌(はしもと たつまさ)
社会的養育総合支援センター一陽 統括所長
社会的養育地域支援ネットワーク 代表理事
NPO法人家庭養育支援機構 副理事長
1990年に越前市に入庁するも社会運動好きが高じて2009年に脱藩。「遠山の金さん」の大ファンで、持ち前のお節介精神と始動力を活かし多動な日々を満喫している。

5. 藤林 武史(ふじばやし たけし)
西日本こども研修センターあかしセンター長
早稲田大学社会的養育研究所招聘研究員
精神科医として医療機関や精神保健福祉センターに勤務後、2003年より福岡市児童相談所長に就任。里親委託推進や児童相談所改革に取り組む。2021年より現職。

【分科会7】インクルーシブ(難病・障害)
1. 内田 治代(うちだ はるよ)
社会福祉法人 興望館 特別支援教育コーディネーター
障害のある子と共に過ごす保育者を目指し興望館に入職。保育事業統括や、リーダー育成、年輩者プログラム等に携わりながら、こども家庭福祉や地域福祉の学びに触れている。

2. 運上 昌洋(うんじょう まさひろ)
特定非営利活動法人 ソルウェイズ共同代表
有限会社アット代表取締役
一般社団法人全国重症児者デイサービスネットワーク副代表理事
札幌市、石狩市を拠点に、医療的ケアが必要な子どもたちやその家族を支援する地域活動を行っている。資格は社会福祉士、二級建築士、介護支援専門員等。

3. 北川 聡子(きたがわ さとこ)
社会福祉法人麦の子会理事長
特定非営利活動法人家庭養育支援機構副理事長
大学卒業と同時にむぎのこ設立。障害のある子や家族の困り感に寄り添い1km圏内に妊娠期から成人期まで支援する50以上の事業所をお母さん達と一緒に設立。
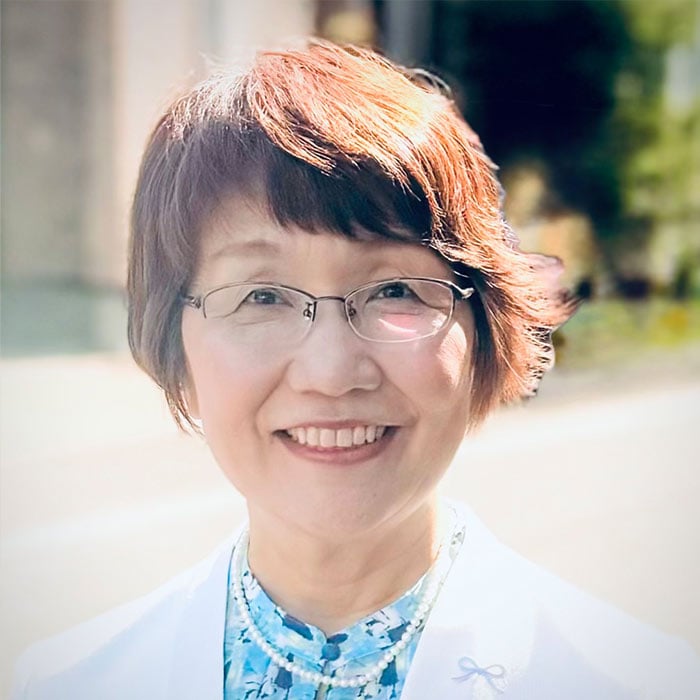
4. 栗原 正明(くりはら まさあき)
こども家庭庁成育局保育政策課 課長
2000年厚生労働省入省。在スウェーデン日本国大使館や三重県庁などでの勤務を経て2023年4月よりこども家庭庁障害児支援課長、2024年7月より現職。

5. 光真坊 浩史(こうしんぼう ひろし)
一般社団法人 全国児童発達支援協議会理事
福井県生まれ。児童相談所の心理判定員や厚生労働省障害児支援専門官を経て現職。障害児支援とインクルーシブ保育等の現場で専門的後方支援にも携わっている。
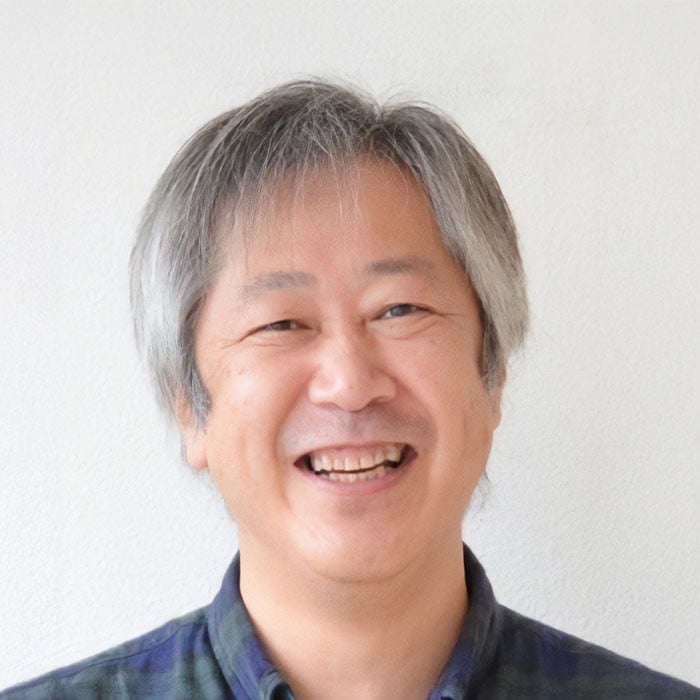
6. 鈴木 久也(すずき ひさや)
こども家庭庁支援局障害児支援課課長補佐
障害児支援の現場経験を経て、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害児支援専門官に着任。現在こども家庭庁支援局障害児支援課にて、障害児施策の推進に携わる。

【分科会8】児童家庭支援センター x 市町村 x 社会福祉協議会
1. 大塚 陽子(おおつか ようこ)
社会福祉法人越前市社会福祉協議会 在宅福祉部 在宅多機能推進担当 課長
越前市社会福祉協議会職員。ホームヘルパーとして入職。時の流れに身をまかせ、地域包括支援センター、権利擁護事業、相談支援専門員等に従事。介護福祉士・社会福祉士。

2. 岡本 由美子(おかもと ゆみこ)
八尾市 健康福祉部 次長兼福祉事務所長
1995年入庁。介護保険や地域包括支援センターの体制構築に携わる。多様な分野の経験を経て、2023年八尾市版重層的支援体制整備事業をスタート。社会福祉士。

3. 小池 由佳(こいけ ゆか)
新潟県立大学教授
専門は子ども家庭福祉。特に、要支援家庭等に関する在宅支援制度やサービスに関する研究に取り組んでいる。

4. 堀 浄信(ほり じょうしん)
社会福祉法人 光明童園理事長
児童家庭支援センターオリーブの木 センター長
全国児童家庭支援センター協議会 事務局長
1995年より児童養護施設光明童園に勤務し、2004年より施設長、2018年より理事長就任。2025年より社会的養育総合支援センターを立ち上げ活動。社会福祉士。

【分科会9】妊産婦支援
1. 赤尾 さく美(あかお さくみ)
一般社団法人全国妊娠SOS ネットワーク 理事 助産師
一般社団法人ベアホープ 理事
総合病院、国際NGO、大学勤務を経て、2014年にベアホープをスタート、日本財団ハッピーゆりかごプロジェクト参画。2015年に全国妊娠SOSネットワーク立上げ。

2. 大神 嘉(おおがみ まこと)
社会福祉法人豊生会 こどもと女性包括支援センターhalu 業務執行理事・センター長
社会福祉法人仏心会 福岡子供の家みずほ乳児院 施設長
小学校の教員を10年務めた後、福岡市内の母子生活支援施設施設長、産前産後母子支援センターのセンター長を経て、現職は困難を抱える子どもと女性への支援に従事。

3. 佐藤 初美(さとう はつみ)
認定特定非営利活動法人 10代・20代の妊娠SOS新宿-キッズ&ファミリー理事長
日本応用心理学会正会員
日本子ども虐待防止学会正会員
1975年から新宿区立保育園勤務、新宿区立子ども家庭支援センター(虐待対応相談員)を経て、2016年に同法人設立。精神保健福祉士、社会福祉士。

4. 野中 祥子(のなか さちこ)
こども家庭庁 支援局 虐待防止対策課 課長
1977年生まれ、2000年厚生労働省入省。労働基準局、年金局等で法改正等を担当。20年、長野県庁出向(こども若者局長)。23年より厚労省女性支援室長を経て、24年7月より現職。

5. 田中 奈名子(たなか ななこ)
日本財団公益事業部子ども支援チーム
税理士法人での勤務を経て、2023年日本財団へ中途入会。現職に配属。
妊娠SOS相談窓口及び困難を抱える妊産婦支援、性教育、子どもの権利普及等に関する事業を担当。

【分科会10】特別養子縁組家庭への支援を考える
1. 大場 亜衣(おおば あい)
社会福祉法人 日本国際社会事業団(ISSJ)事業統括部長
ボストンカレッジ大学院修士課程修了。社会福祉士。2000年にISSJに入職し、現在は事業統括部長として、養子縁組や無国籍児の支援事業に携わる。
2. 熊谷 俊人(くまがい としひと)
※ビデオメッセージ
子どもの家庭養育推進官民協議会会長(千葉県知事)
兵庫県神戸市出身。NTTコミュニケーションズ株式会社、千葉市議会議員、千葉市長を経て、令和3年4月千葉県知事に就任。現在2期目。
3. 胡内 敦司(こうち あつし)
こども家庭庁 支援局家庭福祉課課長補佐
4. 古田島 あかね(こたじま あかね)
千葉県里親会理事
27歳の時に長女を、29歳の時に次女を一般社団法人ベビーライフを通して家族に迎え、養育里親としても活動を続け、多くの子供たちを家族に迎えている。

5. 志村 歩(しむら あゆむ)
特別養子当事者団体ツバメ代表理事
Origin44チャンネル(YouTube)MC
大分県養子縁組里親支援機関ブレス・ユー応援大使
1歳10カ月で特別養子縁組が成立。2022年1月「特別養子縁組が特別ではない未来」をモットーに活動を開始。現在も個人での講演やSNS発信を積極的に行っている。

6. 鈴木 茂(すずき しげる)
名古屋市中央児童相談所・児童相談所に係る企画調整担当課長
名古屋市職員として、児童相談所の児童福祉司やスーパーバイザー、本庁所管課で社会的養護施策や前期社会的養育推進計画の策定に従事。令和7年4月から現職。社会福祉士。

7. 土井 香苗(どい かなえ)
国際人権NGOヒューマン・ライツ・ウォッチ日本代表
日本での弁護士活動を経て、2008年から現職。日本の国内および外交政策において、人権が優先課題となるよう活動。1998年東京大学法学部、2006年ニューヨーク大学ロースクール卒業。

8. 福井 充(ふくい みつる)
元福岡市こども家庭課
児童福祉司や社会的養育推進担当としてパーマネンシーをめざす実践と施策を進めた経験から自治体職員の育成・研修に従事、著書に『パーマネンシーをめざす子ども家庭支援』。

9. 本庄 公多子(ほんじょう きたこ)
乳幼児総合支援センター栄光園 養子縁組里親支援機関ブレス・ユー統括責任者・里親リクルーター
栄光園の保育所で保育士として勤務した後、乳児院にて里親支援専門相談員として勤務。現在ブレス・ユーにて養子縁組里親の養成、県内の養子縁組里親、養親の支援を行う。
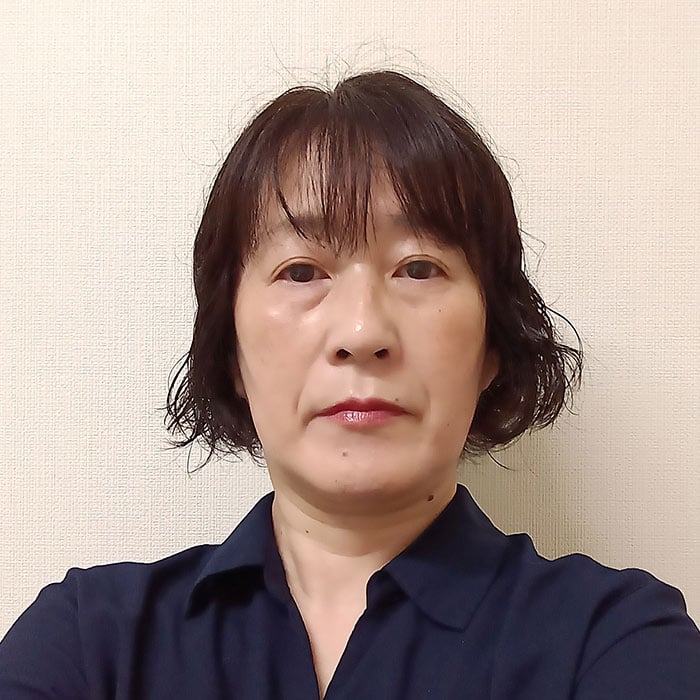
【分科会11】子ども若者支援のネクストリーダーたち
1. 川邊 笑(かわべ えみ)
一般社団法人 うみのこてらす 代表理事
2000年徳島県生まれ。筑波大学教育学類卒。人口3,400人の徳島県牟岐町を起点に、地域住民や学生とともに居場所運営に加え、訪問・オンライン支援も行う。

2. 濱野 将行(はまの まさゆき)
一般社団法人 えんがお 代表理事
栃木県大田原市にて、徒歩圏内に9軒の空き家を活用し、子どもから高齢者まで、全世代が集い、互いに支援し合う地域のコミュニティづくりを実践している。

3. 藤田 琴子(ふじた ことこ)
一般社団法人 青草の原 代表理事
母子生活支援施設でDV・貧困・障害など様々な事情で入所した親子と関わる中で「家族」を少し離れられる時間や場所の必要を感じ、「れもんハウス」を開く。社会福祉士、保育士。

4. 李 炯植(り ひょんしぎ)
認定特定非営利活動法人 Learning for All 代表理事
一般社団法人 社会的養育地域支援ネットワーク 共同代表
2014年にNPO法人Learning for All を設立、同法人代表理事に就任。困難を抱えた子どもへの無償の学習支援や居場所づくりを行う。一般社団法人社会的養育地域支援ネットワーク共同代表。

【分科会12】
1. 川瀬 信一(かわせ しんいち)
一般社団法人 子どもの声からはじめよう 代表理事
こども家庭庁 参与
千葉大学 非常勤講師
こどもの声をきいて、こどもともに声をあげる人。こどものとき、施設や里親家庭で育つ。大学院修了後、教師として10年働いて、独立。朝5時起きに挑戦中。うどんが好き。

2. 髙木 萌伽(たかぎ もか)
Leaf College Project副代表
認定特定非営利活動法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン(子どもアンバサダー2022-2023年度)
川崎市子ども会議子ども委員
子ども権利、子ども参加、アドボカシーについて活動する高校生。21年度子どもの権利条約フォーラムが契機となり、子どもの団体Leaf College Projectを設立。

3. 中島 早苗(なかじま さなえ)
特定非営利活動法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン・代表理事
新潟市子どもの権利推進委員会委員
1997年に米国NGOインターン時にFree The Childrenを知り理念に共鳴し、1999年に団体を設立。共著に「こども基本法こどもガイドブック」など。

4. Najla LEWAL(なじら れわる)
名古屋市立中学1年生
2024年秋に、アフガニスタンから難民として家族で移住。現在は名古屋市公立中学校に通う中学1年生。趣味は刺繍、手縫いの服つくり。

関連リンク
お問い合わせ
日本財団「子どもWEEKEND 2025」運営事務局
- メールアドレス:support@ideft.jp
※お問い合わせの際は件名に【子どもWEEKENDについて】とご記載ください。
※事務局ドメイン(@ideft.jp)が受信可能な設定にしていただきますようお願いいたします。





