未来のために何ができる?が見つかるメディア
第2回 NPO法人が知的財産を利用する際の注意点。注意すべき権利は? 許諾が不要な場合も含め弁護士が解説

執筆:阿部由羅
NPO法人が商品やコンテンツを開発または利用する際には、知的財産権に注意する必要があります。知的財産権にはどのような種類があるのか、侵害を避けるためにはどうすればよいのかなどについて、正しい知識を備えておきましょう。
本記事では、NPO法人の運営者や担当者が知っておくべき知的財産権の基礎知識を解説します。

知的財産権とは
知的財産権とは、知的な創造活動によって生み出された創作物について、その創出者に認められる権利です。主な知的財産権の種類としては、次の例が挙げられます。

特許権・実用新案権・意匠権・商標権は、特許庁の登録を受けることによって発生します。これに対して著作権は、登録を要することなく、著作物が創作された時点で当然に発生します。
知的財産権を侵害した場合のペナルティ
他人の知的財産権を侵害した場合には、次のペナルティを受けるおそれがあります。
- 知的財産権の利用差止め
- 損害賠償
- 刑事罰
●知的財産権の利用差止め
知的財産権の権利者は、自らの知的財産権を侵害され、または侵害されるおそれがある場合に、侵害行為の差し止めを請求できます。
差止請求を受けると、すでにリリースしている商品やサービスの自主回収や名称変更などを強いられ、多額の損失が生じるおそれがあるので要注意です。
●損害賠償
知的財産権の侵害によって権利者が損害を被った場合には、侵害者に対して不法行為に基づく損害賠償を請求できます。
特に、知的財産権を侵害する商品やサービスの売上によって得た利益は、その全額が損害賠償の対象となるケースが多いのでご注意ください。
●刑事罰
知的財産権の侵害は、刑事罰の対象とされています。
例えば、他人の特許権や著作権を侵害した者は「10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」に処され、または懲役と罰金が併科されることがあります(特許法196条、著作権法119条1項)。
逮捕されるリスクもある上に、実際に有罪判決を受けると前科が付き、刑務所に収監されるおそれもあるので十分ご注意ください。
知的財産権を侵害しないためのポイント
NPO法人においても、技術を活用した商品を開発・販売する場合、商品やサービスの名称を決める場合、コンテンツを制作する場合などには、他人の知的財産権を侵害しないように注意する必要があります。
知的財産権の侵害を避けるためには、次の対策を行いましょう。
- 先行の技術やコンテンツを事前に調査する
- 知的財産権について知見を有する従業員を雇用する
- 外部の弁護士や弁理士のアドバイスを受ける
●先行の技術やコンテンツを事前に調査する
特許権・実用新案権・意匠権・商標権(=産業財産権)については、「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」(外部リンク)などを参照すれば、先行している出願の情報を確認できます。
技術を活用した商品やサービスを設計する場合や、商品のデザイン・名称を検討する場合などには、必ず先行出願情報をチェックしましょう。
著作物については、オリジナルを参照しておらず、たまたま似てしまっただけであれば著作権侵害は成立しません。
しかし、権利者に著作権侵害を指摘されてトラブルになるリスクも想定されます。コンテンツを制作しようとする際には、似たような先行コンテンツがないかどうかをインターネットなどで検索して調べることが望ましいでしょう。

●知的財産権について知見を有する従業員を雇用する
NPO法人において、技術やコンテンツを取り扱う機会が多い場合は、知的財産権について知見を有する従業員を雇用することも検討すべきでしょう。
企業の法務部や弁理士事務所などに所属していた人材を雇用すれば、知的財産権に関する即戦力として期待できます。
●外部の弁護士や弁理士のアドバイスを受ける
知的財産権について相談できる外部の専門家としては、弁護士と弁理士が挙げられます。
弁護士は主に知的財産権の侵害に関するリスク分析や対応、弁理士は主に知的財産権の出願手続きを取り扱っています。ニーズに応じて弁護士と弁理士を使い分けましょう。
知的財産権の利用許諾が不要となるケース
各種の知的財産法では、権利者の許諾を得ることなく知的財産権を利用できる例外的ケースが定められています。
利用許諾の例外は多岐にわたるため、全てを一挙に紹介することはできませんが、次の代表的なケースを紹介します。なお、独断で知的財産権を無許諾利用することはリスクが高いので、弁護士などにアドバイスを求めることが望ましいです。
- 特許権・実用新案権・意匠権|法定通常実施権が認められる場合
- 著作権|私的使用・引用など
●特許権・実用新案権・意匠権|法定通常実施権が認められる場合
特許権・実用新案権・意匠権については、権利者の許諾を受けなくても、法律上当然に通常実施権(知的財産権を実施できる権利)が付与されることがあります。これを「法定通常実施権」といいます。
例えば特許法では、次のようなケースにおいて法定通常実施権が認められています。
- 従業員等が職務発明について特許を受けた場合には、使用者等に法定通常実施権が認められる(特許法35条1項)
- 特許出願に係る発明の内容を知らずに自らその発明をし、実際の当該発明を用いた事業やその準備を日本国内でしていた者には、法定通常実施権が認められる(同法79条) など
●著作権|私的使用・引用など
著作物については、著作権者の許諾を得ることなく利用できる例外的場合が、著作権法において数多く定められています。そのうち代表的なものとしては、「私的使用」と「引用」が挙げられます。
「私的使用」とは、著作物を個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することをいいます。
著作物の私的使用に当たっては、原則として著作権者の許諾を要しません。ただし、コピーガードの解除や違法ダウンロードなどは、無許諾で行うと著作権侵害となります(著作権法30条1項)。
「引用」とは、報道・批評・研究などの目的のために、他人の著作物を自己の作品に採録することを意味します。
次の要件を全て満たす場合には、他人の著作物を引用するに当たって、著作権者の許諾が不要となります(著作権法32条1項)。
- 引用する著作物が公表されていること
- 引用の必要性が認められること
- 引用部分とそれ以外の部分が明瞭に区別されていること
- 本文と引用部分が主従の関係にあること
- 引用する著作物を改変しないこと
- 出典を明記すること
まとめ
NPO法人においても、一般的な会社などと同様に、他人の知的財産権を侵害しないように注意する必要があります。特に技術やコンテンツなどを取り扱うNPO法人の担当者は、知的財産権に関する正しい知識を身に付けておきましょう。
〈プロフィール〉

阿部由羅(あべ・ゆら)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。注力分野はベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続など。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆・監修も多数手がけている。
ゆら総合法律事務所 公式サイト(外部リンク)
阿部由羅 公式X(外部リンク)
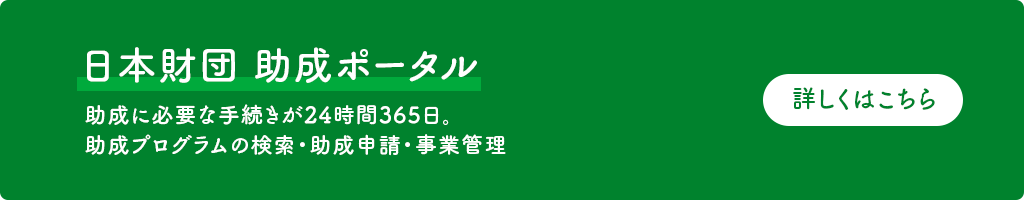
- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。











