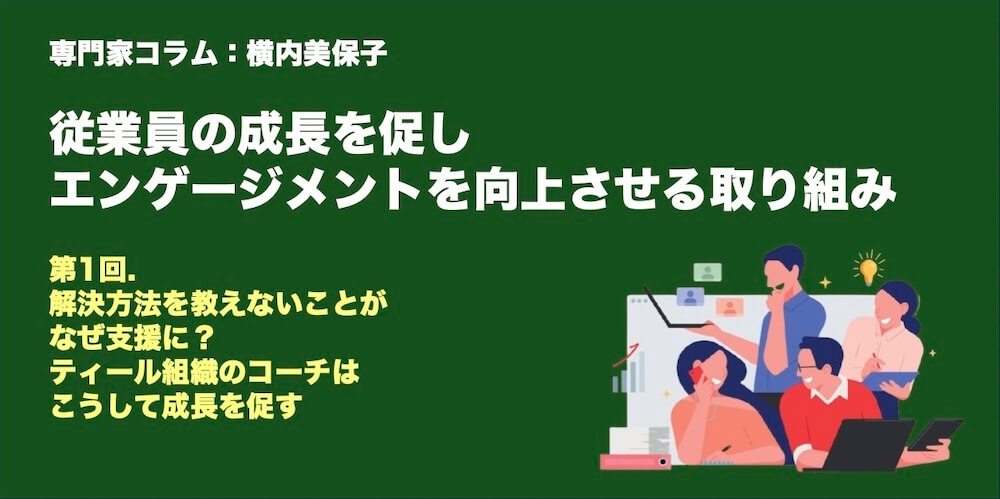未来のために何ができる?が見つかるメディア
第2回 失敗は学びの絶好のチャンス! 成長を促す「失敗とのつき合い方」とは?
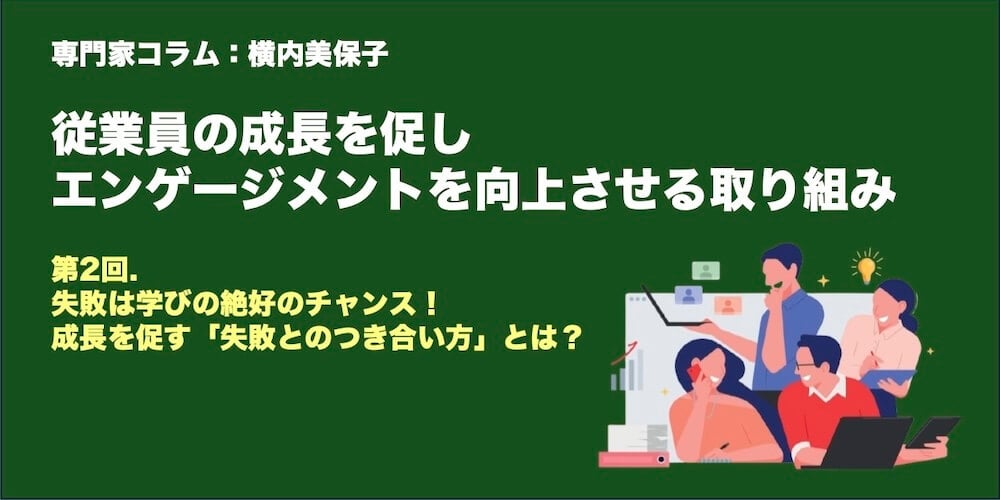
執筆:横内美保子
失敗は成功のもと。
よくいわれる言葉ですが、本当にそうなのでしょうか。
最近では、失敗は「し方ないもの」から「してもいいもの」へと捉えられ方が変化し、さらにそこからもう一歩進んで、「成長のために欠かせないもの」と考える人々もいます。
もしそれが本当だとしても、失敗した後にはなんともいえないネガティブな気持ちになるのがふつうではないでしょうか。
また、他者の失敗を許し、あたたかい気持ちで見守ってくれる人ばかりではありません。
科学的な知見を参照しながら、人の成長や組織の進化を促す「失敗とのつき合い方」について考えます。
失敗から学ぼうとする姿勢
航空業界は、安全が重視される業界の1つです。
この業界の失敗への向き合い方をみていきましょう。
飛行機は事故率が低いとよくいわれますが、どのくらいかご存じでしょうか。
国際航空運送協会(IATA)の年次安全報告書によると、民間航空業界では2023年に30件の事故が起こり、世界全体の事故率は100万フライトあたり0.80件、単純換算すると125万フライトにつき、わずか1件の割合になります。*1

このように、きわめて安全性が高い状況の背景には、技術革新や競合の厳しさ、保険コストなどの商業的なインセンティブの存在があります。*2
また、高解像度のシミュレーションシステムを用いた効果的な訓練法なども安全性に寄与しているでしょう。
しかし、その原動力は、航空業界の組織文化の奥深くにある「失敗から学ぼうとする姿勢にある」―イギリス『タイムズ』紙の第1級コラムニストのマシュー・サイド氏は著書『失敗の科学』の中でそう述べています。*3
その例としてサイド氏が挙げているのは、「ハドソン川の奇跡」です。
映画化もされているので、ご存じの方もいらっしゃるでしょう。
2009年、ニューヨークでの出来事です。*2
USエアウェイズ1549便が離陸した直後に、2羽の鳥がエンジンに飛び込み、左右のエンジンがどちらも停止するという緊急事態が発生しました。
ごく短時間での決断を迫られたサレンバーガー機長は、管制のアドバイスを拒み、ハドソン川への着水を成功させます。そして着水後は、乗客が全員、脱出したかどうか、客室内を2往復して確認しました。
死者数、ゼロ。
その冷静な判断と優れた操縦テクニックに称賛が集まり、機長はたちまちヒーローになります。
一方で、事故を分析した航空専門家は、機長の貢献だけでなく、システム全体をみていました。
専門家の中には、CRM(クルー・リソース・マネジメント)の成果を挙げた人がいました。
CRMとは、安全運航を達成するために、人、機器、情報など操縦室内で得られる利用可能なリソースを効果的に活用し、チームメンバーの力を結集して、チームの業務遂行能力を向上させる手法です。*4
パイロットは、CRMを通じて、コミュニケーション、乗員間の連携、指揮系統、意思決定に関する方法、技術を学び、その向上を図ります。
この事故では、機長と副操縦士は円滑なコミュニケーションをとりつつ、見事な連携プレーを発揮しました。*2
別の専門家は、機体の傾きを検知するセンサーが装備されていたことを挙げました。
緊急事態の際に不要なミスを犯さないための、チェックリストや人間工学デザインを評価した人もいました。
「ハドソン川の奇跡」の背景には、こうした複数の要因が絡んでいたのですが、実はこれらはすべて、過去の航空事故を教訓にして生まれたものです。
サレンバーガー機長は、事故の数か月後、こう述べています。
我々が身に付けたすべての航空知識、すべてのルール、すべての操縦技術は、どこかで誰かが命を落したために学ぶことができたものばかりです。(中略)大きな犠牲を払って、文字通り血の代償として学んだ教訓を、我々は組織全体の知識として、絶やすことなく次の世代に伝えていかなければなりません。
同氏は2019年、相次ぐ墜落事故を起こしたボーイング737MAX機のシミュレーターを操縦した経験をアメリカの下院議会で証言し、その経験に基づく提言を行っています。*5
「ハドソン川の奇跡」以降も、失敗からの学びは続いているのです。
非難や懲罰は失敗からの学びを阻害する
しかし、私たちは、常に失敗から学びを得られるとはかぎりません。
学びを妨げるものに「非難」があります。
非難は組織に強力な負のエネルギーを産んでしまいます。*2
何かミスが起こったときに「犯人捜し」をして非難を始めるような環境では、誰でも失敗を隠したくなります。
悪意のないミスを責め立てられたら、自分の失敗を進んで報告しようなどとは誰も思わないでしょう。
それではシステムが改善されることはありません。
「非難や懲罰には規則を正す効果がある」という考え方が組織の管理職に浸透していることが問題を深刻化させていると、サイド氏は指摘しています。
ハーバード・ビジネス・スクールの調査では、企業幹部が本当に非難に値すると考えているものは全体の2~5パーセントなのに対して、実際には70~90パーセントを非難すべきものとして処理しているという実態が浮き彫りになりました。
人間の失敗はシステムパフォーマンスを阻害する要因になるため、どうしても人間をシステムの安全性を脅かす存在だとみなしてしまう傾向があります。*6
そして、ミスの多い人間を「腐ったリンゴ」として扱い、システムから排除すれば安全性を維持することができると考えがちです。
しかし、環境が改善しなければ、また別のリンゴが腐ってしまう。
そう指摘するのは、人間工学の研究者、芳賀繁(はが・しげる)氏です。
人間工学では、ヒューマン・エラーは失敗の原因ではなく、より深いところにある問題の兆候であると考えられています。
ヒューマン・エラーは原因調査の結論ではなく、調査の開始点であるという捉え方です。
事故は注意力では防げないというのは、現在、安全問題の専門家の間では常識になっています。ヒューマン・エラーはランダムに発生するのではなく、道具やタスク、作業環境の特徴と規則的なつながりがあるのです。
そういう意味でも、ミスを犯した個人を非難するのは的外れです。
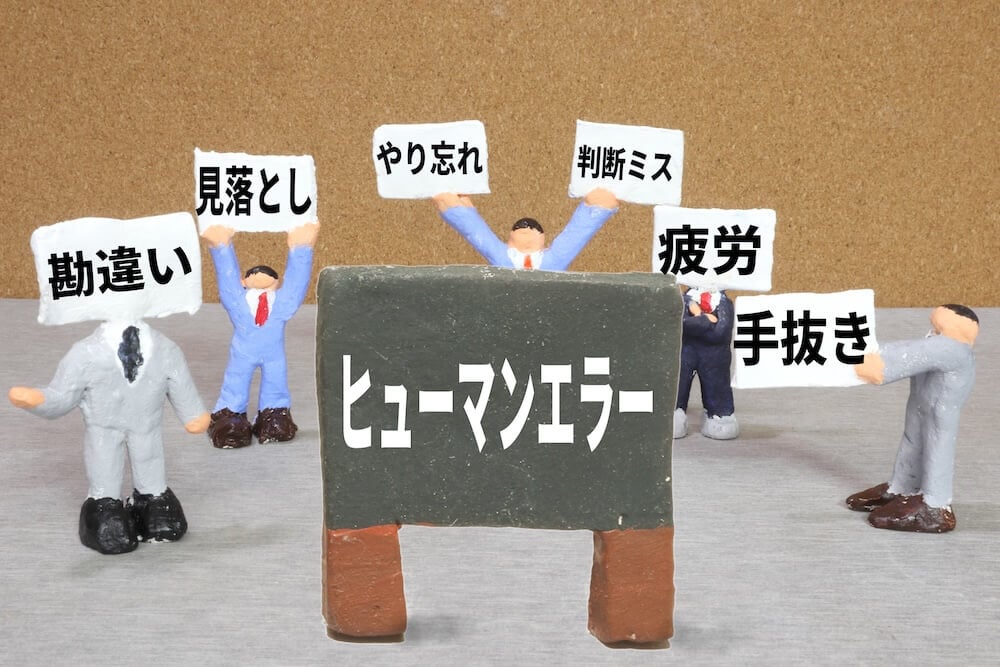
エラーを罰すれば、エラーを隠そうとしたり、エラーについて正直に話さなくなる可能性が高まります。それでは、事故の原因調査は阻害されてしまい、予防策を講じることもできません。
ハーバード・ビジネス・スクールのエイミー・エドモンド教授がある病院で行った調査では、興味深いことが判明しました。*2
懲罰志向のチームでは、看護師からのミスの報告は少なかったのですが、実際には他のチームより多くのミスを犯していました。
一方、非難傾向が低いチームでは逆にミスの報告数は多かったのですが、実際に犯したミスは懲罰志向のチームより少なかったのです。
世界的に著名な人間工学の専門家であるシドニー・デッカー氏も、「非難すると、相手はかえって責任を果たさなくなる可能性がある」と述べています。
非難されると、ミスの報告を避け、改善のために進んで意見を出すこともしなくなるおそれがあるのです。
不当に非難すればするほど、重い罰則を科せば科すほど、ミスは埋もれ、失敗から学ぶ機会を失って、同じミスが繰り返し生じることになります。
その結果、さらに非難が強まり、隠蔽体質が強化されるという、負の連鎖が生じてしまうのです。
失敗から学ぶための組織文化
もし「失敗は学習のチャンス」と捉えるような組織文化があれば、思わしくないことが起こったときに、犯人捜しをしたりミスを犯した人を非難するのではなく、まず何が起こったのか詳しく調べてみようという方向性が生まれるでしょう。*2
例えば、上でみた航空事故の場合はどうでしょうか。
アメリカでは国家運輸安全委員会(NTSB)が全面的な事故調査の権限と責任をもっています。*7
航空事故に関連した過失致死・傷害罪に当たる連邦刑法上の規定は見当たらず、連邦航空法でも航空法違反行為に対する罰金および行政処分についての規定はあるものの、刑罰は規定していません。
アメリカでは航空事故への責任追及の手段として、個人への刑事訴追は非常にまれです。*8
また、もし航空会社の乗組員・従業員やメーカーの従業員が会社から不利益をこうむることをおそれて証言しない場合には、会社が証拠隠匿罪に問われます。
このように、当事者がありのままを語りやすいシステムがあるため、それが情報開示性を高めているという側面があるのです。
調査終了後、NTSBは事実報告書を作成しますが、その報告書は原則として証拠資料や当時の気象情報とともに公開書類として扱われ、請求があれば誰にでも開示されます。
小さなミスも同様です。パイロットはニアミスを起こすと報告書を提出しますが、10日以内に提出すれば処罰されない決まりになっています。*2
さらに、航空機の多くには、設定した高度などを逸脱すると自動的にエラーレポートが送信されるデータシステムが装備されていますが、そのデータからは操縦士が特定されない仕組みになっています。
「失敗は学びのチャンス」と捉える文化があり、適切な調査を行えば、2つのチャンスがもたらされるとサイド氏は指摘しています。
ひとつは貴重な学習のチャンスです。失敗から学んで問題解決ができれば、組織の進化につながります。
もうひとつは、オープンな組織文化を構築するチャンスです。
ミスを犯しても不当に非難されなければ、当事者は自分の偶発的なミスやそれに関わる情報を進んで報告するようになり、組織の進化はさらに進みます。

失敗から学ぶ「成長型マインドセット」
では、失敗から学び、成長するためのマインドセット(思考傾向)とはどのようなものでしょうか。
興味深い実験があります。*2
ミシガン州立大学の心理学者ジェイソン・モーザー氏は、異なるマインドセットをもつ人たちの、失敗への向き合い方を調べたのです。
そのマインドセットとは、「固定型マインドセット」と「成長型マインドセット」です。
「固定型マインドセット」の傾向のある人は、知性や才能は生まれつきのもので、変えることはほぼできないと信じています。
一方、「成長型マインドセット」の傾向のある人は、先天的な資質がどうであれ、根気よく努力を続ければ、自分の資質を高めて成長できると信じています。
失敗に対するそれぞれの被験者の脳波反応をみると、2つのグループには劇的な違いがありました。
失敗に気づいたときの反応には差がなかったのですが、失敗に意識的に着目する反応は、成長型マインドセットの人たちの方がはるかに強いという結果になったのです。
この実験では、失敗に意識的に着目する反応の強い人ほど失敗後の正解率が上昇するという結果が得られ、失敗への着目度と学習効果との密接な相関関係が窺えました。
こうした結果を受け、失敗から学べる人と学べない人との差は、「失敗の受け止め方の違い」にあるのだと、サイド氏は指摘します。
個人でも組織でも、失敗に真正面から取り組めば、成長できるのです。
おわりに
失敗にはどうしても負のイメージがつきまといます。
失敗を嫌い、避けようとするのは、自然な感情かもしれません。
また、私たちにはややもすると、失敗した人を非難しがちな傾向があります。
しかし、失敗は組織の学びにとって必要不可欠なものであるとして、「戦略的なつまずき体験」の重要性を主張する研究者もいます。*9, *10
また、実は「成功する見込みの最も高い戦略は、失敗する見込みも最も高い」ことから、成功の反対は失敗ではなく、「凡庸」であると指摘する研究者もいます。*11
失敗を恐れるあまりリスクをとらないという態度は、トライ&エラーからの学習機会を失うことにつながり、そうしていたら成功は訪れないということです。
人間である以上、失敗は避けられません。
しかし、失敗を過度に恐れず、失敗しても逃げずに、失敗を真正面から受け止める。
そして失敗の責任を追及するのではなく、原因を分析してそこから学び、その学びを共有すれば、人も組織も成長することができます。
「失敗は学びの絶好のチャンス」と捉える組織文化が、そうした成長の源泉になるでしょう。
[資料一覧]
*1.参考:IATA“IATA Annual Safety Report Executive Summary”(外部リンク)
*2.参考:マシュー・サイド(2016)『失敗の科学』株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン(電子書籍版)No.327, 439, 616, 624, 635, 644, 653, 675, 2896, 2900, 3003, 3024, 3035, 3472, 3482, 3494, 3504
*3.参考:東洋経済オンライン「マシュー・サイド(ましゅー・さいど)」(外部リンク)
*5.参考:CNN「ハドソン川の奇跡」の操縦士、737MAXの模擬飛行体験を議会証言」(2019.06.20 Thu posted at 12:02 JST)(外部リンク)
*7.参考:公益社団法人日本航空機操縦士協会(山森久彰)「航空事故調査の制度について思う—- 処罰では過ち正せず」 p.3(外部リンク/PDF)
*8.参考:城山英明・村山明生・梶村功「米国における航空事故をめぐる安全確保の法システム~日本への示唆~」『社会技術研究論文集』Vol.1 p.149, p.151, p.152(外部リンク/PDF)
*9.参考:Web of Science“LEARNING THROUGH FAILURE – THE STRATEGY OF SMALL LOSSES”(外部リンク)
*10参考:池田浩・三沢良「失敗に対する価値観の構造―失敗感尺度の開発」p.368(外部リンク/PDF)
*11参考:石坂庸佑「戦略的失敗の論理の探求―「成功のパラドックス」の超克をめざして」『九州共立大学経済学部紀要』p.8
〈プロフィール〉

横内美保子(よこうち・みほこ)
博士(文学)。総合政策学部などで准教授、教授を歴任。専門は日本語学、日本語教育。高等教育の他、文部科学省、外務省、厚生労働省などのプログラムに関わり、日本語教師育成、教材開発、リカレント教育、外国人就労支援、ボランティアのサポートなどに携わる。パラレルワーカーとして、ウェブライター、編集者、ディレクターとしても働いている。
横内美保子 公式X (外部リンク)
横内美保子 公式Facebook(外部リンク)
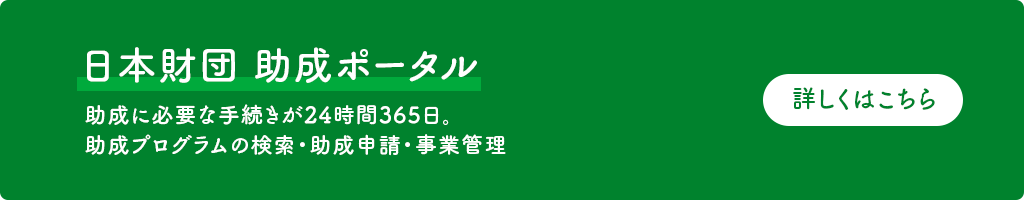
- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。