未来のために何ができる?が見つかるメディア
新型コロナウイルスに翻弄される里親家族。「子どもを預かる」家庭に必要な支援とは

- “子どもを預かる”里親家庭では、新型コロナウイルスに対し「絶対に感染させてはいけない」という強い思いや不安を抱えている
- 「LOVE POCKET FUND」(愛のポケット基金)では、全国の里親家庭への衛生用品やタブレットの支援を実施
- 感染防止を徹底すると共に、リアルとオンラインの強みを生かして里親制度の普及を目指す
取材:日本財団ジャーナル編集部
私たちの日々の暮らしに、大きな影響を与え続けている新型コロナウイルス。日本財団ジャーナルでは、これまでも逼迫する医療機関や貧困で苦しむ家庭に必要な支援について取り上げてきた。
今回、焦点を当てるのは、里親家庭への支援だ。
親の病気や離婚、虐待などさまざまな事情により、生みの親と一緒に暮らせない子どもが、別の家庭で一定の期間暮らしを共にする「里親制度(養育里親)」。日本では、約4万5,000人にいる社会的養護(※)下にある子どものうち約20パーセント(約7,000人)が、里親家庭で暮らしている。
- ※ 子どもが家庭において健やかに養育されるよう実親や親族を支援する一方、親の虐待や病気等の理由により親元で暮らすことのできない子どもを里親家庭や児童養護施設等において公的に養育する仕組み
新型コロナウイルスの影響で、人と人とのつながりが分断されがちな今、里親家庭が置かれている現状と必要な支援について、公益財団法人「全国里親会」(別ウィンドウで開く)会長の河内美舟(こうち・みふね)さんと、NPO法人「東京養育家庭の会」(別ウィンドウで開く)の副理事長を務め、ご自身でも里子を養育する星野優子(ほしの・ゆうこ)さんに話を伺った。
新型コロナによって分断されたもの
「新型コロナウイルスの影響で、すでに2020年に行われる予定だった全国里親大会は全て中止・一部延期(2020年8月時点)になり、他にも里親支援プログラムの一環である『里母の集い』や地域単位での集まりが実施できなくなっています」
そう話すのは、全国里親会で会長を務める河内さん。全国里親会では、里親制度に関する調査研究、里親希望者の開拓、里親や里親に委託されている児童の相談指導などを行い、里親制度の普及発展に努めている。
また、日本の各地域にある里親会と連携し、里親や児童相談所、乳児院の職員、研究者などが集まり問題や解決策を共有する全国里親大会の開催や、里親研修会なども実施している。
「居場所を必要とする子どもたちは、その数が分かるだけで全国に約4万5,000人もいます。そんな彼らの受け入れ先となる里親家庭も、新型コロナの影響で新規の募集が滞っている状況です」
里親になるには、研修や家庭訪問調査を受ける必要があり、里親として認定されるまでに数カ月から半年以上かかることもある。現在は、オンラインでの研修プログラムを開発中ではあるが、しばらくは里親家庭を増やせないということも河内会長の悩みのタネでもある。
「子どもの安全第一を念頭に置きつつ、全国里親会としてもやるべきことを進められたらと考えております」
ここからは、里親家庭の現状についても焦点を当てていきたい。新型コロナウイルスの感染拡大によってどんな問題を抱えているのだろうか。
東京養育家庭の会の副理事長を務め、現在3人の里子を育てている星野さんに話を伺った。
「新型コロナの影響としては、一般のご家庭と同じ大変さと、里親家庭ならではの大変さがありました。一般家庭と同じ大変さとしては、卒業式や入学式といった子どもにとって大切な学校行事をやるのかやらないのか分からない状況が長引いたこと。仕事も育児も家でしなくてはならず、仕事に集中しづらく、長期間に及ぶ自粛でストレスがかかってしまうこと。たくさんの宿題を抱えた子どものサポートをする大変さなどでしょうか」

「一方で、里親ならではの苦労としては、里親は一般家庭や養子縁組とは異なり、お子さんを『預かっている』立場なので、絶対にコロナに感染させてはいけないし、私たちも感染してはいけないという思いはかなり強かった。しかしコロナが流行り出した時には、すでに衛生用品は売り切れでしたし、マスクも詐欺のような高額なものしか手に入らず、とても不安に駆られたことを覚えています」
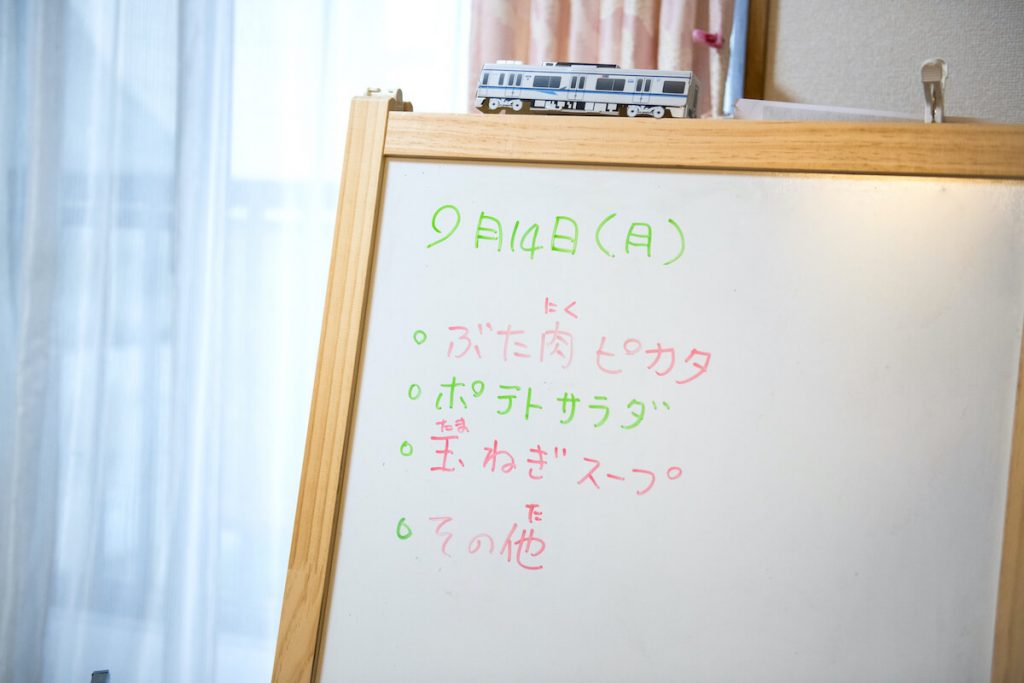
恒例にしていた家族旅行はもちろんキャンセル、日々の買い物も含めて自身も子どももできるだけ家から出ないように心掛けていたという星野さん。他にも、星野さんが副理事長を務める東京養育家庭の会では、里親同士の交流イベントや、夏のキャンプなどは中止を余儀なくされた。
「いま、気掛かりなのは今年や来年、社会的養護を終えて自立していく子どもたちの心のケアでしょうか。本人、里親さん共に先行きの見えないコロナの状況に、いろんな不安を抱えていらっしゃることでしょう。そのためにも、東京養育家庭の会でも、できることがあれば何でもサポートしていきたいと思っています」
人と人とのつながりと、希望や勇気を届けた支援
日本財団は、タレントの稲垣吾郎さん、草彅剛さん、香取慎吾さんによる「新しい地図」と共に「LOVE POCKET FUND(愛のポケット基金)」(別ウィンドウで開く)を立ち上げ、そこで集まった寄付金を支援の必要なNPOや団体に届けている。

その助成先の第3弾として、全国里親会への支援を実施。全国里親会を通して、全国約7,000カ所の里親家庭に衛生用品(消毒用アルコール、マスク、非接触体温計、防護服など)やタブレットの無償提供を行なっている。
現在も密な接触を控える必要がある状況の中で、里親家庭の孤立と、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐことが目的となり、タブレットは、インターネットに手軽にアクセスできる環境を整え、オンラインによる研修や面談を実施しやすくするためのものだ。

「私が所属する東京養育家庭の会にも、会員の方から『大切に使います』『里親同士でつながりたいときに活用します』といった、喜びのメッセージがたくさん届いています」
衛生用品やタブレットを全国里親会から受け取り、東京養育家庭の会に所属する里親家庭へ届けたという星野さんは、各家庭からの反響をこう語る。

「これまで日本では、海外と比べて里親制度に対する理解や普及が進んでいない面もありました。でも、国民的なアイドルの皆さんが立ち上げた基金ということもあって、この支援を機会に、今後より里親に対する理解が社会全体に広まっていくとうれしいですね」
全国里親会の河内さんも「コロナ禍で暗くなっていたところに支援をいただいて、本当に勇気づけられました」と喜びの気持ちを語った。

リアルとオンラインの活用で里親制度の普及を目指す
今後の展望について、全国里親会会長の河内さんに伺った。
「オンラインは私たちの活動に欠かせないものになってくると思います。会員同士のオンライン会議による情報共有はもとより、里親研修のオンライン化が実現すれば、より多くの方に里親に対する理解を深めていただく機会を増やしていくつもりです」
今回の新型コロナウイルスの影響により打撃も受けたが、これを機会にリアルとオンラインをうまく活用しながら里親家庭を増やしていきたいと、思いを語る河内さん。
「各地域の里親会とも連携して、悩みや成功事例などの共有をスムーズにできればと。オンラインを積極的に活用して、多くの情報を発信していけたらと考えています」
今後、オンライン化が加速していくと言われるウィズ・コロナ時代。社会的養護の子どもへの理解、里親制度の普及も加速することを願ってやまない。
撮影:新澤 遥
- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。













