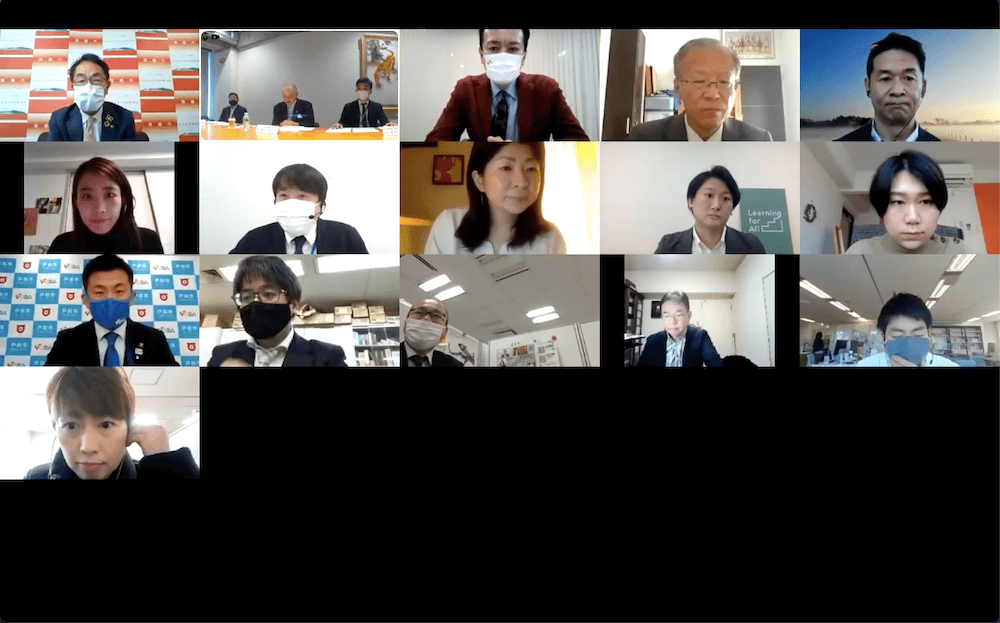未来のために何ができる?が見つかるメディア
子どもと親の成長に寄り添う「子ども第三の居場所」A拠点レポート 前編

- コロナ禍に困難を抱える子育て家庭も多い
- 「子ども第三の居場所」A拠点では、子ども・親の問題に向き合い、きめ細かく支えている
- コロナ禍の影響で、生活の乱れが目立つ。その対応や、持続可能な体制づくりが課題
取材:なかのかおり
2020年春、新型コロナウイルス拡大の影響で学校が突然、休校になり、子育て家庭は大きな衝撃を受けた。そうしたコロナ禍の子どもの暮らしについて、当事者として取材・研究する中で、子どもの食と学習を支え、寄り添う大人がいることの大切さを痛感している。
日本財団は、多様な困難を抱える子どもたちが安心して過ごせて、自立し生きていく力を育む「子ども第三の居場所」(外部リンク)プロジェクトを進めている。困難を抱えた保護者や子どもたちを支えるコミュニティを目指し、全国500カ所の拠点整備に取り組む。
子どもたちは、どんな場所で、どんな過ごし方をしているのか。今回は、関西のA拠点を取材した。前編では、拠点の日常や、スタッフと子どもとの関わり、親のサポートについて紹介する。
関西の「子ども第三の居場所」A拠点は数年前に開所し、日本財団が助成した。2021年度からは地元の自治体の補助金も活用して、非営利団体に業務委託している。
放課後や長期休みに通う小学生は10人ほどいて、パートタイムも含めスタッフは日々4~5人。学校の教室にプラスして、食卓・台所のダイニングスペースぐらいの広さで、入浴できる設備もある。利用料は収入に応じて支払う。

愛着感じるコミュニケーションも必要
拠点の日常は、どんな様子なのだろうか。関西のA拠点のスタッフの佐藤さん(仮名)に2021年5月、オンラインで取材した。
佐藤さんはこれまで、発達障害のある子の支援や学習支援に携わり、不登校の子の居場所などで働いた経験もあるそうだ。緊急事態宣言が繰り返され、落ち着かない毎日だが、何とか日常が過ごせているという。
「現在は、マスクを着用し、テーブルにアクリル板の仕切りを付けています。感染予防もしつつ、子どもとの距離感も大切にしています。ソーシャルディスタンスは大事ですが、必要以上に距離を取ることはしません。愛着形成がうまくいっていない子にとっては、寄り添うコミュニケーションが必要だからです。
日常のスケジュールは、こんな感じです。学校が終わったら、低学年の子はスタッフがお迎えに行き、大きい子は歩いて拠点に来ます。鬼ごっこやボールを転がして遊ぶなど体を動かしたい子と、カードやボードゲームをやりたい子とで、分かれて遊びます。全員が揃う4時頃におやつを食べて、5時頃から、スタッフがサポートしながら宿題をします。
6時半頃に、夜ご飯です。おかずは配食サービスを利用し、ご飯は寄付されたお米を炊いています。それに汁物を作っていましたが、緊急事態宣言中はインスタントにしています。7時半頃、お迎えの保護者が来て帰ります。お風呂に入ってから帰る子もいます」
一般的な学童保育や小学生の預かりでは、コロナの影響でスタッフとの物理的な触れ合いが制限され、それぞれ前を向いて座っているだけの時間もあり、子どものおしゃべりを禁止するのが心苦しいというスタッフの声も聞いた。
拠点では「愛着形成には、子どもの状況・背景を理解し、丁寧に関わることが必要」と心理的な触れ合いも心がけている。また、拠点で入浴もできる。入浴させてもらえなかったり、おっくうになっていたり、という家庭もある。入浴しないと体が温まらないし、清潔が保てず、自信が持てなくなるからだという。
子どもと時間をかけて話す関係づくり
佐藤さんによると、拠点を利用するのはシングルマザーの家庭が多い。他に、両親や祖父母がいるが、困難を抱える場合や、発達障害のある子もいる。
小学生のまことくん(仮名)は、家庭の中で、抑圧的な親子関係を強いられていた。
「体に傷をつくってくることもありました。自分の意思を、支配的なお母さんに認めてもらえない。行政からリスクが高いと聞いていましたが、そういった事情は、接してみないと分かりませんでした。普段の関わりの中で、態度や表情から、徐々に問題を読み取って行きました。スタッフと打ち解けるのに、数カ月かかりました。
まことくんは、何が食べたいとか、やりたいとか言えなくて、年単位で時間をかけて、気持ちを出せるように、丁寧に接しました。次第に、気持ちを言ってもいい、受け止めてくれる人がいると思えるように。まことくんは、やりたいことを表現するようになりました。お母さんに何かされて困った時、『嫌だった』と言えるようになったんです。そんな相談できる空気づくりを大事にしています」(佐藤さん)
子どもたちの抱える問題はそれぞれ違うので、その都度、手探りで向き合う。
「まことくんの場合、毎月、働きかけの方法を変えました。信頼関係をつくって、当時取り入れていたアートワークを、気持ちを表現する手段に活用しました。工作では、きれいな色使いをするのですが、お母さんとの関係がうまくいってないと、グレーになる。これってどんな気持ち?と聞くと、モヤモヤを現わしていると答えました。表現する手段が増えましたね」

厳しい母親だった…。子との関わり方を学ぶ
困難を抱える子どもの支援をする際、家庭・保護者へのアプローチも欠かせない。だが、関わり方によっては、信頼をなくして子どもが拠点に来なくなる可能性もあり、家庭とつながった糸を切らないように、繊細な配慮が必要だ。
行政や学校からがいいのか、どう伝えるのがベストか、リスクも含めよく考える。保護者自身に、サポートが必要な場合も多い。
「あるお母さんは完璧主義で、お迎えに来たら、まずお子さんの宿題を確認していました。漢字のはねができていないとか、その場で直させる。お母さんが、子どもを力でコントロールする以外のコミュニケーションがありませんでした。お子さんが帰りたがらない時、強く言って、引っ張っていました。
でも、帰りたがらない時のスタッフの関わり方を見て、参考になったみたいです。『なんで帰りたくないの?』って聞いてみたり、気持ちが高ぶっているからクールダウンスペースで待ってみたり。居場所が楽しくて気持ちが切り替えられない、クールダウンができなかったとお母さんも分かって、『時間だからこうしなきゃ』ではなく、待ってくれるようになりました。子育てに困難を感じて、お母さん自身も、苦しかったのではないでしょうか」(佐藤さん)

地域の中で増えてほしい
このように、子どもに寄り添い、共感して、生きていく力を育てる。食事や学習のサポートをする。そんなシンプルなことが、現代の親たちには困難になっている。通常の学童保育より少人数で、サポートも手厚いこうした拠点は、もっと必要なのではないだろうか。
「ニーズは、対象範囲や条件を広げればもっとあると思います。できれば、学校から歩いて行ける場所にあればいいですね。支援が必要な家庭を掘り起こすのは、行政との連携が必要です。学校と連携していても、学校から家庭にアプローチをするのはハードルが高い。きっかけがあればいいですが、家庭に『困っていませんか』と声をかけるのは難しいでしょう。私たちの拠点では、行政がニーズのある家庭に丁寧に説明して、見学まで導いています。
学校には、拠点に来ている子のことを報告しています。年に一回ぐらいは、『こういう課題があり、働きかけたことでこういう状態になりました』とまとめてレポートを渡します」
地域に溶け込み、持続可能な居場所であり続けるために、努力もしているという。
「スタッフも常に勉強しています。大学生やパートも含め、研修をします。大学の先生やスーパーバイザーを招き、みんなで考えています。小学校を卒業した後に通う、次の居場所とも連携しています。コロナで中止している商店街のバザーが復活したら、私たちも参加したいです。お迎えの時、挨拶して地域の人に知ってもらったり、建物の消防訓練に参加したりしています」
後編では、2020年の休校から学校再開、現在まで、コロナ禍の子どもの居場所について紹介する。
子どもと親の成長に寄り添う「子ども第三の居場所」A拠点レポート 前編
コロナ禍に揺れる心身を支えて「子ども第三の居場所」A拠点レポート 後編
〈プロフィール〉
なかのかおり
ジャーナリスト、早稲田大参加のデザイン研究所招聘研究員。早大大学院社会科学研究科修了。新聞社に20年余り勤め、地方支局や雑誌編集部を経て、主に生活・医療・労働の取材を担当。著書に、ダウン症のあるダンサーと芸能界の交差を追ったノンフィクション『ダンスだいすき!から生まれた奇跡 アンナ先生とラブジャンクスの挑戦』(ラグーナ出版)。調査報告書に『ルポ コロナ休校ショック〜2020年、子供の暮らしと学びの変化・その支援活動を取材して見えた私たちに必要なこと』『社会貢献活動における新しいメディアの役割』など。講談社現代ビジネス・日経電子版・ハフポスト等に寄稿している。
- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。