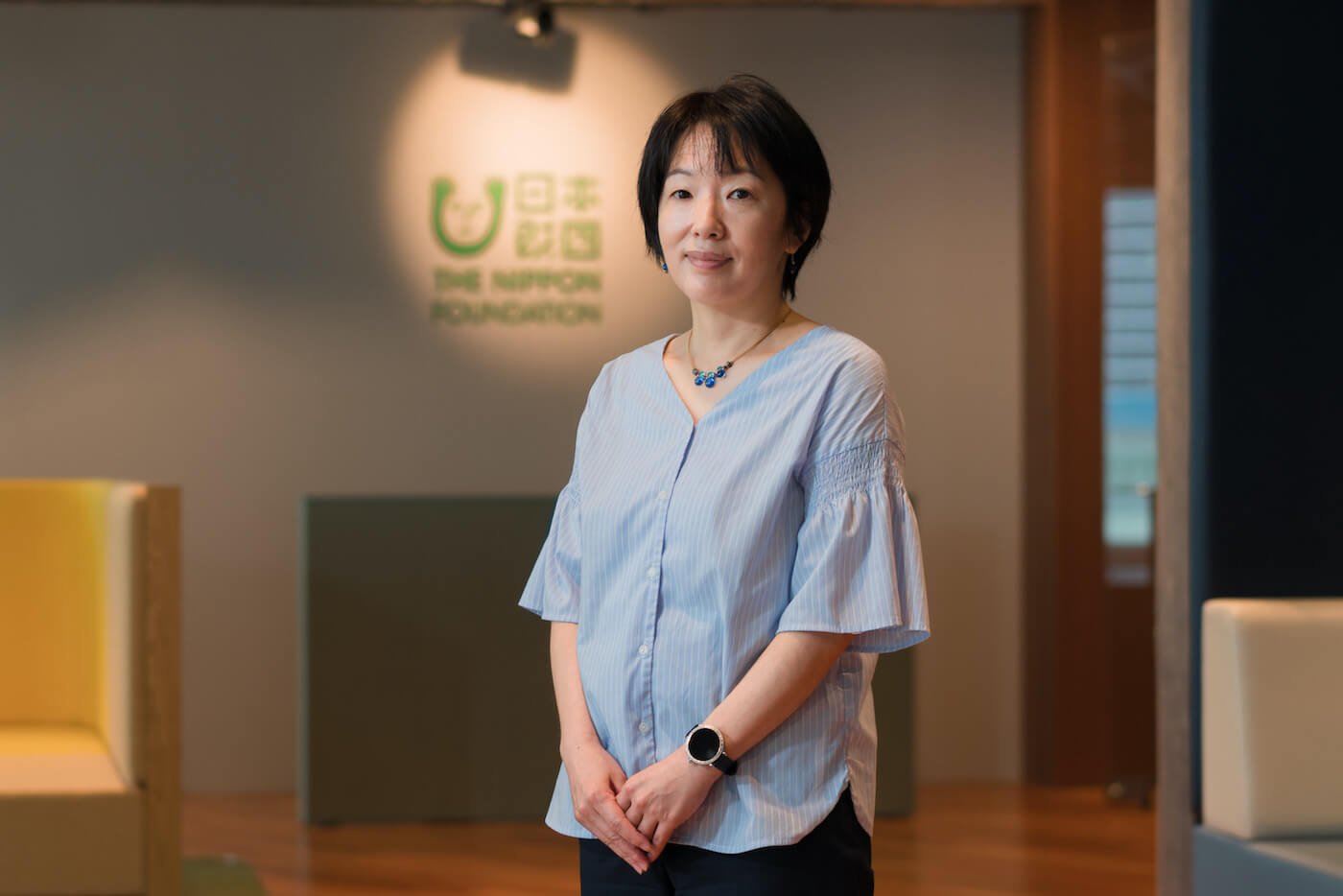未来のために何ができる?が見つかるメディア
【子どもたちに家庭を。】「血のつながりがない」事実は家族の土台。特別養子縁組で子を迎えた池田麻里奈さんの思い

- 養子縁組に対する意識のすれ違いを無くすためには夫婦での「対話」が重要
- 妊娠~出産という準備期間が養子にはない。突然の暮らしの変化に備える
- 養子も養親も「ただの人・ただの家族」。特別な配慮より、普通の接し方を
取材:日本財団ジャーナル編集部
特集「子どもたちに家庭を。」では家庭養育の中でも、養子となる子どもの生みの親との法的な親子関係を解消し、実の子と同様の親子関係を結ぶ「特別養子縁組」に焦点を当て、制度の現状や利用拡大に対する課題について多様な当事者たちに取材を続けてきた。
今回登場する不妊ピア・カウンセラー(※)池田麻里奈(いけだ・まりな)さんは、民間の養子あっせん団体への登録を経て、2019年に0歳児の子どもを迎え、特別養子縁組制度を利用して家族となった「養親」当事者だ。
- ※ 同じ背景を持つ人同士が、対等な立場で話を聞き合い、仲間の自立支援を行うカウンセラー
最初は社会的養護(※)に関心がなかったという夫の池田紀行(いけだ・のりゆき)さんと共に特別養子縁組という選択をするまでの夫婦間の葛藤、養子縁組家庭が直面する課題、そして血のつながりを超えて育まれる養子との関係について、その体験と心の変化について話を伺った。
- ※ 保護者がいない、または保護者による養育が難しいと判断された子どもを、公的責任によって養育・保護する仕組み
「私は、家庭をつくりたい」。長い不妊治療を経て再確認した思い
池田さんが結婚したのは28歳の時。当事30歳だった夫共々、いつか子どもを産み育てることを思い描いていたが、なかなか妊娠につながる兆候が見られず、結婚2年目から不妊治療を開始した。10年以上も続いた治療生活の中で、2度の流産と死産を経験。特別養子縁組という選択肢は、2度目の流産をした頃から頭の片隅にあったという。
「不妊治療って終わりがないんです。またダメだった……と先が見えない日々を過ごす中、養子という選択肢を検討するのも方法ではないか、と考えました。しかし夫に相談したところ『他人の子を引き受けて愛せる自信がない。40歳までは不妊治療を続けてほしい』と。その頃、友人たちは妊娠・出産ラッシュ。『目がパパに似てるよね』とか『産んでくれた妻にありがとう』などの言葉を見聞きすると、私自身も養子を選ぶのは実子を諦めることに思えて決断できませんでした。産めない、顔が似ていない、血のつながりがない、など、当事は“ない”ことばかりに目が向いていたと思います」

ひとりで悩むのに限界を感じた池田さんは、35歳で「養子縁組を考える会」を発足。養子縁組を検討する10~15人が集まり、養親や里親など当事者を招いて勉強する集いを始めた。
「私も含めメンバーの多くは、実際に養子を迎えて暮らす家庭を見たことがありません。血のつながりがなくても愛せるのか?周囲の人たちの反応は?など抱く不安は共通していました。でも、目の前の養親さんが『愛せます』と話しても、自分たちがそうできるかは事前に分かるものではない、と気付いて。不安が解消されるかというより『この不安は、真剣に考えるほど生まれる自然な感情なんだ』と気付けたことが大きな一歩だったと思います」


36歳で待望の妊娠をするも、妊娠7カ月での死産を経験。その後、乳児院の赤ちゃんに対する抱っこボランティア、中高生の性の悩みを電話で受ける団体など子どもに関わる活動を続けるうちに、養子を迎えたいという意志が固まっていったのだとか。
「電話相談には『親には悩みを言えない』という子が本当に多いんです。外に助けを求めることはもちろん大事ですが、普段から子どもを守る言葉をかけ、自己肯定感を育めるのは親であり家庭。その影響がどれだけ強いのか実感させられました。もちろん親じゃない大人の役割も大切で、私もそんな大人の1人でいいと思い、ボランティアをしていたのですが、子どもに関わるたびに『親になりたい。ひとりの子の隣にいたい』という思いがあるのを実感したんです」
養子を迎えるにあたって、ためらう夫との意思統一には数年を要した。共通の趣味を持つ仲のいい夫婦とはいえ、うまく「対話」ができなかった、と池田さんは当事を振り返る。
「楽しいことは気軽に話せても、不妊に悩む苦しさ、子どもを育てたいのに叶わないつらさは口に出しにくいものです。一緒に暮らし、隣にいるのだから気付いているだろう、と思っても決してそうではありません。養子を検討してほしいことを話しても『今は無理』『夫婦2人でもいいのでは?』と答えが返ってくる。したかったのは、私が“なぜ”養子を迎えてまでも子育てがしたいのか、彼が“なぜ”無理だと思うのか、という話し合い=対話なのですが、単なる要望と回答のやり取りになりがちでした」
そんな中、30代後半から悪化した子宮腺筋症の影響で、42歳の時に子宮を全摘出することに。もう子どもは望めないと覚悟したその時『産めないけれど、育てたい!』という強い気持ちが湧き上がってきたという。
「そこで夫に手紙を書き、私の人生で叶えたい夢は子どもを育てることで、産めなくても育てることを諦めたくない、養子を考えてほしいという気持ちを綴り、手術直後に渡しました。それを読んで初めて『分かったよ、君に付き合うよ』と答えてくれたんです」

その日は突然やって来た。「明日までに、返事をください」
意思統一した後の2人の行動は早かった。退院翌月には児童相談所に行き、養親希望者として面談を受けたのだ。そこで、養親認定を受けるまでの道のりの長さに驚かされる。
「2月に面談を受けても、基礎研修を受けられるのが最短で夏。その後に認定を受けられるのが翌年3月で、もしそのタイミングを逃したら次の認定は秋だと言われました。養親になるには年齢上限の目安がありますから、40代を超えた私たちに残された時間はあまりないのだと、そのとき実感しました」
このことがきっかけで、民間の養子あっせん団体の利用を視野に入れ始めた池田夫妻は、関心を持った団体の説明会に夫婦で参加する。
「登壇した代表者は、最初から『特別養子縁組は子どもがほしい親のための制度ではなく、子どもの福祉のための制度である』と厳しいほどしっかり話されました。養子さんを伴った養親の先輩が3~4組、リアルな体験談を話してくださる場や、養子を検討している夫婦同士の交流もありました。『子どもと母親を救う』という団体の理念が明確なことに夫も感銘を受けたようで、ここにお願いしようと2人の気持ちが固まったんです」
委託される子どもの年齢は0~6歳(2020年の民法改正により現在は0~15歳)で、性別・年齢・障害の有無を問わないことは児童相談所・民間あっせん団体に共通する条件となる。どのような子どもを迎えるか分からないことに対し、不安がなかったと言えば嘘になる、と池田さんは言う。
「私たちの場合は、最終的に自分が産めないのに他人に条件をつけるのはおかしい、という形で納得できました。自分の子どもですら、たとえお腹の中で健康であっても産まれてみるまで何があるのか分からないものだから同じことだ、と。でも無理に覚悟をする必要はないとも思います。例えば不妊の場合は、そのままでも夫婦2人の生活が続いていきます。それを漫然と送るのではなく、他の選択肢を夫婦で検討した結果2人で生きていこうと決める、というプロセスがあることは今後の人生を前向きにするのではないでしょうか」

研修や面談、家庭訪問などの過程を経て、団体の養親登録を終えた池田さんご夫妻。そして“その日”は突然やって来た。団体から電話があり、10日以内に生まれる赤ちゃんがいるため、委託できるかどうか明日までに返事がほしい、と伝えられたのだ。
「支援が必要な母子の中には、飛び込み出産など急を要するケースがあるとは知っていました。しかし心の準備をしていたはずが、電話を切ってもドキドキが収まりません。これだけ急であれば、養親とつながれずに乳児院に入所せざるを得ないケースが多いのも理解できる気がしました」
奇しくもその日は夫の誕生日。早速話したところ「断る理由ないよね?」と前向きな即答。そのひと言に助けられた、と感じたそう。
「不妊治療でもそうですが、優しさのつもりで『君がやりたいなら続けよう』と夫が妻に言うことで、判断を丸投げされたように感じて女性が苦しむ例がたくさんあります。もしその時に『決めていいよ』と言われていたら1人で多くの責任を背負っていたと思いますが、夫がはっきりと意志を示してくれた。そこで不安の霧が晴れたように感じました」
ママ友や地域の人たちとの交流を、自らつくっていく意識で
衣類やベビーベッドなど赤ちゃんに必要な物を慌てて買い揃え、迎えたのは生後5日の男の子。赤ちゃんとの24時間がいきなり始まる、この急なシフトチェンジは正直大変だった、と池田さんは当事を振り返る。
「通常の出産なら妊娠中に赤ちゃんを迎える準備をし、体調の変化に慣れ、夫も育児休暇を申請するなどサポートの準備をします。でも養子の場合はその期間がないため、夫も既に予定を入れています。出産による心身の負担がない分、私1人でもなんとかなるかな? と思っていましたが、ミルクにおむつに抱っこと、赤ちゃんの尽きない要求につきっきりで応えるだけでヘトヘト。3日間も徹夜すると心身がおかしくなってきて、夫の積極的なサポートがなければ乗り切ることはできませんでした。これから養子を迎えるご家庭には、最初にこの急激なシフトチェンジが来るということをぜひお伝えしたいです。会社など周囲にあらかじめ事情を伝えておくと、育休など柔軟に対応してくれるケースもあるようなので、養親になることを決意したら、夫婦で協力してこの時期を乗り越えられるよう準備しておくと良いのではないでしょうか」


育児の主な担い手となった池田さんは、ファミリーサポート(※)などの公的支援のほか、地域の子育て支援センターを積極的に利用。月齢が近い赤ちゃんのイベントにも参加するように心掛けた。
- ※ 子育ての援助を受けたい人と、援助を行いたい人が、地域の中で助け合いながら子育てをする有償のボランティア活動
「病院で出産すれば、院内学級や1カ月検診などでママ友ができるチャンスがあります。養子の場合それがないので、自分から交流の場に行きました。親しくなったママ友グループには早いうちに養子であることを伝え、今でも仲良くしています。また、突然赤ちゃんを連れて歩くようになるので、よく行くお店やご近所の人たちには『妊娠してたの?』『お子さんいたんだ!』と驚かれます。そういう時には隠さず『養子をもらいました』と伝えるよう心掛けました。良かったねえ、という好意的な反応が多く、真実告知の良い訓練になりましたし、地域の人たちに知っていただくことは、この先子どもの成長を見守っていく上でも安心です」
夫婦双方の家族に報告した時は、世代も違うしどう思われるか、とさすがに緊張しました。最初は『大変じゃない?』と言っていた親族もいましたが、赤ちゃんに会わせるとみんな『かわいいねえ』とメロメロに。生みの親を探るような話もなく、ただただかわいがってくれる様子に、こういう人たちだったんだ、と新たな一面を見た思いで感動しました」

「血のつながり」に対する迷いや劣等感を手放しておくのも準備
池田家に赤ちゃんが来てから約1年後。審判を経て、特別養子縁組が成立し現在息子は3歳になった。心配していた「血のつながらない子を愛せるのか?」という当初の疑問は、すっかり払拭されたという。
「最初は、目の前の赤ちゃんを無事に育てることに懸命で、余計なことを考える暇もありませんでしたが、『愛そう』という努力は全く必要なく、気付いた時にはもう3人家族になっていて。初めての育児で大変なこともありますが、子どもと一緒に過ごす日常は本当に楽しい。不安でいっぱいだったあの頃から考えると、こんなに幸せな日々がやってくるとは思ってもみませんでした」

成長に伴って息子はおしゃべりも上手になり、関心の幅も広がってくる。ある日テレビで陣痛のシーンを見て「ママもお腹が痛くなったの?」と聞かれたことが。
「息子には常々、あなたにはママとパパが2人ずついるんだよ、と話していました。ですから『ママじゃなく、産んでくれたお母さんのお腹が痛くなってあなたが産まれたんだよ』と伝え、お母さんとお腹の中でつながっていた時の紐があるからと、あっせん団体から預かったへその緒を出してあげました。しげしげとへその緒を眺める様子を見て、実子も養子も、どんな人もお母さんから生まれていて、1人の人間として変わらないんだ、という思いが伝わればいいな、と」
他にも「なんでママが産めなかったの?」と、時に子どもは率直な質問を投げかけてくるもの。養子であること・血のつながりがないことに養親が劣等感を持っていてはいけない、と池田さんは言う。
「子どもはもちろんですが、育児をしていると大人相手でも『どこの病院で産んだの?』『母乳ですか?』など、何気ない会話の中で養子であることを認識させられる質問を頻繁に受けます。養子の事実をお伝えすると『変なこと聞いてごめんなさい』と言われることもあります。私は不妊がきっかけで養子を検討しましたが、もし“産めない自分”という劣等感を抱えていたままであれば、触れないでほしいと思ってしまうかもしれません。養子を迎える前に自分の思いと向き合って、産めない劣等感を手放しておく、というのも養親に必要な準備ではないか、と思います」
「血のつながりがない」という事実は家族のベース、と池田さん。子どもが健やかに成長していくために、生涯勉強を続けるのが養親の役目だと感じている。
「私たちが利用した民間あっせん団体は、養親の交流会を定期的に行っています。年齢に応じた真実告知の仕方など勉強会もあり、これからの歩みをサポートしてくれるんです。例えば、小学校に入ってから『もらわれっ子なんでしょ?』と友達にからかわれた場合、どうする?というテーマの元、養親同士が意見交換をするとか。養子の育児には正解がない問題が多いからこそ、団体や他の養親さんなど悩みを相談できる場があることが心強いですね」

養子を迎えた家族に対し、社会を構成する私たち一人一人ができることについて伺った。
「気遣いのある人ほど『配慮しなくては』と思うかもしれません。でも当事者は態度の違いを感じ取りますし、それに気付くのは少し寂しいものです。どこで産まれたか、施設で育ったか、親が違うのか。そういうことを気にせず『ただの人・ただの家族』として普通に接し、一緒に笑ってもらえるのが一番です!」
〈プロフィール〉
池田麻里奈(いけだ・まりな)
不妊ピア・カウンセラー。妊活・流死産・養子縁組相談の「コウノトリこころの相談室」主宰。28歳で結婚し、30歳から10年以上、不妊治療に取り組む。人工授精、体外受精、2度の流産、死産を経験。2017年に子宮腺筋症が悪化し子宮全摘出。その後「それでもやっぱり育てたい」という自らの思いを確信し、特別養子縁組を決意。2019年、0歳の養子を迎える。現在は自主保育団体「青空自主保育なかよし会」の代表も務める。著書に不妊治療を経て特別養子縁組に至り、迎えた子どもが1歳になるまでの夫婦の経験を綴った『産めないけれど育てたい。不妊からの特別養子縁組へ』(著者:池田麻里奈、池田紀行)(KADOKAWA)がある。
コウノトリこころの相談室 公式サイト(外部リンク)

産めないけれど育てたい。 不妊からの特別養子縁組へ(外部リンク)
10年以上も不妊治療し、2度の流産、死産を経て、子宮全摘。その手術後の病室で「産めなくても、育てることはあきらめたくない。養子縁組をしたい」と書いた手紙を渡し、夫も決意。研修を受け「待機」に入った矢先に、赤ちゃんが突然やって来た!養子縁組を決意するまでの葛藤と、赤ちゃんを迎えてからのドタバタだけれど幸せな子育て、審判で実子となり1歳になるまでを夫婦それぞれの視点から綴ったエッセイ。「新しい家族のかたち」として注目の「特別養子縁組」の貴重な実例。
- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。