未来のために何ができる?が見つかるメディア
学ぶって楽しい! 発達障害や学習障害のある子どもたちに印刷技術を活かした読み書き教材の体験の場を

- 発達障害や学習障害は見た目では分からないため、学校生活のさまざまな場面で困難を感じやすい
- 自分に合った教材を使うことで、学習面での困りごとが解消されるケースも多い
- 「みんな違って当たり前。得意なこと苦手なことは一人一人違う」と周囲が理解を深めることが大切
取材:日本財団ジャーナル編集部
発達障害や学習障害がある子どもたちが感じている困りごとは、「文字を正確に捉えることができないため、書くことや声に出して読むことが苦手」「手先が不器用なため、書く、ハサミを使うなどの指先を使う動作が苦手」など、多岐にわたります。
ただし、発達障害や学習障害は見た目では分からないため、周囲から理解を得られず孤立したり、勉強についていくのが難しくなったりして、学校生活のさまざまな場面で困難を感じることが少なくありません。
東京・荒川区で印刷業を営む株式会社オフィスサニーは、そうした子どもたちに、1つでも多くの「できた!」を体験してほしいと、専門家の監修のもと、読み書きを支援する教材「できるびより」シリーズ(外部リンク)の企画・開発に取り組んでいます。
また、「自分に合う教材は、実際に使ってみなければ分からない」との考えから、自社製品だけでなく、国内外のさまざまなメーカーが製造した支援教材やグッズを集めた体験会を開催しています。
今回はオフィスサニーが開催する教材体験会に伺い、代表の高橋淳一(たかはし・じゅんいち)さんと高橋晶子(たかはし・あきこ)さんに、教材開発に込めた思いや、学習面でつまずく子どもを一人でも減らすためにできることについて伺いました。
はじめは発達障害や学習障害のことはほとんど知らなかった
――学習支援が必要な子どもたちは、具体的にどんな点でつまずくのでしょう?
高橋晶子さん(以下、敬称略):例えば、多くのお子さんが抱える困りごとの1つに、手先が不器用でえんぴつや消しゴム、ハサミなどの文房具をうまく使えないということがあります。そのため、書くことそのものが嫌になったり、かんしゃくを起こしてしまったりするケースがあります。
ひと言で発達障害、学習障害といっても、文字が読めない、文章が理解できない、語彙力が伸びないなど、つまずきを感じるポイントは本当にさまざまです。

――もともとオフィスサニーは印刷業が本職とのことですが、「できるびより」のアイデアはどこから生まれたのでしょうか。
高橋淳一さん(以下、敬称略):オフィスサニーは、昭和41年に「サニー写植(しゃしょく※)」として創業しました。時代の流れに合わせて印刷業へ業態を変えたのですが、ネット印刷が普及して価格競争が厳しくなってきた。そんなときに、紙の表面に凹凸を付ける「バーコ印刷」という技法に出合い、あるときパッと「バーコ印刷の技術を活用して、文字の輪郭をなぞって学習できる教材が作れないかな」とひらめいたんです。
ただ、試作品を作ってみたものの、素人ゆえに子どもたちにとって本当にいい教材かどうか分からない。そこで、地元でもある荒川区の経営支援課に相談に行ったところ、産学官連携で進めるのがいいだろうと東京電機大学の先生を紹介されました。
ただ、よくよく調べてみたら既に大手業者が似たような教材を販売していました。話が頓挫しかけた時に、大学の先生が、当時静岡県立こども病院に所属していた作業療法士・鴨下賢一(かもした・けんいち)先生を紹介してくださいました。
鴨下先生は、子どもの発達支援に関わる教材や福祉用具の開発に関わっている方で、初めて会って名刺交換をした直後から「こんな教材は作れますか?」とたくさんアイデアを出してくれました。この出会いが支援教材を開発する大きなきっかけになりました。
- ※ 写植(しゃしょく)とは、「写真植字」の略で、文字を写真のようにフィルムに焼き付けて印刷用の版下を作る技術のこと

――ちなみに、その頃は学習支援が必要な子どもたちの存在を知っていましたか。
高橋淳一:全く知りませんでした。そもそも、鴨下先生が子ども発達支援分野における作業療法士の第一人者であることも知らなくて……。ですから文字をなぞって学ぶカードも、当初は私の単なるひらめきから生まれたものでしかなかったんです。
高橋晶子:私たちの間にも子どもが3人いますが、支援を必要とせずに成長したので知る機会がなくて……。鴨下先生との出会いを機に、いろいろな課題を抱えている子どもたちがいることを知り、もっと知りたいと思うようになりました。
高橋淳一:私たちには、子どもたちの発達を支援するもの作りがしたいという思いがある。一方で、鴨下先生には保護者や学校の先生に向けたセミナー、後進育成のための研修会を開きたいという思いがありました。
そこで、コロナ前は先生と全国各地でセミナーを共催することで私たちも学びを深め、子どもたちが感じているいろんな困りごとや、保護者や先生たちが抱える悩みについても知っていきました。
ただ、その頃はまだ「できるびより」という名前はなく、鴨下先生の事務局として活動していました。
――「できるびより」が誕生したのは比較的、最近だったんですね。
高橋淳一:コロナ禍になってセミナーが開けなくなり、立ち止まらざるを得なかった時期がありました。その時に自分たちが作っているものを知ってもらうためにはブランド名があった方がいいのでは、と「できるびより」を立ち上げました。
ホームページを分かりやすく整備したり、デザイナーの知人に頼んでイラストを描いてもらったりしてブランドを確立させました。

高橋晶子:ブランド名は「子どもの『できた!』が増える素敵な毎日」という意味を込めています。
発達障害のお子さんを持つ保護者の中には、悩みを一人で抱えて“いっぱいいっぱい”になり、気持ちの余裕がなくなっている方がたくさんいらっしゃいます。そんな保護者たちに向けて、少しでもポジティブに明るく、子どもたちの「できた!」が増えることを信じてあげよう!と呼びかける意味も込めて、ポップで明るいデザインを意識しています。
――活動を続ける中で、大事にされていることはありますか?
高橋淳一:自然体でいることかな(笑)。私、子どもが好きなんですよ。子どもたちにとっていいと思えるものを作りたいし、困っていることがあるなら1つでも減らして「できた!」を体験してほしい。それが一番の思いです。
高橋晶子:発達障害がある子どもたちの中には「できない」「困った」と口にすることができない子もいます。静かにしている分、先生にも気づいてもらいにくいという現状があります。そんなふうに、困りごとを抱えている子どもたちにも「できた!」を経験してほしいし、そのために私たちできることはなんでもやりたいなと思っています。
自分に合う教材と出合うことが「できた!」を増やすきっかけになる
――支援教材やグッズの体験会を始められたきっかけはなんだったのでしょうか。
高橋淳一:「できるびより」シリーズは、実際に見て、触ってもらわないと良さが分かりにくい教材です。そこで、自分に合うなと思っていただいた上で買ってもらえたらという思いで体験会を始めました。
自社製品以外のグッズを展示するようになったのは、荒川区で開催した際にご協力いただいた齋藤恵美子(さいとう・えみこ)さんとの出会いがきっかけです。体験会では齋藤さんが個人で集めた支援教材、グッズを持参して紹介してくれて、ぜひ一緒にやりたいと声をかけました。

高橋晶子:私たちもそれまで知らなかったんですが、えんぴつ1本、消しゴム1個とっても、メーカーによって書き心地、消し心地、持ちやすさが全然違うんですよ。でも、実際に使ってみなければ、どれが自分にとって使いやすいかは分かりませんよね。
――ちなみに、世の中には、そんなにたくさんの支援教材やグッズが売られているのでしょうか?
高橋晶子:最近では100円グッズでも手先トレーニングシリーズが販売されていて、充実してきています。大手メーカーから市販されているものの中にも、支援が必要な子どもでも使いやすいものが増えてきています。

高橋晶子:例えば、えんぴつ。私たちが子どもの頃は六角形のものが一般的でしたが、三角形のえんぴつは親指・人差し指・中指の収まりが良く、手先を使った細かい動きが苦手なお子さんも比較的持ちやすいといわれています。
さらに、指が安定するようにえんぴつ本体にくぼみがついているものや、正しい持ち方をサポートしてくれるホルダーもいろんなメーカーから出ています。体験会にいらっしゃる方たちも「こんな商品があったなんて!」と驚かれますね。
高橋淳一:縄跳びもグリップが握りやすいもの、ロープ部分がビーズになっているものなどいろいろな製品があって、それまで飛べなかったお子さんが体験会で飛べるようになった場面にも何度も目にしてきました。


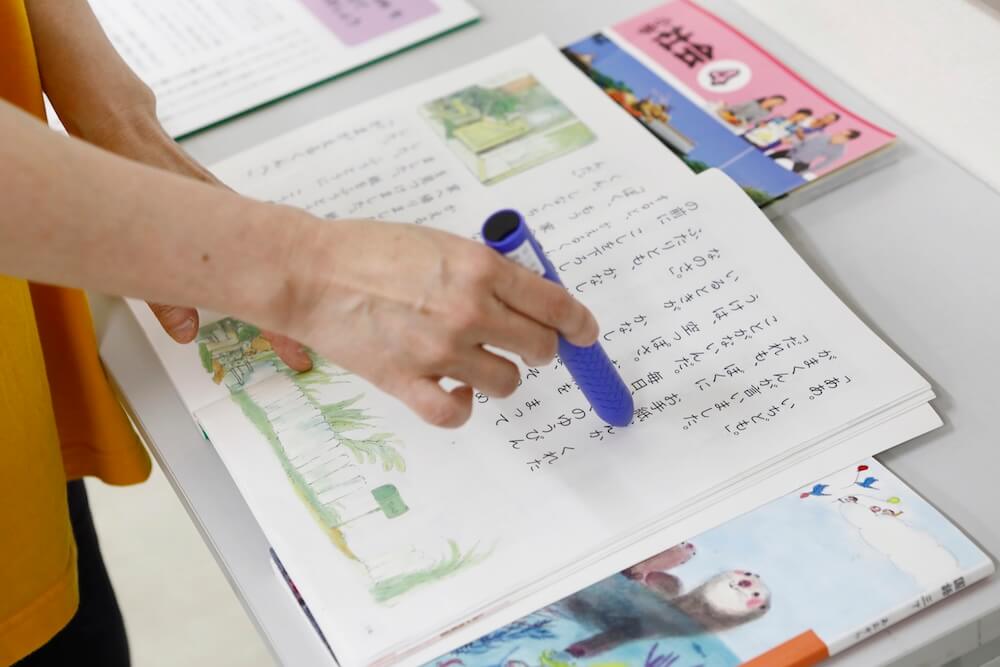
発達障害や学習障害の子どもを持つ家族に寄り添うペアレント・メンターの存在
――体験会をサポートされている齋藤恵美子さんにもお話を伺います。東京都の「ペアレント・メンター(※)」に登録されているとのことですが、齋藤さんは普段、どのような活動をされているのでしょうか?
齋藤さん(以下、敬称略):発達障害の子どもを持つ家族の支援サークル「プティパ」を運営しています。ペアレント・メンターは、私自身も発達障害の子どもを持つ親として、同じような環境にある親御さんたちに共感し、お話を傾聴させていただくことが活動のメインです。
- ※ ペアレント・メンターとは、発達障害のある子育てを経験し、かつ相談支援に関する一定のトレーニングを受けた親を指す言葉

――年々、「発達障害」という言葉の認知が広がっていますが、子どもたちをとりまく環境は変化していますか。
齋藤:私の長男が発達障害だと分かったのが15年前なのですが、その頃から、東京都では小中学校の全校に特別支援教室が設置され始めました。今ではだいぶ理解が深まっていることを実感しています。
また、周囲の理解が進んだことで、それまでは障害を隠そうとしたり、「うちの子は違う」と認められなかったりした保護者が多かったのが、「うちの子も発達障害かもしれない」「もしもそうだったら、助けてもらおう」という、ポジティブな価値観に変わってきたように感じます。
一方で、「発達障害」の“障害”という言葉をどうしても受容できないという保護者も多いです。子どもが成長すれば、悩むポイントも変わってくるものですよね。ですから、私自身も共感しながら一緒に歩んでいるような感覚です。

――さまざまなメーカーの教材、グッズを個人で集められていたと聞きました。
齋藤:初めのうちは、自分の子どもが使っていたものや、支援サークルの仲間たちが「うちの子が使って良かったよ」というものを集めていたのですが、だんだん来てくださった方が「こんなものもあるよ」と教えてくださるようになって。どんどん増えていきました。
――体験会に来る子どもたちの反応はいかがですか。
齋藤:みんな、それぞれにいろんな困りごとを抱えているんですね。でも、これまでできなかったことが、この体験会ので初めてできるようになって「ママ見て!できたよ!」と喜んだり、なかには嬉し涙を流す子もいたりして……。そんな姿を見るたびに私たちも本当にうれしくて、活動してきて良かったと思います。

学校教育の現場にも「できるびより」を届けたい
――改めて淳一さん、晶子さんにお話を伺います。今後、「できるびより」ではどのような展開を考えていますか。
高橋淳一:学校の先生たちを対象に、支援教材やグッズの体験会と、発達支援研修会をセットで開催することを企画しています。
これまで全国各地でセミナーや体験会を開催する中で、特別支援について専門的な知識を持つ先生が少ないこと、さらに学校の先生方が子どもの発達や特性について学べる機会が少ないことを痛感してきました。
先生たちが子どもたちの発達をより深く理解して、具体的な支援の方法や、支援教材の活用方法を学ぶ機会があれば、子どもたちが自分にとって使いやすい教材を見つける近道になるのでは、と思っています。

高橋淳一:また、体験会は情報交換や、相談の場にもなっているので、心理理士など専門家を招いて、保護者の方たちの個別相談の場も設けたいですね。
――発達障害や学習障害がある子どもたちが、自分に合った教育を受けるために、どんなことができるでしょうか。
高橋晶子:「いろんな子どもがいて当たり前なんだ」という意識を持つことだと思います。ある専門家の方に「一人一人の顔の形、見た目が違うように、脳のつくりも違う」と教わりました。だから違って当たり前だし、それをみんなが理解していたら、もっと公平なな世の中になるんじゃないかなと思っています。
それから、保護者を独りにしないこと。社会全体の理解が進んでいるとはいえ、まだまだ世代が上がるほど理解が得られない状況です。実家や義理の親の理解不足から「他人には隠しておきなさい」と言われ、孤立してしまっている保護者もたくさん見てきました。
この体験会を通して、同じ悩みを持つ親同士で共感し合ったり、ペアレント・メンターに話を聞いてもらったりして少しでも気持ちが楽になってもらえたらと思いますし、いま悩んでいる保護者たちには「一人じゃないよ」「いま、子どもにできないことがたくさんあっても大丈夫」と伝えたいです。
発達障害や学習障害のある子どもが楽しく学べる環境をつくるために、地域や周りの人ができること
- みんな違って当たり前。個々に合った学びの環境をつくることの重要性を理解する
- 支援教材やグッズを見つけたら周りの人に情報を共有し、当事者の親や子どもに届きやすくする
- 当事者の親は1人で悩みを抱えがち。孤立しないように支えることが大切
体験会では、開場とともにたくさんの親子連れが来場し、子どもたちが楽しそうに教材やグッズに触れ、体験する姿が印象的でした。
取材中、心に強く残っているのは高橋淳一さんの「僕は子どもが大好きだから、子どもたちにとって何が最も良いかを一番に考えたい」、そして晶子さんの「子どもたちの『できた!』が増えるためだったら、できることはなんでもやりたい」という言葉でした。
「目の前にいる子どもたちを笑顔にしたい」というシンプルで切実な願いが、一人一人が理解を深め、子どもたちの「できた!」を増やす大きなきっかけになるのではないかと思いました。
撮影:永西永実
- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。













