未来のために何ができる?が見つかるメディア
第3回 NPO法人に顧問弁護士は必要? 依頼先の選び方や費用を抑えるためのポイントも解説
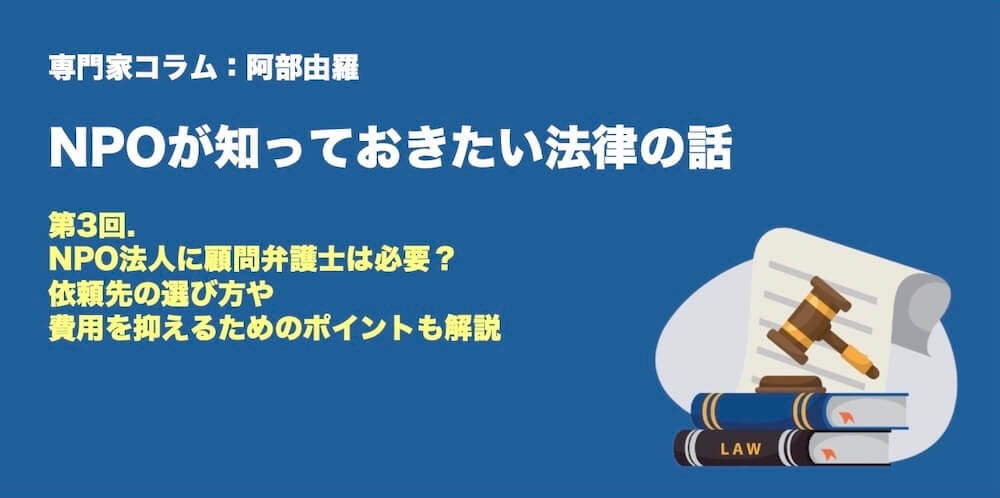
執筆:阿部由羅
NPO法人の業務も、一般の企業と同じように契約や法律が関係するため、弁護士のアドバイスを受けた方がよい場面があります。
しかし、NPO法人は営利法人でないため潤沢な資金を持っておらず、弁護士への依頼費用を捻出するのが難しいケースも多いようです。毎月顧問料がかかる顧問弁護士と契約すべきかどうか、悩んでいるNPO法人経営者もいらっしゃるかと思います。
弁護士に相談する方法は、顧問契約だけではありません。無料相談やスポット契約も活用して、NPO法人のニーズに合わせた形で弁護士をご利用ください。
本記事ではNPO法人経営者に向けて、顧問弁護士がいた方がよい場面や依頼先の選び方、弁護士費用を抑える方法などを解説します。

NPO法人に顧問弁護士は必要?
NPO法人に顧問弁護士が必要かどうかは、費用対効果の兼ね合いによるので一概に言えません。
NPO法人の業務にも、一般の企業と同じように契約や法律が関係します。そのため、業務に関して弁護士のアドバイスを受けた方がよい場面があることは、NPO法人も一般の企業も変わりません。
しかしながら、顧問弁護士と契約すると毎月顧問料がかかります。相談の頻度が少ない場合は、顧問料の負担が重いと感じてしまうかもしれません。
どのくらいの頻度で相談が発生するのか、契約違反や法律違反のリスクがどの程度懸念されるのかなどを総合的に考慮して、顧問弁護士と契約すべきか否かを判断しましょう。
NPO法人に顧問弁護士がいた方がよいケース
以下のようなケースでは、NPO法人でも顧問弁護士と契約することをおすすめします。
- 頻繁に契約を締結する場合
- 不特定多数の顧客がいる場合
- 多数の従業員を雇用している場合
- 知的財産を取り扱っている場合
頻繁に契約を締結する場合
NPO法人も一般企業と同様に、取引先との間で契約を締結する場面があるかと思います。契約を締結すると、契約の内容に従った権利を取得し、義務を負います。
締結した契約の内容が不適切だと、相手方との間で契約トラブルが発生するリスクが高まります。そのため、契約を締結する際には、弁護士のリーガルチェックを受けることが望ましいです。
特に、契約を締結する機会が頻繁にあるNPO法人においては、いつでもスムーズにリーガルチェックを依頼できるように、顧問弁護士と契約しておいた方がよいでしょう。
不特定多数の顧客がいる場合
不特定多数の顧客に向けてサービスを行っているNPO法人は、常に顧客からの問い合わせやクレームなどへの対応を迫られます。
顧客の問い合わせやクレームに不適切な対応をしてしまうと、NPO法人としての信頼を失うおそれがあるほか、訴訟を起こされるといったトラブルに巻き込まれるリスクが高まります。
対応の仕方に悩む部分がある場合は、顧問弁護士のアドバイスを受けながら適切な対応の在り方を検討することが望ましいでしょう。
多数の従業員を雇用している場合
NPO法人も一般企業と同様に、従業員を雇用するのが一般的です。特にNPO法人の事業が大きくなればなるほど、雇用すべき従業員の数も多くなります。
従業員を雇用する法人においてよく問題となるのが、労務関係のトラブルです。
例えば労働基準法では、賃金・労働時間・休憩・休日・有給休暇などに関するルールが定められています。残業代の未払いや違法な長時間残業、有給休暇の取得拒否などを理由に、労働基準監督署から違反を指摘されたり、従業員に訴訟を提起されたりするケースが少なくありません。
NPO法人においても、従業員との労務トラブルを十分に警戒する必要があります。労働基準法・労働契約法・労働安全衛生法など、労務に関係する法令を適切に遵守するためには、弁護士のアドバイスを受けることが望ましいといえます。
特に多数の従業員を雇用しているNPO法人では、労務トラブルに巻き込まれるリスクが高いと考えられます。
従業員とのトラブルを未然に防ぐため、また実際にトラブルが発生したらすぐに対応できるようにするため、顧問弁護士と契約しておいた方がよいでしょう。
NPO法人が顧問弁護士を選ぶ際の着眼点
NPO法人が顧問弁護士を選ぶに当たっては、以下のようなポイントに着眼するとよいでしょう。
- 企業法務に関する経験
- 顧問料の金額
- 顧問料に含まれるサービスの内容
企業法務に関する経験
弁護士の業務領域は幅広いですが、その中でもNPO法人の顧問は「企業法務」と呼ばれる分野です。
一般企業に対するサポートを含めて、企業法務の経験を豊富に有する弁護士に顧問を依頼すれば、NPO法人の事業や体制に応じた適切なアドバイスを受けられるでしょう。
顧問料の金額
顧問料の金額は、依頼先の弁護士によって異なります。
NPO法人においては、顧問弁護士の費用に充てられる資金が潤沢にはないケースが多いため、リーズナブルな顧問料で依頼できる弁護士を選ぶのがよいでしょう。
顧問料に含まれるサービスの内容
顧問料の範囲内で対応してくれる業務の内容も、依頼先の弁護士によってさまざまです。
予期せぬ追加費用が発生し、予算をオーバーしてしまうような事態を避けるためにも、顧問料に含まれる弁護士の業務内容を事前に確認しましょう。

NPO法人が顧問弁護士費用を抑える方法
顧問弁護士と契約したいものの、顧問料の負担はできる限り抑えたい場合には、複数の弁護士に相談して見積もりを比較することをおすすめします。
顧問料の金額は弁護士によって異なるところ、複数の弁護士を比較すれば顧問料の相場感が分かります。その上で、サービスが充実していて顧問料がリーズナブルな弁護士に依頼するのがよいでしょう。
また、比較的少数ではありますが、固定の顧問料を無料としている弁護士もいます。このような弁護士は、実際の対応内容や稼働時間に応じて弁護士費用を請求するのが一般的です(タイムチャージ制など)。
月額固定の顧問料とタイムチャージのどちらが安く済むかは、相談の内容や頻度などによって異なりますが、固定費の負担を避けたい場合は完全タイムチャージ制などを採用している弁護士を探すことも選択肢の一つです。
顧問契約が難しいなら、無料相談やスポット契約の活用を
相談の頻度がそれほど多くなさそうで、顧問料に割ける予算もないという場合には、弁護士と顧問契約を締結するのは難しいかもしれません。
しかし、顧問契約を締結していなくても、弁護士に相談する方法はあります。
特に最近では、多くの弁護士が無料法律相談を受け付けています。30分から60分程度無料で相談できるケースが多いほか、メールや電話での相談を受け付けている弁護士もいます。
ちょっとした悩みであれば、無料相談だけで解決するかもしれません。
また、具体的な問題が発生した際に、その都度弁護士に相談して委任契約を締結することも考えられます(=スポット契約)。スポット契約であれば、毎月の顧問料を支払うことなく、弁護士に必要な業務を依頼することができます。
NPO法人においては、予算やリスク管理の必要性を総合的に考慮して、ニーズに合わせた形で弁護士の利用をご検討ください。
〈プロフィール〉

阿部由羅(あべ・ゆら)
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。注力分野はベンチャー企業のサポート・不動産・金融法務・相続など。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。各種webメディアにおける法律関連記事の執筆・監修も多数手がけている。
ゆら総合法律事務所 公式サイト(外部リンク)
阿部由羅 公式X(外部リンク)
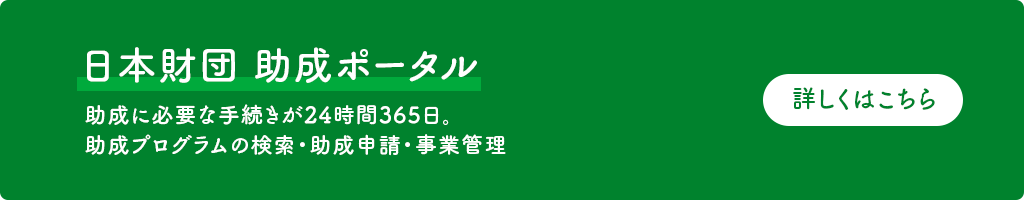
- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。












