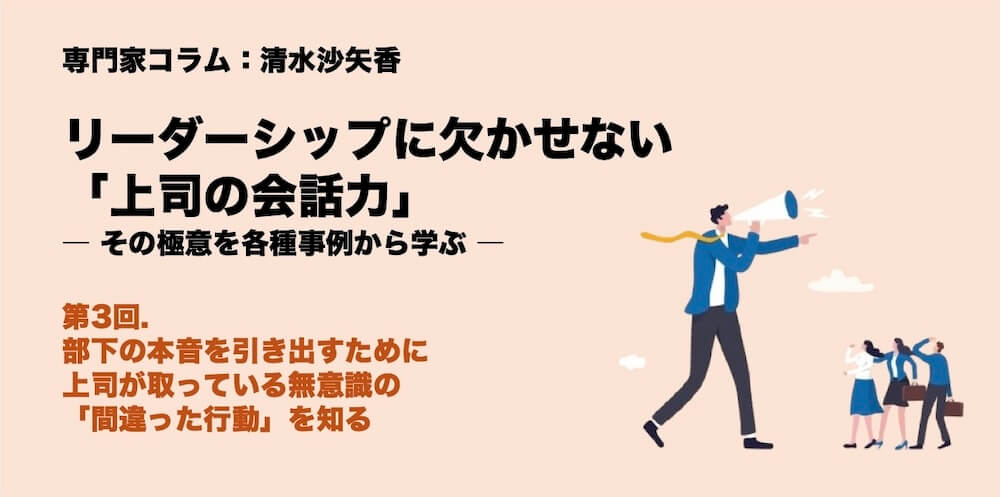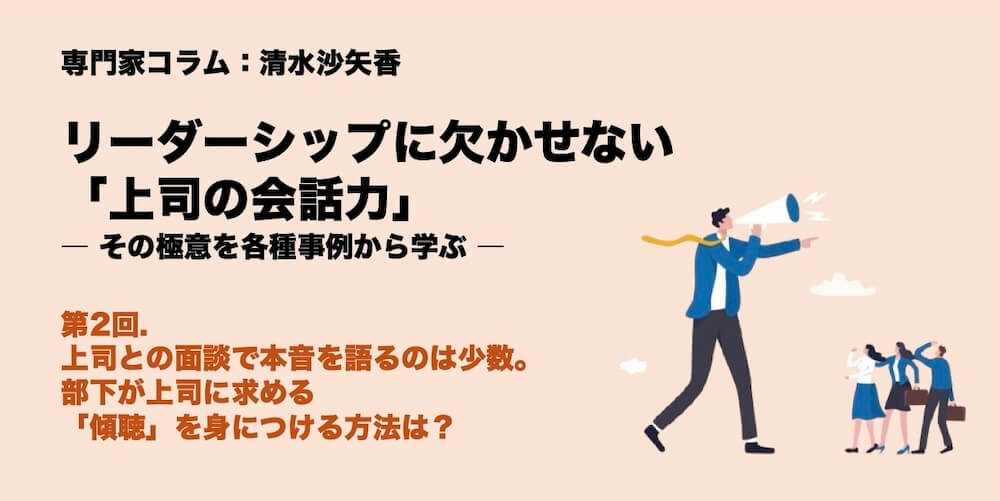未来のために何ができる?が見つかるメディア
第4回 部下に質問する前に、自分に向ける「質問力」が大切な理由
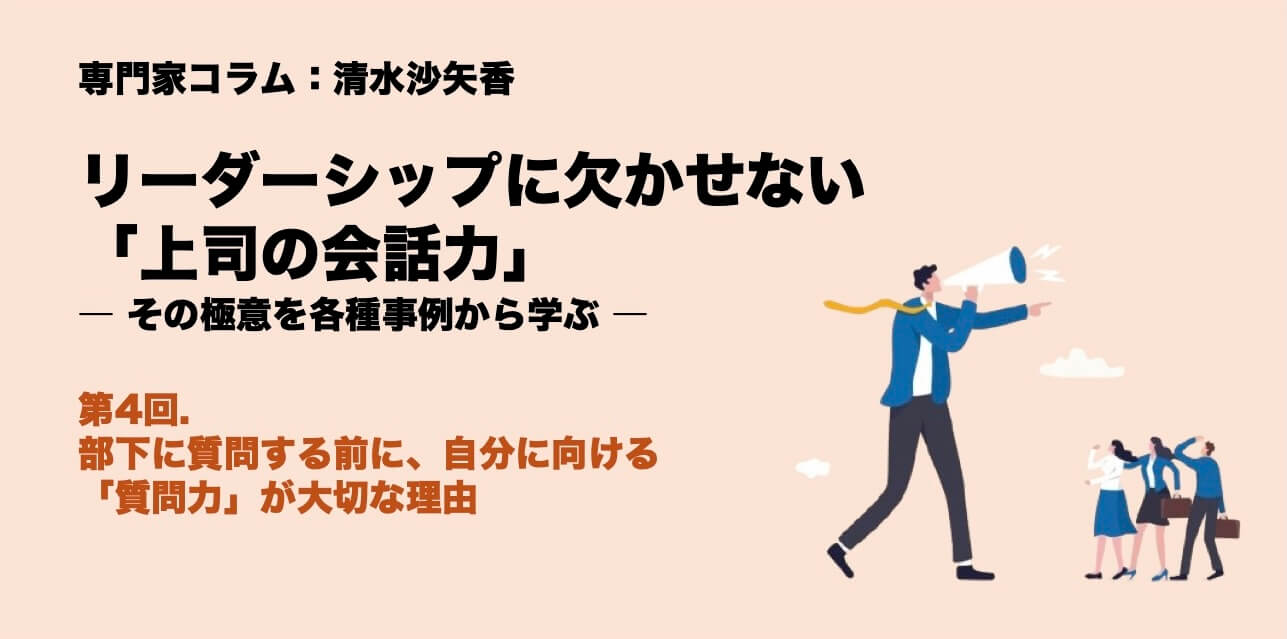
執筆:清水沙矢香
上司に当たる人は、どのように部下に接すれば良いコミュニケーションを取れるのか、という課題を軸にここまでお伝えしてきました。特に部下の本音を引き出す術についてです。
今回は、有意義なコミュニケーションに欠かせない「質問」の力と上司の心構えについて「世界一のメンター」と呼ばれるジョン・C・マクスウェル氏の著書などをもとにご紹介していきたいと思います。
「質問力」の基本
アメリカのリーダーシップ論の権威であり、毎年2万5,000人を指導する「世界一のメンター」と呼ばれるジョン・C・マクスウェル氏は、著書「人を動かす人の『質問力』」で冒頭からこのような言葉を突きつけています。
人生では『投げかけた質問』の答えしか返ってこない。
引用:ジョン・C・マクスウェル「人を動かす人の『質問力』」三笠書房 p23
当然と言えば当然のことです。
例えば面談などの場で、部下に何かを質問するとしましょう。
「いま何か、業務で困っていることはあるか?」という質問に対して、「特にはありません」と返ってきたとします。
ただ、そう答えてはいるのに、普段の表情があまり明るくない、結果が出ていない、となると、
「なぜ楽しそうではないのだろうか?」
「本当に困っていることがないのだろうか?」
「あったとしたら、なぜ『ある』と答えなかったのか?」
このように「なぜ?」がおのずと次々と湧いてこない人は、それ未満の答えしか受け取れないということです。
そして、マクスウェル氏はこう続けています。
「こんなつまらないことを聞くのはどうか」と、質問するのをためらった経験はないだろうか。自分の愚かさを隠すために、必要な知識を手に入れ損なったことが、私には何度もある。しかし「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」だ。
(中略)
「底の浅い質問しかできない人」は「底の浅い答え」しか得られず、自信も欠如している。意思決定はお粗末で、優先順位も曖昧、未熟な対応しかできない。
一方、「深い質問」ができる人は、「奥深い答え」が得られ、人生に自信が持てる。賢い意思決定で最優先事項に集中でき、大人の対応ができる。
引用:ジョン・C・マクスウェル「人を動かす人の『質問力』」三笠書房 p23
「自分の愚かさを隠すために、必要な知識を手に入れ損なったことが、私には何度もある」。耳の痛い言葉ではないでしょうか。
しかし「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」。よくある言葉ですが、それを本当に身に染みて感じ、実践できているリーダーはどのくらいいるでしょうか。
部下に対して、何か「聞きたいけれど聞けない」という心理的ハードルを上司が意識的にも無意識的にも感じているのならば、コミュニケーションは進みようがありません。
自分の無意識レベルでの「抵抗感」を克服する必要が上司にはあるのです。あるいは無意識のうちに抵抗感を持っている自分に気づく必要があります。

「純粋な興味」を持っているか?
マクスウェル氏は同じ著書のなかで、非常に根源的なことを指摘しています。なかでも「結果を出すリーダーが自問していることのひとつとして、「自分が持つ『人に対する関心』は純粋か?」というものがあります。
人は、いろいろな理由でリーダーになります。ただ、自己中心的な理由でリーダーになる人には4つの動機があるといいます。*1
- 権力=人を支配するのが好きで、人を貶めることで自分の価値を高めようとする
- 地位=「肩書き」はエゴを満足させる。リーダーの権力と権限を誇示する
- 富=金銭的利益のために他人を利用し、自分を切り売りする
- 名声=人格や品性より、見た目や名声を重視する
そしてこう述べています。
リーダーとは「他の人よりも優位に立っているか否か」が問題なのではない。優位に立っていることは当たり前だ。
着目すべきは、「その優位性を自分の利益のために利用するか、それとも他のチームメンバーのために利用するか」である。
引用:ジョン・C・マクスウェル「人を動かす人の『質問力』」三笠書房 p44
言い換えれば、好むと好まざるとに関わらず、あなたが部下のリーダーであることは、物理的に揺るぎない事実です。
よって、「部下は自分のことをリーダーと認めてくれているか?」を確認したくて部下に投げかける質問、これほど無駄なものはないということです。
部下と上司という関係。それが単なる肩書き上だけのものなのか、真に信頼を得た存在なのかは、あなた自身の振る舞いにかかっているのです。
もし上司が「部下に自分の考えを浸透させたい」「影響力を与えたい」そのような動機で部下に接しているとしたら、その考えそのものを改める必要があります。
そんなことは部下のほうが案外お見通しであり、逆に部下の本音を引っ込めてしまうからです。
「部下への影響力」に走ったリーダー
筆者も昔、そのようなリーダーのもとで仕事をしたことがあります。
彼は社内の体制という大きなものに反発精神を持つ人でしたが、その反発心に賛同するかどうか?という質問をメンバーに投げかけることがなかったのです。ただ、背中を見ればわかるだろう、と考えていたことでしょう。
しかし、そんな空気を読めないほどまだ若かった筆者にはさっぱりわかりませんでした。
そして彼は自分の「思想」を共有している(と彼が考えている)部下だけを集めた飲み会を開き、担当を外れた後の筆者もその場に呼ばれたことがありますが、逆に居心地の悪さをおぼえたものです。
よって「信頼して本音を話せる相手」にはなり得ませんでした。「この人が気に入る返事をしておけば無難で面倒にはならなさそうだ」となっていました。他のメンバーでも「とりあえずあの人のことを担いで気分よくしておけばいいから」と話す人もいました。
彼のチームは局内でも優秀な人物の集まりでしたが、彼は集めたメンバーを育てるためではなく、自分の名声のためにそのようなメンバー集めをしていたのでは、という気持ちにすらなったものです。
それでは筆者らは「リーダーを格好良く見せるための装飾品」ということになってしまいます。それを楽しいと思う部下はあまりいないでしょう。
確かにそのリーダーには、筆者は「鍛えられた」と思っています。しかしそれは「筋力」や「古い根性論」だけであった気もしています。
彼は「自分が嫌われ役になることも必要だ」と話していたこともありましたが、そんなことをしなくてもチームを回すことは十分可能なはずで、そのほうが誰もが日々楽しくいられるはずです。

質問の「言葉をデザインする」ということ
自分の立場や利害に全くこだわらずに相手と向き合った時、真に「有効な質問」が得られると筆者は考えます。
組織において、部下は「お客様」ではないかもしれません。
しかし、日本を代表する2大テーマパーク、東京ディズニーリゾートとユニバーサル・スタジオ・ジャパンで多くの従業員研修にあたってきた今井千尋(いまい・ちひろ)氏は、質問の大切さについてこう述べています。
「人は往々にして大事なことの3割ぐらいしか言葉にしていない」のだそうです。*2
その前提で、
相手が3割しか伝えてくれないからといって、3割分の情報で返事をしたら、ゲストからすると、期待していた3割、もしかしたらそれ以下での返事でしかなかったということになりかねません。
相手から情報を引き出す質問を重ねることでやりとりは増えますが、その分、相手のことを知ることができるため、ゲストがより満足できる返事を提供することができます。
誰のために言葉を発するのか、そのことを意識して会話をすることを、私は「言葉をデザインする」と言っています。
引用:今井千尋「新しいリーダーの教科書」あさ出版 p128
相手が自ら語る3割以外の部分、7割は聞く側が引っ張り出さなければ出てこない、というわけです。言葉に出していないことの方が非常に多いということでもあります。
まず相手を観察すること。そして、困りごとや探しごとをしているようなゲストに声をかけたとしても、ゲストは「レストランを探している」としか言わないかもしれません。
しかし、そこから
「何名様でお越しですか?」
「お子様は、キャラクターはお好きですか?恐竜とか、他に好きなものはありますか?」
「今朝や昨夜は何を召し上がりましたか?」
「お腹の具合はどうですか?ペコペコでしっかり食べたいか、さくっと小腹を満たしたいか、ご希望はありますか?」
このような質問をどんどん繰り出せるかどうかが重要なのです。*3
そして、繰り出せる質問の数は、ひとえに質問する側が「どれだけ多くの選択肢をイメージできているか」「日頃からどれだけ広い考え方を持っているか」によります。
かつ、これこそがマクスウェル氏も指摘する「相手への関心は純粋か」ということにもつながります。
部下に接するにあたって必要なのは「部下という人間を知りたい」という純粋な欲求であり、「どうすれば自分の言うことを聞いてくれる人物になるか」「どうすれば自分のやり方を理解し、それに沿ってくれるようになるか」ではありません。
そのためにも、上司自身が「自分によからぬ動機はないか」と問い続けることが必要なのです。これは、時によってはしんどい作業でもあります。
しかし「質問力」は、自分に向けた時こそその威力を発揮し、外に対しても有効なツールになってくれるのです。
人に問う前に、自分に問う。
リーダーの基本動作なのかもしれません。
[参考文献]
*1.参考:ジョン・C・マクスウェル「人を動かす人の『質問力』」三笠書房 p43-44
*2・3.参考:今井千尋「新しいリーダーの教科書」あさ出版 p127、129
〈プロフィール〉
清水沙矢香(しみず・さやか)
京都大学理学部で生物学を専攻し、学部卒業後2002年にTBSに入社。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種産業やマーケットなどを担当。その後人材開発にも携わりフリーライターとして独立。国内外での幅広い取材経験と各種統計の分析をもとに多くのWebメディアや経済誌に寄稿。
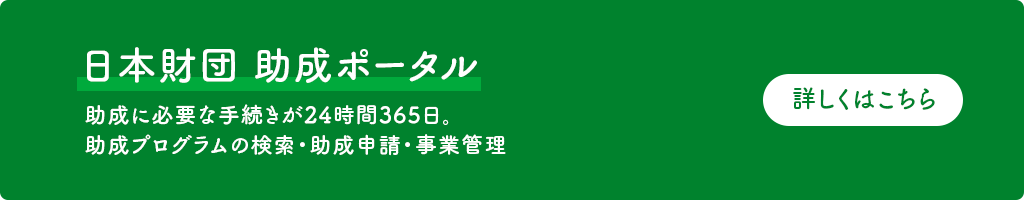
- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。