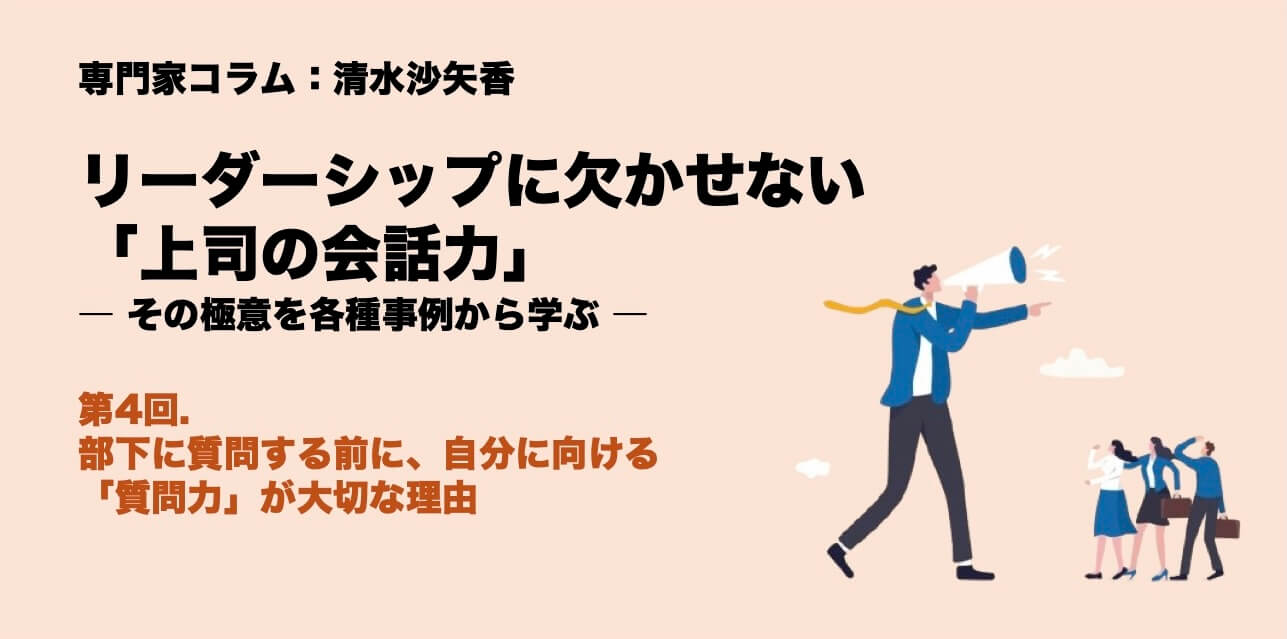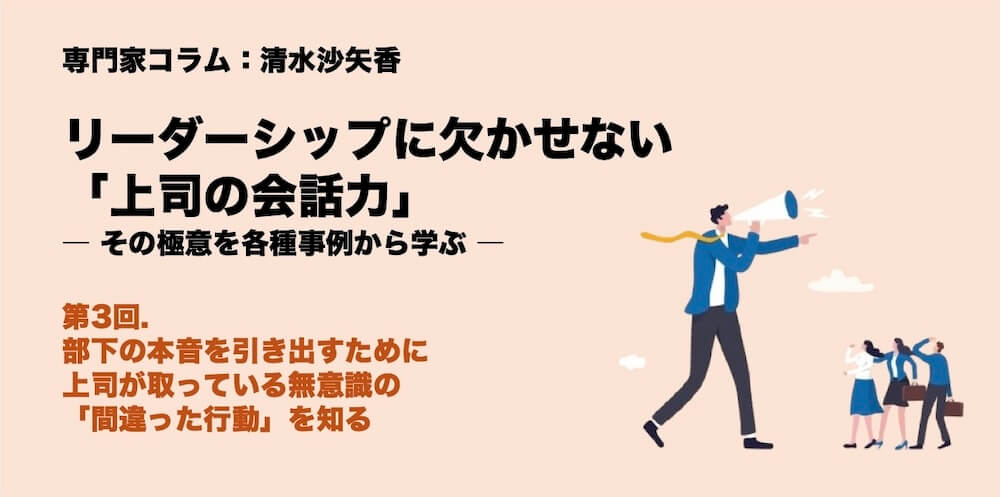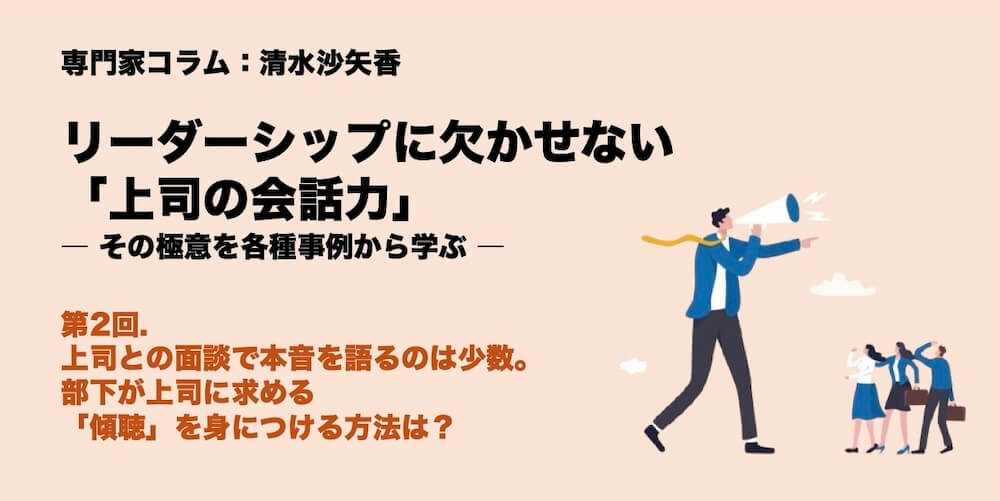未来のために何ができる?が見つかるメディア
第5回 先頭に立つことが役割ではない。「リーダーシップ3.0」について知ろう
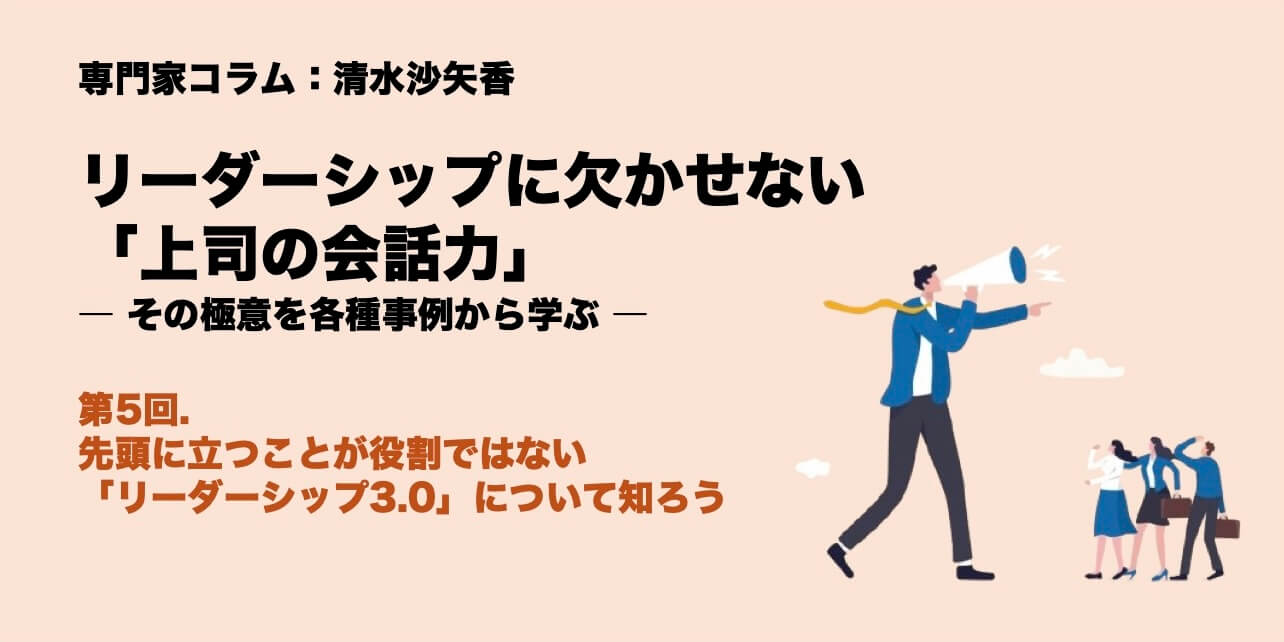
執筆:清水沙矢香
「どうして今の若者は自分たちとこうも違うのか」
答えは非常にシンプルです。
そもそも生まれ育った時代が違い、そして現在彼ら・彼女らを取り巻く環境やテクノロジーが、上司層が若手だった頃と大きく違うからです。
今企業で若手とされる年齢の社員たちは、子どもの頃からパソコンやインターネットが当たり前に存在し、大量の情報に触れて、いわゆる「多様性」の中で育っています。
また、多感な時期に社会の不安定さを感じさせる出来事に遭遇し続けています。
ビジネスを取り巻く環境も変化しました。よってリーダーシップの形もまた変化する必要があります。
今回は、近年注目されている「羊飼い型リーダーシップ」「リーダーシップ3.0」をご紹介します。
2000年代生まれの世界
過去の話をするとき「ああ、もうあの出来事からこんなに時間が経ったのか」と感じることは多々あります。昭和生まれの筆者からすれば「2000年代生まれがもう社会人なのか!」とたびたび驚いたものです。
2000年代=平成の後期を遡れば……
2001年 米同時多発テロ
2002年 日朝首脳会談で北朝鮮が拉致を認める
2006年 新語・流行語大賞で「格差社会」がトップ10入り
2008年 リーマン・ショック
2011年 東日本大震災
2015年 「イスラム国」が日本人2人殺害の映像公開
2019年 元号が「令和」に
など、挙げればキリがないのですが、これらは彼ら・彼女らが「子どもの時に」経験している出来事です。大人とはまた違う捉え方をしていることでしょう。
そう考えれば、上司世代と全く異なる価値観が芽生えて当然です。
そしてビジネスを取り巻く環境も激変しています。外部環境の不安定さもありますが、テクノロジー面ではSNSの普及が消費者心理を移ろいやすいものにした要因のひとつでしょう。
時代が変われば、当然リーダーシップの姿も変わらなければなりません。
そこでご紹介するのが「リーダーシップ3.0」です。
リーダーシップの変遷
南アフリカの大統領であったネルソン・マンデラ氏はかつて、優れたリーダーを「羊飼い」に例えました。
「羊飼いは群れの後ろにいて、賢い羊を先頭に行かせる。あとの羊たちはそれについていくが、全体の動きに目を配っているのは、後ろにいる羊飼いなのだ」*1
この「羊飼い型」は近年注目される「リーダーシップ3.0」の一例でもあります。*2

「リーダーシップ1.0」と「リーダーシップ2.0」
リーダーシップ3.0とは何なのか。
それを知るために、まず、これまでのリーダーシップの変遷を見ていきましょう。
「3.0」というからには、その前の「1.0」「2.0」が存在します。マッキンゼー・アンド・カンパニーの経営コンサルティングや、アップルコンピュータの人事総務本部長などを経た慶應義塾大学大学院理工学研究科の小杉俊哉(こすぎ・としや)特任教授(2022年退任)によれば、それぞれ次のようなものです。*3
- リーダーシップ1.0=強大な権力を背景に従えた、権威によるリーダーシップ
- リーダーシップ2.0=変革者によるリーダーシップ
いずれも、リーダーに強いカリスマ性を求めるものです。リーダーシップ2.0で言えば、スティーブ・ジョブズのような人物です。
しかし、ジョブズのようなカリスマ性は誰にでもあるわけではありません。さらに今は、リーダーや経営者ですら常に「正しい方向」や「正解」を見つけ続けられる時代ではなくなっています。
「リーダーシップ3.0」へ
さまざまな専門分野において突出した才能を集めれば、1人の天才をも凌ぐことができる——。
この考え方をハーバード・ビジネス・スクールのリンダ・ヒル教授は、「集合天才(コレクティブ・ジーニアス)」と呼んでいます。*1
この「集合天才」こそ、現代に求められています。そのためにも、前出の小杉特任教授は、これからのリーダーはメンバーひとりひとりと向き合って、その人の力を引き出す「支援型」へ変化しなければならないと指摘しています。*3
それが「リーダーシップ3.0」の姿です。
先頭に立ってメンバーを率いるのではなく、むしろ羊飼いのように羊の群れを後ろから見守り、羊たちが「自ら」小屋に帰る姿を見守るのです。支援型のリーダーシップで自律を促し、個々の能力を引き出すことで組織を強化するという必要性があるのです。
リーダーシップ3.0の実践事例
では、実際にリーダーシップ3.0での成功事例をご紹介します。
人材評価を100パーセント顧客に任せる〜資生堂
まず資生堂です。*4
資生堂は数千人のビューティー・コンサルタント(以下、BC)を抱えています。百貨店などの化粧品売り場で働く契約社員です。
しかしある時、部門の売上げが落ち、しかも「資生堂にいくと高い商品を売りつけられる」という噂まで広がりました。原因はBCの評価基準が「その期の戦略商品をどれだけ売ったか」というものだったからです。
そこで前田新造(まえだ・しんぞう)会長(当時)は大胆な手法を取ります。BCの評価を100パーセント顧客に任せるというものです。しかも、顧客に評価アンケートのハガキを渡し、投函してもらうという古典的なやり方です。
するとBCたちは自律的に顧客満足度を高める方法を模索し、中には薬局でも買える化粧水を勧めるBCや、ヘチマコロンのような他社製品を勧めるBCもいたといいます。
場合によっては他社製品も勧めてくれる。その親身さが再び顧客を取り戻しました。「顧客第一」という企業理念にも一致する形になりました。
情報共有の徹底で自律的行動を促す〜サウスウエスト航空
続いてアメリカの格安航空会社(LCC)、サウスウエスト航空です。*5
ありのままの自分を好きなように自由に表現して、その個性をいかしてユニークな会社をつくろう、というのが創業時からの精神で、自発的になんでもやる、だから仕事のやり方はすべて任せる、という方針を取っています。
荷物の積み下ろしにトラブルがあればパイロットが腕まくりをして積み下ろしを手伝うといいます。
そして、経営情報をひとりひとりの社員に徹底的に共有させています。
情報が多いほど社員は努力する、との考え方です。
自ら考える力を養うことでもあるでしょう。かつ、どんな事態が発生しても従業員が賢明な判断をし、正しい選択をしてくれると信じている、というメッセージを折に触れて流すのだといいます。特にこうした自己肯定感を高めるメッセージは、今の日本社会で必要とされるものだと筆者は考えます。

リーダーの役割を分解してみる
ひとりひとりと向き合う。そのためには、リーダーにある程度の余裕が必要です。
オーストラリアの大手通信会社であるテルストラは、マネージャー職を2分割し、それぞれ別の人物を充てています。*6
人材を把握する「リーダー・オブ・ピープル」と業務を把握する「リーダー・オブ・ワーク」で、それぞれ別の基準で社員を評価します。
この手法によって社員にとっては「相談に乗ってくれるリーダーが2人いる」状態になったことで大好評を得ているといいます。
考えてみれば従来のマネジメントは、ひとりのリーダーがこの2つを同時に背負っています。リーダー層にとっても大きな負担であり、ひとりひとりと向き合う、と言ってもそのような余裕がない、となっていることでしょう。
テルストラの手法は大いに参考になります。
眠れる金脈を掘り起こせるか
今の若手を一括りに「ゆとり世代」と揶揄する人は多くいます。
しかしこれは国としての当時の教育方針の結果であり、必ずしも本人たちに責任があるわけではありません。本来持っているはずのポテンシャルを引き出せるかどうかは、リーダー次第という時代です。
いわゆる「多様性」を逆手に取り組織を成長させる。
そのためにはひとつの方向性に縛り付けるのではなく、まずは後ろから洞察することから始める必要があります。
[参考文献]
*1.参考:ハーバード・ビジネス・レビュー「リーダーは背後から指揮をとり、「集合天才」を活用せよ」(外部リンク)
*2.参考:アデココーポレートサイト「「自律性」と「関係性」がVUCA時代のリーダーシップのカギ」(外部リンク)
*3.参考:ハーバード・ビジネス・レビュー「自らのリーダーシップの原体験はどこにあるか 自分をさらけ出して得られるオーセンティック・リーダーシップ」(外部リンク)
*4.参考:小杉俊哉「リーダーシップ 3.0-カリスマから支援者へ」祥伝社 p146-148
*5.参考:小杉俊哉「リーダーシップ 3.0-カリスマから支援者へ」祥伝社 p142-p144
*6.参考:「ハーバード・ビジネス・レビュー」2022年5月号 p32-33
〈プロフィール〉
清水沙矢香(しみず・さやか)
京都大学理学部で生物学を専攻し、学部卒業後2002年にTBSに入社。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種産業やマーケットなどを担当。その後人材開発にも携わりフリーライターとして独立。国内外での幅広い取材経験と各種統計の分析をもとに多くのWebメディアや経済誌に寄稿。
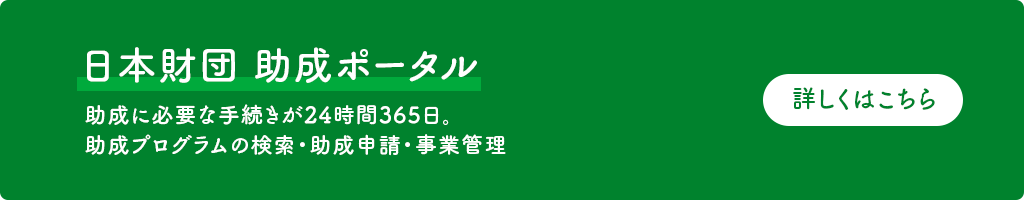
- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。