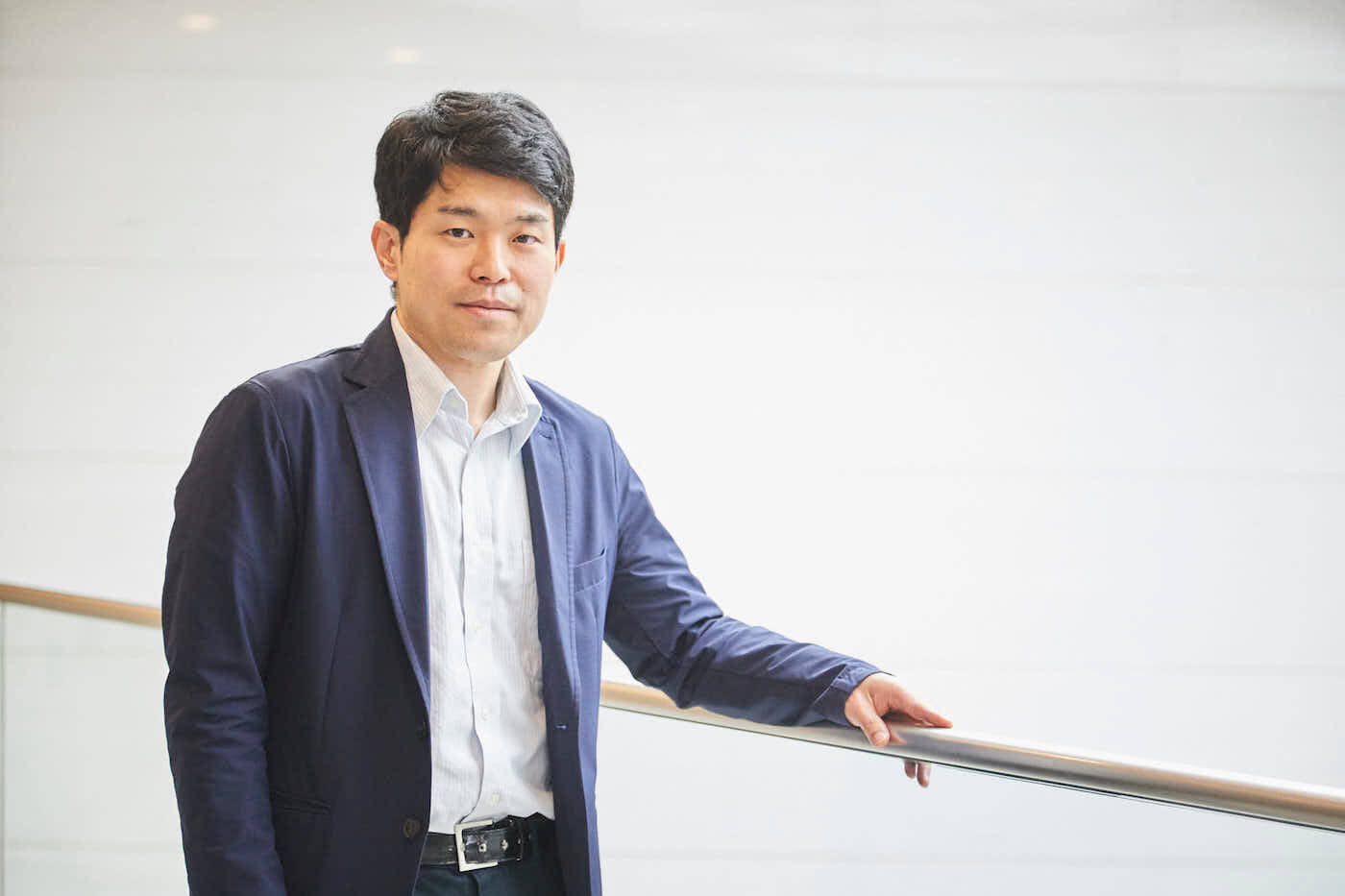未来のために何ができる?が見つかるメディア
子どもたちのワクワクに応えたい。地域の子どもたちのもう一つの家で成長を見守る“親しいお兄さん”の思い

- 「第三の居場所」は子どもたちにとって安心・安全な場所であり、好奇心を育む場所でもある
- 自分で決めることや何かに挑戦する経験が、子どもたちの「自立する力」を育てる
- 子育てに地域の力を利用し人と人をつなげることで、子どもが暮らしやすい世の中をつくる
取材:日本財団ジャーナル編集部
美しい海や、豊かな自然に恵まれた沖縄県。そんな沖縄県の子どもの貧困率が全国ワースト1位であることをご存知だろうか。経済的に問題がなくとも、子どもたちが成長する上で欠かせない教育・体験の機会が不足している状態を意味する「相対的貧困」。厚生労働省の「平成28年 国民生活基礎調査」によると、全国平均では13.9%と、7人に1人の子どもが相対的貧困状態にあるが、沖縄県ではその2倍以上に及ぶ29.9%の子どもたちが貧困に苦しんでおり、その背景には全国的に安い賃金と、高い生活費・車の維持費用などの原因があると言われている。
そんな子どもたちに、食事や歯磨きといった基本的な生活習慣から、勉強のサポート、地域の人々との交流を通して子どもたちの将来に必要な自立する力を育むのが、日本財団が全国に展開する「第三の居場所」だ。その現場では、一体どのような取り組みが行われているのだろうか。2019年の3月にオープンした、沖縄県うるま市の田場拠点マネージャーの平林勇太さんにお話を伺った。
子どもたちのワクワクに応える居場所を提供したい
「ここは、子どもたちに安心・安全な居場所を提供すると同時に、彼らの『やってみたい』という好奇心を応援する場所でもありたいと考えています」
そう語るのは、田場拠点でマネージャーを務める平林勇太(ひらばやし・ゆうた)さんだ。学校でも家でもない場所だからこそ、可能性があり、ここで得た成功体験や失敗体験が、子どもたちの自立に役立つはずだと語る。子どもの気持ちを尊重するスタイルは、普段のカリキュラムにも表れている。

「一日のスケジュールも、18時からお風呂、18時半からごはんということ以外、全て子どもたちに任せています。宿題をやりたくなければ、本人の自由にさせ、次の日『やらなかったけどどうだった?』と聞くなど、こちらから『これをやりなさい』と何かを強制させることはしないようにしています」
判断の大半を子どもに任せると同時に、自分の「やりたい」ことがどうすれば形になるのか、みんなで探求していくのも、田場流。必要であれば外部の人間も巻き込んで、子どもたちの好奇心に応えていく。
「この間『セミを食べてみたい』という子どもがいて、みんなでセミの唐揚げを作りました。もともと沖縄にはセミを食べる文化があるので、沖縄大学の理科の先生に連絡をとり、セミの安全な食べ方についてレクチャーしてもらいました。最初は遠巻きで見ていた子どもたちも、出来上がった唐揚げを見て『ちょっと食べてみたい』となり、最後にはみんなで『塩よりカレーのほうが美味しいね』なんて品評会もやりましたね」

施設の造りや内装にもかなりのこだわりがある。まず、子どもたちが自分たちで遊びを生み出せるように、施設内に余計な物は置かない。けれど、トカゲや金魚などの小さな生き物や、ベイゴマなど子どもたちが手づくりした物は置くようにしている。


「何でも遊びに変えられる子どもたちの能力を伸ばせたらと思っています。雨が降ったときには『どうやって遊ぶ?』という話になり、『外で雨に濡れたい!』という子どもがいました。うちには入浴施設があるので、『じゃあ遊んでみたら?』と伝えると、30分後には子どもたち全員が外で泥だらけになって遊んでいました。ベイゴマも、ヤスリの掛け方ひとつ、回し方ひとつで、かなり回り方が変わってくるんです。子どもたちは、それを1日以上かけて、手が真っ黒になるほど熱中して作り込んでいました。そういった時間をかけ、汗を流して遊び込む経験は、子どもたちの集中して打ち込む能力を伸ばせるんじゃないかと考えています」


施設は大きく分けて、元気良く遊び回れる「動」の空間、食後などにリラックスできる「静」の空間に分かれている。壁の色なども、琉球大学の人間行動学の専門家と話し合い、落ち着く色合いや明るい色合いを部屋ごとに採用。子どもたちが気分を切り替えやすい造りになっている。


また、子どもたちがけんかしたときに一人になってクールダウンできる面談室も設置。スタッフ一人一人に「お父さん」「お母さん」「おねえちゃん」「おじさん」といった役割があり、子どもたちがここをもう一つの家だと感じ、安らげる配慮も忘れない。
「僕は、『困ったときに相談できる、親しいお兄ちゃん』的な役割ですね(笑)。子どもたちの親でもなければ、学校の先生でもない。一歩引いた第三者的な立場から、子どもたちと接することができるんです。そういった良い意味で“いい加減”な大人たちがいることで、子どもたちも親や先生に言えないことも打ち明けやすくなると考えています」

元は学童職員。施設に行きたくても行けない子どもたちの存在を知って…
大分県出身の平林さんは、沖縄県に暮らして18年目になる。今の仕事に関わることとなったきっかけは、学童の仕事を通して、学童に通いたくても通えない子どもたちの存在を知ったことだ。
「学童の前を、残念そうな顔で去っていく子どもたちが結構いたんです。『こっちで一緒に遊ばない?』と誘って遊ぶのですが、『遅くなったから、学童で遊んでいたことをお母さんに伝えてね』と言うと、次の日から、親に『お金を払えないから行ったらダメ』と言われるのか、ぱったり来なくなるんです。そんな子どもたちを何人も見ていると、家や学校以外、学童以外の居場所が必要なのではないかと考えるようになりました」

その後、学童保育支援者センターという学童全体の底上げに関わる仕事や、子どもの貧困に関する調査に当たっていたという平林さん。不登校や引きこもりの支援や、子ども食堂の立ち上げ、居場所のコーディネーター事業にも関わり、その流れで田場拠点のマネージャーに選ばれた。
「現場はかなり久しぶりですが、めちゃくちゃ楽しいですね!子どもたちと近い距離で関わることができますし、現場でしか感じられないところもたくさんあります」
田場拠点では、とことん子どもたちに向き合いながら、数字で表せないところまでしっかり記録に残すことを意識しているという。
「子ども同士のトラブルや、スタッフが感じた表情の変化などと共に、子どもの行動を過去と未来を結びつけ、ここでの体験がこの行動や考え方に影響を与えたといった因果関係を確認するようにしています」
子どもは、幼稚園から中学3年生まで全員で14名がこの「居場所」に通っている。不登校で最初は大人を信用せず、とげとげしいところもあった子どもが、施設に通ううちに、小さな子どもの手をつないだり、おぶってあげたりする優しい面をたくさん見せるようになってきたという。
「ここで安心や安全を手に入れることができたからこそ、その子どもが元々持っていた優しさを表に出すことができたんだと思います」と平林さんは語る。
生活リズムが崩れ、朝食や入浴、歯磨きの習慣がなかったという子どもも多い。田場拠点ではそんな子どもたちに、手を洗ったり、みんなでごはんを食べたり、お風呂に入ったりといった当たり前の習慣もみんなで一緒に行う。


「片親の家庭で育ったある子どもは、親が忙しいためか、一緒にお風呂に入るという経験があまりなく、入浴の際の頭の洗い方もシャンプーを付けて流すだけでした。スタッフに洗い方を教わり、しっかり洗えるようになってからは、他の子どもに『シャンプーの時、耳の後ろも洗うんだよ!』と教えてあげていましたね」
こういった習慣面の改善は、大人になったとき自分の子どもにもしっかりそれを教えられるという、良いサイクルにつながる。
点から線に、線から面にすることで、より多くの子どもたちを救える
最後に、平林さんに今後必要とされる子どもたちへの支援について尋ねてみた。
「経済的にそれほど裕福でなくても、幸せな家庭はたくさんあると思います。そこをゴールとするなら、地域コミュニティの再生は欠かせませんね。『地域で子どもを育てる』という意識を培うことで、虐待の早期発見や、地域レベルで安全性の向上、子育てで困っても相談できる環境を生み出すことができると思います」

地域でつながるためは、人と地域をつなげるソーシャルワーカーや、コミュニティソーシャルワーカーが欠かせないという。
「こういった方々が、人をつなげることで、面白い取り組みや、困ったときのセーフティネットが生まれるのではないでしょうか。拠点名には、『地域の大人や子ども、さまざまな人が集う場所』という意味を込めています。点と点をつないで線にし、その線と線をつないで面とする。その網目が細かければ細かいほど、救える子どもの数がもっと増えるのではないかと考えています」


沖縄の方言に「ゆいまーる」という言葉がある。これは、「助け合い」「共同作業」「一緒に頑張ろう」といった意味があり、重労働であったサトウキビの精製作業を地域の人々が助け合って行ったことに由来するそうだ。一人でできることには、限りがある。だから他人や地域との結びつきが必要になる。沖縄に限らず、全国でもそんな「ゆいまーる」の精神が広がれば、心から安心してワクワクできる子どもが増えることだろう。
撮影:永西永実
- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。