未来のために何ができる?が見つかるメディア
豊かな未来の鍵は地方にある「余白」?全員参加で「ポスト資本主義社会」を探る

- お金だけではない。自然とのつながり、自由な時間など「豊かさ」の定義は多様化している
- 予測不可能といわれる今の時代、自ら問題提起をしていくクリエイティブな能力は重要
- 地方にある「余白」は、本当の「豊かな」未来を切り開く可能性を秘めている
取材:日本財団ジャーナル編集部
「VUCA(ブカ/ブーカ)」という言葉をご存知だろうか。Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字をとった造語で、1990年代後半にアメリカで軍事用語として使われていた「カオス化する時代」を指すものだ。そんな20年ほど前の用語がビジネスニュースなどでよく見られるようになった。
それと同時に近年、指摘されているのが「資本主義の限界」だ。自由な競争を認める資本主義では、資本家と労働者の格差が広がり続けてしまう。また、地球全体の資源、環境の問題が深刻化し、GDPなどの「数字」だけでは、将来性なども含めた本当の意味での「豊かさ」が測れなくなってきている。
では、私たちはこの予測不可能な時代をどう生き抜けばいいのだろう?そのヒントを探るべく、日本財団ソーシャルイノベーションフォーラム2019で開催されたプログラム「未来実装会議」では、4つのテーマで「ポスト資本主義社会」のあり方について切り込んだ。
地方にある「余白」とは可能性である
「本日は、ちょっと変わった形式でプログラムを進めたいと思います」
「未来実装会議」の冒頭でそう話したのは、さまざまな起業家たちが地域社会で活躍するプラットフォームづくりを通して、ポスト資本主義社会のあり方を探求する、Next Commons Lab(以下NCL)(別ウィンドウで開く)代表の林篤志(はやし・あつし)さんだ。

「人口減少や高齢化、過疎化といった問題が注目されがちな日本の地方ですが、見方を変えれば、土地代が安く、競争相手が少ない、いわゆる『余白』が多い場所と考えることもできませんか?そんな余白を『可能性』ととらえポスト資本主義のあり方を探るのが我々NCLです」
林さんの周りには、何重にも円状になった座席が配置されている。これは「フィッシュボウル(金魚鉢)形式」と呼ばれる対話手法で、中心部分の円座(今回は5席)には話す人、その周りには話を聞く人が座る。中心に座るメンバーは流動的で「私もこのテーマで話したい」と思った人が中心まで行って話に加わる参加型パネルディスカッションとも言える。
中心の5つの席のうち、1席だけは空席にしておくことがルール。そこに話し合いに加わりたい人が座り、新しい空席をつくるために4人のうちの誰かが自主的に席を立つことになる。

「未来実装会議」では、会議の進行と併せてそのポイントをイラストでまとめる「グラフィックレコーディング」も採用。今話し合っている内容を直感的に把握することができる。
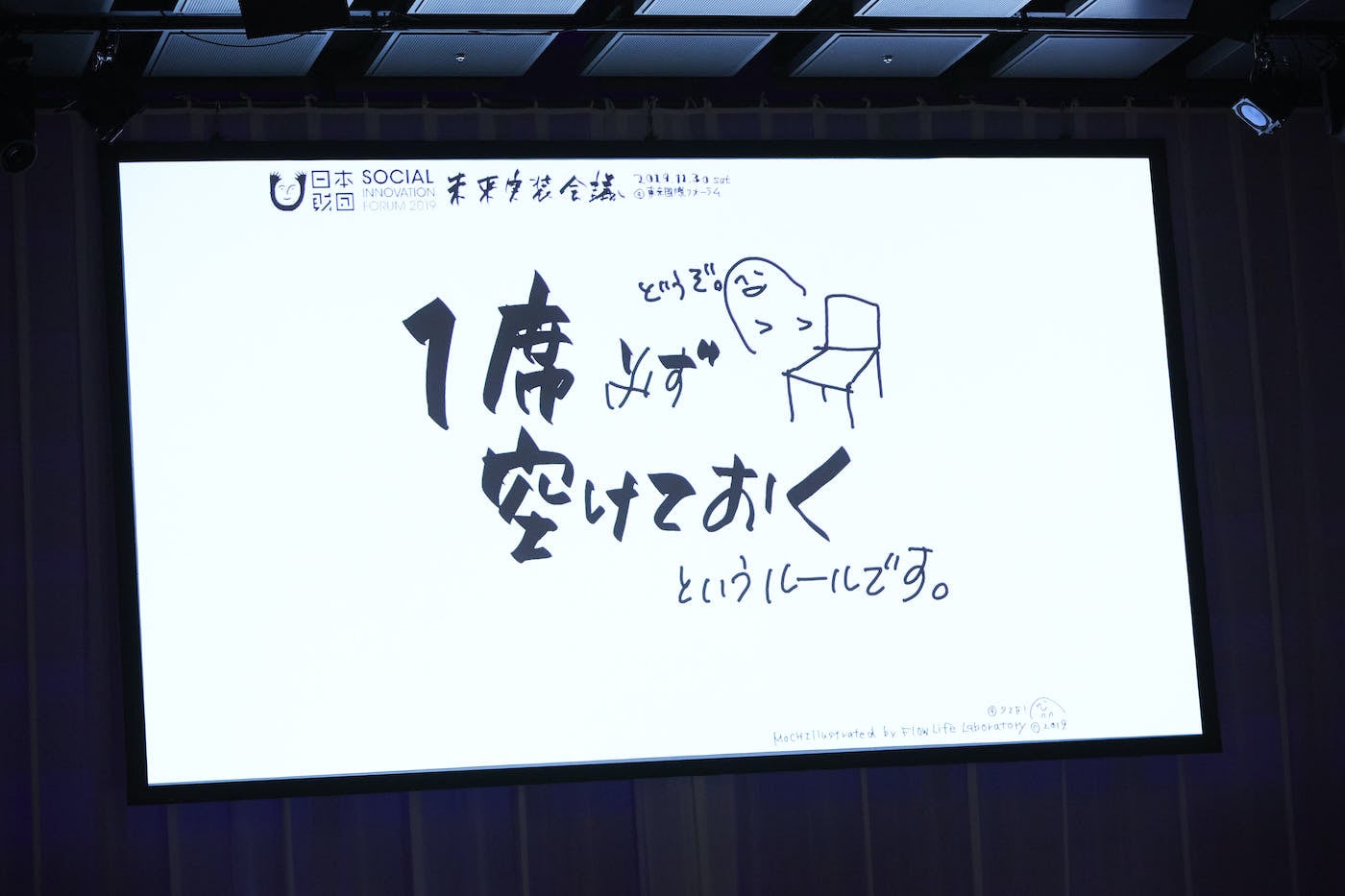
「僕が話をするのはここまで。本日は4つのテーマを用意しました。各テーマの導入部ではテーマオーナーが話をしますが、その後実際に会議を進めていくのは皆さんです」
〈テーマオーナー〉
テーマ:お金
鈴木直之(すずき・なおゆき)
愛媛県西条市で「ありがとう」を見える化する基金サービスの開発やブロックチェーンを使った地方通貨づくりに携わる。

テーマ:アート
明貫紘子(みょうかん・ひろこ)
メディアアートクリエイター。映像を切り口に、人のコミュニケーションや街の在り方を提案する。

テーマ:食べる
三原惇太郎(みはら・じゅんたろう)
奈良県天川村で暮らすハンター。以前は東京で、M&Aアドバイザリー会社に勤めていた。

テーマ:けもの
富川岳(とみかわ・がく)
東北の地域文化に傾倒し、フィールドワークや商品開発、デザイン、教育機関と連携した取り組み等を展開。

揺らぐお金の価値観。本当の「豊かさ」とは?
「NCLでは、資本主義に続く社会の在り方を考えていますが、いきなりポスト資本主義と言われてもよく分かりませんよね。このセッションでは、まず現在の資本主義と切っても切れない関係にある『お金』について考察していきたいと思います」
1つ目のテーマ「お金」のテーマオーナーである鈴木さんは、ここ数年で人々のお金に対するスタンスが変わりつつあり、以前は絶対的価値が高かったお金が「民主化」「相対化」しているという。

「以前は会社をつくるには、数百万円ほどの資本が必要でしたが、最近では、クラウドファンディングを使って、誰かがやりたいことをみんなでサポートする方法が浸透しつつあります。これが民主化ですね。お金の相対化に関しては『お金以外にも大切なことがあるのでは?』と考える人が増え、お金があれば幸せになれるという考え方が揺らいでいることが挙げられます」
猟師の三原さんも「2年前に仕事を辞めて、現金収入は減りましたが、可処分時間が大幅に増えて、トータルでとても幸せですね。今の暮らしの方が断然良い」と話す。
印象的だったのが、参加者の大学生から挙がった「お金が労働者を生み出しているのでは?」という意見。「働くことには、誰かのためにする『労働』と、自分や社会のためにする『仕事』の2種類があると思う。私は、労働ではなく、仕事をしたい」、「労働をしているだけでは世の中は変わらない。仕事をする人が増える教育が大切なのではないか?」と議論は盛り上がる。

独自の視点で社会に問いかけるアートが持つ力
今回、1時間という短い時間の中で、各テーマに割り当てられた時間は約15分。「教育」という話から「アート」に話をつなげたのは、テーマオーナーである明貫さんだ。
「21世紀の教育としては、有名なSTEM(ステム)教育(※)がありますが、最近ではそこにArt(アート)の「A」をプラスしたSTEAM(スティーム)教育が脚光を浴びています」
- ※ Science(化学)の「S」、Technology(技術)の「T」、Engineering(工学)の「E」、Mathematics(数学)の「M」の頭文字をとったもの。先生に教えてもらうのではなく、子どもたちが自分で学び、理解していく実践的な経験に重きを置いている

「こんなこと言ってしまうと怒られるかもしれませんが、アーティストが役に立つ時代になってきたと感じますね。これまで問題解決といえば、合理性重視のロジカルシンキングが重要視されてきましたが、そういった枠組みの外から勝手に問いかけるのが、アートなんです。予測不可能な時代と言われる今、自分で問題提起をしていく能力はとても大切なのではないでしょうか?」
アーティストが人工的に生み出した霧や天体の映像を会場の大画面に映し出した明貫さんは、「そこに人工的な宇宙や自然現象を生み出すことで何かを問いかけようとしている、これまでと違った問題提起の在り方やアプローチ方法がある」と語った。

参加者からは「『宇宙』というキーワードはいいですよね。現在、『宇宙』をテーマに鳥取県をPRするプロジェクトを進めているのですが、分からないものが多いほど魅力的に見えます」といった声も。
人類は昔から、星を読み、星座にまつわる物語を紡いできた。人の想像力の起源は、宇宙にあるのかもしれないと明貫さんは語る。
「人は何かと宇宙とつなげるアンプ(増幅器)的な役割を果たしているのかもしれませんね。そこにAIもできない、アーティストのちゃぶ台返し的な可能性もあるのではないでしょうか」
現代人が見失いつつある、原始的な自然とのつながり
続く「食べる」「けもの」の2つのテーマは、人と自然のつながりについて思考を深めるトピックが中心となった。
「一人で山へ分け入り、鹿や猪の足跡を見つける。慎重にその跡をたどると、やがて獲物が視界に入る。ここからは、獣と自分、一対一の駆け引き。人間社会とか野生の生態系とかいう枠組みは、全て消え、僕と僕を見つめる鹿だけの世界になる。そんなふうに仕留めた獲物を、解体し、家に帰って料理して食べた時に自分も自然の一部だったのだという、感動に近い感情が湧き上がりました」
奈良県の山奥で猟師をする、「食べる」のテーマオーナーの三原さんは、猟を始めた時のことをこう語る。

「食べる」ことは、ただ胃袋を膨らませ、栄養を摂取するための行為ではなく、自然とつながりを持たせてくれる幸せな体験だと三原さんは話す。
「この感動を誰かに伝えるべく、奈良県で炎を見ながら料理を食べられるゲストハウスづくりを進めています」
岩手県の遠野市で暮らす、「けもの」のテーマオーナーの富川さんは、遠野を舞台した逸話、伝承などを記した説話集『遠野物語(著:柳田國男)』の世界に夢中だという。

「僕には、79歳の師匠がいるのですが、『この坂道で山の神とすれ違ったんだよ』『そこの川に河童が住んでいたんだよ』という話を聞いて、河童って本当にいたんだ!と感心する毎日です(笑)。本気で信じているわけではありませんが、これだけ日本中で河童の話が残っているのなら、そこには何かしらの目的や共通項があるのではと思いますね」

日本で河童の目撃談がなくなったのは、1970年代の高度成長期からだと話す富川さん。
「テクノロジーが進化していく時代に、身体性や第六感、自分の中の野生性をどうやって取り戻していくか、そういったものを遠野で考えてみたいですね」
会場からは「以前にブラジルに住んでいた時、ワニに食べられそうになったことがあります。その時、人って食べられるんだなって感じました(笑)。自分も食物連鎖の中にいることを感じた体験です」といった話や、「最近のサウナブームも、死を感じる熱気の中にいて、水風呂に入って生き返るといった生を感じる体験なのかも」「日常で人の死に触れることがほとんどない。死とはいったい何なのか」といった「生と死」ついて言及する意見まで出た。
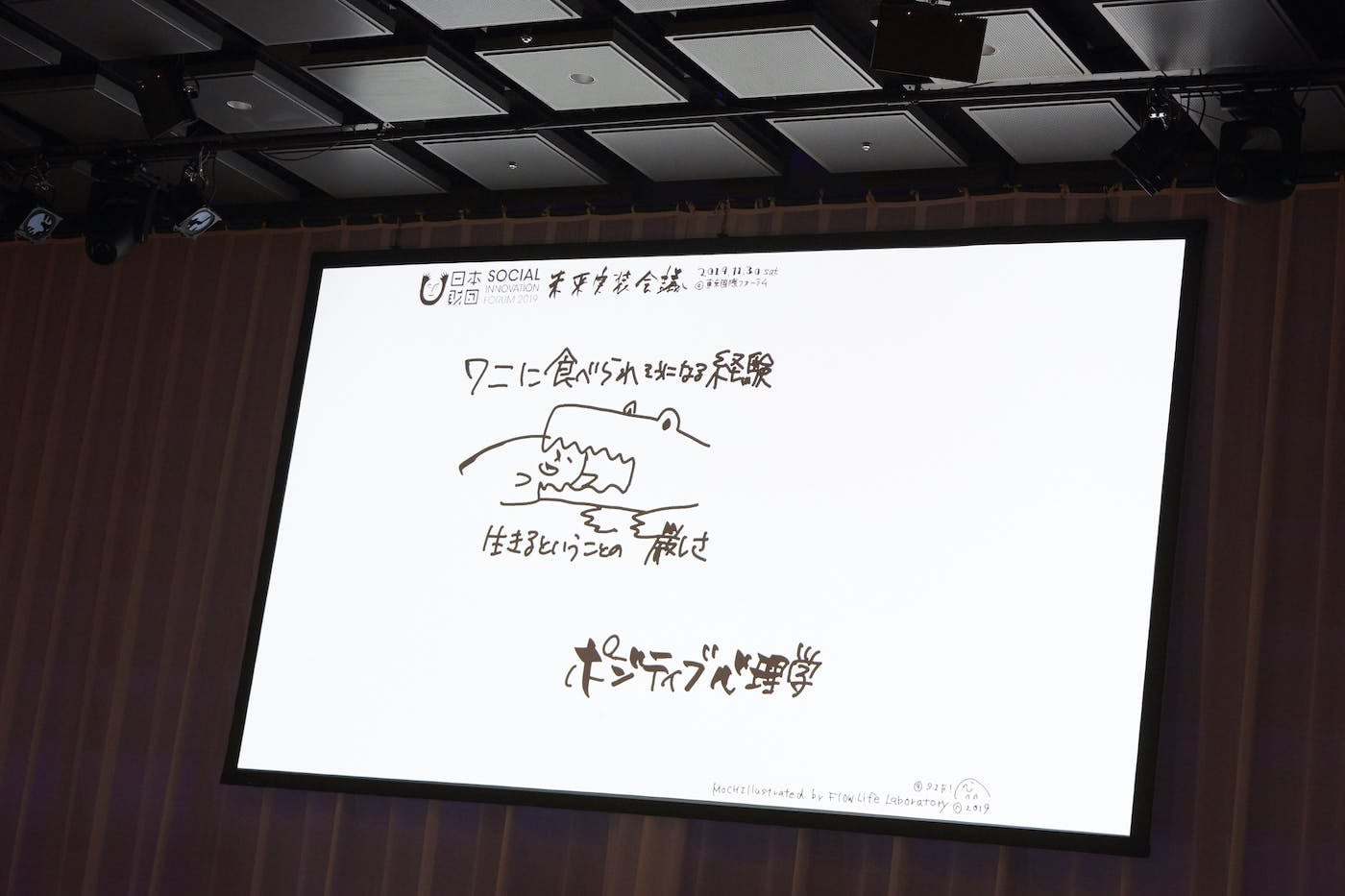
地方には、現代人が見失いつつある「生きる」ことの意味、「創造する」ことの面白さを回帰させてくれるきっかけがたくさん残っているのではないか。未来は自分たちで考え、自分たちの手で築いていくものなのだということを、プログラムを通して改めて感じた。そのための鍵になるのが、地方にある「余白」であって、真の意味で「豊かな」未来を切り開く可能性を秘めているのかもしれない。
撮影:十河英三郎
- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。













