未来のために何ができる?が見つかるメディア
歌は命の証。偏見や差別を受けながらも誇り高く生きた、ハンセン病患者たちの後世への願い

- 高齢化が進む元ハンセン病患者。療養所の存続や、差別の歴史を後世にどう引き継ぐかが課題に
- 『訴歌』はハンセン病患者が詠んだ短歌や俳句、川柳など約3,300点を収録した唯一無二の歌集
- 過酷な状況の中で誇り高く生きたハンセン病患者の思いに触れ、「何ができるか」を考えるきっかけに
取材:日本財団ジャーナル編集部
感染力は極めて弱く治る病気であるにもかかわらず、誤った政策のもと山奥や離島にある療養所に強制隔離され、長い間偏見や差別にさらされ苦しんできたハンセン病患者とその家族たち。1996年に「らい予防法※1」が廃止されてから25年が経った現在も、ハンセン病療養所には国立13カ所に1,001人、私立1カ所に3人(※2)の元患者が入所している。
- ※ 1. ハンセン病 (らい) の発生を予防すると共に,患者の隔離,医療,福祉をはかり,それによって公共の福祉の増進に資することを目的とした法律。旧法(1907年)に代わって1953年に制定された
- ※ 2.令和3年5月1日現在。厚生労働省調べ
平均年齢87歳という高齢であることや、視覚や手足に後遺症が残ることも理由にあるが、社会の偏見や差別を恐れ、「最後は住み慣れたこの場所で」と残る人も多い。この現場をいかに維持していくか、決して繰り返してはならない歴史を後世にどのように引き継ぐかが課題となっている。
2021年5月、全国のハンセン病療養所で詠まれた短歌、俳句、川柳を集めた歌集『訴歌(そか) あなたはきっと橋を渡って来てくれる』(皓星社)(外部リンク)が刊行された。隔離生活で強いられた患者たちの喜怒哀楽、家族や故郷を思う心などが情感豊かに謡われた作品の数々は、私たちに療養所での暮らしや、入所者が日々の中で味わうさまざまな感情を教えてくれる。
この本を手掛けたフリーランス編集者の阿部正子(あべ・まさこ)さんは、「これらの歌は、読者の頭に、心に変容をもたらしてくれる」と考え、出版社に企画を持ち込んだと言う。その経緯と共に、彼女が社会に伝えたい思いを伺った。
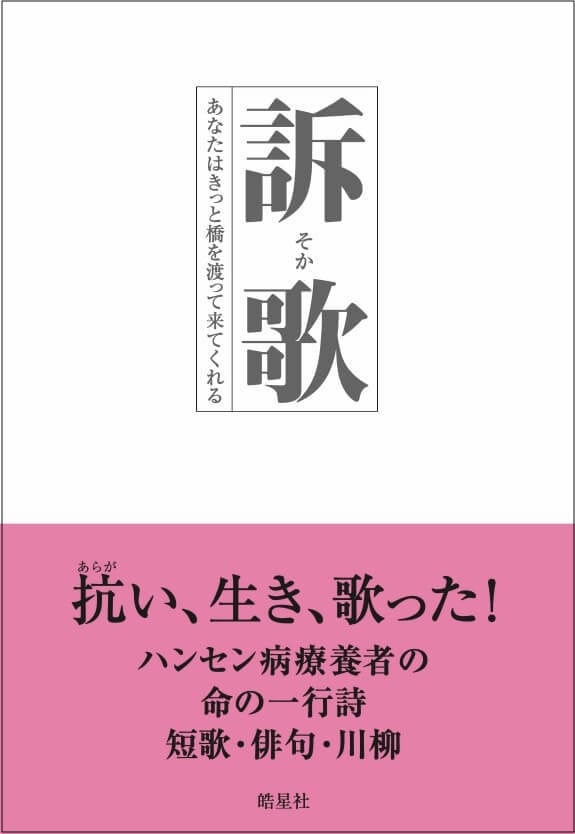
ハンセン病療養所での暮らしを伝える文学全集との出合い
「小説」52篇、「記録・随筆」133篇、「詩」1,000篇、「短歌」2万首、「俳句・川柳」1万句を収録し、長年にわたる強制隔離政策下におけるハンセン病療養所の実態を証言する『ハンセン病文学全集』(皓星社 全10巻)(外部リンク)。この本との出合いが、阿部さんのその後の人生に大きな影響を与えることになる。
「恥ずかしながらそれまでハンセン病について全くの無知で、同じ時代を生きていながらこんな病気や差別があったなんて……と衝撃を受けました」
当時(2015年)、編さんをしていた『俳句・短歌・川柳と共に味わう 猫の国語辞典』(三省堂)に掲載する歌を探すために訪れた日比谷図書館(東京・千代田区)で、たまたま手に取ったのがきっかけだった。
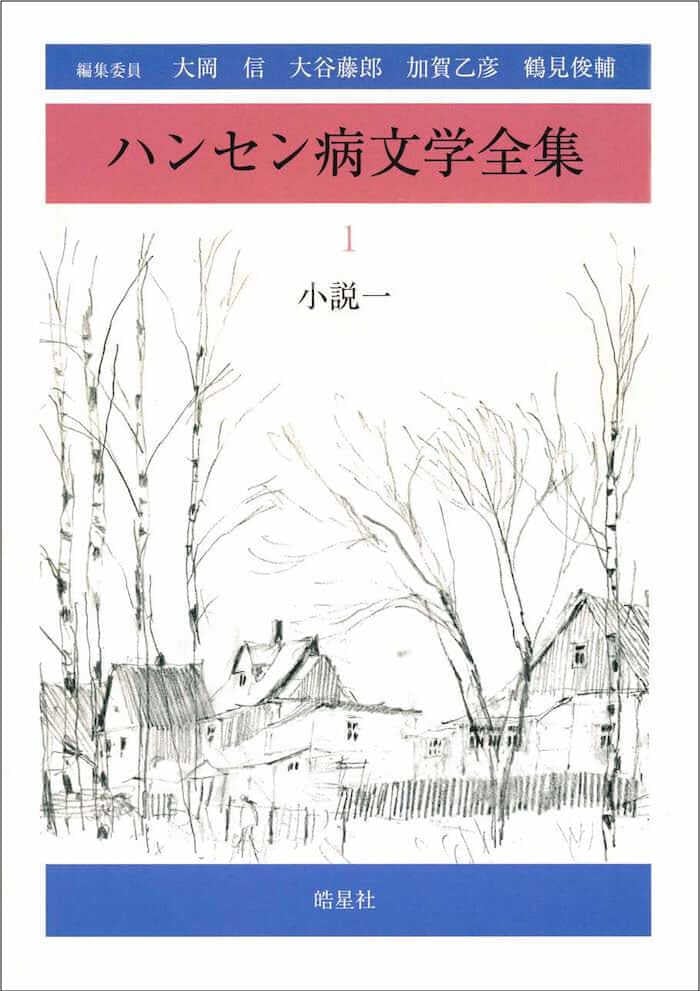
「初めのうちは歌の背景も分からなくて。例えば『猫の子に飯(めし)を冷やしてあたえけり』(中野三王子 1926年)という歌があるのですが、なんで『冷ます』ではないのだろう?と。でも、ハンセン病について調べ、何度も繰り返し読むうちに、作者の手の感覚が麻痺していて、猫にやけどをさせないための気遣いなんだと想像できるようになりました。猫の歌が多いのは、療養所に猫を捨てる人がたくさんいたからということも、後になって知りました」

『ハンセン病文学全集』を読み進めるうちに、「文芸作品としてもっと評価されてもいいのでは」という思いと、「近い将来、療養所で暮らす人がいなくなったら、こういった患者たちの想いを伝えるのが難しくなるのでは」という思いが重なり、「今こそ、療養所で生きた人たちの苦難を心で受け止めなければ」と『訴歌』の企画を立ち上げたと言う。
「本当は皆さんに『ハンセン病文学全集』を読んでいただきたいのですが、初めてハンセン病に触れる方にはハードルが高いかと。その足掛かりになるような本を作りたいと思ったんです」
『訴歌』に収録されているのは、『ハンセン病文学全集』の第8~10巻に収められた短歌や俳句、川柳から抜粋された約3,300点。作者は10歳に満たない子どもから年配者までと幅広く、1,000人余りの“生きた証”が綴られている。
ジャンル別ではなく「生き別れる」「幼くて病む」「形見を着る」など1,000のテーマで歌をまとめることで、療養所内で暮らす患者たちの情景が伝わるよう工夫したと言う。
阿部さんは、2020年に出版した『てにをは俳句・短歌辞典』(三省堂)においても『ハンセン病文学全集』から約6,000点の歌を収録している。江戸から昭和まで、有名・無名を問わず6万を超える短歌・俳句を集めた同書の中で、ハンセン病患者たちの作品は、松尾芭蕉(まつお・ばしょう)や与謝蕪村(よさ・ぶそん)、種田山頭火(たねだ・さんとうか)といった希世の歌人たちの作品と同列に並んでいるが、「どの歌も作品としてとても優れていて、全く引けを取りません」と阿部さんは話す。
『ハンセン病文学全集』を編集した皓星社の編集者・能登恵美子(のと・えみこ)さんは、全国各地の療養所を訪ねて回り、地道に作品を集めた。ハンセン病患者たちから絶大な信頼を受けて、同全集を完結させたという。
阿部さんは、能登さんがいなければこの本はできなかったと、何度も繰り返し話す。
「能登さんは『ハンセン病文学全集』が完結した翌年に病気で亡くなられているので、面識があるわけではありません。でも、今思うと、日比谷図書館で能登さんの魂が私を呼び止めたのかもしれませんね」
能登さんは、10巻目が完結して間も無い2011年に49歳という若さで亡くなった。2012年に出版された彼女の遺稿集『射こまれた矢』(皓星社)(外部リンク)でも、ハンセン病患者や回復者たちに寄せる想いを読み取ることができる。

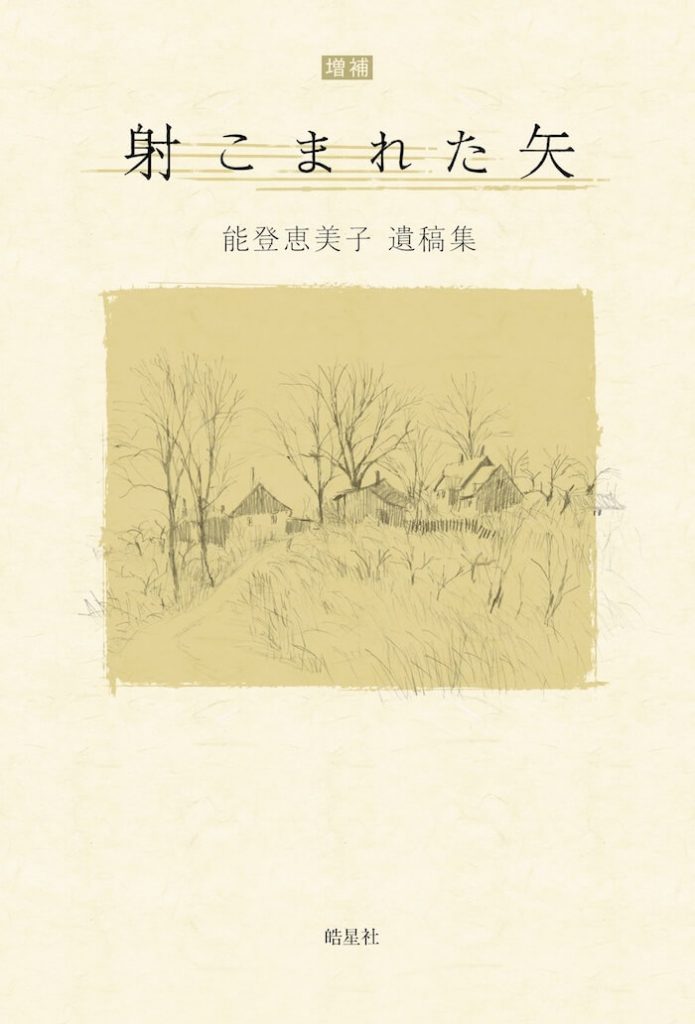
日々の暮らしの中で感じる喜怒哀楽。感性が光る作品の数々
ハンセン病の歴史を「歌」という形で残したいと思う一方で、ハンセン病に関する資料はさまざまな形でメディア化されており、自分の出る幕ではないとも思っていたという阿部さん。背中を押したのは、『ハンセン病文学全集』に収められた一つの歌だった。
「密(ひそ)かにも読み残されゐし歌のほか患者らの惨劇(さんげき)伝ふるものなく」
山本吉徳 1998年
「この歌を読んだ時に、本当は自分が置かれている状況を知ってほしい、惨劇を伝えてほしいと言っているんだ。よし、やろうと決めました」


歌を括る1.000のテーマの中には「足を絶つ」「死んでくれ」「中絶」など、思わずドキリとさせられるものも多い。
「姉は死ねと妻は生きよと云ひて来る便(たよ)りを置きてただに切(せつ)なし」
富永友弘 1956年
「襖越(ふすまご)しに死んでくれよと長兄(ちょうけい)の言いいし声の耳を離れず」
入江章子 1998年
「ただし、歌に詠んでいるということは『死んでくれ』と言われても死ななかった、生き延びたということなんです。過酷な状況の中ではありますが、言葉がとても力強く、自分を鼓舞する作品の多さを感じます」と阿部さん。
作品の中には「戒名(かいみょう)を享(う)けて遍路の旅に出(い)づ」(桂自然坊 1988年)など、「遍路」について詠われたものが多い。その理由について尋ねると、「当時、ハンセン病に罹患(りかん)した人の選択肢は、隠れ病む(※)か、終生遍路し続けるか、療養所に終生隔離されるかしかありませんでした。ハンセン病患者は一般的な遍路道を歩くことができず、過酷な旅路だったと聞きます。だからこの歌では、遍路に出る前に『戒名を享け』ているのですね。遍路の果てに療養所に入所した人も多かったようです」と、阿部さんは教えてくれた。
- ※ 人目を避けて家に隠れ住むこと。通報され、強制的に療養所に隔離されるケースも多かった
読み進めていくと、入所者の日々の暮らしぶりが少しずつ見えてくる。
例えば、「物売りが来る」のテーマに並ぶ歌からは、療養所には四季を通じてさまざまな物売りが訪れ、入所者が楽しそうにやりとりをする様子が目に浮かぶ。
「金魚金魚急ぎて出目(でめ)を二つ買ふ」
牧野典 1958年
「風鈴(ふうりん)や言葉巧(たく)みに布地売る」
石垣美智 1971年
一方、「雑居部屋」「雑居夫婦部屋」のテーマからは、穏やかな療養生活とはかけ離れた暮らしがうかがえる。
「やすらぎのなき生活とだしぬけに妻の言ひたる言葉身にしむ」
鈴木楽光 1957年
「三十六畳に十七人の男住み病む吾が枕辺(まくらべ)を荒荒(あらあら)しく通る」
山口義郎 1955年

また、これらの歌からは、病と闘いながら四季の移ろいを喜び、花を愛でる様子が垣間見える。
「足萎(な)へのわれに見せむと初咲きのライラックを夫(つま)が剪(き)り来てたびぬ」
松永不二子 1988年
「退室日夫(つま)に見えぬが花を生け」
影山セツ子 2003年
療養所における「入室・退室」は社会(療養所の外)で言うところの「入院・退院」のこと。ハンセン病患者にとって療養所は病院だが生活の場でもあり、病や後遺症が悪化すると「病室」に入室することになる。だから、この句は夫が改善して病室から退室する喜びを詠ったものでもあるのだ。
「『ハンセン病文学全集』と出合うまで、ハンセン病療養所で暮らす人たちに日常生活や喜怒哀楽があったこと、人間らしい生活を奪われながらも人間らしく、誇りを持って生きていたことに思い至りませんでした」
読者からも「昔のことだと思っていたが、私が生きてきた時代にも悲惨な現実があったことを知らずにいた。それと同時に、歌を詠むことがこれほど人に力を与えることを知った」「ハンセン病を患い、絶望の中にも創作や表現の喜びを見出し、小さな希望を持っていたのかと思い、人間の底力を見た」など、多くの賞賛の声が阿部さんのもとに寄せられている。
歌を「タイムカプセル」に乗せて、後世へ思いをつなぐ
阿部さんは『訴歌』の副題にこの歌を添えた。
「あなたはきっと橋を渡って来てくれる」
辻村みつ子 1992年
一見、特定の人物の面会を待ちわびる気持ちを詠っているように思える歌だが、「あなたはいつかきっと私たちのことを知り、理解してくれると思うから、待っていますよ」という社会に向けた悲願が託されていると阿部さんは話す。
この本に集められているのは、ハンセン病患者たちのそんな「いつか、きっと」という願いでもある。
それ以上に「文芸作品として楽しんでもらえたら」と阿部さん。
全ての作品には、歌が発表されたおおよその年号が記されている。一番新しいものでは2002年。歴史で学んだ知識や自分が同時期に過ごしていた時間と重ね、もしも自分や家族がこの場所にいたら……と想像しながら読むと、情景が浮かびやすいのではないだろうか。

「私はこの本を『タイムカプセル』だと思っているんです。読んでくださる方が発掘して、タイムカプセルを開けた瞬間が始まりです。開けるのに遅いということはありません」
『訴歌』の最後はこの歌で締め括られる。
「はこべらよもう生い立ちを喋(しゃべ)ろうよ」
辻村みつ子 1992年
偏見や差別を恐れ、自身がハンセン病の回復者であることや、身内に元ハンセン病患者がいることを話すことができる人は多くない。高齢化により、自らの体験を語れる人も減りつつある。
この悲しい歴史を繰り返さないためにも、タイムカプセルを開けることから始めよう。過酷な状況の中でも誇り高く生きた人たちの歌に触れ、ハンセン病の偏見・差別、施設の維持問題に対し「自分に何ができるか」を考えるきっかけにしてほしい。
撮影:十河英三郎
〈プロフィール〉
阿部正子(あべ・まさこ)
1951年、千葉県生まれ。元三省堂編集者。同社では農薬やがん治療の問題、障害児、薬害エイズ、誕生死等、社会問題を取り上げた単行本や『てにをは辞典』シリーズなどの企画・編集に携わる。現在はフリーランスの編集者として活躍中。
- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。













