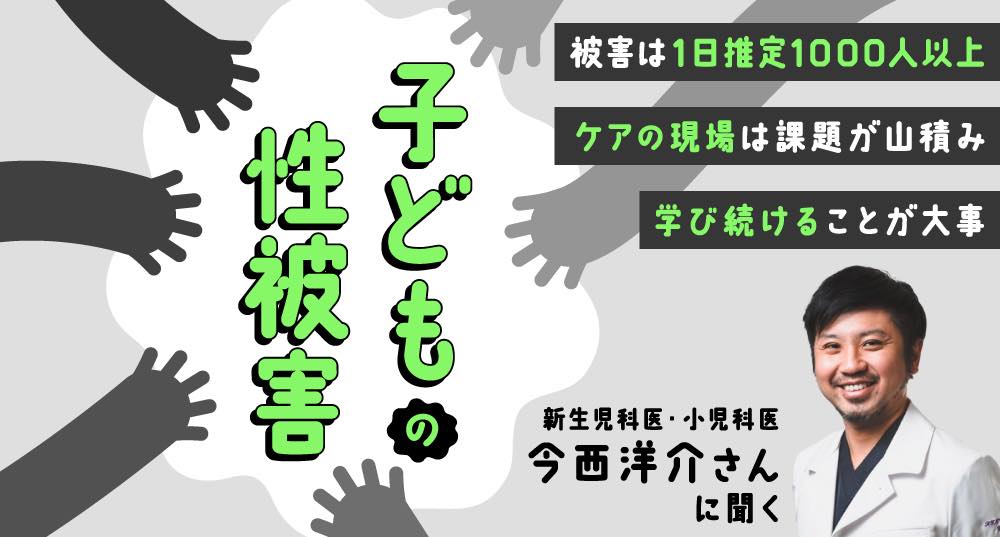未来のために何ができる?が見つかるメディア
【避難民と多文化共生の壁】専門家に問う、ウクライナ問題から見た日本で暮らす「外国人との共生」の意味

- 大きな流れで見ると、日本は外国人の受け入れを促進しつつある状況
- 日本の人口が減少していく中、多様な人を受け入れることが地域社会を持続可能にする
- 「外国人」ではなく、同じ地域社会を構成する住民同士という意識が大切
取材:日本財団ジャーナル編集部
ウクライナ避難民の受け入れを通じて、命を守るため来日した人々が安心して暮らすためにはどのような社会づくりが必要か、多角的な視点から探る特集「避難民と多文化共生の壁」。
ロシアによる軍事侵攻の状況から、避難民の来日生活は長期化するだろうと予測されている。
ウクライナ避難民家族にインタビューした前回の記事(別タブで開く)では、日本語の習得や社会制度の違いを知ることに加え、働いたり友人をつくったりするなど「普通の生活」を送る難しさが見えてきた。
そこで第3回は、ウクライナ避難民に限らず、私たちが外国人と共に暮らしてく上で、どのような課題があるのか、また共生することの意味を探りたい。
日本には現在(※1)、276万635人の在留外国人がいる。最も多いのが「永住者」の83万1,157人で、以降は「特別永住者」29万6,416人、「技能実習」27万6,123人、「技術・人文知識・国際業務」27万4,740人、「留学」20万7,830人と続く。総人口に占める外国人の割合は2.2パーセントと決して多くはないが、2015年から2020年の間で日本人人口が1.4パーセント減少する一方で、外国人人口の増加率は43.6パーセント(※2)。今後も増えていくことが予想される。
- ※ 1.出入国在留管理庁「令和3年末現在における在留外国人数について」(外部リンク)
- ※ 2.総務省統計局「令和2年国勢調査 -⼈⼝等基本集計結果からみる我が国の外国⼈⼈⼝の状況-」(外部リンク)
国籍や民族などが異なる人たちが共に生きていく「多文化共生」社会は、もう目の前まで来ている。日本人と外国人が、お互いに違いを認め合いながら暮らすことには、どういった意味や必要性があるのか?
筑波大学・教授(外部リンク)の明石純一さんと、一般財団法人ダイバーシティ研究所(外部リンク)代表の田村太郎さん、日本に暮らす外国人の事情に詳しい2人の専門家による対談をお届けする。
30年間で日本に暮らす外国人の多様性が増している
――近年、日本に暮らす外国人の数は増え続けています。その背景についてお聞かせください。
田村さん(以下、敬称略):契機になったのは1990年の改正入管法(出入国管理及び難民認定法※1)の施行です。当時の政府は「外国人労働者は受け入れない」という方針を掲げていましたが、この改正で例外的に「日系人は受け入れる」としたため、日系ブラジル人やペルー人が多数来日するきっかけになりました。1993年には、日本の高い技術を学んで母国に持ち帰る国際貢献を目的とした「外国人技能実習制度※2」もスタート。アジア諸国から技能実習生もやってくるようになったんです。
- ※ 1.日本へ入国、または日本から出国する全ての人の出入国の公正な管理を図り、難民の認定手続きを整備することを目的とした法律
- ※
2.日本で培われた技能、技術または知識を開発途上地域等へ移転することによって、その地域等の経済発展を担う人材の育成に貢献することを目的に1993年に創設された制度
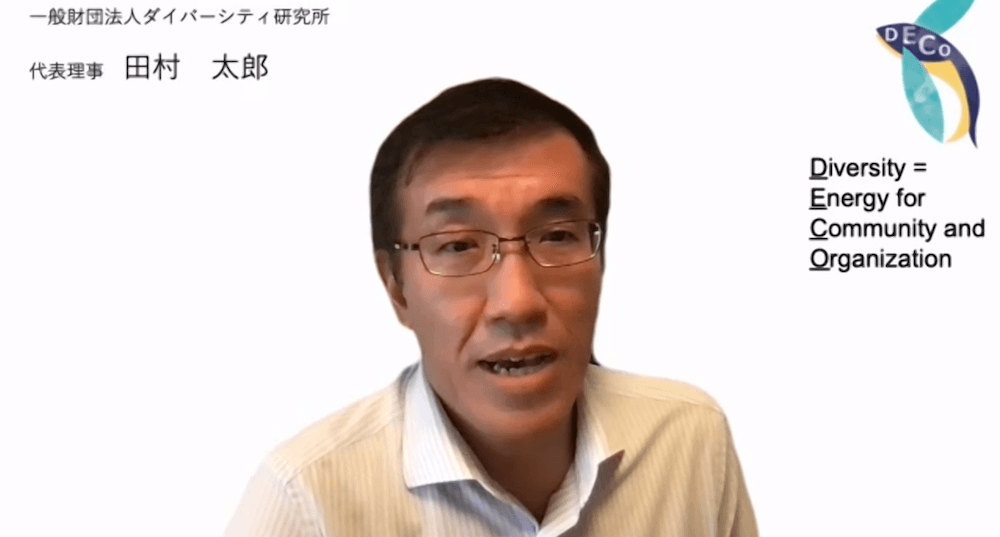
明石さん(以下、敬称略):日本に居住する外国籍者のマジョリティ(多数者)は、長らく、在日コリアンでした。しかし1990年の入管法改正を1つのきっかけに状況が変わり始め、南米、中国、東南アジアなど来日する外国人の出身やエスニックな属性は多様化しました。その目的もさまざまで、出稼ぎに来て数年で帰る人もいれば、留学や就労で中長的に期滞在する人もいます。中には日本人との結婚により定住する人もいます。もっともその多くが期間限定の滞在で、定住を前提に受け入れているケースは少数であったと言えるでしょう。

田村:基本的に日本の在留資格は、留学や就労など目的ごとに認定され、その目的の範囲で日本での在留を認める、というものですからね。でも、在留外国人のうち最も多いのが「永住者」です。日本はいきなり永住ができないだけで、原則として継続10年間日本に在留しているなどの要件を満たして申請すれば、「永住者」の在留資格を取得する制度は用意されています。
例えば、以前は技能実習生として来日すると、3~5年で必ず帰国しなければいけませんでした。しかし今は、一定の専門性や技能を有する外国人を受け入れる「特定技能制度※」ができたため、条件に該当すれば資格を切り替えることができる。「技能実習」や「特定技能」は永住者資格の申請要件である継続10年の年数にはカウントされませんが、「特定技能」から「技術・人文知識・国際業務」など年数がカウントされる資格に変更することができれば、一度も帰国せずに永住者までたどり着ける道が開けたのです。
- ※ 国内人材を確保することが難しい産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度
明石:そういう大きな流れで見ると、近年の日本は、外国人の受け入れを促進している趨勢(すうせい)にありますし、これまでの政策展開をみても、外国人がより広い分野で、より長い期間にわたり働けるように舵を切っています。外国から日本に移動・移住してくる人の少なくとも一部が定住・永住につながることは歴史が証明している事実ですし、今後もその数は不可逆的に増えていくでしょうね。
20~30代と40代以上で、外国人に対する意識にギャップがある
田村:「外国人=そのうち自分の国に帰る人」と思い込んでいる人は決して珍しくないでしょうね。外国人と共生する感覚については世代によって差があるとも考えられています。というのも、約30年前の入管法改正をきっかけに、日系人をはじめとする外国人が増加したことは先にお話ししました。つまり現在20~30代の人たちは、クラスの中に日本語が母国語ではない外国ルーツ(両親またはいずれかが外国出身)の同級生がいたかもしれない世代なんです。彼らにとっては「外国人」という前に「お友だち」ですから、同じ地域社会の一員という意識を自然に持つでしょう。しかし40代以上の世代となると、外国人の友だちもいないばかりか、日常的に接した体験もほとんどないという人も多いんです。
明石:外国人に対する世代間の意識ギャップについては、ある新聞社が行った移民政策に対する意識調査で目にしたことがあります。世代が上になるほど、外国人が日本に住むことに対して反対する人が多かった。確かに、若者の方が、外国ルーツの人々が身の回りにいるという状況への“慣れ”があるのかもしれません。接触・交流体験は、当然ながら対象への意識に大きく作用します。
田村:あとは年齢が上の人ほど、アジアで唯一の経済大国だった「昭和の日本」の意識から脱却できていない可能性があります。例えば「アジアは貧しく、日本は金持ち」「国境を開放したら、外国人が押し寄せて大変なことになる」といったイメージです。
国境を越えて人が移動する要因は大きく2つあり、1つは国から押し出される「プッシュ」要因。生命の危険や賃金の安さといったもので、ウクライナ避難民はこれに当てはまります。もう1つは国に人を惹きつける「プル」要因。生命の安全や賃金の高さのほか、LGBT(※)の人たちにとっては「あの国に行けば受け入れられる」なども該当するでしょう。30年前のアジアでは、日本だけが「プル」で、他は全て「プッシュ」だった。年齢が上がるほど、当時の認識を改める機会がないまま今に至っているのかもしれません。
- ※ レズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛者)、トランスジェンダー(生まれた時から自身の性別に違和感がある)の英語の頭文字を取った性的少数者の総称

明石:日本に暮らす外国人の年齢分布を図で見ると、若い人が多くきれいなピラミッド型をしています。一方、少子高齢化社会である日本は寸胴型の図になります。外国人と交流が生じやすい、よって抵抗感が少ない若い世代は人口が少なく、外国人との交流経験に乏しい人たちが日本の人口のボリュームゾーンであるという構造は多文化共生へのブレーキになり得る、とも言えますね。いずれにしても、世代論で一般化はできませんけれど。ちなみに、田村さんも私も昭和の同世代です。
田村:現在のアジアは著しい経済成長を遂げており、「プッシュ」の時代はすでに終息しています。しかも韓国や中国など、日本以外に「プル」の国が登場して、わざわざ日本に行かなくてもいい状況になっている。一方で人口が減少している日本こそ「プル」の必要性が30年前よりも高まっています。人が来てくれないと、いずれ地域社会が立ちゆかなくなるからです。40代以上の人たちはボリュームゾーンであり、年代的に意思決定者層に多いわけですから、イメージで語らず、現状をきちんと認識した上で外国人との共生を考えてもらうことが重要です。
外国人を受け入れずに地域を持続できるのか
明石:「多文化共生」は、国籍や民族による違いを認めつつ対等な関係を築く、という極めて当たり前の規範です。単なる良識の1つです。しかし、外国人の増加と共にその必要性が今も語られているのは、まだそれが実現されていないから、と逆説的に捉えることができます。
移民の受け入れをすべきかどうか、という政策的な是非やその論拠については、意見が分かれるのは当然でしょう。でも現実問題、日本は実態として外国人の受け入れを促進し、その定着を必ずしも強固に阻んでいないわけです。それなら彼ら彼女らのウェルビーイング(心身と社会的な健康)の向上を早い段階で意識したほうがいい。その潜在能力を引き出す試みは有望な先行投資です。しかし実際は、経済的な境遇や語学の習得、外国籍の若者の進学率や就職率といった社会的格差がおざなりになっている面があります。すでに可視化されている不平等を改める仕組みを用意し、提供していくべきでしょう。
田村:先ほど日本の人口が減っていることに触れましたが、地方の市町村ほど「外から人を受け入れずに今いる人たちだけで地域を持続させていくのは難しい」という強い危機感を持っています。働き手の確保という面もありますが、外国人を含む多様な人たちが生き生きと暮らすことができ、チャンスあふれる地域にしなければ、いま地域にいる日本の若い人も海外の国へ出ていってしまう、ということも考えなくてはいけません。
実際に、外国人人口の増加率が高いのは、北海道や沖縄、九州の市町村です。そもそも人口が少ない市町村が多いですから、200~300人外国人が来ると人口の2~3割を占めるようになるんです。
――都会よりも、地方都市の方が「多文化共生」による社会的インパクトが大きいわけですね。
田村:今までは地方の方が保守的だ、と思われがちでしたが、外国人なしでは産業も回らないので「受け入れに舵を切ってくれ」という要望は、地方都市から上がってきた。その結果、国は外国人との共生に対する予算を設け、交付金という形で自治体に支給を始めています。でも、取り組むか取り組まないかはあくまで自治体の判断。2022年4月現在、多文化共生プランをつくった自治体は約1,700あるうちのまだ140強です。
明石:増加しているといっても、まだ外国人人口は日本全体の2パーセント強ですし、彼らには選挙権もありません。当事者の政治的発言権が限られていて、ホスト社会の日本側にとっても多文化共生を進めるのが義務ではない以上、多文化共生の意味を理解し、地域にとってどうプラスになるのか実感を持って主体的に取り組む自治体と、そうでなく無関心のままの自治体に分かれていくでしょうね。多文化共生の実現を目指すにあたって、自治体や地域社会が持っている経験、ノウハウ、リソースにも違いあります。受け入れないと多文化共生意識が芽生えない、意識が芽生えないと受け入れにちゅうちょするという、ニワトリと卵のジレンマも悩ましいですね。
田村:在留資格により、外国人の社会保障が異なることも自治体の対応を難しくしています。例えば、1990年以降に来日した「日系人」は家族も帯同でき、職業選択の自由もあり、生活保護を受ける権利もある。しかし「技能実習生」は3~5年で原則帰国、生活保護も受けられません。リーマンショックの時に困窮した外国人はその多くが日系人でしたので、就労や生活の支援は日本人と同じように対応できました。
でもいまは外国人が社会的支援を必要としたとき、自治体はそれぞれの在留資格や世帯の状況に応じた対応を考えなくてはなりません。しかも日系人受け入れを決めた1990年の改正入管法施行はあくまでも「例外」としての外国人受入れだったので、日本語教育や医療が必要になった場合の通訳といった問題について、国は何も手を付けずにきました。自治体が独自に施策を提供しなければならず、長年対応に苦慮しています。
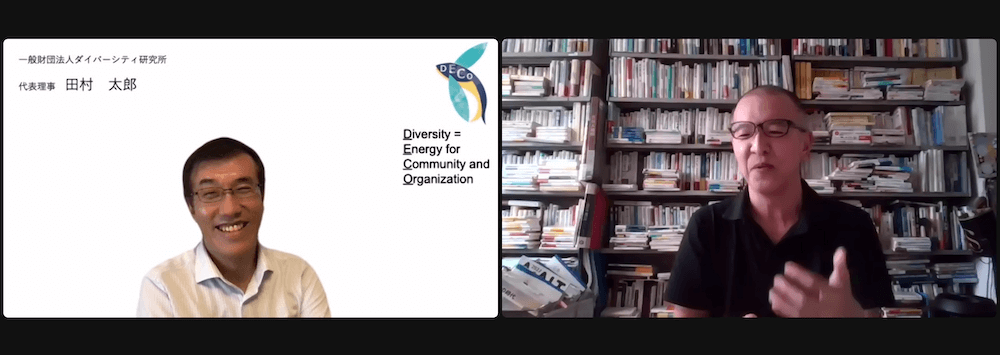
コミュニケーションを支援する人材が足りていない
――地域が主導して多文化共生を進めるために、まず解消しなければいけない課題はどこにあるのでしょうか?
田村:外国人と共に暮らすための地域に必要な人材の不足です。通訳や日本語教師が全く足りていません。100倍の予算を付けたところでいきなり人材が100倍になるわけではないので、まずは人材を育てるところから始めなくてはいけないんです。アメリカやヨーロッパだと、移民2世・3世などの当事者がNPOをつくり、自治体からの委託を受けて移住者のサポートに回るケースが多く、日本も今後そういう人たちを増やしていかなければいけません。
明石:田村さんが指摘するとおり、日本においても、支援されている側がやがて支援者の立場になる流れをつくることは重要です。また、外国からの移住者が経済社会に貢献している姿に、つまり外国ルーツの人たちが日本にいることのプラスの側面に着目していくことが大切です。
私はもう10年以上、外国籍児童のキャリア形成をサポートする活動に従事しています。というのも、日本語習得がままならず、ゆえに進学も困難で、希望どおりの仕事に就けず、場合によっては失業状態から抜け出せず、社会への負担や依存という側面から自分自身に自己肯定感を持てなくなってしまうことが、外国ルーツの人々に起こりうる最悪のシナリオの1つだからです。つまり、プラスを伸ばしつつマイナスを抑える両面作戦が求められます。日本自体が階層社会化して二極化が起こっている今、外国人の中にも豊かな人とそうでない人の格差が生まれています。だからこそホスト社会の公用語の習得などのハンディキャップは早めに取り除くことが、長い目で見て日本社会と本人双方の将来に益することになる。
大学で学生を相手に教えていると、多文化共生に対する興味・関心や志を持っている若者が非常に多いことに驚かされます。ただ、在学中はボランティア活動に勤しんでいても、就職の段階で離れてしまうケースが圧倒的です。外国ルーツの人たちに向けた通訳や教育も、高度な専門性が必要な一方で募集先が多いわけではなく、条件がいつも好ましいわけでもなく、仕事として相対的に選ばれにくい。人材不足の解消は重要な課題であり続けています。

田村:今の外国ルーツの人たちに対する支援の状況は、介護保険制度ができる直前の福祉業界に似ていると感じます。当時、介護の多くは家庭やボランティアが担っていましたが、「入浴介助」や「食事のサポート」といった内容に共通の定義をつけてマニュアル化し、誰でも同じクオリティのサービスを提供できるようにしました。それにより、介護は職業として確立されていったのはご存じのとおりです。
ケアマネージャーが介護プランを作成するのと同様に、外国人の世帯を面接して、この家族には何時間分の通訳と何時間分の日本語教育が必要、この分野の学習ならあの先生がいい、などと見立てをするコーディネーターを設け、外国人が自分で必要な支援を選んで利用できるようにすれば、自治体も予算も生かしやすくなりますし、日本語教育の質も上げられる。これまで日本では、通訳や日本語教師といったコミュニケーションを支援する人材をきちんと評価してきませんでしたが、今後はそこを改善していかなければ。
明石:日本語は、日本以外では使われない非グローバル言語です。日本で生きていくには必須でも、習得することの機会費用が大きい言語です。それを高いモチベーションをもって学んでもらうには、定住や就職、そしてキャリアアップといった長期目標が視野に入ってこないと難しいのではないでしょうか。しかも前にも言及したとおり、日本語学習等を含む外国ルーツの人々への支援が誰にとっても魅力的な、いわば人気業種・産業として成り立つだけの条件が、まだ十分に揃っていないように思えます。自治体に任せきりにせず、政府も今後さらに前向きに取り組んでいってほしいところです。地域主導の多文化共生においては、ボランティアに頼る必要もありますが、ボランティアだけに頼ることはその持続可能性を損ないます。
――私たち一人一人が、日本で多文化共生が進まない問題に対して起こせるアクションについて、アドバイスをいただけますか?
田村:私は神戸が地元ですが、第一次大戦の前後にロシアなどから避難してきた人を受け入れた歴史があります。現在のウクライナ避難民は、強烈なプッシュ要因が起きたため日本にやってきました。これからも世界各地で、同様のことが起こるかもしれません。そのとき「それは大変ですね、うちに来てください」と言えるか、受け入れた人たちと共に寛容な地域をつくれるかが今試されていると思います。そのためにも世界を俯瞰して、外国人を受け入れるとはどういうことか、今何が起きているのか現実を見る。すでに日本にはたくさん外国人がいますから、そういう人たちと出会う場をつくるところから始めてみるのもいいですね。
明石:多文化共生は多文化を「強制」することではないんです。ただ、人を見た目で差別しないとか、外国ルーツに偏見を持たないとか、ごく普通のことを守れば良いものと考えます。小・中学生のうちからさまざまな文化的出自の人とコミュニケーションを持つ機会を得ることも有益でしょうが、成人前にそういう関りを欠いたら無理という話でも全くありません。
政策的な舵取りや社会の制度設計にとっては、「国家」といった単位は依然として外れにくい要素なのでしょう。しかし外国出身者が増える現代において私たち一人一人が日々を健やかに暮らす上では、「国民」と「外国人」といった分類や区別を意識するよりも、「同じ社会の構成員」という認識を持つのが自然なのではないでしょうか。住民同士で特別にかまえることはありません。困ったときはお互いさま。多文化共生のハードルは多くの人が思うほど高くはないのです。
〈プロフィール〉
明石純一(あかし・じゅんいち)
神奈川県横須賀市生まれ。筑波大学大学院国際政治経済学研究科博士課程修了。博士(国際政治経済学)。著作に『入国管理政策』(単著、ナカニシヤ出版)、『人の国際移動は管理されうるのか』(単著、ミネルヴァ書房)、『移住労働と世界的経済危機』(編著、明石書店)、『「グローバル人材」をめぐる政策と現実』(共編著、明石書店)、『変容する国際移住のリアリティ』(共編著、ハーベスト社)などがある。内閣官房第三国定住による難民の受入れ事業の対象の拡大等に係る検討会有識者メンバー、法務省入国管理政策懇談会委員、収容・送還に関する専門部会委員などを歴任。難民審査参与員を務める。
筑波大学 明石研究室(外部リンク)
田村太郎(たむら・たろう)
兵庫県伊丹市生まれ。阪神・淡路大震災直後に外国人被災者へ情報を提供する「外国人地震情報センター」の設立に参加。1995年に設立された「多文化共生センター」では、事務局長を経て代表に就任。自治体国際化協会参事などを経て2007年に「ダイバーシティ研究所」を設立し、多様性に配慮した地域社会の仕組みづくりに取り組んでいる。総務省「地域における多文化共生の推進に関する研究会」構成員、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議「外国人との共生社会の実現のための有識者会議」構成員、復興庁復興推進参与なども務める。共著に『多文化共生キーワード事典』(明石書店)、『つないでささえる。災害への新たな取り組み』(亜紀書房)などがある。
一般財団法人ダイバーシティ研究所 公式サイト(外部リンク)
- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。