未来のために何ができる?が見つかるメディア
毎月、投票で寄付する団体を決定。「一般社団法人 新しい贈与論」がつくった新しい寄付のかたち

- 「新しい贈与論」は、月に1度みんなで話し合い、投票で寄付先を決定するコミュニティー
- 投票1位の団体に全額を寄付。多くの人たちにとって非営利の世界を知ることは新鮮
- 寄付文化醸成に必要なのは、「恩返し」の気持ちをうまく寄付につなげる仕組み
取材:日本財団ジャーナル編集部
2019年に設立された「一般社団法人 新しい贈与論」(外部リンク)は、寄付や贈与について学び、実践してゆく月会費制のコミュニティーです。月に1度、「どこに寄付するか」「どのような寄付がより良いのか」をメンバー同士で議論した上で、投票で決定した1つの団体・企業・個人に、集まった会費を寄付するというユニークな活動をしています。
一般的に寄付というと「ハードルの高い行為」と捉えられ、「どこに寄付すればいいのか分からない」「寄付をするくらいなら自分のことに使いたい」と考える人もいるのかもしれません。
- ※ こちらの記事も参考に:世界人助け指数ワースト2位。なぜ日本は寄付文化が広まらない?(別タブで開く)
今回、「新しい贈与論」で代表理事を務める桂大介(かつら・だいすけ)さんに、「新しい贈与論」の活動内容や、メンバーはなぜ寄付を行うのか、また寄付文化を広めていくためにできることについてお聞きしました。

お土産やプレゼントは贈与であり、寄付の親戚
――桂さんはいつから寄付に興味を持ち始めたのでしょうか。
桂さん(以下、敬称略):大学生の頃ですね。サークルとして環境問題を扱うNPOに参加したのがきっかけです。叔父が日本赤十字社で働いていたので、その影響もあるかもしれません。
ただ、大学生の時の寄付は少額で、株式会社リブセンス(※)を創業する際に、非営利の世界からは一旦離れました。
本格的に行動し始めたのは、リブセンスが上場した後です。周りの起業家たちは、みんなスタートアップ企業への投資をしていましたが、僕はそういったお金を中心とした経済には限界があると考えていて、そうじゃないところに資金を回していくことが自分の役割だと思っていたんです。
それから本格的に寄付を行うようになったのですが、一人だと寄付先を考えるのにも限界があると思って、継続的な寄付活動を行える場所として「新しい贈与論」を設立しました。
- ※ 「マッハバイト」「転職会議」などを運営するインターネットメディア運営事業会社
――「新しい贈与論」の活動内容について教えてください。
桂:寄付や贈与について学び、実践していく月会費制のコミュニティーです。2024年8月時点で会員数は90人ぐらいで、月に1回の割合でみんなで話し合い、投票で寄付先を選び、寄付することが活動のメインです。
他にもチャット上での雑談や、勉強会、交流会なども行っています。
――なぜ「新しい寄付論」ではなく、「新しい贈与論」としたのですか?
桂:対外的に行っているのは寄付だけなのですが、普段の雑談や勉強会では、無償で相手に財産を与える「贈与(※1)」についてよく話しているからです。
贈与というと堅苦しく聞こえるかもしれませんが、お土産やプレゼント、ご祝儀、ボランティア活動も贈与と捉えています。私は寄付というのは贈与の親戚のようなものだと思っているんです。
また、「贈与論」という学問があるんですよ。これは1920年代にヨーロッパで生まれた、比較的新しい学問なのですが、日本で語っているのはアカデミックの方々くらいしかいないので、そことNPOやファンドレイザー(※2)の方々がつながると面白いんじゃないかとも思っています。
- ※ 1.寄付は「公共事業や社寺などに、金品を贈ること」。贈与は「金品を人に贈ること」「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立する契約」を指す。参考:コトバンク(外部リンク)
- ※ 2.NPOなどの非営利団体において、寄付金を集める専門の職業
――「欧米に比べると、日本は寄付が根付いていない」とよくいわれます。桂さんはその理由についてどう考えていますか。
桂:まず、NPOという枠組みは欧米から始まったものなので、単純に日本はスタートで出遅れているというのが1つです。
あとは、見知らぬ人、特に貧しい人に何か施しをするチャリティー文化自体が、キリスト教から生まれたものだと思っています。仏教でもそういうものはありましたが、キリスト教のチャリティほど大規模にならなかった。
日本が古来より育んできたのは相互扶助で、見知らぬ人を助けるチャリティー文化は少ないですよね。

――身近な人同士で助け合う文化はあったけど、見知らぬ人を助ける文化は薄かった、ということでしょうか。
桂:そうです。日本では、まずは家族で助け合うことが基本ですよね。生活保護についても、「家族が面倒を見るべき」という声が根強くあります。
家族や仲間で助け合うという意識が強いからこそ、見知らぬ人を助けるという意識が根付きにくかったと考えています。また「他人に助けを求めることが苦手だ」という人も多い気がしますね。
寄付を考えることは新鮮。「心の切り替えになる」と語る人もいる
――「新しい贈与論」には、どういった人が集まっているのでしょうか。
桂:圧倒的に多いのは会社員で、寄付の初心者と上級者が多いですね。
初心者とは、「なんとなく寄付に興味があったけど、何をすればいいか分からなくて、ここなら寄付できるかも……」という人。
上級者とは、NPOを研究している先生や、NPO界隈で有名な方です。そういった人はメジャーなNPOを多く知っているので、「『新しい贈与論』だと、全然知らない団体が挙がってくるから面白い」ということで参加されているようです。
すでに支援したい団体が決まっている人は、自ら寄付をしているので、「新しい贈与論」には参加しないんだと思います。
――寄付先はどのように決めているのでしょうか。
桂:毎月1つのテーマを設けています。「草」「記憶」「島」「悪」など、一見寄付とは関係なさそうなテーマをあえて選んでいます。
次に、2人1組の推薦人を3組作ります。推薦人はテーマをもとに2人で話し合い、推薦する団体や個人を探して1つに決め、約1,000文字の推薦文を書いてもらいます。
3つの推薦文が集まり次第、公開して、それに対してみんなで投票をするというルールです。
票が分かれたからといって分配せず、1位の団体に全額寄付するということにしています。
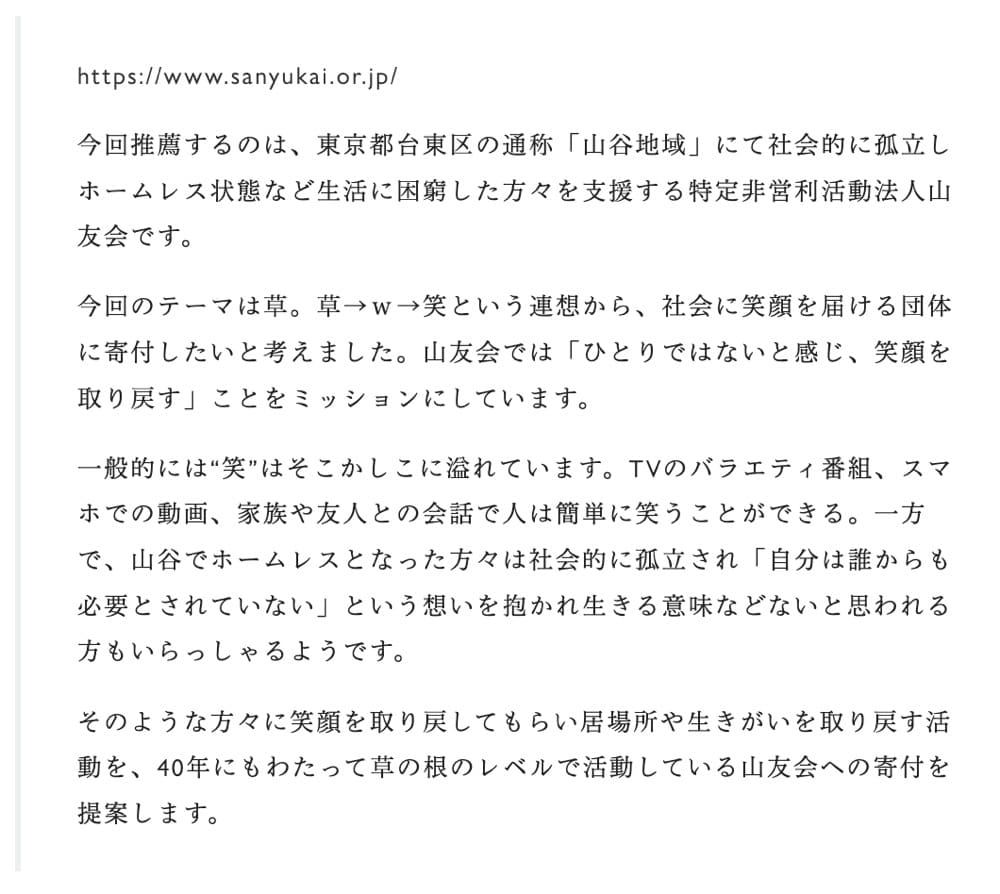
――メンバーの皆さんは自分が投票していない団体に寄付されることに対して、どう思っているんでしょうか。
桂:それも含めて楽しんでいると思います。
皆さん社会人なので、やはり普段は経済合理性の中で生きているんですよね。それとは関係ない部分で議論をして、さまざまな活動をしている団体を知り、考えるということは新鮮なようです。
「1カ月に1度、寄付について考えることが心の切り替えになる」という方もいらっしゃいました。
――寄付をした団体からのリアクションはいかがでしょうか。
桂:メンバーのコメントと共に寄付をしているので、とても喜ばれます。「新しい贈与論」では、小さなNPOや、個人に寄付を送ることもあるので「日の当たらない活動だと思っていたので、報われた気がします。勇気をもらえました」のような声をいただくこともありました。
「恩返し」の気持ちを、うまく寄付につなげる仕組みを広めたい
――日本において寄付文化を広めるためには、何が必要でしょうか。
桂:1つ考えているのは、日本の相互扶助文化とチャリティーとの間をつなぐことですね。具体的にはコミュニティー財団(※)のような地域の基金です。
コロナ禍では、東京都や大阪府がかなりの寄付を集めました。地方行政への寄付って、今でもすごく多いんですよ。「とある町のおじいちゃんが、自治体に1億円寄付した」みたいなニュースは、度々目にします。そういう意味でいうと、コミュニティー財団のような役割を、地方行政が担っているともいえます。
お世話になった地域への恩返しのような気持ちは根強いと思うので、それをうまく寄付やチャリティーにつなげる仕組みがあればいいと思います。
- ※ 地域社会に対する知識を持ち、公共的関心を代表する者として選ばれた市民により構成される役員会が運営する公共的な社会貢献機関。個人、企業、団体、その他から寄付・遺贈された多数の個別基金を管理する。参考:コミュニティ財団とは(定義など) – 全国コミュニティ財団協会(外部リンク)
――寄付文化を醸成していくために、私たち一人一人ができるのはどんなことでしょうか。
桂:寄付をしたことがない人も、贈与は必ずしています。バレンタインやお年玉、旅行のお土産、知人の家を訪問するときに持っていくお菓子とかですね。
自分以外の人、つまり他人に何かを贈るという意味では寄付も同じで、そう考えると、寄付は決してハードルの高い行為ではなく、お土産を渡す感覚でできるんじゃないかというふうに思っています。
――会社の同僚にお土産を渡すときはリターンを求めていないはずで、それと寄付も同じじゃないか、ということですね。
桂:そうですね。ですから、「バースデードネーション」というのが、日本の文化にぴったりだと思うんですよ。
バースデードネーションとは、誕生日などのおめでたい日にプレゼントの代わりに、その人が支援している団体への寄付をお願いするという仕組みのことです。「私へのプレゼントはいらないから、そのお金は○○という団体に寄付してね」といった感じです。

桂:相互扶助的な贈与からチャリティーにつなぐ架け橋のようなもので、日本人にはうまくはまるのではないかと思っています。
本人にお祝いの気持ちが伝えられ、団体にも寄付できる仕組みがあれば、日本における寄付文化が盛り上がっていくと思います。
編集後記
「新しい贈与論」に参加すると、寄付を求めている団体を自発的に調べることになるので、世の中にある社会課題もたくさん知ることになります。
その中で、自分は何に興味があって、何に興味がないのかを知り、さらには自分を掘り下げることにもつながると感じました。
〈プロフィール〉
桂大介(かつら・だいすけ)
1985年、京都府生まれ。早稲田大学在学中の2006年に、同大学で知り合った村上太一さんとIT企業「リブセンス」を共同創業。2012年10月には、当時史上最年少での東証一部上場を果たす。2019年に一般社団法人「新しい贈与論」を設立し、代表理事に就任。現在は「新しい贈与論」をはじめとした寄付活動を通じて、贈与や寄付の在り方を見直している。
新しい贈与論 公式サイト(外部リンク)
- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。













