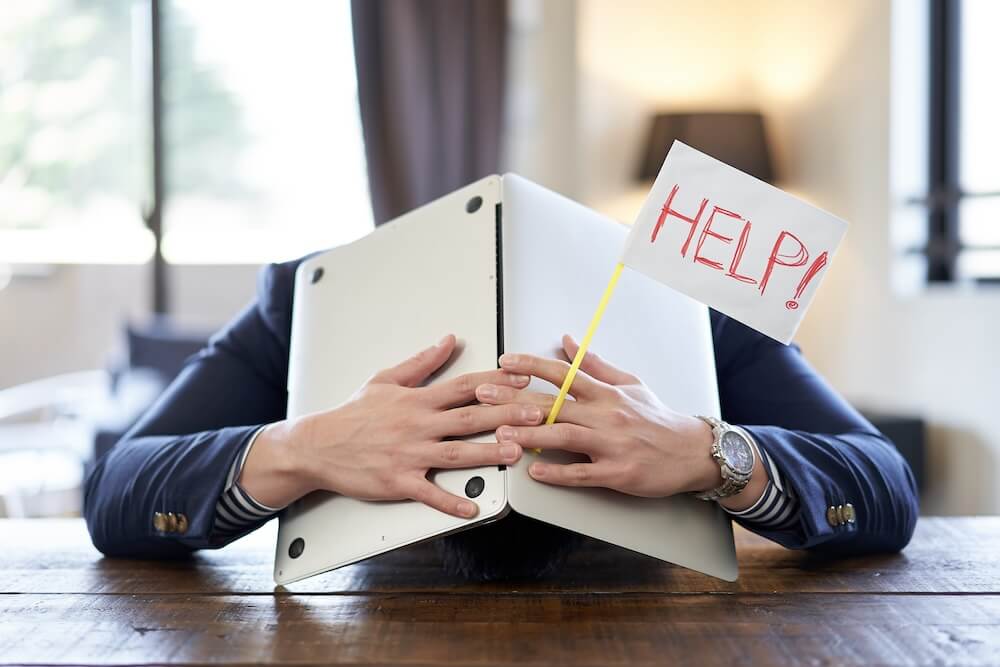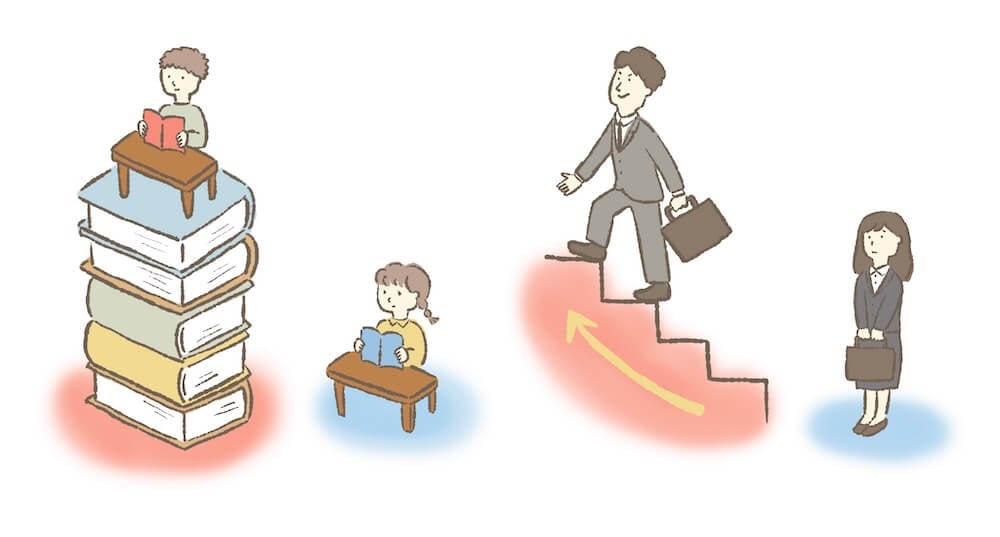未来のために何ができる?が見つかるメディア
なぜ男性は「女性優遇」に敏感になるのか? 社会学者・澁谷知美さん、文筆家・清田隆之さんが語るジェンダー問題

- 女性への支援策に対して、「女性優遇だ」と男性が反応する背景には、社会の根底に、「無意識の思い込み」がある
- 男性がジェンダーを自分事化するには、自分の気持ちや弱さをさらけ出せるような安全な場所や信頼できる人が必要
- 性別による先入観にとらわれず、「みんなが一人の人間」という目線で考えていくことが大切
取材:日本財団ジャーナル編集部
国際機関・世界経済フォーラム(WEF)が発表した2024年のジェンダーギャップ指数で、日本は146カ国中118位(※1)と先進7カ国(※2)中最下位でした。この現状を変えようと、日本では女性の政治参画ほかさまざまな分野で女性活躍推進の取り組みが進められています。
- ※ 1.参考:World Economic Forum「Global Gender Gap Report 2024」(外部リンク/PDF)
- ※ 2.カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国の7カ国を指す
例えば、政治分野では「クオータ制」の導入が議論されています。これは、国会議員や地方議会議員の候補者数を男女同数にするといった、一定の「割り当て」を設けることで、女性の政治参画を増やそうという施策です。
また、企業においては、管理職に占める女性の割合を増やすための数値目標を設定したり、女性リーダー育成のための研修を実施したりする動きが広がっています。
しかし、こうした取り組みに対して「女性だけを優遇するのは逆差別だ」「能力本位の評価が大切なのに、数合わせのために女性を登用するのはおかしい」といった声もあります。なぜ、一部の男性はこうした施策に強く反応するのでしょうか。
さらに彼らの主張から、ある共通の興味深い声が聞こえてきます。
「努力や実力が正当に評価されない」
「なぜ男性は常に加害者扱いされるのか」
「男だって生きづらさを抱えているのに……」
一見、個別の不満に見えるこれらの声を理解するために注目したいのが、男性が抱えるプレッシャーや苦しさの根底にある「男らしさ」という価値観です。男は「仕事」、女は「家庭」という時代が終わり、女性も男性と同じように活躍するようになった今、これまで当たり前とされてきた男性の役割や立ち位置が大きく変化しています。
この変化は、男性たちの内面にどのような影響を与えているのでしょうか。
男性の性の歴史を研究する社会学者の澁谷知美(しぶや・ともみ)さんと、「男らしさ」をテーマに多くの一般男性へのインタビューを重ねてきた文筆家の清田隆之(きよた・たかゆき)さん。お二人の対談を通じて、「男らしさ」という価値観を生む背景や「男はこうあるべき」といったジェンダーバイアスがもたらす社会への影響に迫ります。
男性たちから「女性ばかりが優遇される」という感情が生まれる背景とは?
――世の中で女性活躍推進の取り組みが進む一方で、「逆差別だ」という反応が必ずと言っていいほど起こります。こういった反応の背景にはどういう構造や心理があるとお考えでしょうか。
澁谷さん(以下、敬称略):私の専門は、社会学的観点からのジェンダー研究と男性のセクシュアリティの研究ですが、「逆差別」という反応の背後には、「男だって苦しいのに、なぜ女性だけ」という感情のほかに、「男性の方が女性よりも有能である」という、根拠のない思い込みがあると見ています。
例えば、管理職といった指導的立場にいる人の30パーセントを女性にしようという政府目標があります。これに対して、「『女性だから』という理由で管理職の30パーセントを女性にするのは男性への逆差別だ」という反応がよく見られます。しかし、「『男性だから』という理由で管理職の多くを男性が占めているのは女性への差別だ」という声はほとんど上がりません。
そこにあるのは、「男性のほうが女性よりも有能である。だから管理職には男性が多い」という根拠のない思い込みです。管理職の多くが男性なのは、現状の働き方が、ケア責任がなく、長時間労働が可能な男性に合わせてつくられているからです。そのような仕組みの下で、家事や育児などのケア責任のある女性が会社に時間を割くことができず、管理職になれないのは当然です。
また、シカゴ大学教授の山口一男さんによる日本企業を対象とした研究では、大卒女性よりも高卒男性のほうが課長職以上の管理職になりやすいことが分かっています。学歴という「業績」よりも男性か女性かという「生まれ」のほうが重視されているということであり、そのような社会は業績主義の社会ではない、と指摘されています。

清田さん(以下、敬称略):一般男性に取材をしたり、SNSでのジェンダー議論を眺めたりしていると、「能力で選抜された結果、男性が残ったのであって、性別は関係ない」という主張を確かによく見聞きします。
でも、例えば女子学生の方が男子学生より成績が優秀であることは各国の専門機関の調査で明らかになっているわけで、もし本当に能力によって選抜されているならば、社会のさまざまな分野でもっと女性が重要なポストを占めていてもおかしくないはずですよね。
女性を登用したほうがビジネスでも良い結果が出るというデータは他にも揃っている。でもなぜかそれを認めようとない。それはある種の「信仰」みたいなもので、澁谷さんの言う「男だって苦しいのに、なぜ女性だけ」という感情が影響しているように僕も感じています。

――そうした男性たちの感情や反応の背景には、どのような構造があるのでしょうか。
澁谷:男性同士の関係性を考える上で重要な「ホモソーシャル」という概念があります。これは、性愛を除いた男性同士の連帯や絆という意味です。「ホモソーシャル」にはメンバーになれる男性となれない男性がいて、なれるのは妻や恋人がいる男性。彼らは、そうでない男性に対して優越感を持っています。
そのほかにも、仕事ができるか否か、勉強ができるか否か、スポーツができるか否かなど、さまざまな基準で、男性同士で格付けをしあっています。そして、「上」の立場の男性は「下」の立場の男性に対して優越感を抱く。そうした構図が、意識するしないにかかわらず、あちこちに存在しているのです。
清田:確かに、会社などの組織に限らず、日常の本当に些細な場面においても男性たちは序列意識にとらわれているなと感じます。自分自身も他人事ではなく、例えば中高の男子校時代を例にお話しすると、勉強ができるとか、運動ができるとか、おしゃれであるとか、それぞれが持っている何らかの条件によって、クラスの中の目に見えない序列が決まっていくところがありました。
集団の中であらかたポジションやキャラクターが決まれば、それに則った形で表面上は円滑なコミュニケーションがなされていく。けれどもよく見ていくと、実は「上」にいる人にとって都合のいい空気やルールに「下」が合わせるという構図になっていたりする。
澁谷:会社の会議などでもそういう力学は見られますよね。組織の中間層の男性たちが自分の意見を言わず、社長や上長など「上」の人の意見に合わせて、無難な発言に終始する、といった具合です。
――そのような序列意識は、女性同士の関係でも存在するのでしょうか。
澁谷:清田さんの言った「見えない序列」があるのは女性も同じです。ただ、その存在は明確に意識されていて、瀧波(たきなみ)ユカリさんと犬山紙子(いぬやま・かみこ)さんの『女は笑顔で殴りあう』や、水島広子(みずしま・ひろこ)さんの『女子の人間関係』といった本でも描かれています。ですが、男性間の序列に関しては、そこまで意識されているようには見えません。
日常の中に、一方的なからかいやいじりなど、序列を感じさせるコミュニケーションがたくさんあるのに、それらは「ただの冗談」「ふざけているだけ」などと言い換えられ、序列が見えなくされてしまっている。
清田:バラエティ番組やYouTubeの動画でも、男性同士がからかい合ったり、いじり合ったりするのが「面白い」とされていますしね。
澁谷:「ホモソーシャル」では、妻や恋人がいる人、性経験がある男性が「上」の立場として、そうではない男性のことをバカにしたり、からかったりするという現象が見られます。はたから見ていても嫌な気分になります。
清田:序列の中で格下として扱われ、密かに傷ついている男性はたくさんいると思うんです。ただ、序列があることを認める=「自分は格下だ」という事実も認めなくてはいけない。だから「俺たちはふざけあっているだけだ」と思い込もうとする。加えて、「弱音を吐いたり、感情的になったりするのは男らしくない」といった世の中の風潮が、つらい、苦しい、寂しいといった感情を認めるのを阻んでしまう。
こういった流れが、自分ができるだけ格下にならないよう、少しでも優位な立場になろうとする男性間での力関係をつくりだしているような気がしてなりません。
澁谷:「感情的になったりするのは男らしくない」という思考と、ジェンダー平等推進を「逆差別」と思ってしまう感情とには、おそらく関係があります。ジェンダー平等推進によって、自分の立場や既得権益が脅かされるのでは、と不安を感じる男性は少なくありません。ですが、不安という感情を見せるのは「男らしくない」。かつ、序列の中で不利に働いてしまう。ですから、「不安だ」というかわりに「逆差別」という言い方を選んでいるのではないでしょうか。

幼い頃から刷り込まれる「男らしさ」という価値観
――序列意識に代表される男性ならではともいわれる振る舞いは、どのように身についていくのでしょうか。
清田:うちには双子の女の子がいて、今は保育園の4歳児クラスに通っているのですが、「男の子たちはロボットや電車が好きだよね」「プリンセスは女の子だよね」みたいな話をよくしていて、その段階からすでにジェンダーの影響を感じます。いくら家で気をつけていても、日常のあらゆる場面で性別による役割やイメージが価値観の中に入り込んできてしまう。
例えば、テレビを見れば司会は中高年の男性でサポートは女性のアナウンサーという構図が多かったり、駅にあるポスターも料理をしているのは女性ばかりだったり……。
そういった光景を目の当たりにしていれば、子どもたちも「男と女ってそういうものなんだろうな」という感覚を持ってしまうだろうし、それを何万時間も重ねていけば、ジェンダーにまつわる感覚や価値観が分厚い地層のように形成されていくはずで、どうやっても社会の影響を受けてしまうよなって思います。
澁谷:昔に比べれば「男女平等」「分け隔てなく育てましょう」という意識は高まっているはずなのに、実際にはまだまだ「男のくせに泣くな」「男なら○○しろ」といった言葉が残っています。
大学生に聞くと、2000年代はじめ生まれの彼らですら「親や教師から言われた」と話します。
清田:昔は「おしゃれにかまける男は男らしくない」だったものが、現在では「身だしなみを整えない男はダサい」という風潮が広がるなど、「男らしさの規範」自体にも変化や振れ幅があります。
ただ、内容が変わっても「男らしくないことを責める」構図自体は変わっていない。そこだけはずっと社会に温存されているような気がするんですよね。
──ということは、「男らしくない」と序列が下がって劣位に置かれるため、弱みを見せまいと本音や感情の表出を抑制する、という力学も変わりづらいということになりますね。
澁谷:おっしゃるとおりです。男性間の序列によって傷つけられている者が、「その序列は嫌だ、苦しい」と声を上げればますます傷つけられるので、結局、黙るしかなくなる。しかし、黙っているから、苦しみが癒やされることもない。そして、「男だってつらいのにケアされない。女ばっかりずるい」という発想に至る。
清田:根深い問題だと思います。取材を通じて、男性特有の「状況判断」みたいなものも感じるんです。例えば、電車の中に空き缶が転がっていて、目障りだし危ないんだけど、マジマジ見てしまったり、自分の足元に転がってきたりすると、自分がどうにかしなくてはいけない感じになるから、スッと気配を消して気づかないふりをする……みたいなことってあるじゃないですか。
ああいう感じが日常や対人関係のあらゆる場面でも習慣化されていて、例えば「ここで手を挙げたら、責任を押し付けられるかも……」「この場面で自分の意見を言ったら、反発を買うかも……」といったような、リスクを察知するアンテナが常に働いていて、序列の中で損をしないよう行動しているような印象があります。
澁谷:ある種の「生存戦略」とも表現できる行動ですね。
その戦略だと、集団では生き残っていけるかもしれないけれど、本来あった自分の感情は死にますよね。「本当は言いたかったこと」を言えなかった不満が、はけ口を求めて、自分より「下」の男性への、あるいは女性への、暴力や差別として発露するかもしれない。
――こうした行動原理は、社会にどのような影響を与えるとお考えでしょうか。
清田:例えば、会社で素晴らしい企画が現場から上がってきたのに、現場を知らない上層部の一存で意味の分からない方向に変更になり、誰も異を唱えられないまま結局不本意な形に仕上がってしまう。こういった経験をしたことがある人は多いのではないでしょうか。
このような現象は、男性集団の序列意識やリスク回避が生む悪影響を端的に表しているように思います。
澁谷:組織の硬直化、ひいては経済の停滞といったかたちでも影響が出ていると思います。海外の投資家たちが日本企業に「管理職の女性割合を30パーセントにしろ」「男女の賃金格差を小さくしろ」と求めるのは、単なる「多様性の推進」ではありません。男女問わず、能力のある人材を適切に登用し、組織の成長につなげようという実利的な判断なんです。
実際、世界経済フォーラムの統計でも、ジェンダー平等と経済発展には相関関係が示されています。
清田:組織の中で「兵隊」のように扱われたり、雑に扱われたりする経験を重ね、そのことで傷つけられてきた男性は多いと思うんです。でもなぜか、その痛みや不満を目の前の権力構造に向けるのではなく、外から序列を揺るがすように見える「女性活躍」への反発という形で表出してしまう……。
澁谷:序列の中で不利になることを避けようとする習慣が、男性たちが本来持っているはずの可能性、例えば自分の意見を自由に表明したり、新しいアイデアを提案したり、あるいは職場の在り方そのものを変えていったりする動きを制限してしまっています。
結果として、個人としても組織としても成長の機会を逃してしまう不幸な状況だと言えますね。
変化の可能性と、そこにある不安
――こうした状況を変えていく可能性はあるのでしょうか。
澁谷:可能性は確実にあります。私は大学で性暴力についての講義をしているのですが、以前、女性被害者の話から講義を始めたとき、男子学生たちが興味なさげに机に突っ伏してしまったんですね。
そこで、男性被害者の話から始めるようにしたところ、関心を持って聞くようになりました。兵士などの屈強な男性でも性被害に遭うことを話し、誰でも性被害に遭う可能性があることを具体的に示していきました。すると、女性の被害についても共感を持って耳を傾けるようになりました。
つまり、自分事として捉えられる入り口があれば、変化は十分に起こり得るんです。

清田:僕も可能性はあるんじゃないかと感じています。
ここ最近、男性同士の「おしゃべり会」というものを定期的に開催しているのですが、みんなで話し手の語りにじっくり耳を傾けるワークを通じ、「こんなふうに自分の話を聞いてもらった経験は初めて」という感想を語ってくれる男性がとても多い。おそらく、弱みを見せられないコミュニケーションが当たり前になっている影響で、不安や悩み、嫉妬といった感情を受け止めてくれる人間関係を築けている人が少ないからだと思うんです。
たとえ普段強がっていたとしても、実は誰かに話を聞いてほしいという思いを持っている男性は少なくない。そういう「男らしくない部分」を安全に話せる場所が増えれば、自分がどういう状態にはまり込んでいるのか、発見につながっていくように思います。

――男性たちの変化を促すために、どういうアプローチをするのが有効だと思われますか?
澁谷:まずは、「女性差別なんてない」という男性には、客観的データを示しながら「ありますよ」と示していくことです。ですが、それでもなお認められない男性には、「自分は差別者として糾弾されるのではないか」という恐怖心があるのかもしれません。その恐怖心を解除することも、男性たちの変化を促す手段の1つかと……。
具体的には、「差別は、意図せずして誰でもしてしまうもの」ということを共通認識にすることです。「誰でも間違うし、間違ったら素直に認めて、二度と繰り返さないようにすればよい」という考え方を広める必要があると思っています。
清田:確かに「弱い部分を見せても安心」と思える場所があって初めて、自分の中にある「男らしさ」の影響に目を向けられるようになる。「おしゃべり会」でも、だいたい最初は「妻にこんなことを言われた」といったグチから始まり、男性同士で「めっちゃ分かります!」と共感し合うことから会話が広がっていく感じがある。
「男性の話を否定せず聞いてあげましょう」って、どことなく男性を甘やかしているように感じられるかもしれませんが……そうやってある種の“被害者性”を安心して吐露するプロセスを通じ、抱えていた傷に手当てがなされ、ようやく自分の過ちや加害者性に目を向けたり、コミュニケーションの在り方や関係性を内省的に問い直したりする余地が生まれてくるんだと思います。
男、女ではなく、私たちはみんな「一人の人間」
――「男らしさ」という価値観から自由になってみたい、と感じた男性たちができるアクションについて、アドバイスをいただけますか。
澁谷:「自分は『男らしさ』にとらわれている」と意識した上で、自身の行動をモニタリングしてみることをおすすめします。自分は、男性間の序列の中でこういう身の振り方をしている、ここで弱みを隠したくなった、など「男らしい」行動に気づくことができるはず。そんな「男らしい」行動をちょっとずつ変えていけば、結果的に「男らしさ」から自由になれます。
また、意識的に「男らしくない」行動をしてみることも提案したいです。「お店で接客してくれる人に対して、横柄な態度を取らず、丁寧に接してみる」とか、「飲み会で、自分ばかり話すのではなく、聞き役に徹してみる」とか……。周囲からよい反応があったりして、「『男らしさ』なんて捨ててしまったほうが楽しい」と思えるかもしれません。
清田:僕からは、自分の気持ちを安全に吐き出せる人や場所を持つことをおすすめしたいです。「おしゃべり会」に来てくださるのも大歓迎ですし、信頼できる友人や仲間をつくり、その人たちと交流するのも大切だと思います。
また、「男らしさ」に関する本を読むことで、自分の経験を言語化するヒントを得ることもできます。そういった経験の積み重ねが、自己理解を深めるきっかけになっていくのではないでしょうか。
――男性のみならず、社会にいる私たち一人一人にはどんなことができるでしょうか。
澁谷:社会には、「男だったら、弱音を吐かずに黙って言われたことをやれ」といった固定観念を押し付ける風潮がまだまだ残っています。そういった「男だから」とか「女だから」という価値観に出合ったら「本当にそうなのか?」と疑ってもらいたいですね。
よく「男らしさ」の特性として「リーダーシップ」「行動力」などが上げられますが、それらは本来「人」としてプラスの特性であって、わざわざ「男」らしさと結びつける必要はないはず。
性別による先入観にとらわれず、「みんなが一人の人間」という目線で考えていくことが大切だと思います。
清田:ほんとそうですよね。「男女どちらが優遇されているか」という議論よりも、「社会の一人一人が暮らしやすい社会をつくるための課題は何か」と考えていけば、自ずと性別にかかわらず自分らしく生きられる社会に続いていくはずで……。あとは、できることから等身大のアクションを起こしていくのも大事だと思います。
例えば、男性の長時間労働の是正を求める署名活動に参加したり、ジェンダー平等を推進する政党や候補者に投票したり……。一人一人の小さな行動が集まれば、やがて大きな変化につながっていくはずです。

編集後記
国や企業で推し進められる女性への支援策に対し、一部の男性から批判の声が上がる構造について探るべく、澁谷さんと清田さんにお話を伺いました。
「日本ではいまだに男女不平等が続いている」「いや、最近は女性ばかりが優遇される。逆差別だ」といった論争は、ある種のテンプレートとなってSNS上を賑わせています。そこに「男性が優遇されているというが、家では夫の立場が一番弱く、妻や娘によく怒られている」といった個人の観点も交じり合い、対話が続かない……といった場面も見られます。
そういったSNSの情報を見て、「ジェンダーやフェミニズムは関わると面倒」と、本質を見ないまま敬遠されてしまう傾向すらあります。
ですが、ジェンダーのもたらす課題から目を逸らさず、誰もが自分事として捉えていくことが多様な価値観の共有につながると思います。
澁谷さんがおっしゃるように「性別による先入観にとらわれず、『みんなが一人の人間』という目線で考えていくことが大切」だと感じました。
また、「『男女どちらが優遇されているか』という議論よりも、『社会の一人一人が暮らしやすい社会をつくるための課題は何か』と考えていけば、自ずと性別にかかわらず自分らしく生きられる社会に続いていく」という清田さんの言葉も深く心に響きました。
撮影:永西永実
〈プロフィール〉
澁谷知美(しぶや・ともみ)
東京経済大学全学共通教育センター教授。博士(教育学・東京大学)。東京大学大学院教育研究科で教育社会学を専攻。ジェンダー及び男性のセクシュアリティの歴史を研究。著書に「日本の童貞」(河出文庫)、「平成オトコ塾――悩める男子のための全6章」、「日本の包茎――男の体の200年史」(共に筑摩書房)、「立身出世と下半身――男子学生の性的身体の管理の歴史」(洛北出版)など。また本対談に登場した清田隆之さんとの共著「どうして男はそうなんだろうか会議――いろいろ語り合って見えてきた『これからの男』のこと」(筑摩書房)がある。
澁谷知美 公式サイト(外部リンク)
清田隆之(きよた・たかゆき)
文筆業。恋バナ収集ユニット「桃山商事」代表。早稲田大学第一文学部卒業。ジェンダー、恋愛、人間関係、カルチャーなどをテーマにさまざまな媒体で執筆。朝日新聞beの人生相談「悩みのるつぼ」では回答者を務める。著書に「よかれと思ってやったのに――男たちの『失敗学入門』」(双葉文庫)、「さよなら、俺たち」(スタンド・ブックス)、「自慢話でも武勇伝でもない『一般男性』の話から見えた生きづらさと男らしさのこと」(扶桑社)、「おしゃべりから始める私たちのジェンダー入門」(朝日出版社)などがある。2024年に新刊「戻れないけど、生きるのだ 男らしさのゆくえ」(太田出版)が発売予定。
桃山商事 公式サイト(外部リンク)
- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。