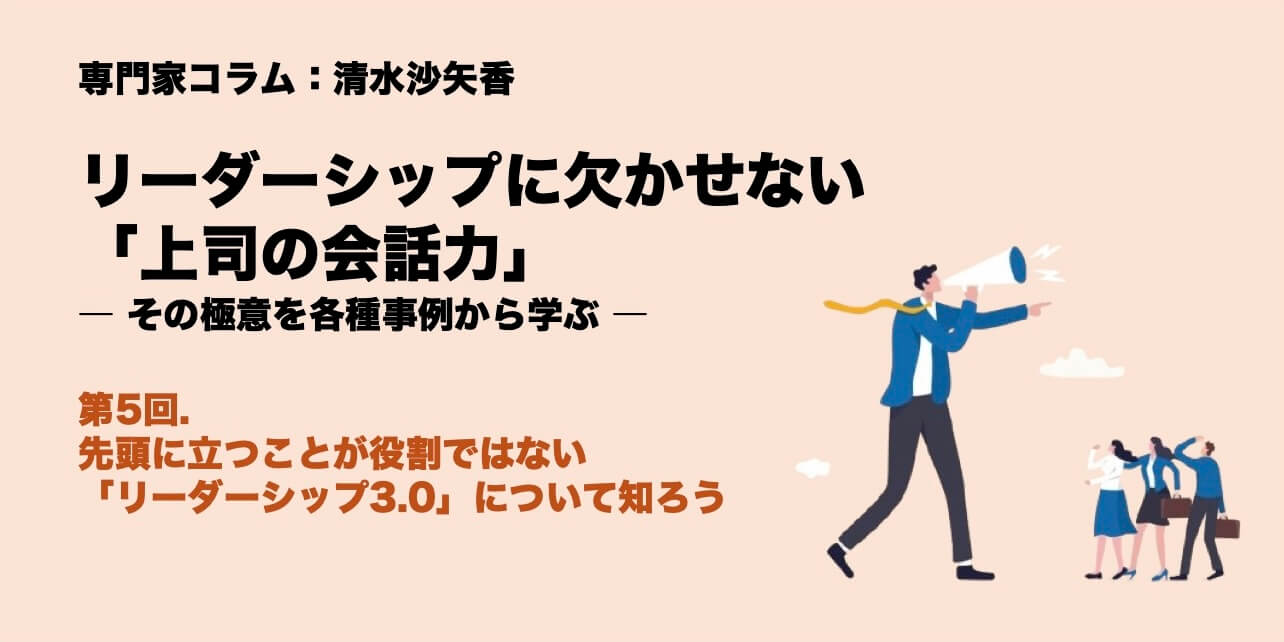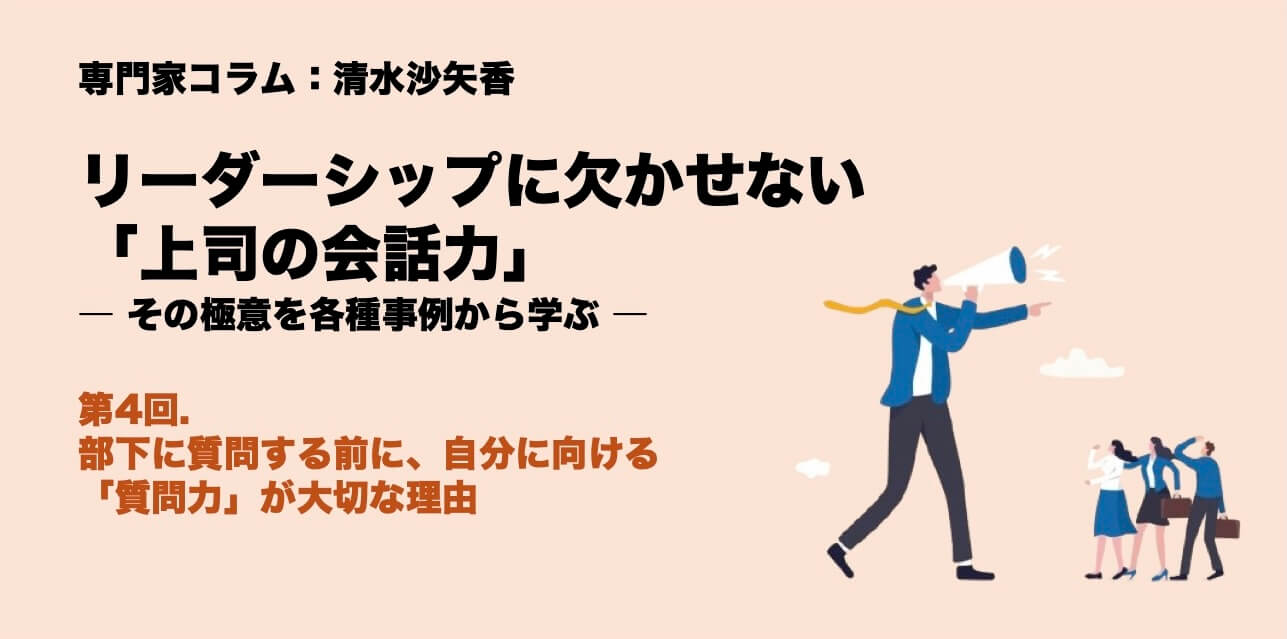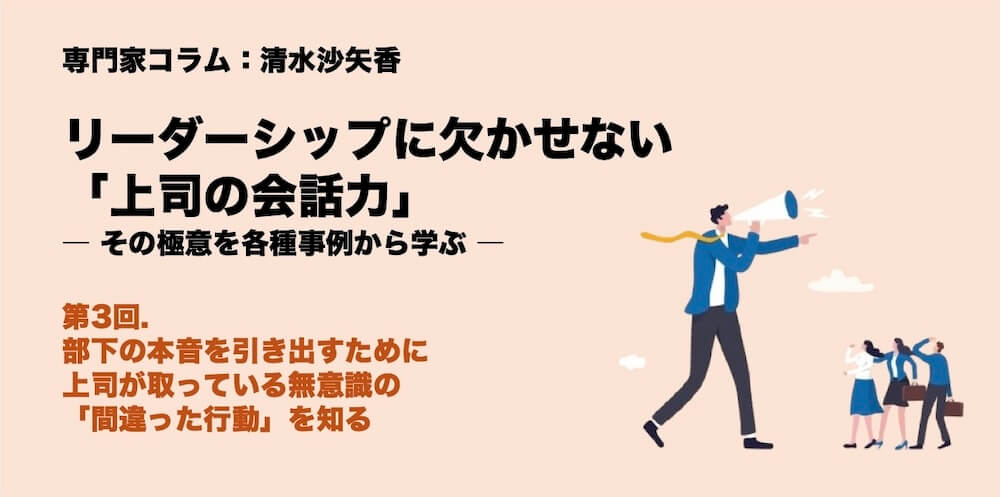未来のために何ができる?が見つかるメディア
第6回 「ボスになるな リーダーになれ」。若手社員離職に対する豊田章男会長の答え
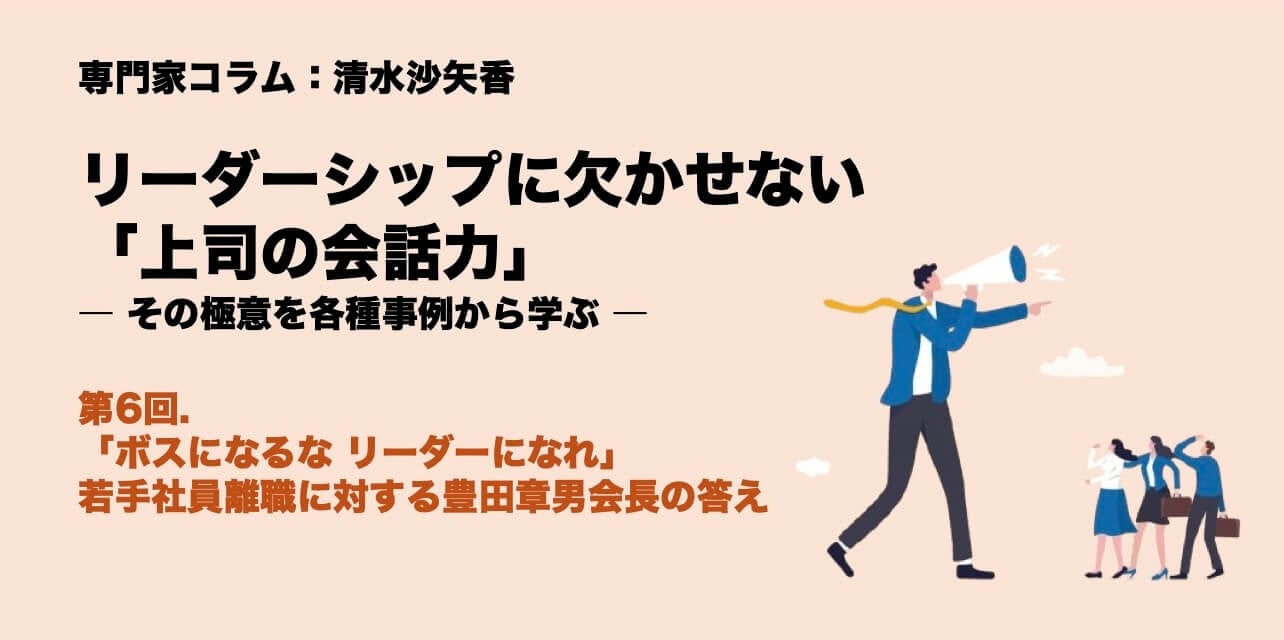
執筆:清水沙矢香
この連載ではリーダーシップの在り方、そのために欠かせない会話の形についてご紹介してきました。
次いで最終回として、自然界の話を交えてリーダーシップを捉え直したいと思います。
若手の離職に悩まされたトヨタ
トヨタ自動車での2020年春の2回目の労使交渉では、「若手の退職」と「技術部門の風土改革」が中心議題でした。それぞれの立場から意見が出ています。*1
組合側が口にした現場の現実は、このようなものでした(太字は筆者加筆)。
組合員が何かを変えようと上司に相談した際、(中略)「組合員の提案は分かるけれども、限られた時間でリスクもあるし、今はやめておこう」。そうした上司の反応では、その想いもいつしかくじけ、目の前の業務をひたすらこなすだけになるというのも、正直なところです。
これが繰り返されると、若手からは「何も変えられない自分と、周りをみても本気で変えようとする先輩、上司がほとんどおらず、(そうした職場に)染まりつつある自分にもがっかりする」という声も聞いており、一部の仲間はトヨタを退職しています。
これに対し友山茂樹(ともやま・しげき)副社長(当時)はこう発言しています。
職場のリーダーに求められることが、いつの間にか自分の職場の仕事や部下を決められたルールで管理することになってきてしまっていると思う。本来職場のリーダー(に求められること)はメンバーにダイナミックな「虹」を見せること、描くことだと思う。
そして豊田章男(とよだ・あきお)会長は、こう語りかけました。
皆さん、ボスとリーダーの違いをご存知でしょうか。イギリスの高級百貨店チェーンの創業者の方の言葉です。その内のいくつかをご紹介したいと思います。
ボスは私と言う。リーダーはわれわれと言う。
ボスは失敗の責任をおわせる。リーダーは黙って失敗を処理する。
ボスはやり方を胸に秘める。リーダーはやり方を教える。
ボスは仕事を苦役に変える。リーダーは仕事をゲームに変える。
ボスはやれと言う。リーダーはやろうと言う。
その上で、友山副社長が自分(豊田会長)のことを「ボス」と呼んでいること、ディディエ・ルロワ副社長(当時)はいつも「ボスを喜ばせるな」と書いた紙をポケットに入れており、実際にルロワ副社長は「私のいうことは聞きませんし、私のことはボスと言っております」と茶化しながら語りました。
「ボス」を喜ばせるとどうなるか。「失敗の責任をおわせ、仕事を苦役に変えるボス」が増長するのです。

自然界にみる「ボス」と「リーダー」の違い
京都大学の元総長でゴリラ研究の第一人者である山極寿一(やまぎわ・じゅいち)氏は、サルとゴリラの違いを通して人間の組織について語っています。
サルとゴリラ。動物園での景色を思い浮かべてみてください。様子は全く異なります。
サルはボスが猿山のてっぺんで胸を張っていますが、ゴリラは皆同じ地面でくつろいでいます。実際、両者の群れの社会構造は見た目通りです。
サルの社会では、劣位な個体は優位な個体の目の前ではものを食べることはありません。ものを食べているところを見られると、優位なサルに食べ物を取られてしまうからです。食べる時は分散して、違いに目が合わないようにします。サルの社会では、相手の目を見ることは威嚇を表すからです。
引用:山極寿一「サル化する人間社会」集英社インターナショナル p128(太字は筆者加筆)
一方、ゴリラはこのような行動を取ります。
しかしゴリラはじっと見つめ合って、挨拶をします。視線を合わせることはゴリラにとっては大切なコミュニケーションです。食事をするときにも、ゴリラは互いの顔が確認できる距離で集まっています。
(中略)
子どものゴリラが、大人のゴリラに「それ、ちょうだい」とねだって、食べ物を分けてもらうこともあります。ゴリラには優劣の意識がないから、平和的に食事をすることができるのです。
サルは食べ物を分け合うことはありません。しかし、ゴリラは食べ物を分け合います。ゴリラが食べ物を分ける時は、相手の前にぽん、と置いてあげるのです。面白いですね。
引用:山極寿一「サル化する人間社会」集英社インターナショナル p128-129(太字は筆者加筆)

サル社会のトップが「ボス」だとすれば、ゴリラの場合は「リーダー」です。「上の存在と目が合う」ことが、ボスとリーダーではこんなにも違うのです。
しかし山極氏によれば、人間社会は「サル化」しつつあるといいます。その理由をこう説明しています。
今は自分の幅を広げていくということが人間社会でなくなってきているのではないかと思います。その原因は、人間が自然と段々付き合わなくなって、自分でコントロール可能な機械や、機械のような人工物とばかり付き合うようになってしまったことだと思います。インターネットもその中の1つです。自分でコントロールできる、あるいはコントロールできないと止めればいい、潰してしまえばいい 、そういう世界になり過ぎたのではないかと思います。
引用:環境省「第16回 京都御苑ずきの御近所さん 京都大学総長 山極寿一様」p2 (太線は筆者加筆)
部下の内面、これは「コントロールできないもの」として向き合う必要があります。
サル社会のように絶対的ヒエラルキーの中で無理にでもコントロールすること。これはトヨタの労使交渉で友山副社長が語った「自分の職場の仕事や部下を決められたルールで管理すること」そのものであり、実際にトヨタで若手の離職という出来事に繋がったのです。
「十把一絡げ」と「思い込み」を排すること
さて、この連載の執筆中に、筆者はある所で若い男性3人が話し込んでいる姿に遭遇しました。週末の夜のことです。
聞き耳を立ててしまって申し訳ないのですが、3人とも20歳くらいでしょうか。そのうちの2人が、「来週の仕事が楽しみか憂鬱か」という話をしていました。
ひとりは「憂鬱」、ひとりは「楽しみ」だというのです。理由はそれぞれ、
「きつく言われるのが嫌で、そうならないようにしていると気疲れするから憂鬱」
「いろんな所に行けるから楽しみ」
というものです。そして「憂鬱」という本音は、ここでしか話せないということでした。
もちろん、甘やかせば良いというものではありません。しかし理解しようという努力をリーダーがしなければ「今の若者は打たれ弱くて困る」といくらつぶやいても、響かない相手にどう厳しく接しても、話は先には進みません。「憂鬱」を溜め込ませ、どんどん距離が離れていくだけです。
「きつく言われるのが嫌」というのは、誰だって当然のことではないでしょうか?
ただ、以前は、なぜきつく言われるのかを理解しやすかったことでしょう。先行きを読めない今とは違い、目指すものが単純明快だったからです。あるいは、それに報いるだけの報酬や福利厚生があったから耐えられていたということもあるでしょう。
なお、冒頭にご紹介したトヨタの労使交渉では、菅原郁郎(すがわら・いくろう)取締役がこう述べています(太字は筆者加筆)。*1
上司の自分に対する評価に恐怖感を持つ、もしくは怯えを感じている組織に未来はなくて、閉塞感しかない。
そしてトヨタがそこに陥っている原因のひとつは2つ、「十把一絡げ」と「思い込み」だといいます。
1つは「十把一絡げ」で人を捉える風土がトヨタにはないかと。やはり人は、一人ひとりその人に応じて、働き方なり、育成の仕方(がある)というのが、本来あるべきところ。しかし、そこの手を抜き始めているのが今のトヨタにはあるのではないかと思います。
2点目は、幹部職も組合員の若手もそうですが、「若手は劣っているもの」、「教育されるべきもの」という思い込みがあると思うんです。僕は、変化の時代にそれは違うと思います。むしろ、「老い」、「衰え」、「感度の低さ」、「世間とのずれ」こそが最大の敵であって、これに侵されていないのは誰ですかという問題。
「十把一絡げ」と「思い込み」を排し、部下についての分からないことを自分の物差しで「相手がどれだけ間違っている」と考えるのではありません。
物差しの長さは人によって違って当然です。
自分と違うものに遭遇したとき、「常識」の定義を見直すことです。そして思い込みのない純粋な興味で接することはリーダー自身の知見と器量を広げ、自身の人間としての成長にも繋がるはずです。
[参考文献]
*1.参考:トヨタイムズ「ボスになるな リーダーになれ トヨタ春交渉2020 第2回」(外部リンク)
*2.参考:山極寿一「サル化する人間社会」集英社インターナショナル
*3.参考:環境省「第16回 京都御苑ずきの御近所さん 京都大学総長 山極寿一様」(外部リンク)
〈プロフィール〉
清水沙矢香(しみず・さやか)
京都大学理学部で生物学を専攻し、学部卒業後2002年にTBSに入社。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種産業やマーケットなどを担当。その後人材開発にも携わりフリーライターとして独立。国内外での幅広い取材経験と各種統計の分析をもとに多くのWebメディアや経済誌に寄稿。
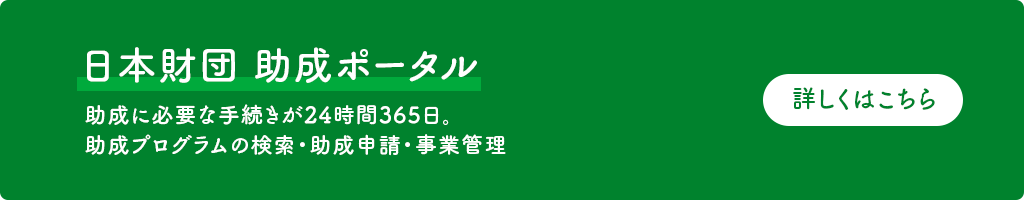
- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。