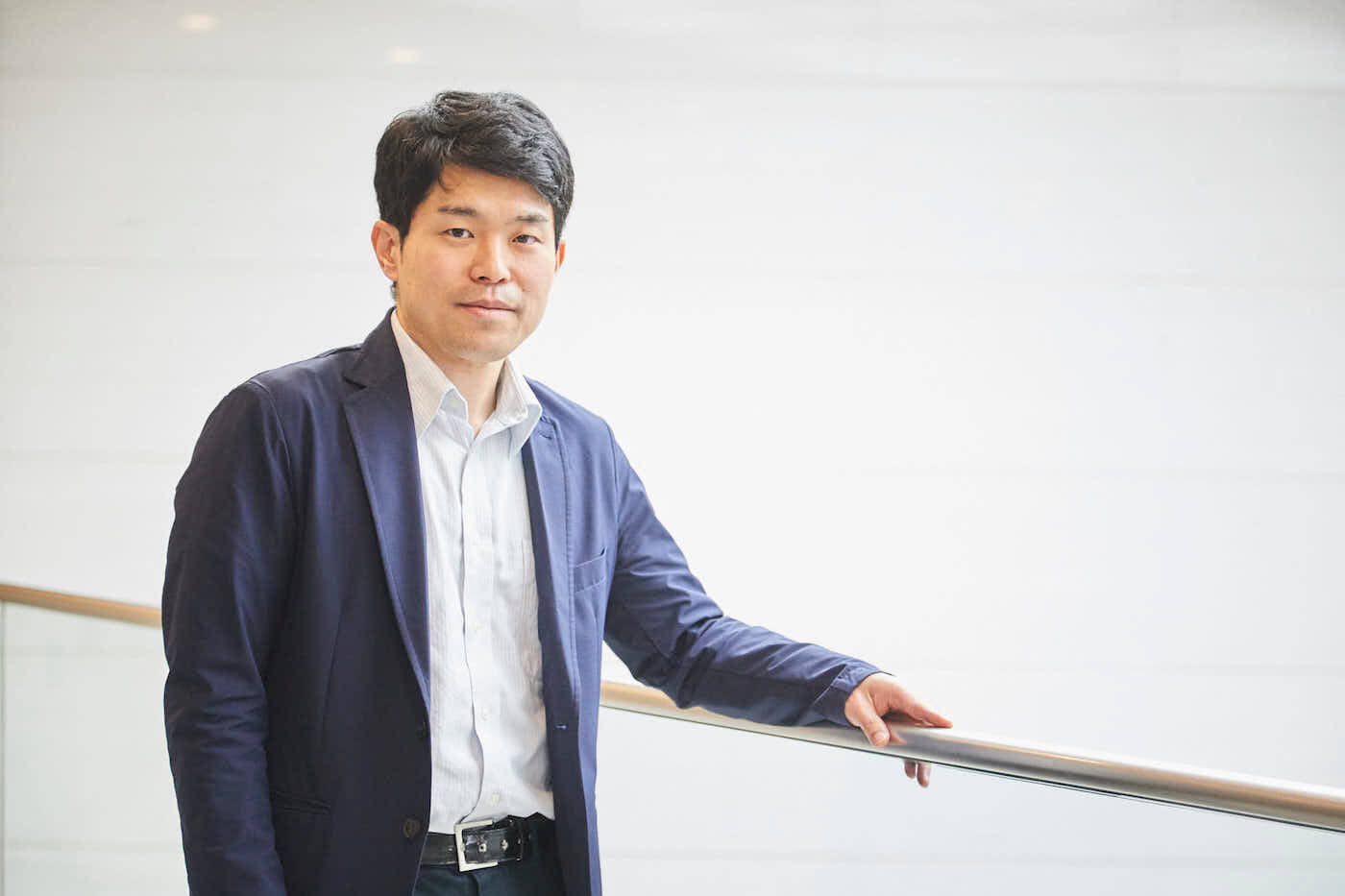未来のために何ができる?が見つかるメディア
教えて笹川会長!日本財団って何をしているところ?大学生が会長に直撃!

- 日本財団は、社会課題を見つけて、解決するためのモデルをつくり、広める組織である
- 大切なのは「自ら行動を起こす」こと。現場に足を運ぶからこそ見えてくることがある
- 健常者も障害者も、子どももお年寄りも、みんなでみんなを支え合う社会を目指す
取材:日本財団ジャーナル編集部
子どもの貧困問題への取り組みや障害者の就労支援、災害復興支援、2020年のオリンピック・パラリンピックのボランティアサポートやアスリートの社会貢献プロジェクト…と、多方面において社会課題を解決するための活動を行っている日本財団。テレビCMなどでも触れる機会があるが、特に若い世代は日本財団を知らないという人も多いかもしれない。
今回は、日本財団の笹川会長に、大学生3人がインタビュー。「日本財団の目指すものは?」、「どんな基準で事業を進めているの?」、そして「会長の仕事って?」。若者目線から日本財団の「仕事の裏側」に迫る。
〈参加者紹介〉
笹川陽平(ささかわ・ようへい)
日本財団会長。WHO(世界保健機関)ハンセン病制圧大使や、ミャンマー国民和解担当日本政府代表も務め、自ら世界各国の奥地へ赴き、支援活動を続けている。2019年1月には、これまでの世界的なハンセン病の制圧活動や患者・回復者への差別撤廃に対する活動が評価され、インド政府から、独立の父ガンジーの名を冠した「ガンジー平和賞」を授与された。
田村しえり(たむら・しえり)
慶應義塾大学1年生。大学では社会心理学を学ぶ。日本財団のボランティアサポートセンターにインターンとして参加している。
祝とも(いわい・とも)
慶應義塾大学1年生。10歳まで中国で過ごす。主に先進国などで問題になっている、本来はまだ食べられるのにもかかわらず食品が捨てられる「フードロス問題」などに関心を持っている。
古賀翔太郎(こが・しょうたろう)
早稲田大学1年生。情報テクノロジー分野に関心が高い。スマホのアプリを作るメディアにインターンとして参加している。
日本財団ってどんな活動をしているの?
古賀さん:本日はお会いする機会をいただき、ありがとうございます!実は日本財団について知らない部分も多く…。まずは日本財団という組織について教えていただければと思います。

会長:簡潔に言えば「社会課題を見つけて、解決のモデルをつくり、広める組織」です。社会課題の解決へいち早く行動し、成功のモデルケースをつくることによって、政府や行政が動ける道筋をつくる、というもので、これを「日本財団という方法」と呼んでいます。商品を作ったり、売ったりして利益を得るというような組織ではないですね。
田村さん:NPOの活動支援もされていますが、どんな基準で助成先を選んでいるのか教えてください。
会長:日本財団と政府の援助の大きな違いは、政府は公正・公平が原則であるのに対し、日本財団は、「集中と選択」を重視します。基準は、「我々が日本の将来のために解決すべき問題である」と思える社会課題に取り組んでいて、なおかつ「継続して成長し続ける仕組みがしっかりしている組織」であることですね。
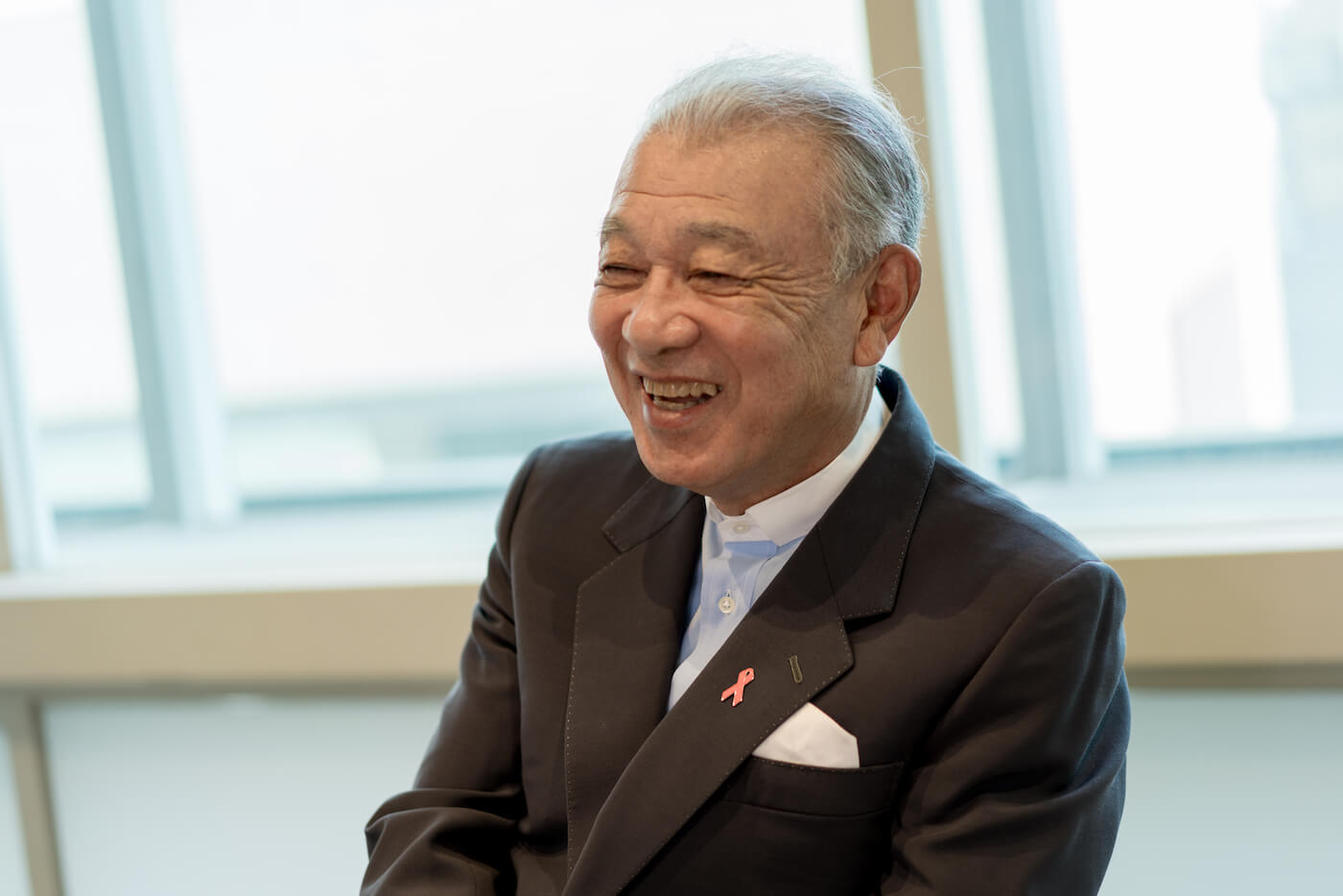

田村さん:継続して成長できるNPOとはどのようなものですか?
会長:ちゃんと組織化されていて、具体的な計画に沿って事業が進められているところですね。お金がどのように使われているかもしっかりチェックしています。NPOの活動の中で一番大切なことって何だと思いますか?お金を集めることなんですよ。もちろん困っている誰かの手助けをする活動も大切ですが、そのためには、自分たちで活動を持続させるだけの資金集めが大切です。「可哀想だから手助けする」とか「私は活動する人で、お金は国や他の人が出すべき」という考え方を持っているような組織ではダメなんです。
祝さん:世界各国に行かれていますが、一番印象に残っている活動は何でしょうか?

会長:インドにおけるハンセン病の制圧(※)(別ウィンドウで開く)ですね。インドには多いときで年に7回行きました。ハンセン病患者や回復者が暮らす療養所や集落を訪ねて激励する一方で、彼らの人権回復や生活改善を政府に働きかけるなどしていますが、インドは連邦制だから、各州を回ってそれぞれのトップを説得しないといけないんです。
- ※
末梢神経と皮膚に病変を起こす感染症。既に薬と治療法が確立され、1985年には世界に約535万人いた登録患者数が2016年には約17万人まで減少。そのうち5割の患者がインドにいると言われている。患者・回復者への偏見や差別には長い歴史があり、現在もなお続いている

古賀さん:現地に行くことで学べることも多そうですね。
会長:僕は、現場に行くからこそ、見えてくるものがあると考えています。もっと好奇心を持って、自分の目で見なきゃだめ。現場には問題点と答えがあるというのが私の考えです。
古賀さん:現場主義なんですね。
会長:今でも1年の半分は海外に行き、僻地の舗装されていない道を 1日6、7時間かけて車で走ることもあります。
祝さん:ハンセン病については、お父様の代から取り組まれているそうですが、どんな気持ちで活動を行っているのでしょうか?
会長:ハンセン病の問題には、「病気」「差別」2つの側面があるんです。私はハンセン病に関する活動をバイクに例えて話すことが多いのですが、前輪は病気の制圧、後輪は差別の根絶です。病気は薬を飲めば治るかもしれない、でも社会にある「差別という病」はなかなかなくすことができないんです。両方を解決しない限り、ハンセン病問題が解決することはありません。両方の車輪が動かなくては、バイクは走りませんよね。

祝さん:差別の方が根強いんですね。
会長:神の罰とか、呪いだとか遺伝するとか、間違った知識が今も世界中で信じられていて、家族からも捨てられることがあるんです。こういう悲惨な生活をしている人々が、世界にはまだ多くいることを皆さんに知ってもらいたいですね。
田村さん:ハンセン病についての一番の課題は「正しい知識を広めること」なんですね。

会長:そうです。課題は山積みなんです。例えばインドだけでも、患者や回復者は普通の人と同じ電車やバスに乗れず、レストランにも入れない、ハンセン病と分かったら離婚してよい、など110もの差別法が残っているんです。誰かが解決しないといけない。
田村さん:ハンセン病の活動で一番印象に残っていることを教えてください。
会長:一番インパクトを出せたのは、日本財団が5000万ドルをかけて、1995〜1999年の5年間、WHOを通じて世界中に無料で薬を提供したことです。
祝さん:ハンセン病を含むさまざまな問題を解決する上で、各国の大統領や首相などとも会談され、親しくされているイメージがあります。
会長:いや、別に親しくないですよ。フランスのマクロン大統領へは、彼のハンセン病への差別的な発言に対する抗議文を送りますし、間違っていると思ったら相手が誰であろうが普通に伝えます。みんな偉そうに見えるけど、人間なんてみんな同じ。家に帰れば、怖い奥さんや生意気な息子なんかもいるんです。
一同:(笑)
日本財団が描く未来像
田村さん:話は変わりますが、日本財団は、東京2020大会の「オフィシャルコントリビューター」として、さまざまな活動を進めていると思います。会長自身は「こういう大会になってほしい」といった目標はありますか。
会長:オリンピックもそうだけど、障害を乗り越えて限界に挑む選手たちを応援するパラリンピックをより盛り上げたいですね。会場を観客でいっぱいにしたい。それを観た若い子たちが「自分ももっと頑張ろう!」と前向きな気持ちになってくれるといいですね。

祝さん:大会が終わった後も良い影響があるということですね。
会長:大会後の日本財団が目指すのは「インクルーシブな社会」です。障害がある人も、健常者も、お年寄りも子どもも、それぞれの個性を尊重し、みんなで支え合う社会をつくりたいんです。
僕は今年で80歳になりましたが、かつて日本には、助け合いの精神があり、地域のコミュニティーがありました。買い物に行く時は近所のおばちゃんが子どもの面倒を見てくれた。近代化の中で、生活レベルが上がると同時に、そんなつながりもなくなってきました。人付き合いの範囲も相対的に狭くなっている気がします。
貧困の子どものために家でも学校でもない場所を作る「第三の居場所」(別ウィンドウで開く)や、引退したアスリートたちがボランティアを通して社会とつながる仕組みづくりでもある「HEROs Sportsmanship for the future」(別ウィンドウで開く)は、そんな未来を築くための先駆けでもあるんです。

田村さん:今の学生に人生のアドバイスがあれば、教えてください。
会長:それぞれが興味のある分野で頑張ればよいと思います。一つでもいいから自信を持って「これができる」というものがあると、人はより強く生きることができると思うんです。そして一番大切なのは、やっぱり現場に行くこと。勉強っていうのは、知識を詰め込むことじゃなくて「体験」することですから。
祝さん:行動を起こすことが大切なんですね。
会長:僕の好きな言葉に「知行合一(ちこうごういつ)」という言葉があります。これは、中国の思想家で、幕末の運動家などに大きな影響を与えた王陽明(おうようめい)の有言実行を説いた言葉ですが、知っているだけじゃだめなんです。自分の目で見て考え、行動しないと。
古賀さん:他にも「今だからこれをやっておいた方が良い!」ということがあれば教えてください。

会長:「苦労は買ってでもしろ」ですね。楽して、良い人生なんて送れませんよ。目標のために、たくさんの困難を乗り越えるからこそ、ちょっとやそっとじゃへこたれない自分になれるんです。人生は最後に「いい人生だったな」と思えたらそれでいいのですよ。
最後に私からの若者へのお願いです。もっと読書をしてください。心の栄養になるような、歴史の風雪に耐えた古典、特に人物の「生き方」に関する本は、皆さんが困難に直面したときや失意のときに、きっと光明を見出してくれるでしょう。
田村さん、祝さん、古賀さん:本日はありがとうございました!!
撮影:佐藤潮
- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。