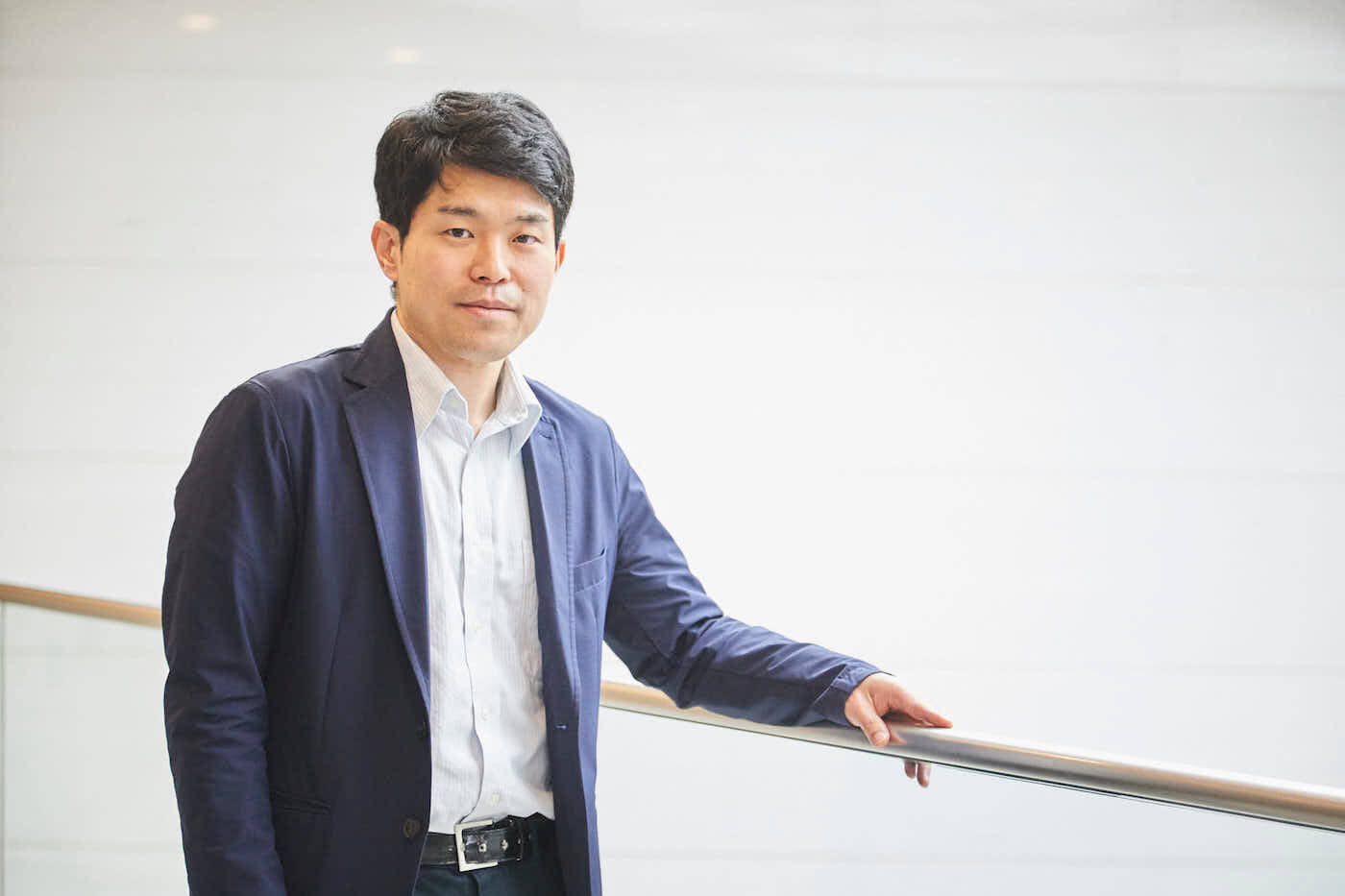未来のために何ができる?が見つかるメディア
「現地資源を生かすこと」が開発支援の真髄。ミャンマーの未来を「薬草」で切り開く

- ミャンマーで伝統的に栽培される薬草は、地域振興の大きな可能性を秘めている
- 内戦で疲弊した国を立て直そうというカレン州の人たちの思いが、薬草プロジェクトを支えた
- 地域開発の支援には、現地にあるさまざまな人的、物的資源を結びつけることが大切
取材:日本財団ジャーナル編集部
長年、経済制裁を受けていたミャンマーは経済的な成長が遅れ、一時は東南アジアの最貧国であった。また国内には100以上の少数民族を抱え、紛争が絶えなかった。そんなミャンマーの発展と人々の生活向上を支援するため、日本財団では2013年からミャンマー南東部のカレン州政府と協力して「薬草プロジェクト」に取り組んでいる。
このプロジェクトは、現地で栽培されている薬草の調査・生産・販売を総合的に支援するというもの。今回は現地でその指揮を執る間遠登志郎(まどお・としろう)さんに、プロジェクトがスタートした経緯と現状、これからのビジョンについて話を聞いた。
「リスクを負うのも役目の一つ」。笹川会長の一言で始まった薬草プロジェクト
「きっかけは、日本財団会長の笹川陽平とカレン州首相の会談でした」
実直を絵に描いたような印象の間遠さんは、そんな風に話を切り出した。ミャンマー政府と少数民族との間で長年続いた内戦が終結した2013年、日本財団の笹川会長はミャンマー南東部のカレン州を訪れた。そこで当時の州首相から、山間・農村部の開発支援を頼まれたのだ。
「カレン州は長期の内戦後のためインフラが破壊され、現地の情報もほとんどありませんでした。そんな状況ではリスクが大き過ぎて、民間企業による投資は難しい。しかし、笹川会長は『そういったリスクを負うのも日本財団の役割である』という判断を下し、薬草プロジェクトを始めたのです」
その薬草プロジェクトの責任者に、なぜ間遠さんが選ばれたのか。実は、彼が歩んできた道のりは、まさにこのプロジェクトにふさわしいものだった。

「私は青年海外協力隊と日本財団で通算20年以上、アフリカで農業支援に取り組んできました。そして2013年当時はミャンマーの隣国のタイで、東南アジア各国における農業支援をしていたのです。笹川会長はカレン州を訪問する前から、州政府からの依頼を予想していたのでしょう。農業関係の仕事を長年やっていた私を同行させ、首相との会談の場でプロジェクトを担当するよう指示したのです」
地元に根ざした事業を考え、たどり着いたのが薬草プロジェクト
どうして「薬草」なのか。その理由は、現地の地理的な条件にあった。
「プロジェクトの対象となった地域は山間・農村部であり、傾斜地に低所得者層が多く住んでいます。その人たちの仕事をつくるには、そこで栽培できるものを選ばなければなりません。また州政府からは、その人たちが住んでいる環境の保全を推進することも求められていたので、広く土地を切り開くのではなく、現状の狭い土地空間を活用し、生産性を上げることが重要でした。それで単価の高い『薬草』を選んだのです」

日陰を好む薬草が販売できれば、影をつくるために森林を保全しようという動機付けにもつながる。つまり、その土地に暮らす人たちが自ら環境を管理しながら、生産活動ができるように考えたのだ。
当初、プロジェクトのために州政府が用意してくれたのは、現在のプロジェクト用地(東京ドーム3個分)の4分の1ほどの狭い土地。雑木林の木々を、農業局・森林局の職員たちと移植し、古い切り株を取り除くことから始めなければならなかった。電気もガスもない。事務所はカレン州政府の伝統医療局の一角を間借りしていたという。また、プロジェクト用地の整備と並行して、周辺の薬草資源の調査も進める必要があった。
「ミャンマーは経済制裁を長く受けていたこともあり、西洋医学よりも伝統医療に依存する期間が長かったんです。貧しくて病院を受診できない人たちは、今でもそういう伝統医療に頼っています。そこで現地の伝統医療師の人たちにどのような薬草を使っているかを尋ね、育苗小屋に薬草を収集し、試験的な栽培を行いました」

「政権交代の危機」で感じたミャンマーの人たちの懐の深さ
プロジェクトが軌道に乗り始めた2015年、薬草プロジェクトは最大の危機を迎える。きっかけは、アウン・サン・スー・チー氏率いる国民民主連盟(NLD)によるミャンマーの「政権交代」だ。
「2015年、プロジェクト用地が現在の40エーカーに拡大されることになりました。そこで事務所・加工施設・品質管理施設・スタッフの寮などを含む『カレン州薬草資源センター』を建設し始めたのです。センターが完成したのは2015年末でしたが、それがちょうどミャンマーにおける総選挙の時期でした」

薬草プロジェクトがスタートしたのは、過去の軍事政権の影響を色濃く残した前政権の時代。世界の政権交代の例でも分かるとおり、新政権において前政権の政策が否定されることは珍しくない。
「新政権になって薬草プロジェクトがどうなるか心配した私は、当時のカレン州首相に相談したのです。すると首相は、ある人物を紹介してくれました」
間遠さんは、その人物が国民民主連盟(NLD)の党員であることしか知らされなかった。会談は州首相と間遠さん、謎の人物の3名で行われた。
「首相は薬草プロジェクトがどれほど意義のあるものか、私に代わって懸命に説明してくれました。するとその人物は『今から現地に行こう』と言い、すぐに出発することに。最後には、『責任を持って新政権として引き継ぎますから、心配はいりません』と言ってくれました」
後日分かったことだが、その人物は新政権におけるカレン州の財務大臣だった。2016年6月に行われたセンター開所式でのテープカットの際には、カレン州の新首相が、遠くで見守っている前首相に気付いて招き、新・旧両首相が並んでテープカットをした。
「私はそれを見て、ミャンマーの人たちの懐の深さに本当に感動しましたね。新政権は現在も、力強い支援をしてくださっています」

地域振興の起爆剤?「薬草栽培」が持つポテンシャルとは
一難去って、また一難。薬草プロジェクトが乗り越えなくてはならない壁は多い。その一つが、継続的な所得の創出だ。
「センターでコレクションしている100種類の薬草のうちから、市場に出せそうな30種類を試験的に栽培しています。されにその30種類の中で、実際にマーケットが見つかり、プロジェクトを通して販売している主要な品目はウコン、ノニ、ムクナ、トウガラシ、ヤマイモの5種類です」

「住民の所得を生み出し、薬草の品質を上げ、市場に流通させるためには、センターで栽培するだけでなく地域農家からの買い取りや一次加工が必要だと考えました。最も取扱量が大きいウコンにしても絶対量が足りないのです。生薬メーカーからは『コンテナを一つ埋めるくらいの単位でもっと出荷してもらわなければペイできない』と言われました。大農家からまとめて買って対処する方法もあるのですが、プロジェクトの目的であるより多くの人々の所得の創出に貢献するためには小規模農家から小ロットずつ買う必要があるので、なんとも難しい問題なのです」
現時点では、センターでかかるコストと販売による利益のバランスは厳しい。しかし一方で、センターが買取りと品質管理を行う成果も出始めている。
「以前は、小規模農家が散在しているため、『コレクター』と呼ばれる仲買人が薬草の買取りをし、市場に持ち込んでいました。しかし、この方式では『違う種類』や『カビの生えているもの』が混ざってしまい、生産者情報も分かりません。そこで当センターは、小規模農家の近くに簡易倉庫をつくり、そこで買い付けをする買い付けセンターを、今年開設します。これにより作物の品質管理ができますし、生産農家に対して求める品質や栽培方法について伝えることもできます。言わば『生産者の顔が見える取引』ができるのです」
地域振興で大切なのは「現地に存在する資源」。目指すべき薬草プロジェクトの未来
「現地に無いものを持ち込んでも、継続性が無い」という信念を持つ間遠さん。それは、アフリカでの経験が元になっている。
「アフリカでの食料増産プロジェクトでは、『ポストハーベスト』という、生産された農産物の加工や貯蔵するための施設の普及を行っていました。現地で採れるトウモロコシやキャッサバを、収穫後に加工し保存が効くようにするのです。加工機械は、あえて外国から輸入せず、現地で製造・普及させました。そうすることで、その国の産業発展につながるからです。地域振興は、地域産業とつながって初めて強くなっていくことをアフリカで学びました」

そんなアフリカで得た気付きをミャンマーで生かしたいと間遠さんは語る。
「地域の開発支援では、現地の人たちにとっての『制約条件』を減らしていくのが私たちの役割。流通や加工など現地に欠けているピースを補完していくことで、地域は自力で発展していくのです。一次加工施設というセンターの商業活動が社会的課題の解決になるという『ソーシャル・エンタープライズ(社会的企業)』の取り組みは、日本財団としても初めて。今後もその継続的な実現に向けて、日本財団の職員や実際に汗を流しているミャンマーの人たちと活動を続けていきたいと思っています」

2018年10月、日本財団は東京農業大学とミャンマー支援で連携協定を締結。薬草栽培に関わる人材を育成し、さらなる品質の向上と日本を含む国外への輸出を目指している。
薬草プロジェクトが成果を収めつつある裏側には、多くの「つながり」がある。現地へ赴き、人々の声を聴き、時にはリスクを負うことによって出来上がった、日本財団とカレン州のつながり。薬草事業を継続させた、州の前首相と新首相のつながり。そして、間遠さんと地域の人たちとのつながり。「ミャンマーを豊かな国に」という大きなビジョンのもと、つながり合うことができたから、一大事業を進めることができたのだ。しかし、ゴールはまだまだ先。間遠さんの挑戦はこれからも続く。
撮影:十河英三郎
〈プロフィール〉
間遠登志郎(まどお・としろう)
日本財団ミャンマーオフィス・農業開発プログラム上級マネージャー。大学卒業後、商社勤務を経て青年海外協力隊としてガーナに赴任。1989年より笹川アフリカ協会職員として、ガーナで農産物の加工プロジェクトなどに取り組む。2002年からエチオピアで農産物の生産・加工・貯蔵技術の普及や指導員の育成などを中心とした笹川グローバル2000に携わり、2010年に国際熱帯農業センター(CIAT)のバンコク・オフィスへ異動。2013年より現職。
- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。