未来のために何ができる?が見つかるメディア
たった一人で福祉機器の開発に情熱を捧げる森岡さん。きっかけはALSの友人の介護支援

- 福祉機器を個人で開発する東北大学名誉教授の森岡昭さん。きっかけは友人の介護支援
- 開発の根底にあるのは、障害者の不便や、介護する人の負担を減らしたいという思いから
- 障害のある人を支援する際は、その人の性格や気持ちを汲み、尊厳に配慮することが大切
取材:日本財団ジャーナル編集部
宮城県仙台市に、障害者の生活を助ける「福祉機器」を一人で開発している人がいます。東北大学名誉教授である森岡昭(もりおか・あきら)さんです。もともと理学博士として研究と教育に携わってきた森岡さんは、大学を退職後、車いすユーザーや手足に障害のある人のため、さまざまな福祉機器を開発してきました。
取り組む中で重視しているのは、ホームセンターや雑貨スーパーなどで手に入る材料を使って、構造をできる限りシンプルにし、「誰でも作れる」こと。その情報は、YouTubeを使って発信しており、それを見て購入を希望する人もいますが、報酬として受け取るのは製作にかかった材料費のみと、あくまでも体に障害のある人の役に立つことを目的としています。
その活動を始めたきっかけは、2011年12月に「ALS(筋萎縮性側索硬化症)」と診断されたひとりの友人の存在。ALSとは、手足やのど、舌の筋肉、呼吸に必要な筋肉が徐々に衰えていく病気で、日本における推定人数は約1万人。1年間で人口10万人当たり平均2.2人が新たに発症するといわれています(※)。
罹患してわずか1年半で友人は他界。しかし、今もなお福祉機器の開発に力を注ぐ森岡さんは、どのような思いを胸に抱き、取り組んでいるのか、お話を伺いしました。
- ※ 参考:公益財団法人 難病医学研究財団/難病情報センター
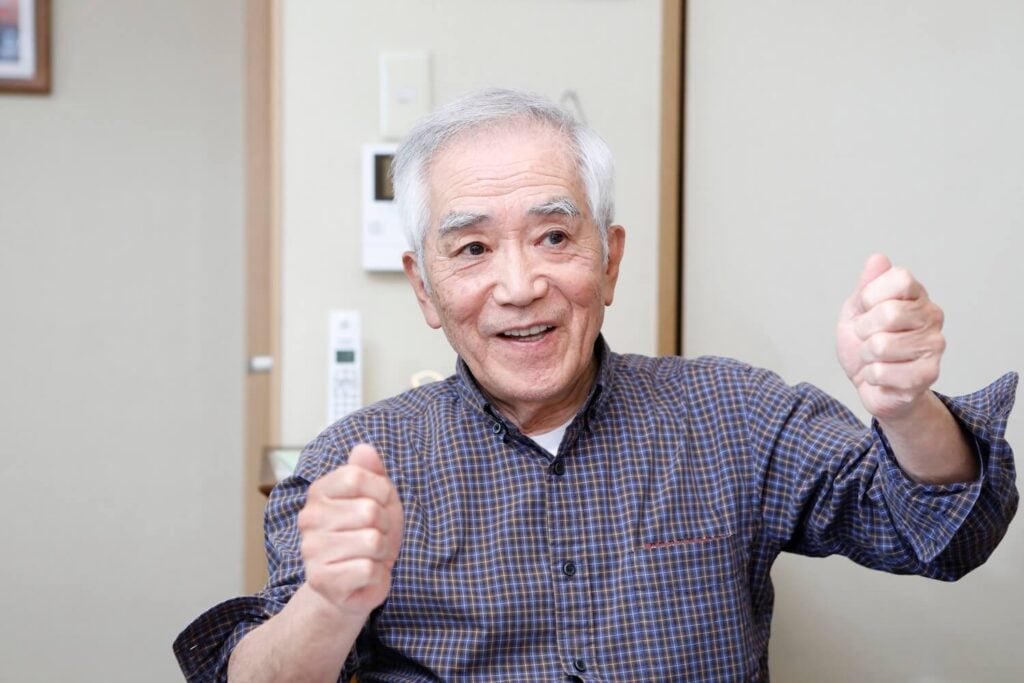
ALSの友人をサポートしたい、という思いで生まれた福祉機器
――福祉機器を開発しようと思ったきっかけを教えてください。
森岡さん(以下、敬称略):13年ほど前に、高校時代の山岳部で一緒だった友人がALSを患ってしまったんです。大学でも共に山岳部に入りましたし、卒業後も時折集まり、スキー登山をしたり、飲み会をしたりする仲間のひとりでした。
ALSが発覚してから、すぐに山岳部OBたちで彼を支援するグループを立ち上げ、折を見ては散歩やスポーツ観戦、ドライブ、旅行などに連れ出しました。そんな中、失われていく身体の自由とQOL(Quality of Life/生活の質)を少しでも保てる方法はないだろうかと考え、日常生活をサポートする機器を手作りするようになっていったんです。
――ご友人の反応はいかがでしたか。
森岡:ALSの進行によって彼の首の筋肉が弱り、頭を自力で支えることが困難になってしまったんです。そこで、頭を支える「ヘッドフィクサー」というものを開発しました。登山用の背負子(しょいこ※)と帽子をつなぎ、その帽子をかぶれば、自然と頭が支えられるというものでした。
試作品を初めて彼に装着したとき、満面の笑みを浮かべてくれて。発病以来、初めて見るような明るい笑顔で、いまでも忘れられません。そのときの彼の反応が、後の開発の励みになりましたね。
――福祉機器のアイデアは、どのようなときに思いつくのでしょうか。
森岡:障害のある方が不便に感じている、あるいは介護されている方が苦労している場面を実際に目の当たりにすることで、アイデアを思いつくことが多いです。それをもとに自室で試行錯誤を重ねながら作業しています。材料はホームセンターやネットで手に入るものばかりを使っています。
例えば、腕の筋肉が弱って、コップを口元まで持っていくことが困難になってしまう人がいます。彼らは熱いコーヒーが飲みたくても、介護する人にお願いをして、冷めたものをスプーンで飲ませてもらうことになる。あるいはビールをグビグビと飲みたくても、ストローを使ってちびちびと飲まなければいけない。
筋肉が衰えているとはいえ、脳も心も正常なままなのですから、本当に無念だと思います。そこで開発したのが「晩酌アーム」。取り付けたコップに唇をそっと押し当てると、コップが傾き、好きな量だけ飲み物を口に含むことができます。ビールならゴクゴクと、日本酒ならちびちびと味わうことができます。
- ※ 背負子は、荷物をくくりつけて背負って運搬するための枠からなる運搬具のこと


介護者の負担を軽減することは、障害のある人の生活の質を高めることにもつながる
――「好きな飲み物を好きなだけ飲める」というのは、実は豊かな暮らしに欠かせない行為ですよね。
森岡:そうなんです。それから先ほども申し上げたように、私は介護する側の人の力にもなりたいと思っていて、そのための機器もいくつか開発しました。
例えば「アプト式昇降補助具」。車いすで生活するようになると、外出するのが大仕事なんです。特に老老介護をしているような高齢者夫婦の家庭は本当に大変。玄関口を上り下りするためには車いす用スロープを使って、慎重に車いすを押していかなければならず、かなりの重労働です。
かといって、外出を控えるのも違います。体に障害があっても頻繁に外出し、外の空気を吸って、元気を出してもらいたい。
そこで「アプト式昇降補助具」を使えば、車いすを小刻みに昇降できるようになります。高齢者でも休み休み車いすを動かせるので、気楽に外出できるようになるのではないでしょうか。
――介護する人の負担を減らすことで、結果として障害者のQOL向上にもつながることが分かります。
森岡:そのとおり、介護する人の負担を軽減することが障害者の福祉につながるんです。車いす関連でいうと、外出後、室内に入るときには汚れたタイヤを拭くという作業が発生します。
これが意外と面倒で、それならいっそのことスリッパのようなカバーを車いすのタイヤに履かせられないだろうか、と考えたのが「タイヤスリッパ」です。
――これはアイデアグッズですね! 非常に簡単な仕組みで、助かる人も多いと思います。
森岡:障害のある人、あるいは介護する人は、「困っているけど仕方ない」と諦めてしまっていることも少なくない。私はその問題を見つけて、常識にとらわれず改善策を発想することを心がけています。
――森岡さんはご自身が開発した福祉機器をYouTubeで公開されていますよね。
森岡:はい。それには2つの狙いがあります。1つは、障害のある方や介護する人の目に留まり、同じようなものを作ってみよう、利用してみようと考えてもらうためです。
そしてもう1つは、YouTubeで公開することにより、私以外の誰かが似たものを開発したとしても、特許を取得することが難しくなります(※)。独占販売も防げるわけです。私はこの福祉機器のアイデアを広めることによって、ゆくゆくはメーカーさんに製造販売してもらえたらと思っています。そうすれば、たくさんの方に安く行きわたりやすくなりますから。
- ※ たとえ自身が創作したものであっても、特許の出願前に展示会や報道、インターネットなどにより公開されたものは、一部の例外を除き原則、特許を取得できない。参考:特許庁「初めてだったらここを読む~意匠出願のいろは~|その意匠、もう公開していませんか?」


障害者の方が外出するのを遠慮しなくて済むように
――ALSになったご友人をきっかけに、こうしてさまざまな福祉機器を開発するようになったわけですが、それによって今の社会に足りていないものも見えてきたのではないでしょうか。
森岡:日本の福祉制度の仕組みは非常にしっかりしていると感じました。ALSを患った彼の場合は指定難病だったこともあり、診断直後から介護支援や給付金に関する手続きの連絡も届き、心強かったそうです。
一方で、ALS患者が自宅で療養する場合は、家族に介護の負担が重くのしかかります。その支援体制は自治体ごとにばらつきがあり、十分に整っているとは決して言えません(※)。こういった問題を解決するための仕組みが行政主導でできていくことを望みます。
また、障害者の方の不自由を補うための福祉機器の種類や数も足りていません。私のような個人や小さな工房、福祉団体などが工夫を施して機器を開発しているのが現状です。
この問題を解決するためには、発案者と製造業者をマッチングし、発案者のアイデアを活かした機器を広く宣伝・販売していく仕組みが必要だと思います。ところが、こういった機器は製造業者の利益追求にはそぐわないと判断されてしまう。そこを補うためにも、行政が方策を立ててほしいですね。
――行政の動きにも期待しつつ、この社会に生きる私たち一人ひとりにもできることはあるでしょうか?
森岡:もちろんあります。車いす利用者は日本の総人口1億2,378万人(2025年4月時点)のうち200万人いると言われています。これはつまり、200人に約3人の割合です。
でも、まちに出てみても、車いすの方を見かけることは少ないですよね。それはなぜか。車いすの方が外出することを遠慮して、自宅にひきこもっているからではないでしょうか。
だから私たちは、彼らが気軽に外出するきっかけをつくる必要があると思うんです。もしも、身近なところに車いすの方がいたとしたら、気後れせずに、外出に誘ってみてほしい。それがきっかけとなって、積極的に外出できるようになるかもしれません。
ただし、その際には、障害のある人たちの尊厳に配慮しなければいけない。親切心で先手先手とお手伝いすることが、かえって当事者の方を悲しませてしまうかもしれない。その人の性格や気持ちを汲むことは忘れてはならないと思います。
それから、近いうちに南海トラフ地震が発生すると想定されています。そもそも日本はとても災害が多い国。障害のある人たちの中にはもしものときに逃げられるのか、と不安になられている方も少なくないと思います。
その不安を少しでも取り除くことができればと考えて開発したのが、「用心棒」なんです。これは火災や地震などの非常時に、車いすを運びやすくするための用具なんです。2本の棒を車いすに取り付けることで、たった2人でも車いすを軽々と担げるようになります。
「用心棒」さえあれば階段や段差、がれきも簡単に乗り越えられるようになります。
森岡:また災害時でなくとも、エレベーターが設置されていない駅に備えておけば、駅員さんが車いすの方を運ぶ手助けにもなるかもしれない。こうした機器を至るところに用意しておくことで、車いすの方が抱える不安を少しでも取り除けるのではないでしょうか。
- ※ 重い肢体不自由者や知的障害者・精神障害者は、公的な介護サービス「重度訪問介護」を利用できる。長時間の介護で生活支援を受けられるが、支援事業者が不足していたり、支給時間が自治体ごとにばらつきがあるなどの問題を抱えている


体に障害のある人たちが安心・安全に暮らすために、地域や周りの人たちができること
●森岡さんのYouTubeを参考に、福祉機器作りに挑戦し、提供してみる
●先回りして手助けするのではなく、まずは相手の性格や気持ちを汲み取ることを大切にする
●ふだんから気軽に声をかけられる関係を築き、有事の際は避難のサポートをする
取材陣の質問に対し、福祉機器の一つ一つの扱い方を、自ら実践しながら丁寧に教えてくれた森岡さん。お話を伺って伝わってきたのは、「ひとりでも多くの障害者の方、介護者の方の不便、負担を無くしたい」という思いです。
近い将来、森岡さんのアイデアをもとにした福祉機器が商品化され、普及していくことを願います。障害のある人、介護する人たちから多くの笑顔が生まれると信じて——。
撮影:永西永実
森岡昭(もりおか・あきら)
東北大学名誉教授。理学博士として長年研究と教育に携わり、大学を退職後、福祉機器の開発に本格的に取り組むようになった。森岡さんの公式YouTubeチャンネル「福祉機器小細工爺」では、自身が開発した福祉機器の使い方や魅力を発信している。
森岡昭さん 公式YouTubeチャンネル「福祉機器小細工爺」
- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。













