未来のために何ができる?が見つかるメディア
「苦しまないで済む不登校」の環境を社会全体でつくりあげる。第三の居場所づくりに大切なこととは?
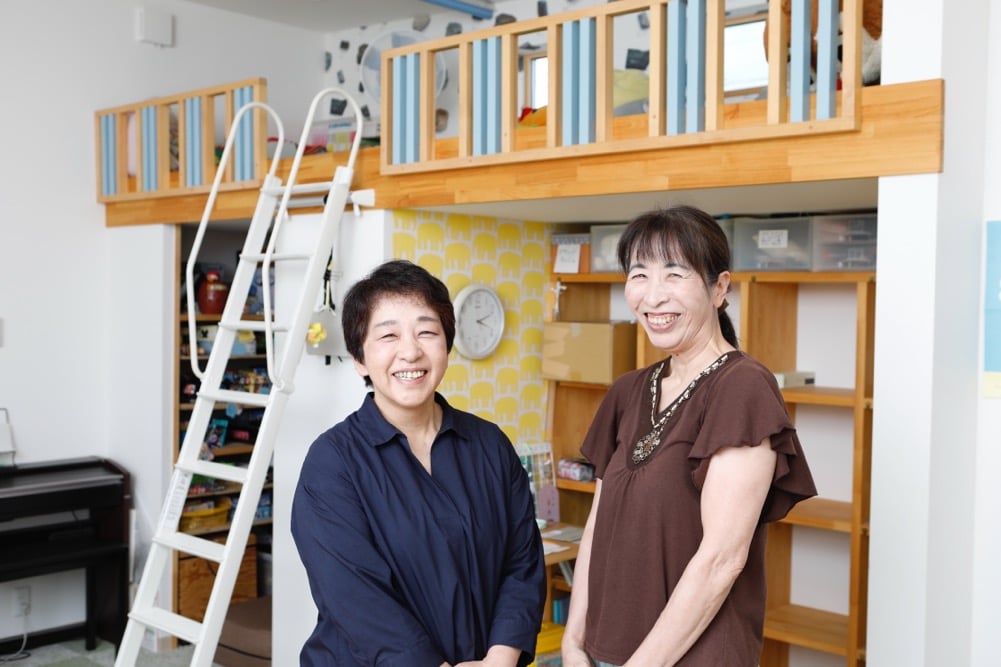
- 不登校支援は子どもだけでなく親の苦しさもサポートする包括的アプローチが必要
- 子どもに対して「支援者」であることを意識させず、フラットな目線で寄り添う
- 不登校でも苦しまない環境を財政的支援、居場所の確保等、社会全体で整えることが重要
取材:日本財団ジャーナル編集部
年々増加する不登校の児童。文部科学省の2023年度の調査では、小・中学校における不登校児童数は過去最多の34万人超と発表されました。
不登校の背景には、心理的・情緒的な要因が複雑に絡み合っており、一概にひとくくりにはできません。不登校という状態を問題視するのではなく、子どもたちが自分に合った環境を見つけ、安全に過ごすことができる場所を社会全体で整えていくことが肝心です。
日本財団ではそうした居場所づくりのために、学校や家庭以外の場で過ごす「子ども第三の居場所」(別タブで開く)事業を全国的に推進しています。信頼できる大人や他の子どもと関わることで、子ども自身の抱える悩みや苦しさを解きほぐすことができます。
一般社団法人フォースマイルが運営する、長野県諏訪市の「みんなのお家すまいる」(外部リンク)もそうした第三の居場所の一つです。不登校児童を持つ親たちが立ち上がり、フリースクールの運営や子ども食堂、親向けの学習会など包括的な支援を行っています。

地域コミュニティーが希薄化し、学校や家以外に居場所がない子どもたちにとって、こうした施設の存在が大きな光になるのではないでしょうか。そして、不登校児童を持つ親や、ひいては社会全体にとって、第三の居場所はどのように不登校に向き合うかのヒントになるはずです。
今回は「みんなのお家すまいる」を運営する木村かほり(きむら・かほり)さん、渡辺裕子(わたなべ・ひろこ)さんにお話を伺いました。
不登校の子どもだけでなく、親の苦しさも積極的に支援
――「みんなのお家すまいる」はどんな場所なのか教えてください。
木村さん(以下、木村):不登校の子どもたちや、家に居場所がない子どもたちが自由に集まることができる施設です。平日の10時〜15時をフリースクール、17時までを居場所として開放しています。
勉強をしたりゲームをしたり、他の子どもたちと触れ合ったりして、誰でも自由に過ごせる空間になっています。現在は不登校の子どもやその他の子どもも合わせて、70人以上が利用しています。

木村:小部屋やロフトを作るなど、一人になりたい子どもに向けたセーフスペースも用意しています。子どもたちがそれぞれ居心地のいい場所を見つけて過ごせるように内装も工夫しました。

――場所がクレープ屋さんの2階というのもユニークですよね。
木村:子どもも私たちもすごく気に入っています。居場所運営がスタートした2017年は友人宅の離れを借りて同様の活動をしていましたが、利用者の声や環境の変化もあって2020年から規模を拡大してこちらに移転しました。もともとの古い和室を、日本財団の助成金で改修工事を行い、今の形につくり変えています。
渡辺:下のクレープ屋さんにすごく助けられています。親御さんが子どもをこの場所に連れてくるときにやっぱり行き渋る子もいるんです。なので、「じゃあ、クレープを食べに行こう」といった形で誘うことで心理的ハードルも下がるので、子どもたちの支援には絶好の場所だと思います。
また、周辺には飲食店やスーパーもあるので利便性も高く、私自身も近くに住んでいるので何かあったときすぐに駆けつけることができるのも大きかったです。

――「みんなのお家すまいる」はどのような経緯で立ち上がったのでしょうか。
木村:不登校について悩みを抱える親同士のネットワークづくりを目的に、2011年に立ち上げた「親の会」が前身となっています。当時はブログや情報誌を作って親向けに情報発信することが中心だったのですが、親同士で子どもたちを含めてお出かけをしたり交流を深めたりする中で「何か拠点をつくりたい」という話になり、2017年に居場所運営をスタートしました。
渡辺:不登校は当事者である子どもはもちろんのこと、親も並々ならぬつらさを抱えています。ずっと家で子どもと過ごすうちに「不登校になったのは私の責任なのでは?」と悩みを抱え込む親御さんも少なくありません。そしてストレスで子どもに強く当たって断絶が生まれてしまっては、親と子の健全なコミュニケーションも難しくなります。
だからこそ、「みんなのお家すまいる」では定期的に親同士の情報交換会やおしゃべり会を開いたり、LINE窓口を開設したりして、親御さんの支援にも力を入れています。

いつでも相談できて、駆け込める居場所にするための工夫
――「みんなのお家すまいる」を訪れた子どもや親御さんの反響はいかがでしょうか。
木村:子どもたちはすごくリラックスして過ごしてくれています。読書に没頭したり、みんなでゲームをしたり、それを眺めたりと、それぞれが自由に過ごせる居心地のいい場所になっています。学校がつらいときにふらっと立ち寄れる安心できる居場所として認識してくれているようで、卒業生も訪ねてくれるんです。
渡辺:親御さんからも感謝の声が寄せられています。施設でのお子さんの様子を伝えたときに「うちの子って大丈夫なのかも」と安心して向き合えるようになったという声もありました。いつでも相談できるし、駆け込める場所があることは、親御さんの安心感につながっているようです。
――不登校など悩みを抱える子どもたちに向けた場所の運営をする中で、何か心がけていることを教えてください。
木村:子どもへの寄り添いと運営方針の両方に言えることですが、「私たちが支援してあげている」といった“支援臭”は出さないようにしていますね。子どもたちはそうした押しつけがましさには敏感ですし、逆に心が遠のいてしまう恐れもあります。だからこそ支援する側・される側の上下関係をつくることなく、フラットに同じ目線で接することが大切だと思います。

“苦しまないで済む不登校”を社会全体でつくっていく
――文部科学省の2023年度の調査で、不登校児童が過去最多の34万人を超えました。この状況をどのように受け止めていますか。
木村:学校や家で居場所がないと感じる子どもが増えているのは事実ですが、時代の変化も大きいのではないでしょうか。世間の理解が進んで、昔は我慢していた子どもたちも、柔軟な選択ができるようになったのだと思います。
渡辺:昔は不登校が目の敵にされていました。「子どもは学校に行くのが仕事だから、それを拒否するのは悪いこと」というイメージがありましたが、芸能人やインフルエンサーが不登校だったことを打ち明けるような発信も増えて、周囲の理解が広がってきています。「自分だけじゃないんだ」と、救われる子どもも多いのではないでしょうか。
木村:ただ、単に「学校は行かなくてもいい」という風潮には疑問もあります。誰かがそう言っても、その先どうなるかは誰も保証してくれません。
不登校になる子どもの悩みは千差万別で、正解はありません。だからこそ、一人一人に向き合って親や子ども、学校や社会が一丸となって考え続けるべき問題だと思います。周囲の大人は「行かなくていい」と言うだけでなく、その子らしく生きるために何ができるのかも考えてほしいと思っています。
渡辺:この先、どんなに不登校の課題が社会に認知されたとしても、「不登校はいいこと」という認識にはならないと思うんですよ。だから、“苦しまないで済む不登校”という選択肢を用意してあげられればいいと思っています。
不登校は「たまたま今そういう状態」なので、当事者には絶望感を抱えず、今何が楽しいか、心地いいかを優先して過ごしてほしいです。
――「みんなのお家すまいる」は学校や地域とどのように連携しているのでしょう。
渡辺:現在は諏訪市とも協定を結び、行政とも連携して密にコミュニケーションをとっています。行政の方が学校側にも進言してくれるなど良好な関係を築けていますね。学校ではできないことを学べる第三の居場所として認めてくれているので、それはすごくいいことだなと感じます。
木村:諏訪市と周辺地域は親の会のネットワークも活発で、フリースクール含めて24団体が活動しています。相互に受け入れ体制も整っているので、諏訪市に住む親御さんが「地元の諏訪市で知り合いに会うのはちょっと……」といったときに、お隣の茅野市の施設に行くこともできるんです。官民連携でそうしたコミュニティーが多数あるのはこの地域ならではかもしれません。
――「みんなのお家すまいる」の今後の展望を教えてください。
木村:不登校の子どもたちや子どもを持つ親に向けて、今後もこの居場所を維持できればいいなと思っています。数年前までは学校と民間の居場所などが連携して一緒に話をするなんてあり得なかったんですが、学校がカバーできない子どもたちがいる以上、今後の不登校支援においては官民の連携が不可欠になってきます。国や企業とも協力しつつ、支援策を拡充しながら今後もより良いアプローチを続けていければと思っています。
渡辺:15年以上この支援活動を続けてきて、将来何があってもこの場所だけは守り抜きたいと考えています。「親の会」を新たに始めたいという相談も寄せられており、そうした方々へのアドバイスなども積極的に行っています。「みんなのお家すまいる」を卒業した子どもや親たちが今度はこの場所を支えたいと言ってくれることも増え、最近ようやく手応えを感じられるようになってきました。
後継者不足の不安もありますし資金も不足しているのですが、ここが本当に大切な場所なんだということが地域に根付いていくとうれしいです。活動を支えてくれる子どもたちが増えることは私の希望でもあり信じている部分でもあるので、うまくバトンを回し続けたいですね。
不登校に悩む人たちのために、私たち一人一人ができること
最後にお二人に不登校に悩む人たちのために、私たち一人一人ができることを伺いました。
[1]不登校の現状をウェブサイトや本で調べ、理解を深める
「不登校はわがまま」といった誤った認識を払拭するためにも、まずは当事者がどんな悩みを抱えているのか、どのような支援がされているのかを知ることが第一歩。記事を読む、当事者の声に耳を傾けるなど、関心を持つことから始める
[2]子どもと接する際、画一的な価値観を押し付けない
子どもの選択肢を広げるため、「人と同じじゃなくてもいい」「あなたのやり方でいいよ」と伝える。ドタキャンなどの行動も失敗ではなく、その時々の気持ちの変化として受け止める。子どもを信じ、否定しない関わり方を心がけることで、子ども自身の自己肯定感を育む
[3]不登校支援を行っている団体への寄付
現状、不登校支援の制度は十分とは言えない。支援団体への寄付は、居場所づくりや活動の継続を支える大きな力となる。経済的な理由でフリースクールなどの施設に通えない子どもたちがいることも忘れてはならない
不登校児童数が過去最多を更新する中、「子ども第三の居場所」事業について調べていたところ、「みんなのお家すまいる」の存在を知りました。
不登校は年々増加する社会的な課題ですが、木村さんや渡辺さんのやわらかな寄り添い方は、当事者への向き合い方の大きなヒントになると感じました。子どもだけでなく親のつらさにも包括的に向き合えるのは、お二人が不登校児童を持つ親として、さまざまな子どもたちや親と向き合ってきたからこそでしょう。
特に印象的だったのは、「学校は行かなくてもいい」といった風潮に対しての、「誰かがそう言っても、その先どうなるかは誰も保証してくれません」という言葉。誰もが正解を持たない社会課題において、耳障りのいい言葉を受け入れて安心してしまうのではなく、常にアンテナを張り、何ができるかを考え続けることの大切さを実感した取材でした。
撮影:永西永実
- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。













