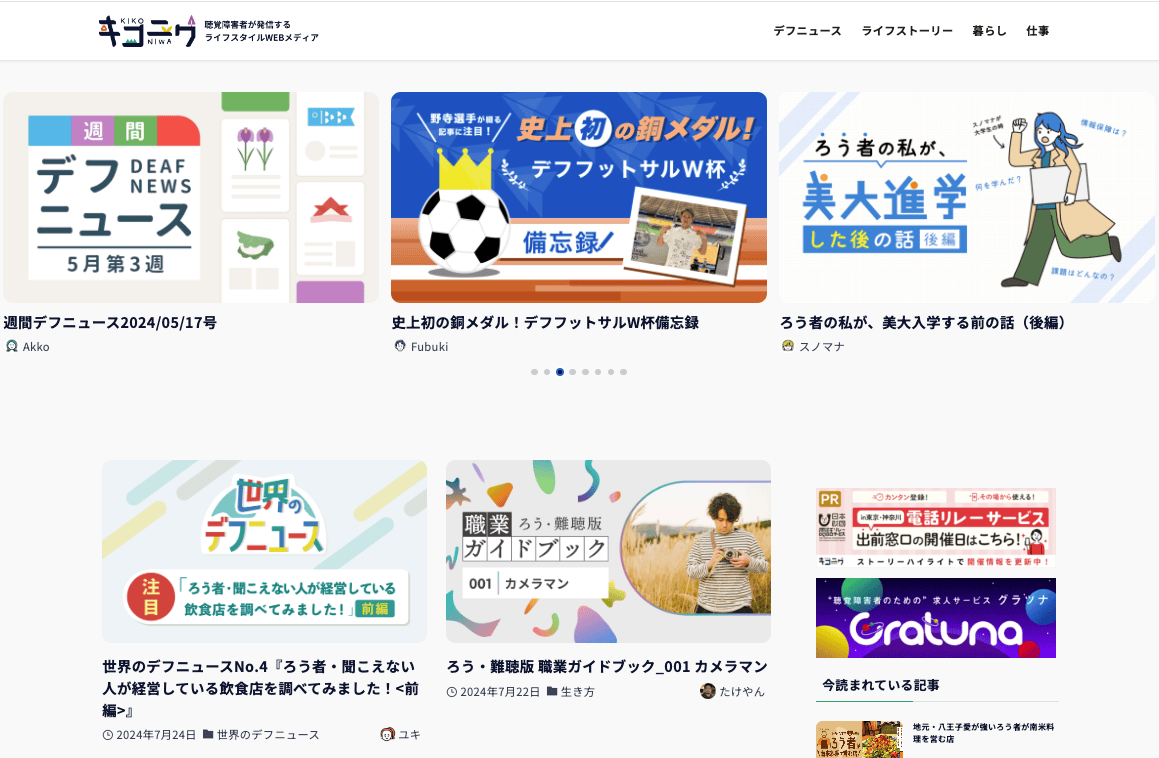未来のために何ができる?が見つかるメディア
スタートの出遅れは当たり前だった。発光してスタートを知らせる「スタートランプ」が聴覚障害競技者の可能性を広げる

- これまで聴覚障害のあるスポーツ選手はスタートの出遅れの問題を抱えていた
- スタートの合図を光で知らせる「スタートランプ」は選手の可能性を広げる
- 「聞こえること」を当たり前だと思っていないか。誰も取りこぼさない視点が一人一人に求められる
取材:日本財団ジャーナル編集部
走る速さを競うトラック競技は「位置について、用意、スタート」の合図で始まります。0.1秒以下のタイムを争うアスリートは、審判の声やピストルの音に細心の注意を払い、最高のスタートを切るために日々練習を重ねています。
しかし、聴覚障害のある選手には、音の合図は聞こえにくかったり、聞こえなかったりします。これまで聴覚障害のある選手たちは目視でピストルを確認し、周りの選手の動きに合わせスタートを切っていました。聴覚障害のある選手が出遅れることは「当たり前」とされてきました。
日本のこの状況を変えたのは、東京都立中央ろう学校の教諭として20年以上陸上競技に携わり、一般社団法人日本デフ(※)陸上競技協会(外部リンク)の事務局次長も務める竹見昌久(たけみ・まさひさ)さんです。
- ※ 「デフ(Deaf)」とは、英語で「耳が聞こえない」という意味

竹見さんは2011年頃からスタートの合図を光で知らせる「スタートランプ」の開発・普及を日本で始めました。この「スタートランプ」の仕組み自体は、2005年のメルボルンデフリンピックにて正式採用されていましたが、日本での普及は進んでいませんでした。しかし、竹見さんの活動もあり、2025年11月に開催される、聴覚に障害がある選手のスポーツ大会「東京2025デフリンピック(外部リンク)」にも採用が決まっています。
11月に日本で初めて開催される「東京2025デフリンピック」を前に、竹見さんに、多くの人がこういった課題に気づき、自分ごととして捉えるために必要なことについて、お話を伺いました。
聴覚に障害があっても平等にスタートを切れる
――「スタートランプ」はどういう機器なのか教えてください。
竹見さん(以下、敬称略):審判の声やピストルの音によるスタートの合図を、光で選手に伝える機器です。スターターはランプを点灯させるボタンとピストルを持ち、「位置について」で光を赤に、「用意」で黄色に、「スタート」でピストルが放たれると緑の光が点灯し、スタートを正確に伝えることができます。
聴覚障害のある選手が、聴者(耳の聞こえる人)の選手と混合で競技を行う大会の一部では、この「スタートランプ」が採用されています。これがあれば、全ての選手が平等にスタートを切ることができます。
現在はスポーツ庁の協力のもと、「東京2025デフリンピック」に向けて講習会や体験会など全国で研修・普及活動を行っています。

――なぜこの「スタートランプ」を日本で開発・普及をさせようと考えたのでしょうか。
竹見:指導していた生徒の言葉がきっかけでした。まず第一に、トラック競技はスタートが競技の命運を分けます。スタートが遅れるといい結果を残すことは難しくなりますし、フライングをすればその場で失格となってしまいます。これまで聴覚障害のある選手は音の合図を聞き取ることができず、出遅れることが当たり前になっていました。
そんな中、生徒が高校3年を締めくくる大切なインターハイに出場しました。生徒自身も大会に向けて必死に努力を重ねていたのですが、スタートの合図が聞こえず、いい結果を残すことができませんでした。
その後、生徒が涙ながらに「こんなに頑張ってきたのに聞こえなかったら意味ないじゃん」と打ち明ける姿を見て、私は指導者として何もしてあげられていなかったのだと強く実感しました。そこから聴覚に障害がある競技者が、平等にスタートできる機器を日本で開発・普及させようと決意したんです。
スタートランプの概念自体は、2005年のメルボルンのデフリンピックで使用された前例があり、そちらを参考に開発を進めました。

――そもそも、「スタートが遅れる」ことが当たり前となっていたのはなぜでしょうか。
竹見:世間の認知が低いことも理由の1つですが、聴覚障害のある生徒への指導の仕方も要因としてあったのではないかと感じます。当時は「一生懸命、周りを見なさい」「聞く努力をしなさい」「自分で工夫して乗り越えなさい」といった、スパルタ的な価値観が横行していました。
私自身も、当時は彼らの抱えるハンディキャップをすごく軽く考えていて、「補聴器をつけなさい」などと言ったこともあります。補聴器は周囲の音を増幅させて音を聞き取りやすくする機器ですが、増幅された観客の声や風の音などからスタートの音を聞き取るのにも、やはり限界があります。難聴の種類によっては、補聴器ではどうにもならない人もいます。
生徒たちにとっては酷な状況だったはずです。当事者の抱える悩みへの理解や寄り添いは、まったく足りていませんでした。「スタートランプ」が、あらためて聴覚障害がある人々への理解を助けるものになればという思いもあります。
関連記事:人工内耳って?補聴器と何が違う?その仕組みと「聞こえ」の大切さを専門家に聞いた(別タブで開く)
選手に希望の光と言われた「スタートランプ」。受け入れられるまでの道のり
――「スタートランプ」が導入されて、選手たちからはどのような反応がありましたか。
竹見:とても喜んでくれました。今までは音が聞こえない分、周りの選手たちに合わせてスタートするしかありませんでしたが、視覚でタイミングが分かるので、思い切ってスタートを切ることができます。中には「希望の光」とまで言ってくれる方もいました。
――選手たちのモチベーションも大きく変わりそうですね。
竹見:はい。今までは耳が聞こえないためにトラック競技を諦め、やり投げや走り幅跳びといったフィールド競技を選ぶ選手が多かったようです。ところがデフリンピックの男子100メートルで金メダルを獲得した佐々木琢磨(ささき・たくま)選手に会った時に、「最近フィールド競技の選手が減ったんだよね」と言われました。なぜかと尋ねたら「『スタートランプ』があるからだよ」と話してくれて、すごくうれしかったですね。選手を取り巻く状況は大きく変わったのだなと感慨深かったです。
――「スタートランプ」の開発や普及を進めていく上でどのような困難がありましたか。
竹見:教育や競技の現場に受け入れてもらうことが大変で、かなりの時間を要しました。「スタートランプ」の普及活動で10年以上全国を回ったのですが、訪れた先で審判の方に「こんなのいらないでしょ」と言われたことを今でもはっきりと覚えています。
その理由を聞くと「私の知ってる選手はちゃんとスタートできていたよ」ということでした。ろう学校の先生方からも「こんなものを使うな」といった意見をいただきました。
――反発があったことが意外です。
竹見:私も現場で指導していた身として、新しい機器への抵抗感は分からなくもなかったのですが、聴覚障害のある人への理解は、教育者でさえまだまだなのだと実感しました。
聴覚障害のある人の聞こえ方はさまざまです。全く聞こえない人や、少しだけなら聞こえる人もいますし、低音は聞こえるけど高音は難しいなど、人それぞれ聞き取れる音の範囲も変わってきます。一括りにしてしまうのは危険ですし、そうした初歩的なことをその後の研修会で丁寧に説明していきました。
この現状を多くの人に知ってもらうために、現在も普及や啓発活動を続けています。
「スタートランプ」は競技者を支え、大会の価値も向上させるツールにもなる
――竹見さんは「東京2025デフリンピックの運営」にも関わっています。企画設計などで気をつけた点を教えてください。
竹見:障害がある人の競技はどうしても「かわいそう」というイメージが先行して、純粋に競技を楽しんでもらえることが少ないのではと感じていました。
そこで、「東京2025デフリンピック」の告知動画では、ほとんどデフリンピックであることを伝えないPR動画(外部リンク/YouTube)を作ったんです。

――耳に近未来的なヘッドギアが着いていて、かなりスタイリッシュな動画ですね。
竹見:はい。デフリンピックに対する意識を変えてもらいたいな、と考えました。「かわいそうな人たちが頑張る大会」では決してなく、純粋に競技として前向きに楽しんでもらいたいという思いがあります。
そのために「スタートランプ」も競技の盛り上げに一役買っているんです。突拍子もないようですが、「スタートランプ」や、ファウルなどを光で知らせる「見えるホイッスル」は競技中に見るとイルミネーションのようですごくきれいなんです。
「スタートランプ」や「見えるホイッスル」が、デフスポーツのエンターテイメント性を高めてくれる1つのツールとして機能するのではないかと考えています。

竹見:デフスポーツをできるだけ福祉っぽくならないようにしたいんです。なので、「聞こえない人のために『スタートランプ』を設置しよう」ではなく、最初は軽いノリで「会場で光って映えるから『スタートランプ』を置こうよ。聞こえない人も一緒に出られるし」といった感じで進めていきたい。そういう軽いノリこそ、裾野が広がっていくのではないかと考えています。
また、デフリンピックでは競技場に横長のモニター「リボンビジョン」を設置し、実況音声をリアルタイムで可視化したり、手話通訳者をモニターに映したりする試みも行われています。どうしても必要だと考え、東京都に掛け合って採用してもらいました。

竹見:競技者と観戦者のサポートの意味合いだけでなく、ひと目でデフリンピックだと分かるようにスタイリッシュに演出することも必要だと感じました。デフリンピックの価値を上げ、大会を持続可能なものにするためにも「スタートランプ」などのツールが大きな役割を果たすと信じています。
誰もがスポーツを楽しめるような社会のため、私たち一人一人にできること
最後に竹見さんに、誰もがスポーツを楽しめるような社会のため、私たち一人一人にできることを伺いました。
[1] 「東京2025デフリンピック」を観戦する
「東京2025デフリンピック」は事前申し込みなく、誰でも無料で観戦可能(※)。まずは生で見ることで、聴覚障害者の挑戦や雰囲気を知り、聴覚障害者が直面する課題や、彼らの挑戦を自分ごととして捉えるきっかけにする
[2]聴覚障害に対する誤解と偏見を捨てる
過去に広く見られた、誤った指導方針や、障害に対する画一的な見方を改める必要がある。障害に対する正しい情報を知ることが大切
[3] コミュニケーションに対する意識を改める
聴者は、「会話によるコミュニケーションができること」を普通のことだと思いがち。障害によっては、会話を前提としたコミュニケーションが困難になる。そのことを意識し、さまざまな場所で取りこぼされている人がいないか配慮することが求められる
「東京2025デフリンピック」の開催が直前ということで、デフスポーツについての課題を伺いたく、今回、竹見さんに取材を申し込みました。
聴覚障害のある選手の出遅れを「当たり前」としてきた背景には、聞こえることを前提とした競技構造があったのだと思います。その構造を変えようとする竹見さんの取り組みは、スポーツ界だけでなく、私たちの日常にも問いを投げかけているように感じます。
競技大会で聴覚障害のある競技者を支える「スタートランプ」は、競技者と聴者のつながりをつくってくれる存在だと思いました。競技者に寄り添いながら、大会を持続可能なものにするために献身的なサポートを続ける竹見さんの姿に、デフスポーツへの大きな愛を感じた取材でした。
撮影:永西永実
〈プロフィール〉
竹見昌久(たけみ・まさひさ)
1975年生まれ。東京都立中央ろう学校高等部主幹教諭。高校、大学と陸上競技部に所属し、大学卒業後に教師の道へ。長年、陸上競技部の指導に携わり、29歳で前任の立川ろう学校に赴任。ろう者への陸上競技の指導に深く関わるようになる。現在は、全国聾学校体育連盟事務局次長、一般社団法人日本デフ陸上競技協会事務局次長を務め、国際大会におけるスタートランプの設置や世界的な普及活動のほか、「東京2025デフリンピック」に向けた取り組みも行っている。
- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。