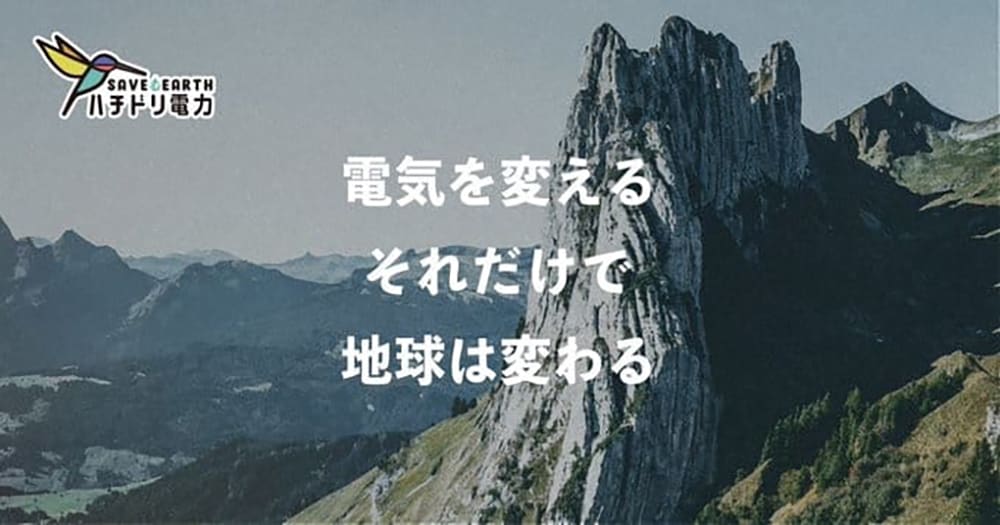未来のために何ができる?が見つかるメディア
新たな地球温暖化対策として注目のCO2回収技術「DAC」とは?

- 地球温暖化の一因、CO2。「DAC」は大気中から直接CO2を回収する技術
- 回収したCO2は地下に貯留したり、農業に再利用したりすることが可能
- 「DAC」が発展しても元の気候には戻らない。小さなCO2削減を同時に行っていくことが重要
取材:日本財団ジャーナル編集部
平均気温や海水温の上昇、記録的な大雨、台風などの異常気象、大規模な森林火災。これらは全て、地球温暖化が関係しているといわれています。
- ※ こちらの記事も参考に:地球温暖化が進めば、いまの場所に住めなくなる人がたくさんいる?(外部リンク)
しかし、地球温暖化の一因である化石燃料によるCO2(二酸化炭素)の排出量は、世界中で増加しつつあり、2024年のCO2総排出量は過去最高の416億トンと予測されました。
CO2排出削減のため、さまざまな取り組みが行われています。その中でも注目されているのが、「DAC(Direct Air Capture)」という新たな技術を活用した取り組みです。
DACとは、日本語で「直接空気回収技術」と呼ばれ、カーボンニュートラル促進に向けた手段の1つ。このDAC技術の開発に取り組んでいる企業の1つが、Planet Savers株式会社(外部リンク)です。「100年後も暮らせる地球を次世代に」をビジョンとして掲げ、2023年から大気中のCO2を回収するDACの開発を進めています。
今回はPlanet Savers株式会社のCEO・池上京(いけがみ・けい)さんに、「DAC」の仕組みやDAC普及によってもたらされる影響、さらには一人一人がCO2削減や地球温暖化を抑えるためにできることについて話を伺いました。

コストを抑えつつ、安全に大気中のCO2を回収・貯留する「DAC」
――はじめに、「DAC」の仕組みについて教えてください。
池上さん(以下、敬称略):「DAC」とは、大気中のCO2を直接回収する技術のことです。世界各国が取り組んでいるCO2の排出削減とともに、すでに排出されたCO2を回収することで、ネット・ゼロ(※1)にとどまらず、カーボンネガティブ(※2)が期待できる技術と考えられています。
- ※ 1.「ネット・ゼロ」とは、再生可能エネルギーの導入や省エネにより、そもそもの温室効果ガスの排出量を削減するとともに、発生した温室効果ガスを、植林や森林保全活動などの取り組みで吸収・固定することによって、活動全体の排出量が差し引きゼロになっている状態
- ※ 2.「カーボンネガティブ」とは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量が、森林や植林による吸収量よりも下回っている状態のこと
――森林や海草にCO2を吸収させて貯留するグリーンカーボン、ブルーカーボンとはどのような違いがあるのでしょうか。
池上:大気中のCO2を減らすという点においては同じですが、CO2を回収するプロセスが異なります。森林や海草は光合成によってCO2を回収・貯留させますが、「DAC」は専用の装置やCO2を定着させる吸着剤を用います。
- ※ こちらの記事も参考に:海草が二酸化炭素を減らす? 地球温暖化対策になるブルーカーボンって?(別タブで開く)
――Planet Saversが開発中の「DAC」は、どうやってCO2を回収するのでしょうか。
池上:私たちが開発している「DAC」は、ゼオライトという鉱物を用いた方法を採用しています。簡単に説明すると、ゼオライトは分子構造的に小さな穴が空いており、そこに空気を流すことでCO2を吸着させます。そして、圧力を下げて、そのゼオライトからCO2のみを分離するといった仕組みです。

池上:CO2を吸着できる物質は他にも存在しますが、ゼオライトには独特の優位性があり、吸着したCO2を取り出す際のエネルギー消費量とコストを低く抑えられることが大きな特徴です。従来の「DAC」で使用されるCO2吸着剤は有機物が主流で、経年劣化が早いことが課題となっていました。
また、吸着剤そのものが高価な場合も多いです。しかし、ゼオライトは無機物であることから約10年という高い耐久性を持ちますし、天然にも存在することから安価です。その結果、吸着剤の交換頻度も少なく、長期的な運用コストの削減が期待できるんです。
さらに、安全性の面でもゼオライトは優れています。吸着剤の中には取り扱いに注意を要する危険な物質もありますが、ゼオライトは触れても吸い込んでも健康上の問題がありません。「DAC」の実装において、安全面は重要な検討事項であるため、ゼオライトの使用は極めて有用性が高いと考えられます。
回収したCO2は、地下で1000年以上貯留。農業に再利用も可能
――回収したCO2はどのように処理されるのでしょうか。
池上:回収したCO2の処理方法は2通りあります。1つは地下に貯留するという方法です。パイプを通して地上からCO2が鉱物化する地層に向けてCO2を送り、1000年以上地上に出てこないようにする技術が確立されています。アメリカやノルウェー、オーストラリアでは、すでにCO2の地下貯留が行われています。
日本の場合、他国と比べると、貯留できる場所が少ないかもしれませんが、実際に2016年から北海道の苫小牧で実証実験が行われており、安全性も確認できていて、現在は実用化に向けたルールメイキングに取り掛かっています。
もう1つはカーボンリサイクル(※)という手法です。特に今、相性が良いのではないかと注目されているのが、施設園芸での再利用です。野菜や果物の光合成を促進するためにはCO2が必要で、現状、多くの農家はCO2のガスボンベを購入し、それをビニールハウスに噴射しており、このコストが意外とかかっています。

池上:「DAC」の装置が農場に設置できれば、大気中のCO2を回収して農作物も育てられるのではないかと考えています。とはいえ、「DAC」の装置は大きくスペースをとるため、農場の大きさにかかわらず設置できるかといわれると難しいところもありますが、初期のCO2供給先として有用ではないかと感じています。
- ※ 「カーボンリサイクル」とは、CO2を資源としてとらえ、分離・回収してさまざまな製品や燃料に再利用すること
CO2回収・貯蓄と同時に排出削減も重要
――池上さんが、地球温暖化問題解決への取り組みを始めたきっかけを教えてください。
池上:子どものときに発展途上国を訪れた際、物乞いをされたり、祖父から戦争の話を聞いたりするうちに、「社会的な理不尽を解決したい」という気持ちが強くなり、学生時代から社会問題解決に対しての関心は高かったと思います。その後、JICA(国際協力機構)に入職しました。
地球温暖化や気候変動に対してアプローチする必要性を強く実感したのは、西日本豪雨災害に見舞われたときですね。「これは誰かが何とかしないといけないのではないか?」と思い、共同創業者である伊與木健太(いよき・けんた)と出会い、Planet Savers株式会社を設立しました。
――地球温暖化解決に向けて取り組む方法はさまざまですが、営利企業として取り組み始めた理由は何でしょうか。
池上:国が主体となって動く場合、多くはルールや制度の整備から始まります。制度が先行して新しい技術が生まれることも確かに価値のあることですが、私は社会問題の解決につながる技術をまず発展させ、その後でルールや制度を整えていくアプローチの方が性に合っていると感じたんです。何より、自分が主体となって物事を推進していくことにやりがいを感じるため、営利企業として取り組むことを選択しました。
――2023年に設立されてから約2年、これまでさまざまな実証実験などを行ってきたかと思いますが、どこまで開発が進んでいるのでしょうか。
池上: 2025年9月を目処に、「DAC」のプロトタイプを完成させるべく日々尽力しています。2年間で研究を重ねた結果、実装に近付ける良いデータが取れたので、一日でも早く世に出せるように、さらに注力していきたいですね。
――世界には、2010年頃からDAC事業に携わっている企業もあると伺っています。
池上:そうですね、年間で100万トンのCO2を回収・貯留できるような施設をつくっている海外企業もあるため、現状の差はあるかもしれません。とはいえ、そういった企業ですら、スケールアップはしているものの、導入コストは落ちていないのが現状です。
また、海外には「DAC」の競合企業が100社以上ありますが、ゼオライトを用いたDAC開発に取り組んでいるのは私たちの会社を含めて4社のみです。世界で先行しているDAC事業に追いつく可能性は十分にあると考えています。
――今後、「DAC」の技術が発展すれば、温暖化が騒がれる前の地球の気候に戻る可能性があると考えていいのでしょうか。
池上:それは難しいでしょう。世界のCO2排出量は想定よりもはるかに多く、以前の地球の気候に戻そうとすると、相当なお金をかけないと大気中からCO2を回収することはできません。
また、地球温暖化の原因は、CO2を含む温室効果ガスの増加、環境や生態系の変化なども一因で、CO2の回収だけでは地球を元に戻すことは不可能です。
ですので、「DAC」の活用や推進だけではなく、さまざまな地球温暖化対策を並行して進めていくことが重要でしょう。
次世代に、壊れていく地球を見せたくない
――DAC事業について、現状どのような課題を抱えていますか。
池上:エネルギー使用量ですね。現在はエネルギー消費が大きいため、再生可能エネルギーを用いないと、CO2排出が更に発生してしまいますし、コストも上がります。また、装置が大きくなれば、更にコストがかかります。実用化に向けて、低エネルギー、コストで運用できるような体制を整えなくてはいけません。
また、吸着剤にも課題はあります。現状、CO2と構造が似ている成分も一緒に回収してしまう仕様となっているため、CO2以外の成分を分離させるプロセスがあり、そこがコストアップにもつながっています。
現在、伊與木と共に、CO2とそれ以外の成分を分別して回収できる新しい吸着剤の作成に取り組んでいるところです。
――さまざまな課題を乗り越えながら、実装に近づいているんですね。池上さんが、地球温暖化をはじめとする気候変動問題に、熱い情熱を持てる原動力はなんでしょうか。
池上:人生は1回きりですし、社会に対してインパクトが強く世の中のためになることを行いたいという思いが強いです。その点では、気候変動は人類にとっての最重要課題だと思うんです。
もちろん、日本には少子高齢化問題や格差の拡大など解決しなければいけない問題は数多くありますが、環境破壊によってもたらされる自然災害は、いままで人類が築き上げてきた努力を全てなかったことにしてしまうほど恐ろしいものだと思っています。そんな状況は見たくないですし、自分の子どもや次の世代に見せたくありません。
少なくとも、現状から大きく変わらないぐらいの環境くらいは、下の世代に残してあげたいという思いが強いです。
――池上さんと同じように地球温暖化問題に危機感を持っている人は多いと思います。そういった人たちが、最初の一歩としてできることは何かありますか。
池上:社会問題に限らず何でも言えることですが、どんなに小さいことでもいいのでアクションを起こしてみることです。行動を起こすと必ず次の課題や、新しい視点が見えてきて、それが次のステップへとつながっていきます。
私自身がスタートアップを経営していることもあり、最初は気候変動に取り組むベンチャー企業等にプロボノや副業でもいいので参加するといったことをお勧めしたいです。
もっと身近なところで言うと、家庭や職場で節電に取り組んだり、自動車をガソリン車からハイブリッドカーや電気自動車に変えたり、太陽光発電を自宅に取り入れたりするといったことも始めていいかもしれません。国や自治体の補助金制度も充実してきています。
また、インターネットで調べれば、全国各地で地球温暖化対策に取り組んでいる団体もたくさん見つかると思います。森林保全活動、清掃活動、環境教育イベントなど、さまざまな形の活動もあります。自分の住んでいる地域や関心のあるテーマに合わせて、一度参加してみてもいいと思います。
一人でも多くの人と同じ気持ちを持って取り組んでいけるとうれしいです。
地球を温暖化から守るために私たちができること
- 気候変動に取り組むベンチャー企業等に、プロボノや副業でもいいのでから参加する
- ハイブリットカーや、太陽光発電の導入など、家庭や職場で節電に取り組む
- 地球温暖化と向き合うNPOや市団体の活動に参加し、身をもって現状と対策を学んでみる
「DAC」についてはラジオで初めて耳にしましたが、まだ広く認知されていない技術だと感じたので、今回、取材を申し込みました。
昨今、「地球温暖化」ではなく「地球沸騰化」と表現されるほど、地球環境の危機は深刻さを増しています。そうした中で、「DAC」は地球温暖化の進行を抑制する新たな切り札となる可能性を秘めた技術だと思いました。
この記事をきっかけに、一人でも多くの方に「DAC」という技術を知っていただき、この技術の発展や社会実装に関わる人が増えることを願います。
〈プロフィール〉
池上京(いけがみ・けい)
1987年生まれ。日本初の大気中CO2回収(DAC)ベンチャーPlanet Savers代表。京都大学法学部、公共政策大学院を卒業し新卒でJICAに入構。中東の電力・エネルギー・運輸交通・上下水等のインフラ開発・政策支援に従事する。ケンブリッジ大学経営学修士(MBA)を経て、ソフトバンク・ロボティクスでAIロボットのグローバル展開に取り組む。2021年に株式会社MIRAIingを設立し、2000名以上の学生にリーダー教育を提供した後事業売却。気候変動を食い止めたい、インパクトあるスタートアップを立ち上げたいという想いで、2023年にPlanet Saversを設立し現職。
Planet Savers株式会社 公式サイト(外部リンク)
- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。