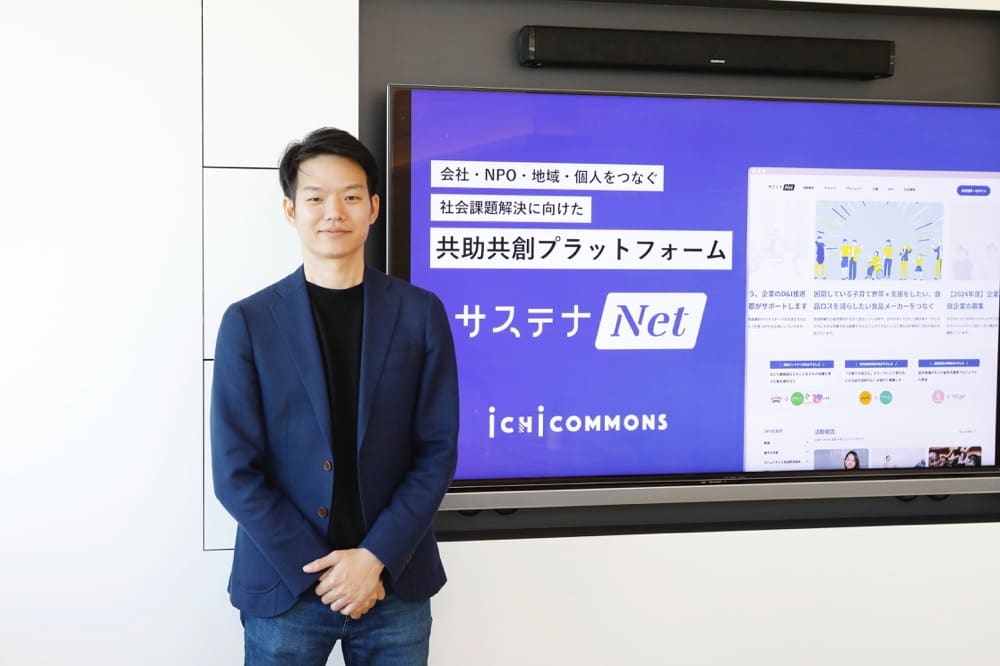未来のために何ができる?が見つかるメディア
社会課題解決も利益も追求する「インパクト投資」とは。取り組む人を増やすには?

- SIIFは「社会課題の解決」を直接的な目的とする「インパクト投資」を実施している
- 社会課題は一時的な支援にとどまらず、根本的な原因となる構造や仕組みを変える取り組みが重要
- 自然と社会課題に触れられる環境で、「気になること」や「引っかかること」への意識を持ち続けることが大切
取材:日本財団ジャーナル編集部
「インパクト投資」とは、財務的リターンと並行して、ポジティブで測定可能な社会的、および環境的インパクトを同時に生み出すことを意図する投資行動を指します。これまで社会課題の解決は主にNPOが担ってきましたが、インパクト投資を通じて企業も積極的に関わることで、より持続的な取り組みが広がります。
このインパクト投資を推進しているのがSIIF(一般財団法人 社会変革推進財団)(外部リンク)です。SIIFでは、経済の力で社会課題のシステムチェンジ(根本的な解決)を目指し、実際にインパクト投資を行うだけでなく、調査研究や政策提言なども行っています。
今回は、同財団の専務理事・青柳光昌(あおやぎ・みつあき)さんに、企業や金融機関などがインパクト投資をすることの重要性や、社会課題解決のプレーヤーを増やすために必要な取り組みについて伺います。
複雑化している社会課題と向き合い、根本解決を目指す
――SIIFはどんな目的で設立された団体でしょうか。
青柳さん(以下、敬称略):日本財団から派生した団体で、経済の力で社会課題の解決に取り組むことを目的としています。日本財団は主に助成金を提供することで社会課題の解決に取り組むプレーヤーを支援していますが、SIIFでは社会課題の解決に取り組むプレーヤーに“投資”を行い、その事業が成功したら財務的なリターンを受け取ることができる「インパクト投資」を行っています。
――SIIFの活動資金はどこから得ているのでしょうか。
青柳:主に日本財団です。この他に、2019年から2024年までは、休眠預金(※)を社会課題解決のために活用するJANPIA(一般財団法人日本民間公益活動連携機構)(外部リンク)の助成を受けていました。
- ※ 「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法)に基づき、10年以上取引のない預金等(休眠預金等)を、社会課題の解決や民間公益活動の促進のために活用する制度
――社会課題解決のための投資というと、最近では「ESG投資」という言葉もよく聞きますが、インパクト投資とは何が違うのでしょうか。
青柳:確かに「投資をする」という観点ではどちらも同じなのですが、目的が違います。「ESG」とは「環境(Environment)」「社会(Social)」「ガバナンス(Governance)」の頭文字を組み合わせた言葉で、これらに配慮した投資を「ESG投資」と呼びます。
インパクト投資は「社会課題を解決する」ことを目的に投資を行いますが、ESG投資は、「会社経営の永続のために、社会や環境に悪影響が起きないように配慮した投資」を行います。
つまりインパクト投資は「社会のため」、ESG投資は「会社のため」と大きく目的が違っているのです。

――SIIFのウェブサイトでは、取り組みの一つとして「システムチェンジ」という言葉が紹介されていますが、システムチェンジとはなんでしょうか。
青柳:これまでの社会課題解決に向けたアプローチは「お腹を空かせている人がいたらパンを与える」というような対症療法的な方法が中心でした。もちろん、直接お腹を満たすことも大切なことですが、「なぜお腹を空かせてしまうのか?」という根本にある課題と向き合わなければ、本当の意味で解決することはできません。
社会課題の背後には、構造的な問題や複雑に絡み合った要素があります。それらを分析して、一つ一つ明らかにしていく。その全体を「システム」と呼び、そのシステムを根本からつくり変えることを「システムチェンジ」と呼んでいます。
――具体的に、どんな活動をされているのでしょうか。
青柳:現在は「ヘルスケア」「地域の活性化」「機会格差」の3つの領域でシステムチェンジに取り組んでいます。
SIIFの内部は、事業部と調査研究・政策提言を行う「インパクトエコノミーラボ」の大きく2つに分かれていて、事業部は直接、あるいは間接的に出資するほか、出資先と一緒に事業開発にも取り組んでいます。
インパクトエコノミーラボでは事業部が現場で得た知見や情報、失敗も含めて、さまざまな情報を分析したり、汎用化できるものはインパクト投資に取り組む他の企業などに向けて情報発信したり、政策に役立ててもらったりするといったことも行っています。
ジェンダーギャップ、地域のコミュニティー、児童虐待……。取り組む課題はさまざま
――現在、出資されている企業について教えてください。
青柳:長野県上田市にある株式会社はたらクリエイト(外部リンク)に出資しています。よく「女性に選ばれない地域は衰退する」といわれますが、地方には男女の賃金格差、女性がキャリアを積みにくいなどの現状があります。その背景には「女性はサポート役」「女性は家庭を守るべき」といった、男性社会的な価値観が根付いていることが、一つの原因として挙げられています。

青柳:そんな中、はたらクリエイトは「地方で女性のキャリアをつくる」をコンセプトに、女性を積極的に雇用し、キャリアアップを推進したり、管理職に女性を登用したりしているほか、女性が働きやすい環境整備にも取り組んでいます。
全ての企業が同じようにできるわけではありませんが、私たちはこの出資を通じて、はたらクリエイトの経営方針や取り組みについて、上田市商工会議所の会員企業に学んでいただき、ルールや環境を平等に整備するなど、各社ができるところから始めてもらうこと、ゆくゆくは地域全体に男女の賃金格差がなくなり、アンコンシャス・バイアス(※)の解消にもつながれば、と考えています。
- ※ 無意識の思い込みや偏見
――実現して、社会全体に広がったら、生まれ育った地域で働くことを選ぶ女性も増えるかもしれませんね。
青柳:はい。「地域活性化」の分野では、岡山県の株式会社エーゼログループ(外部リンク)に出資しています。地域の木材を使ったものづくりや、ローカルベンチャー育成、複合施設の運営などさまざまな事業を生み出している企業で、それによって都会からの移住者も増え、“地域活性化”というキーワードで見れば成功している事例の一つです。

青柳:ただ、既存住民のコミュニティーと移住者コミュニティーの間には、内面的にはお互いに協力し合いたいという思いがありつつも、どうしても壁のようなものができてしまいます。SIIFとしては「こっちの人、あっちの人」という区別なく、一体となった経済圏やコミュニティーを再構築することを目指して、人口2,000人に満たない村を存続させるモデルが構築できたらと思っています。
――他にも出資している企業はありますか。
青柳:児童相談所のDX支援を行っている株式会社AiCAN(アイキャン)(外部リンク)があります。「DX」は「デジタル・トランスフォーメーション」のことで、デジタル技術で人々の生活をより良いものに変革するという意味です。

青柳:児童虐待の背景には、親御さんにも虐待されていた過去があることや、経済的困窮、社会的孤立など、根本から解決するのはとても難しい課題です。
まずはシステムチェンジの手前の水際対策として、虐待の通報があった際に、いち早く対応できる体制を整えることが必要です。しかし、年々虐待相談件数が増えていて、多くの自治体では1人の児童相談所の担当職員が複数の案件を担当しなければならない状況に陥っています。
そこで、AiCANは児童の基本情報や経過記録の登録、各種事務作業などを専用アプリで自動化・効率化することで、児童相談所の担当職員の負担を軽減し、その分各家庭と向き合い、深く介入する時間をつくってもらうことで、一件でも虐待を減らし、未然に防ぐことを狙いとしています。
「効率重視」の社会から、互いを気遣い、思いやり合う社会へ
――「社会課題解決」は利益にならないと考える企業も多いのではないかと思います。「インパクト投資」に取り組む企業や組織を増やすには何が必要でしょうか。
青柳:正直なところ、「投資を通じて社会課題を解決したい」という経営意識を持った企業を増やすための特効薬はないと思います。
資本主義の社会では効率を重視する傾向にあります。というより、今まではそれが当然とされてきました。結果として、障害者に就労機会が与えられない、環境汚染を引き起こす製造ラインを使い続けるなど「負の外部性」(※)が生まれていました。
企業側は、こうした「負の外部性」をどれだけ是正して内部化できるか、知恵を絞らなければならないポイントです。
- ※ 企業の生産活動などにおいて、環境に悪い影響をもたらすが、積極的にその対策をとらないため、コストなどに反映されない活動のこと。こうした環境コストを市場価格に反映させることを「内部化する」という。外部不経済とも呼ぶ。参考:JCCCA 全国地球温暖化防止活動推進センター「外部不経済(がいぶふけいざい) 」(外部リンク)

青柳:ただ、近年ではエシカル消費(※)、SDGsなどの言葉が一般的に広がり、若い世代の方の意識が社会課題に向いていると思います。私はこうした学生時代の学び、幼い頃からのすり込みが非常に重要だと考えていて、将来的には新たにインパクト投資に興味を持つ起業家、経営者が多く出てくるのではないかと期待しています。
そのためにも、社会課題の根本解決に取り組む事業が成果を出し、事業としても持続可能で、出資者にもリターンがあることを示すモデルケースをつくっていくことが重要です。
- ※ 地域の活性化や雇用などを含む、人・社会・地域・環境に配慮した消費行動のこと
――未来に向けて、社会課題解決のプレーヤーになるために、私たち一人一人ができることはなんでしょうか。
青柳:まずは気にかけること。最近では学校教育で社会課題について触れ、自然と学ぶ機会も多いと思います。「気になること、引っかかること」が一つでもあったら、自分自身でその社会課題が起きている原因や背景などについて調べてみてほしいです。
それから、他者に関心を持つことですね。もしかしたら、学校など身近にも困りごとを抱えている人がいるかもしれません。私たちは、自分一人で生きていくことはできません。他者に関心を持つことが、社会課題の存在に気づくきっかけとなります。
この「気になること、引っかかること」への意識を持ち続けることで、自身の選択や行動にも変化が生まれます。就職先を選ぶ際には、企業の社会課題への取り組み姿勢に注目するようになり、仕事で企画を立てる際には、社会課題の当事者の視点を踏まえた検討ができるようになります。
ですから、「気になること、引っかかること」は大事にしてほしいと思います。
■社会課題解決のプレーヤーになるために、みんなができること
- 「気になること、引っかかること」が1つでもあったら、自分自身でその原因や背景を調べ、深掘りし、継続的な関心を持ち続ける
- 身近なところに困りごとを抱えた人がいるかもしれないという視点を常に持つ
- 調べて得た知識や他者への関心を、購買選択、地域活動への参加、情報発信などの具体的な行動に変換する
継続的に社会課題解決に資金が流れるようにする方法が気になり、今回、SIIFに取材を申し込みました。
「特効薬はない」とのことでしたが、若い世代が関心を持つことで、少しずつそのような流れができていくと感じた取材でした。
特に心に残ったのは、「気になること、引っかかることを大事にしてほしい」という青柳さんの言葉です。「気になること、引っかかること」に関心を寄せることこそが、社会課題解決の出発点になると感じました。
効率重視の社会から、互いを気遣い思いやり合う社会へ。その転換点に私たちは立っているのかもしれないと思いました。
撮影:永西永実
- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。